こんばんは。
今日は、芦部信喜『憲法』(第四版)第二章の「日本憲法史」を採り上げます。
なお、文中においては敬称を省略させて頂きました。何とぞご海容頂きたく存じます。
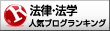
ランキングに参加しています。まず初めに何卒クリックをお願い致します。
1.大日本帝国憲法の特色の捉え方について
まず、大日本帝国憲法の特色をどのように捉えているか、みてみましょう。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
明治憲法は、立憲主義憲法とは言うものの、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強い憲法であった。
・・・(略)・・・まず、主権(この意味について第三章二1参照)が天皇に存することを基本原理とし、この天皇の地位は、天皇の祖先である神の意志に基づくものとされた。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(一条)とは、この天皇主権の原理を明示したものである。また、天皇は、神の子孫として神格を有するとされ、「神聖ニシテ侵スヘカラス」(三条)と定められた。(注1)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
恐らくは、この記述においては「神権主義」なる言葉は「後進性」「非合理性」を示すマイナスイメージとして使われているのかもしれませんが、まず、大日本帝国憲法の条文を読んでみれば分かることですが、具体的にどの条文をもって大日本帝国憲法が「神権主義」だというのでしょうか。
まず、天皇に「主権」が存在するということ、そして第一条についての解説は明らかに誤りです。
天皇は国体を変革するような権限(主権)を持ったことなどありませんし、第一条は「統治ス」となっているのみです。統治する(しらす)ことと、主権を有することは全く何の関係もありません。一体どこに、「主権」の文字があるというのでしょうか?
また、第三条についての解説も誤りです。
「神聖ニシテ侵スヘカラス」とは、天皇の立憲君主としての側面を捉え、政治への無答責を表現したものです。つまり、天皇は政治には関わらず、また責任を負うことはない、「統治すれども親裁せず」という意味なのです。
神聖、すなわち神の子孫である、という神話的側面の表現ではありません。
大日本帝国憲法には、ここにいうような「神権主義」など欠片もありません。
おそらくは、「告文」にある、「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴二シ典憲ヲ成立シ・・・」などの文言からそのようなイメージを受けるのかもしれませんが、これは明治天皇が皇祖神などの祖先の神々や歴代天皇に対してお誓いになったものであって、これが「神権主義」などというならば、先祖の墓参りをすることや正月に初詣に行くことさえも「神権主義」になってしまいます。
・・・・う~ん、全く・・・次!(苦笑)
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
権利、自由は保障されてはいたものの、それは人間が生まれながらにもっている生来の自然権(人権)を確認するという形のものではなく、天皇が臣民に恩恵として与えたもの(臣民権)であった。各権利が「法律の留保」( Vorbehalt des Gesetzes )をともなうもの、すなわち、「法律の範囲内において」保障されたにすぎず法律によれば制限が可能なもの、であったのは、そのためである。(注2)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
「法律の留保」というのは、ドイツのオットー・マイヤー( Otto Mayer, 1846 - 1924 )という学者が立てた法理論です。
法律の留保とは、行政権は、国民の権利や自由に対する制限を恣意的になすことはできず、このような制限は国民の代表機関たる立法府によってなされねばならない、というものです。
つまり、国民の権利や自由を制限することは原則として許されないが、立法府というのは制限される側の国民の代表機関であるから、いわば自分で自分の権利の制限に同意したのに等しいので、立法府が国民の権利や自由を制限することは許されるのだ、といういわゆる「自己統治」の思想に基づいています。
そもそも、この「自己統治」自体が大いにおかしな代物ですが、それはひとまずおくとしても、臣民権が「天皇が臣民に恩恵として与えた権利である」という見解について。
我が国は天皇と臣民との相互の敬愛により、成り立ってきました。一方が義務を果たす代わりに、他方がその見返りとして権利を与える、などという冷たい関係ではありません。
「恩恵として与える」などといえば、どこか「気に入らなければいつでも取り上げてしまう」などという響きが感じられます。しかし、ここに列記されている「臣民の権利」とは、かつてはそのような名称(言論の自由、など)のような呼び名こそなかったものの、我が国の慣習や道徳などの範囲内で歴史的に認められてきた「自由」に他なりません。
もちろん、時代によってその広狭はあり得たでしょうが、一定の範囲内で、武士や庶民はこれらのいわゆる「自由(この言葉もありませんでしたが)」を享受していたのです。
よって、「天皇が臣民に恩恵として与えた」というのも、「歴代天皇陛下が我が国を統治されてきた結果、我が国において培われてきた」権利・自由である、ということなのです。
また、「臣民権」をそのように「いつでも取り上げられるもの」と構成する結果でしょうが、「法律ノ範囲内二於テ」のみ保障されるものということ、すなわち『日本国憲法』上の「基本的人権」に劣るものであるというニュアンスが感じられます。
しかし、ここでいう「臣民権」を「いつでも取り上げられる権利」ではなく、「我が国の道徳や慣習などにおいて歴史的に認められてきた権利」であると解するならば、いくら「法律の範囲内で」との限定をつけようとも、自ずとその「範囲内」には限界が設けられます。
すなわち、ここで保障されている諸権利を、法律の定めさえあればいくらでも制限できる、などというのは全くの誤解、曲解でしかないのです。
法律学的には、「我が国の道徳や慣習などにおいて保障されてきた権利の意義を没却するような形で法律による権利の制限がなされても、その制限は帝国憲法に違反し無効となる」と構成されるのです。
2.八月革命説
さて、憲法学界では通説となっている『日本国憲法』の正当性の根拠として、宮沢俊義により立てられたいわゆる「八月革命説」があります。では、この八月革命説とはどのようなものなのか、見てみましょう。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
次に、日本国憲法と明治憲法との関係が問題となる。すなわち、日本国憲法は、その上諭によると、天皇が明治憲法七三条の改正規定による改正を裁可して公布したということになっており、形式的には、明治憲法の改正として成立したもの(欽定憲法)である。しかし、憲法全文は、「日本国民は、・・・代表者を通じて行動し」、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と規定し、日本国民が国民主権の原則に基づいて制定した民定憲法である旨を宣言している。そこで、この矛盾をどのように解するか、とくに、天皇主権を定める明治憲法を国民主権の憲法へと全面的に改正することは、法的に許されないのではないか、という疑問が生ずる。というのは、そもそも、憲法改正規定による憲法改正には一定の限界があり、その憲法の基本原理を改正することは憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので、それは・・・(略)・・・不可能であると考えられていたからである。(注3)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーー
「天皇主権を定める明治憲法」という誤りを除いては、この箇所は正当です。すなわち、『日本国憲法』は形式上は大日本帝国憲法の改正という体裁をとっているものの、大日本帝国憲法の基本原理を「改正」することはいわゆる「改正の限界」を越えるものであって、不可能であるということなのです。
まさにその通りで、それゆえに、『日本国憲法』の正統性が疑われることとなるのです。
そこで、この点を理論づけようと立てられたのが、「八月革命説」なのです。
では、「八月革命説」とはどんなものなのか、見てみましょう。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
(1)明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
(2)しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
(3)もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、新しい建前に抵触する限り重要な変革をこうむったと解さなければならない。たとえば、明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければならない。
(4)したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による改正という手続をとることによって明治憲法との間に形式的な継続性をもたせることは、実際上は便宜で適当であった。(注4)
ーーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーーー
憲法典には「改正の限界」というものがあります。そして、『日本国憲法』は基本的人権、国民主権などの理性万能思想(左翼思想)を根本精神とするものであり、それが大日本帝国憲法を改正してできたものであるというには、明らかにその「改正の限界」を超えるものであって、改正したものとはいえないというわけです。
ということは、憲法学の理論上は、『日本国憲法』は大日本帝国憲法第73条の「改正の限界」を越えている、すなわち同条に反し、改正は無効である、ということになるのです。『日本国憲法』は無効であるのです。
にもかかわらず、何とかこの違憲、無効な「改正」を正当化できないか、違法を合法化できないか、ということででっちあげられた理屈づけが、この「八月革命説」なのです。
「八月革命説」によると、ポツダム宣言受諾とともに、我が国において法的な「革命」が起こり、その結果として73条の「改正の限界」は消滅した。よって、「改正の限界」を超える日本国憲法への改正は73条に反するものではなく、『日本国憲法』は大日本帝国憲法の改正として有効である、というのです。
では、この「八月革命説」に批判を加えます。
まず、現実の我が国の歴史上、革命などは起こっていません。革命があったなどというのは単なるウソでしかないのです。こんなものは何の正当化にもなりません。
また、革命とは、国体を破壊し、それを成文化した憲法典をも無視、破壊するものであって、まさに憲法学上は違憲、違法、の行為であるというべきです。すなわち、憲法学上は「革命」などというものは、理論の上では存在する余地はなく、これを援用して理屈づけたものはもはや憲法理論たり得ません。
しかるに、この説においては、その憲法破壊行為であるはずの「革命」を、憲法学に取り入れ、それによって理論を組み立てているのです。「法的に」などという修飾語をつけていますが、革命に法的なものなどあるはずがありません。法的、合法というのならばそれは革命ではないのです。この「法的に」とは何のことはない、ただごまかすための修飾語でしかないのです。
誰がどう見ても大日本帝国憲法の根本原理を完全に逸脱していながら、「改正の限界」を超えていることをごまかし、あくまでも大日本帝国憲法の改正として成立したのだということにするための理屈づけなのです。
しかしながら、その改正の限界の逸脱を、「革命」という憲法学外のものによってしか説明できないというのであれば、それはもはや憲法学ではありません。
「八月革命説」は、それ自体、その理屈づけが憲法学の否定になってしまっているのです。
「八月革命説」は我が国の国体破壊を肯定し、かつて革命があったというウソの上に成り立つものであるばかりか、革命という憲法学外のものを憲法学に取り入れている、もはや憲法理論とはいえないものなのです。
(注1)芦部信喜『憲法』第4版 高橋和之 補訂 p.18
(注2)同上 p.19 ~ p.20
(注3)同上 p.29 ~ p.30
(注4)同上 p.30 ~ p31
今日は、芦部信喜『憲法』(第四版)第二章の「日本憲法史」を採り上げます。
なお、文中においては敬称を省略させて頂きました。何とぞご海容頂きたく存じます。
ランキングに参加しています。まず初めに何卒クリックをお願い致します。
1.大日本帝国憲法の特色の捉え方について
まず、大日本帝国憲法の特色をどのように捉えているか、みてみましょう。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
明治憲法は、立憲主義憲法とは言うものの、神権主義的な君主制の色彩がきわめて強い憲法であった。
・・・(略)・・・まず、主権(この意味について第三章二1参照)が天皇に存することを基本原理とし、この天皇の地位は、天皇の祖先である神の意志に基づくものとされた。「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(一条)とは、この天皇主権の原理を明示したものである。また、天皇は、神の子孫として神格を有するとされ、「神聖ニシテ侵スヘカラス」(三条)と定められた。(注1)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
恐らくは、この記述においては「神権主義」なる言葉は「後進性」「非合理性」を示すマイナスイメージとして使われているのかもしれませんが、まず、大日本帝国憲法の条文を読んでみれば分かることですが、具体的にどの条文をもって大日本帝国憲法が「神権主義」だというのでしょうか。
まず、天皇に「主権」が存在するということ、そして第一条についての解説は明らかに誤りです。
天皇は国体を変革するような権限(主権)を持ったことなどありませんし、第一条は「統治ス」となっているのみです。統治する(しらす)ことと、主権を有することは全く何の関係もありません。一体どこに、「主権」の文字があるというのでしょうか?
また、第三条についての解説も誤りです。
「神聖ニシテ侵スヘカラス」とは、天皇の立憲君主としての側面を捉え、政治への無答責を表現したものです。つまり、天皇は政治には関わらず、また責任を負うことはない、「統治すれども親裁せず」という意味なのです。
神聖、すなわち神の子孫である、という神話的側面の表現ではありません。
大日本帝国憲法には、ここにいうような「神権主義」など欠片もありません。
おそらくは、「告文」にある、「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴二シ典憲ヲ成立シ・・・」などの文言からそのようなイメージを受けるのかもしれませんが、これは明治天皇が皇祖神などの祖先の神々や歴代天皇に対してお誓いになったものであって、これが「神権主義」などというならば、先祖の墓参りをすることや正月に初詣に行くことさえも「神権主義」になってしまいます。
・・・・う~ん、全く・・・次!(苦笑)
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
権利、自由は保障されてはいたものの、それは人間が生まれながらにもっている生来の自然権(人権)を確認するという形のものではなく、天皇が臣民に恩恵として与えたもの(臣民権)であった。各権利が「法律の留保」( Vorbehalt des Gesetzes )をともなうもの、すなわち、「法律の範囲内において」保障されたにすぎず法律によれば制限が可能なもの、であったのは、そのためである。(注2)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーー
「法律の留保」というのは、ドイツのオットー・マイヤー( Otto Mayer, 1846 - 1924 )という学者が立てた法理論です。
法律の留保とは、行政権は、国民の権利や自由に対する制限を恣意的になすことはできず、このような制限は国民の代表機関たる立法府によってなされねばならない、というものです。
つまり、国民の権利や自由を制限することは原則として許されないが、立法府というのは制限される側の国民の代表機関であるから、いわば自分で自分の権利の制限に同意したのに等しいので、立法府が国民の権利や自由を制限することは許されるのだ、といういわゆる「自己統治」の思想に基づいています。
そもそも、この「自己統治」自体が大いにおかしな代物ですが、それはひとまずおくとしても、臣民権が「天皇が臣民に恩恵として与えた権利である」という見解について。
我が国は天皇と臣民との相互の敬愛により、成り立ってきました。一方が義務を果たす代わりに、他方がその見返りとして権利を与える、などという冷たい関係ではありません。
「恩恵として与える」などといえば、どこか「気に入らなければいつでも取り上げてしまう」などという響きが感じられます。しかし、ここに列記されている「臣民の権利」とは、かつてはそのような名称(言論の自由、など)のような呼び名こそなかったものの、我が国の慣習や道徳などの範囲内で歴史的に認められてきた「自由」に他なりません。
もちろん、時代によってその広狭はあり得たでしょうが、一定の範囲内で、武士や庶民はこれらのいわゆる「自由(この言葉もありませんでしたが)」を享受していたのです。
よって、「天皇が臣民に恩恵として与えた」というのも、「歴代天皇陛下が我が国を統治されてきた結果、我が国において培われてきた」権利・自由である、ということなのです。
また、「臣民権」をそのように「いつでも取り上げられるもの」と構成する結果でしょうが、「法律ノ範囲内二於テ」のみ保障されるものということ、すなわち『日本国憲法』上の「基本的人権」に劣るものであるというニュアンスが感じられます。
しかし、ここでいう「臣民権」を「いつでも取り上げられる権利」ではなく、「我が国の道徳や慣習などにおいて歴史的に認められてきた権利」であると解するならば、いくら「法律の範囲内で」との限定をつけようとも、自ずとその「範囲内」には限界が設けられます。
すなわち、ここで保障されている諸権利を、法律の定めさえあればいくらでも制限できる、などというのは全くの誤解、曲解でしかないのです。
法律学的には、「我が国の道徳や慣習などにおいて保障されてきた権利の意義を没却するような形で法律による権利の制限がなされても、その制限は帝国憲法に違反し無効となる」と構成されるのです。
2.八月革命説
さて、憲法学界では通説となっている『日本国憲法』の正当性の根拠として、宮沢俊義により立てられたいわゆる「八月革命説」があります。では、この八月革命説とはどのようなものなのか、見てみましょう。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
次に、日本国憲法と明治憲法との関係が問題となる。すなわち、日本国憲法は、その上諭によると、天皇が明治憲法七三条の改正規定による改正を裁可して公布したということになっており、形式的には、明治憲法の改正として成立したもの(欽定憲法)である。しかし、憲法全文は、「日本国民は、・・・代表者を通じて行動し」、「主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と規定し、日本国民が国民主権の原則に基づいて制定した民定憲法である旨を宣言している。そこで、この矛盾をどのように解するか、とくに、天皇主権を定める明治憲法を国民主権の憲法へと全面的に改正することは、法的に許されないのではないか、という疑問が生ずる。というのは、そもそも、憲法改正規定による憲法改正には一定の限界があり、その憲法の基本原理を改正することは憲法の根本的支柱を取り除くことになってしまうので、それは・・・(略)・・・不可能であると考えられていたからである。(注3)
ーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーー
「天皇主権を定める明治憲法」という誤りを除いては、この箇所は正当です。すなわち、『日本国憲法』は形式上は大日本帝国憲法の改正という体裁をとっているものの、大日本帝国憲法の基本原理を「改正」することはいわゆる「改正の限界」を越えるものであって、不可能であるということなのです。
まさにその通りで、それゆえに、『日本国憲法』の正統性が疑われることとなるのです。
そこで、この点を理論づけようと立てられたのが、「八月革命説」なのです。
では、「八月革命説」とはどんなものなのか、見てみましょう。
ーーーーーーー 以下引用 ーーーーーーー
(1)明治憲法七三条の改正規定によって、明治憲法の基本原理である天皇主権主義と真向から対立する国民主権主義を定めることは、たしかに法的には不可能である。
(2)しかし、ポツダム宣言は国民主権主義をとることを要求しているので、ポツダム宣言を受諾した段階で、明治憲法の天皇主権は否定されるとともに国民主権が成立し、日本の政治体制の根本原理となったと解さなければならない。つまり、ポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命があったとみることができる。
(3)もっとも、この革命によって明治憲法が廃止されたわけではない。その根本建前が変わった結果として、憲法の条文はそのままでも、その意味は、新しい建前に抵触する限り重要な変革をこうむったと解さなければならない。たとえば、明治憲法七三条については、議員も改正の発案権を有するようになったこと、議会の修正権には制限はなくなったこと、天皇の裁可と貴族院の議決は実質的な拘束力を失ったこと、国体を変えることは許されないという制限は消滅したこと、を認めなければならない。
(4)したがって、日本国憲法は、実質的には、明治憲法の改正としてではなく、新たに成立した国民主権主義に基づいて、国民が制定した民定憲法である。ただ、七三条による改正という手続をとることによって明治憲法との間に形式的な継続性をもたせることは、実際上は便宜で適当であった。(注4)
ーーーーーーーー 引用ここまで ーーーーーーー
憲法典には「改正の限界」というものがあります。そして、『日本国憲法』は基本的人権、国民主権などの理性万能思想(左翼思想)を根本精神とするものであり、それが大日本帝国憲法を改正してできたものであるというには、明らかにその「改正の限界」を超えるものであって、改正したものとはいえないというわけです。
ということは、憲法学の理論上は、『日本国憲法』は大日本帝国憲法第73条の「改正の限界」を越えている、すなわち同条に反し、改正は無効である、ということになるのです。『日本国憲法』は無効であるのです。
にもかかわらず、何とかこの違憲、無効な「改正」を正当化できないか、違法を合法化できないか、ということででっちあげられた理屈づけが、この「八月革命説」なのです。
「八月革命説」によると、ポツダム宣言受諾とともに、我が国において法的な「革命」が起こり、その結果として73条の「改正の限界」は消滅した。よって、「改正の限界」を超える日本国憲法への改正は73条に反するものではなく、『日本国憲法』は大日本帝国憲法の改正として有効である、というのです。
では、この「八月革命説」に批判を加えます。
まず、現実の我が国の歴史上、革命などは起こっていません。革命があったなどというのは単なるウソでしかないのです。こんなものは何の正当化にもなりません。
また、革命とは、国体を破壊し、それを成文化した憲法典をも無視、破壊するものであって、まさに憲法学上は違憲、違法、の行為であるというべきです。すなわち、憲法学上は「革命」などというものは、理論の上では存在する余地はなく、これを援用して理屈づけたものはもはや憲法理論たり得ません。
しかるに、この説においては、その憲法破壊行為であるはずの「革命」を、憲法学に取り入れ、それによって理論を組み立てているのです。「法的に」などという修飾語をつけていますが、革命に法的なものなどあるはずがありません。法的、合法というのならばそれは革命ではないのです。この「法的に」とは何のことはない、ただごまかすための修飾語でしかないのです。
誰がどう見ても大日本帝国憲法の根本原理を完全に逸脱していながら、「改正の限界」を超えていることをごまかし、あくまでも大日本帝国憲法の改正として成立したのだということにするための理屈づけなのです。
しかしながら、その改正の限界の逸脱を、「革命」という憲法学外のものによってしか説明できないというのであれば、それはもはや憲法学ではありません。
「八月革命説」は、それ自体、その理屈づけが憲法学の否定になってしまっているのです。
「八月革命説」は我が国の国体破壊を肯定し、かつて革命があったというウソの上に成り立つものであるばかりか、革命という憲法学外のものを憲法学に取り入れている、もはや憲法理論とはいえないものなのです。
(注1)芦部信喜『憲法』第4版 高橋和之 補訂 p.18
(注2)同上 p.19 ~ p.20
(注3)同上 p.29 ~ p.30
(注4)同上 p.30 ~ p31