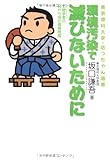未だにずっとトラウマ
6-1、DNAポリメラーゼ
話を1980年代後半に戻すと、その酵素種の精製の過程で奇妙なヌクレアーゼを見つける。これは上記のMus株を用いた実験だった。1980年代の後半である。実はこの研究は痛恨の失敗を犯す。β型と間違えた以上の大失敗を犯す。以後、帰国して後、この失敗は私の大きな教訓となり、院生達の仕事では必ず気をつけるようになるキッカケとなる。
このヌクレアーゼの遺伝子はMus308だった。初めてMus株の遺伝子座を発見したことになる。只、私は1980年代後半の常識に従い、やはり強引に胚からヌクレアーゼ活性で抽出していた。そのヌクレアーゼ活性をMus308の胚が欠いていたのである。そして、このヌクレアーゼ活性は非常に奇妙な性質を示し、その分析に熱中することになる。これがMus308ヌクレアーゼである。ところが、この研究の途中で私は帰国することになる。中断した。
その後を引き継いだアメリカ人が、この遺伝子座はヌクレアーゼにしては非常に変な働きがあるということで見直していた。時は既に1990年代に入っていた(私は理科大にいた)。彼は私のごり押し方式ではなく時代の流れに沿って、このMus308遺伝子のクローニングを先に行った。するとその配列のドメイン解析から、DNAポリメラーゼの可能性があることを発見した。私が大量精製した精製画分が、ヌクレアーゼ活性ばかりでなく強力なDNAポリメラーゼ活性があることが分かる。つまり私の見つけたヌクレアーゼはヌクレアーゼではなく、ヌクレアーゼ活性を併せ持つ巨大なDNAポリメラーゼだったのである(α型もヌクレアーゼ活性を持っている)。しかもこれはどの酵素種とも違う新種だった。後にDNAポリメラーゼθと名付けられている。只、彼等はこの遺伝子からレコンビナント酵素を得ることに失敗し(あまりにも分子量が大きいので、すべてインクルージョンボディになり、生きた状態で得られない)、酵素の実体研究は出来なかった。そこで、このアメリカ人とは後に共同研究を行い、DNAのクロスリンクを修復する際に用いられる修復酵素であることを発見した。この酵素種は今も機能解析が為されている。クロスリンク修復というのは長く(ある意味で現在も)全く未知なる領域だったが、ここから始められることが分かった。そのキー酵素だったのである。θ型はポリメラーゼ種の中でも今後極めて重要な酵素種になる可能性が高い。今後大いに進んでいくだろう。
その時の経緯なども書いた総説が以下のものである。
* 人遺伝病ファンコーニ・アネミアのミトコンドリア・ヌクレアーゼの変異
(医科学応用研究財団研究報告、Vol. 10; 208-212, 1991)
私は若き日からDNAポリメラーゼを大いに研究してきており、ショウジョウバエを用いても最初はそれが主なる研究目標だった。さらにはその画分さえ私が最初に得ていたのである。その私が、これを見逃した。それも今後のDNA修復研究の中で、最も重要と思われるキータンパク質を見逃したのである。時代のドサクサとはいえ、痛恨の極みとしか言いようがない。その理由は時代がタンパク質の強引抽出を出て遺伝子を先に調べる時代に移行しつつあったのに、相変わらず旧式な強引酵素精製に頼っていたせいである。
帰国しても(「絶対に流行などやらんぞ!」という意地もあって)時代を逆行して旧式な方法にかなり執着していた。しかし、さすがに徐々にその方向は放棄していった。1990年代の後半である。ヤケクソでその後は、彼等と同様にDNAポリメラーゼ遺伝子のクローニングを繰り返す。理科大に来てからは、ショウジョウバエからδ型ε型ζ型η型そしてθ型などを取り出した。いずれも完全精製までいっており、生化学的機能解析は終了した。今もって同じ材料から得たDNAポリメラーゼ種で完全精製され、化学的に比較出来るものは、ほぼこれしかないと言える状態である。
これらのDNAポリメラーゼの研究は、学位を出すには格好のテーマだった、幾らでも論文が出来た(気分的にはもう完全に粗製濫造だった。しかし、外部では国際的に高く評価された)。ζ、ηに関しては今もって世界で最も研究が進んでいる状態である。しかしθを見逃したという気分は、私の心底では未だにずっとトラウマになっている。私はもともとそういう敗北感というものは持ったことがなく、人がやらない(馬鹿にする)方向ばかり模索してきたので、やった研究では何事も全て不敗だった。θ以外はその後も現在に至るまでない。やられた!負けた!何を考えていたんだ!という気分に陥ったのは40数年の研究生活の中で、このθだけである。なおかつ残念なのは、このθを見つけたアメリカ人がその後アメリカで成功して一流になってくれれば気も紛れたのだが、成功はこれ一つで、そのおかげで大学教授にはなったが、その後は続かずグラントさえ取れなくなり、あえなくその大学さえ首になったという結末の人物だった。私はそれに負けたのである。
私は学術的に負けた勝ったなど、帰国後は考えたことがない。気分が変わり、学生の養成、学位の授与しか考えなくなったからである。しかし、このθだけは、まだアメリカ時代の残影の記憶があった。そして研究方向の選び方もあり「無敗である」という不敗神話の気分と自信だけは何処かにあった。実は今もある。だからこそ理科大で20年以上、自信満々で学生の訓練が出来たのである。時間内での学位の授与などに不安など抱いたことがなかった。
ヌクレアーゼが話題になった分、θだけは未だにトラウマが抜けない。
つづく
発売中です


話を1980年代後半に戻すと、その酵素種の精製の過程で奇妙なヌクレアーゼを見つける。これは上記のMus株を用いた実験だった。1980年代の後半である。実はこの研究は痛恨の失敗を犯す。β型と間違えた以上の大失敗を犯す。以後、帰国して後、この失敗は私の大きな教訓となり、院生達の仕事では必ず気をつけるようになるキッカケとなる。
このヌクレアーゼの遺伝子はMus308だった。初めてMus株の遺伝子座を発見したことになる。只、私は1980年代後半の常識に従い、やはり強引に胚からヌクレアーゼ活性で抽出していた。そのヌクレアーゼ活性をMus308の胚が欠いていたのである。そして、このヌクレアーゼ活性は非常に奇妙な性質を示し、その分析に熱中することになる。これがMus308ヌクレアーゼである。ところが、この研究の途中で私は帰国することになる。中断した。
その後を引き継いだアメリカ人が、この遺伝子座はヌクレアーゼにしては非常に変な働きがあるということで見直していた。時は既に1990年代に入っていた(私は理科大にいた)。彼は私のごり押し方式ではなく時代の流れに沿って、このMus308遺伝子のクローニングを先に行った。するとその配列のドメイン解析から、DNAポリメラーゼの可能性があることを発見した。私が大量精製した精製画分が、ヌクレアーゼ活性ばかりでなく強力なDNAポリメラーゼ活性があることが分かる。つまり私の見つけたヌクレアーゼはヌクレアーゼではなく、ヌクレアーゼ活性を併せ持つ巨大なDNAポリメラーゼだったのである(α型もヌクレアーゼ活性を持っている)。しかもこれはどの酵素種とも違う新種だった。後にDNAポリメラーゼθと名付けられている。只、彼等はこの遺伝子からレコンビナント酵素を得ることに失敗し(あまりにも分子量が大きいので、すべてインクルージョンボディになり、生きた状態で得られない)、酵素の実体研究は出来なかった。そこで、このアメリカ人とは後に共同研究を行い、DNAのクロスリンクを修復する際に用いられる修復酵素であることを発見した。この酵素種は今も機能解析が為されている。クロスリンク修復というのは長く(ある意味で現在も)全く未知なる領域だったが、ここから始められることが分かった。そのキー酵素だったのである。θ型はポリメラーゼ種の中でも今後極めて重要な酵素種になる可能性が高い。今後大いに進んでいくだろう。
その時の経緯なども書いた総説が以下のものである。
* 人遺伝病ファンコーニ・アネミアのミトコンドリア・ヌクレアーゼの変異
(医科学応用研究財団研究報告、Vol. 10; 208-212, 1991)
私は若き日からDNAポリメラーゼを大いに研究してきており、ショウジョウバエを用いても最初はそれが主なる研究目標だった。さらにはその画分さえ私が最初に得ていたのである。その私が、これを見逃した。それも今後のDNA修復研究の中で、最も重要と思われるキータンパク質を見逃したのである。時代のドサクサとはいえ、痛恨の極みとしか言いようがない。その理由は時代がタンパク質の強引抽出を出て遺伝子を先に調べる時代に移行しつつあったのに、相変わらず旧式な強引酵素精製に頼っていたせいである。
帰国しても(「絶対に流行などやらんぞ!」という意地もあって)時代を逆行して旧式な方法にかなり執着していた。しかし、さすがに徐々にその方向は放棄していった。1990年代の後半である。ヤケクソでその後は、彼等と同様にDNAポリメラーゼ遺伝子のクローニングを繰り返す。理科大に来てからは、ショウジョウバエからδ型ε型ζ型η型そしてθ型などを取り出した。いずれも完全精製までいっており、生化学的機能解析は終了した。今もって同じ材料から得たDNAポリメラーゼ種で完全精製され、化学的に比較出来るものは、ほぼこれしかないと言える状態である。
これらのDNAポリメラーゼの研究は、学位を出すには格好のテーマだった、幾らでも論文が出来た(気分的にはもう完全に粗製濫造だった。しかし、外部では国際的に高く評価された)。ζ、ηに関しては今もって世界で最も研究が進んでいる状態である。しかしθを見逃したという気分は、私の心底では未だにずっとトラウマになっている。私はもともとそういう敗北感というものは持ったことがなく、人がやらない(馬鹿にする)方向ばかり模索してきたので、やった研究では何事も全て不敗だった。θ以外はその後も現在に至るまでない。やられた!負けた!何を考えていたんだ!という気分に陥ったのは40数年の研究生活の中で、このθだけである。なおかつ残念なのは、このθを見つけたアメリカ人がその後アメリカで成功して一流になってくれれば気も紛れたのだが、成功はこれ一つで、そのおかげで大学教授にはなったが、その後は続かずグラントさえ取れなくなり、あえなくその大学さえ首になったという結末の人物だった。私はそれに負けたのである。
私は学術的に負けた勝ったなど、帰国後は考えたことがない。気分が変わり、学生の養成、学位の授与しか考えなくなったからである。しかし、このθだけは、まだアメリカ時代の残影の記憶があった。そして研究方向の選び方もあり「無敗である」という不敗神話の気分と自信だけは何処かにあった。実は今もある。だからこそ理科大で20年以上、自信満々で学生の訓練が出来たのである。時間内での学位の授与などに不安など抱いたことがなかった。
ヌクレアーゼが話題になった分、θだけは未だにトラウマが抜けない。
つづく
発売中です