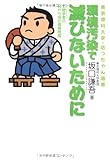多少は「変だな」とは思った
6-1、DNAポリメラーゼ
膨大な量のショウジョウバエの卵(胚)をすり潰し、強引にDNAポリメラーゼ活性のある画分を取り出したら、やはりメジャーなものが2種類引っかかってきた。さらにカラムクロマトで簡単に分離するマイナーな成分も幾つか見つかった。当時の常識では、このマイナー成分はメジャーなものが抽出精製時に壊れた活性部位だけの破片だろうということであった。現在からみれば、これは多くの他の種類のDNAポリメラーゼ種だったのだろうと思われる。DNAポリメラーゼ種はα、β、γの3つしかないと考えられていた時代で、もし各々を精製して違いを報告しようとしたら、たちどころに問題点を指摘されて葬り去られただろう。当時の技術ではこれを精製して分け取り「分解物ではなく新種だ」と確定することは不可能だった。今(2011年)でさえ、遺伝子操作技術を用いてレコンビナント酵素として分取、その機能解析をするのはかなりの難物である。やり手があまりいない。でも今から思うと、そういう状態でも活性が測れるくらいの量はあるんですね、意外です。
さて、メジャーな2つ。片方は典型的なα型だった。もう一つは、明らかにγ型ではなかった。すると残りはβ型しかないことになる。強引に精製した、成功した。ヤケクソに分子量が大きいのである。110 kDa以上あった。1983年頃はまだα型が亜粒子構造を持つということさえ分かっていなかった頃で、単純にそんな巨大なDNAポリメラーゼではβ型というには異常だった。でも生化学的性質の幾つかはβ型に似たところもあった。そこで、ショウジョウバエ型のβ型として発表した(自分でも多少は「変だな」とは思ったが、これをγの次のギリシャ文字を用いて新種とすれば、もっと抵抗が大きくなる)。あっさりと掲載されたばかりでなく、大きな話題を呼ぶ。この時もし、これを新種としてγの次のδと言っておれば、これがδになったに違いない。これは今のδ型とは異なる。
この頃までのショウジョウバエのMus株を用いた私達の研究は、以下の総説にまとめられている。
* A genetics and molecular analysis of DNA repair in Drosophila.
(J. Cell Sci., suppl. 6; 39-60, 1987)
* Analysis of DNA repair in Drosophila.
("DNA repair". A Laboratory manual of research procedures, ed. Friedberg and
Hanawalt、Bekker Inc., 3; 99-113, 1988)
* しょうじょうばえのDNA修復1および2
(遺伝、42(9); 42-45および56-60, 1988)
* DNA metabolizing enzymes of Drosophila.
("The Eukaryotic Nucleus: Molecular Biochemistry and Macromolecular
assemblies" Vol. 1; 293-314, 1989)
* しょうじょうばえ、、この古くて新しい実験動物
(バイオサイエンスとインダストリー、49; 23-27, 1991)
これらいずれもチと古いが、最新の総説は現在執筆中である。比較的新しいがいろいろなものが混じっている総説は以下のものである。
* Evolution and roles of X-family DNA polymerases (a review)
(Biochimie 91: 165-170, 2008)
* 生物進化とX-family DNA ポリメラーゼの役割
(生化学 2008年7月号、第80巻、646-651)
上記の2008年の総説に要約されているが、現在では、ショウジョウバエにはXグループに属する酵素種はないことが確定しており(言い訳になるが、これを証明したのも私達である)、これはβ型ではない(今日の分類では、たぶん、ζ型と考えられる)(ショウジョウバエのζ型自体も私たちが発見した)。これ自体は間違いだったが、これ以後は、真核生物にはDNAポリメラーゼはもっと種類があるらしいということが常識化することになる。
蛇足を付け加えれば、後に明らかになるζ型というのは、ショウジョウバエばかりでなく脊椎動物系にも普遍的に存在する。脊椎動物系ではβ型がXRCC1という補助因子と共に行うショートパッチ塩基除去修復(spBER)(後述)を行う。ところが、β型のないショウジョウバエでは、このζ型が代わって行っている。ζ型の主作用は損傷乗り換え修復(後述)以外はまだ完全には分かっていないが、少なくともspBERへは関与していない。ところがショウジョウバエでは(ショウジョウバエ型に特別に)変型したRCC1(“XRCC1”)と共に、ζ-“XRCC1”複合体となり、β-XRCC1複合体に代わってspBERを行うことが、今日では分かっている。そして、それを発見報告したのも私の研究室である。
これはまだ推定に過ぎないが、spBERあるいはその発展形態が神経の形成と関係がある可能性がある。そして、それにβ型や(ショウジョウバエでは)ζ型が大いに関係しているのかもしれない。後述する。一方、組換え修復に関してはXグループの酵素種の関与はもはや疑うまでもないが、しかし、それは真核生物のほとんどにある現象、特に減数分裂と密接に関係している。それ用は植物ではλ型だった。植物に限らず、ほぼ全ての真核生物からλ型は見つかる。そして、λ型はNHEJの酵素種であることは既に国際的に認定されている。HRもこれであっても全くおかしくないし、実際にλしかない真核生物にもHRはある。組換え修復の中心である相同染色体の組換えはλ型が関係している(βではない)。
つづく
発売中です


膨大な量のショウジョウバエの卵(胚)をすり潰し、強引にDNAポリメラーゼ活性のある画分を取り出したら、やはりメジャーなものが2種類引っかかってきた。さらにカラムクロマトで簡単に分離するマイナーな成分も幾つか見つかった。当時の常識では、このマイナー成分はメジャーなものが抽出精製時に壊れた活性部位だけの破片だろうということであった。現在からみれば、これは多くの他の種類のDNAポリメラーゼ種だったのだろうと思われる。DNAポリメラーゼ種はα、β、γの3つしかないと考えられていた時代で、もし各々を精製して違いを報告しようとしたら、たちどころに問題点を指摘されて葬り去られただろう。当時の技術ではこれを精製して分け取り「分解物ではなく新種だ」と確定することは不可能だった。今(2011年)でさえ、遺伝子操作技術を用いてレコンビナント酵素として分取、その機能解析をするのはかなりの難物である。やり手があまりいない。でも今から思うと、そういう状態でも活性が測れるくらいの量はあるんですね、意外です。
さて、メジャーな2つ。片方は典型的なα型だった。もう一つは、明らかにγ型ではなかった。すると残りはβ型しかないことになる。強引に精製した、成功した。ヤケクソに分子量が大きいのである。110 kDa以上あった。1983年頃はまだα型が亜粒子構造を持つということさえ分かっていなかった頃で、単純にそんな巨大なDNAポリメラーゼではβ型というには異常だった。でも生化学的性質の幾つかはβ型に似たところもあった。そこで、ショウジョウバエ型のβ型として発表した(自分でも多少は「変だな」とは思ったが、これをγの次のギリシャ文字を用いて新種とすれば、もっと抵抗が大きくなる)。あっさりと掲載されたばかりでなく、大きな話題を呼ぶ。この時もし、これを新種としてγの次のδと言っておれば、これがδになったに違いない。これは今のδ型とは異なる。
この頃までのショウジョウバエのMus株を用いた私達の研究は、以下の総説にまとめられている。
* A genetics and molecular analysis of DNA repair in Drosophila.
(J. Cell Sci., suppl. 6; 39-60, 1987)
* Analysis of DNA repair in Drosophila.
("DNA repair". A Laboratory manual of research procedures, ed. Friedberg and
Hanawalt、Bekker Inc., 3; 99-113, 1988)
* しょうじょうばえのDNA修復1および2
(遺伝、42(9); 42-45および56-60, 1988)
* DNA metabolizing enzymes of Drosophila.
("The Eukaryotic Nucleus: Molecular Biochemistry and Macromolecular
assemblies" Vol. 1; 293-314, 1989)
* しょうじょうばえ、、この古くて新しい実験動物
(バイオサイエンスとインダストリー、49; 23-27, 1991)
これらいずれもチと古いが、最新の総説は現在執筆中である。比較的新しいがいろいろなものが混じっている総説は以下のものである。
* Evolution and roles of X-family DNA polymerases (a review)
(Biochimie 91: 165-170, 2008)
* 生物進化とX-family DNA ポリメラーゼの役割
(生化学 2008年7月号、第80巻、646-651)
上記の2008年の総説に要約されているが、現在では、ショウジョウバエにはXグループに属する酵素種はないことが確定しており(言い訳になるが、これを証明したのも私達である)、これはβ型ではない(今日の分類では、たぶん、ζ型と考えられる)(ショウジョウバエのζ型自体も私たちが発見した)。これ自体は間違いだったが、これ以後は、真核生物にはDNAポリメラーゼはもっと種類があるらしいということが常識化することになる。
蛇足を付け加えれば、後に明らかになるζ型というのは、ショウジョウバエばかりでなく脊椎動物系にも普遍的に存在する。脊椎動物系ではβ型がXRCC1という補助因子と共に行うショートパッチ塩基除去修復(spBER)(後述)を行う。ところが、β型のないショウジョウバエでは、このζ型が代わって行っている。ζ型の主作用は損傷乗り換え修復(後述)以外はまだ完全には分かっていないが、少なくともspBERへは関与していない。ところがショウジョウバエでは(ショウジョウバエ型に特別に)変型したRCC1(“XRCC1”)と共に、ζ-“XRCC1”複合体となり、β-XRCC1複合体に代わってspBERを行うことが、今日では分かっている。そして、それを発見報告したのも私の研究室である。
これはまだ推定に過ぎないが、spBERあるいはその発展形態が神経の形成と関係がある可能性がある。そして、それにβ型や(ショウジョウバエでは)ζ型が大いに関係しているのかもしれない。後述する。一方、組換え修復に関してはXグループの酵素種の関与はもはや疑うまでもないが、しかし、それは真核生物のほとんどにある現象、特に減数分裂と密接に関係している。それ用は植物ではλ型だった。植物に限らず、ほぼ全ての真核生物からλ型は見つかる。そして、λ型はNHEJの酵素種であることは既に国際的に認定されている。HRもこれであっても全くおかしくないし、実際にλしかない真核生物にもHRはある。組換え修復の中心である相同染色体の組換えはλ型が関係している(βではない)。
つづく
発売中です