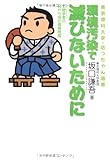個体と突然変異と培養細胞
6、ショウジョウバエのDNA修復の研究
さて、これを開始したのは1983年頃である。私は大学では植物学を専攻し、その後企業では医薬品研究に付随して哺乳動物系の実験をしていたが、このような古典的な昆虫を材料にした遺伝学は初めてだった。ショウジョウバエは遺伝学研究の材料として大変著名な生き物だが、経歴のせいで教科書的な知識のみしかなかった。初めて見たときは、オスメスの区別も分からない有様。もう40歳近くになっていた。でも、そういう年齢的な抑制はなかった。初めてショウジョウバエという材料を用い、昆虫とはこういう特徴があるのだということを知った。興味深かった。
まず驚いたことは、非常に簡単に個体で突然変異株を創れることである。そして創るまでもなく、驚異的な種類と数で既に変異株ストックがあることだった(変異株の系統保存バンクがある。これは他の領域から来た遺伝学者にとっては驚異だった)。時既に40歳近く(科学者としてはもはや中堅の年齢になる)それまでの経験では、植物も哺乳動物も突然変異体を人為的に得るなど考えられなかった。キノコの場合は努力すれば創れたのかもしれないが、それまではほとんど例がなかった(後に私達が人為的に創れる方法を創成した)。ショウジョウバエという材料に驚愕した記憶が今も鮮明である。そのせいだろうが、後の現在に至るまでの私の基礎生物学方面では、出した論文の数が一番多いのもショウジョウバエを用いる領域である。
この個体から変異株を得るというのは、以下に述べるように、後に実は高等動物の遺伝学にとっては決定的に重要であることが分かる。これは、1990年前後くらいからは認識されるようになるが、私が始めたこの時点(1983年)では、まだ全く分かっていなかった。
1980年代は哺乳動物の培養細胞を使う技術が普及し盛んだった。その為、この培養細胞も使って突然変異株をバクテリアのように使いこなせばもう何でも試験管レベルで高等動物が扱えるのではないかという楽観時代だった。大腸菌の分子生物学が分かればもう人間でも何でも分かり見えてくるという言葉がその頃はあった。ちょうどその線に沿った楽観論である。今からみれば陳腐そのもの「アホかいな」という気分だが、それが当時の世界の常識であり中心だった。しかし全世界が1980年代一杯をかけて、失敗を実感する。幾ら変異株を得ても、たちまち元に戻るか他に変異して行ってしまうのである。安定して維持出来ないのである。当然である、培養すること自体が細胞に取って特殊な環境で、そこに適合するために変異を続けており、落ち着かないのである。物凄い費用と10年という時間をかけて分かったことは、「個体が突然変異株でそこから分取した培養細胞なら、安定的に元の変異した性質をずっと維持するが、しかし、培養細胞になってから得た変異の性質は全く維持出来ない、ダメ」ということだった。まず、個体で突然変異株を得なければ遺伝学にならないのである。人や哺乳動物では遺伝病患者から得た細胞以外は使い物にならなかった。
微生物学で汎用された方法が全く通じないのである。単細胞の原核生物のごとく、人為的な突然変異株が作成出来ねば、生化学研究は出来ても、分子生物学にはならないのである。このため、単細胞の真核生物が材料として最も注目されることになる。いわゆる“酵母”時代である。
つづく
発売中です


さて、これを開始したのは1983年頃である。私は大学では植物学を専攻し、その後企業では医薬品研究に付随して哺乳動物系の実験をしていたが、このような古典的な昆虫を材料にした遺伝学は初めてだった。ショウジョウバエは遺伝学研究の材料として大変著名な生き物だが、経歴のせいで教科書的な知識のみしかなかった。初めて見たときは、オスメスの区別も分からない有様。もう40歳近くになっていた。でも、そういう年齢的な抑制はなかった。初めてショウジョウバエという材料を用い、昆虫とはこういう特徴があるのだということを知った。興味深かった。
まず驚いたことは、非常に簡単に個体で突然変異株を創れることである。そして創るまでもなく、驚異的な種類と数で既に変異株ストックがあることだった(変異株の系統保存バンクがある。これは他の領域から来た遺伝学者にとっては驚異だった)。時既に40歳近く(科学者としてはもはや中堅の年齢になる)それまでの経験では、植物も哺乳動物も突然変異体を人為的に得るなど考えられなかった。キノコの場合は努力すれば創れたのかもしれないが、それまではほとんど例がなかった(後に私達が人為的に創れる方法を創成した)。ショウジョウバエという材料に驚愕した記憶が今も鮮明である。そのせいだろうが、後の現在に至るまでの私の基礎生物学方面では、出した論文の数が一番多いのもショウジョウバエを用いる領域である。
この個体から変異株を得るというのは、以下に述べるように、後に実は高等動物の遺伝学にとっては決定的に重要であることが分かる。これは、1990年前後くらいからは認識されるようになるが、私が始めたこの時点(1983年)では、まだ全く分かっていなかった。
1980年代は哺乳動物の培養細胞を使う技術が普及し盛んだった。その為、この培養細胞も使って突然変異株をバクテリアのように使いこなせばもう何でも試験管レベルで高等動物が扱えるのではないかという楽観時代だった。大腸菌の分子生物学が分かればもう人間でも何でも分かり見えてくるという言葉がその頃はあった。ちょうどその線に沿った楽観論である。今からみれば陳腐そのもの「アホかいな」という気分だが、それが当時の世界の常識であり中心だった。しかし全世界が1980年代一杯をかけて、失敗を実感する。幾ら変異株を得ても、たちまち元に戻るか他に変異して行ってしまうのである。安定して維持出来ないのである。当然である、培養すること自体が細胞に取って特殊な環境で、そこに適合するために変異を続けており、落ち着かないのである。物凄い費用と10年という時間をかけて分かったことは、「個体が突然変異株でそこから分取した培養細胞なら、安定的に元の変異した性質をずっと維持するが、しかし、培養細胞になってから得た変異の性質は全く維持出来ない、ダメ」ということだった。まず、個体で突然変異株を得なければ遺伝学にならないのである。人や哺乳動物では遺伝病患者から得た細胞以外は使い物にならなかった。
微生物学で汎用された方法が全く通じないのである。単細胞の原核生物のごとく、人為的な突然変異株が作成出来ねば、生化学研究は出来ても、分子生物学にはならないのである。このため、単細胞の真核生物が材料として最も注目されることになる。いわゆる“酵母”時代である。
つづく
発売中です