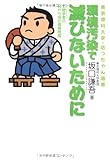ハエ君、ありがとう。
5-2、DNA修復因子
このような背景があったため、私が上記のような分野を始めた頃は何をやっても例がなく新しかったのである。その当時は私がこういう話をどのように主張しても無視された。私が天才的な才能の持ち主だったのではなく、天下の秀才達が“蔑まれた”“ちっこいちっこいマイナーな”領域などやりたくなかったせいである。このような話をしても、秀才達のほとんど全部が「フーン、そういうこともあるね。“面白そうだね”(鼻であしらう小馬鹿にした響きを伴う)、頑張ってやりなさいよ」というような反応だった。アメリカやカナダでも同じでしたね。
進歩の過程から見ても分子系の化学屋が優先しており、バクテリアや哺乳動物以外の生物屋は遥かに取り残されていた。化学屋にとっては複雑な高等生物をやることは遥かなる異分野だった。述べたように私は最初から分子生物学のスペシャリストのような訓練を受けた。そして、その下らなさを非常に感じて、徐々に顕微鏡系の形態学(いわゆる古典的な基礎生物学)に入って行った。人とは通常の逆のコースを進んだ。そのため最初から高等生物系それも何の役に立ちそうもない基礎生物系の材料に入って行ったのである。“ちっこいちっこいマイナーな”領域に興味が行った。基礎生物学上は、そこに起きる生物現象の説明が最も優先されるべきだ、と信じていた。
だから、私は何の疑いもなく早くからそこに入って行ったのである。只、それだけのことであった。ところが時代が少々早すぎた。1990年でさえ、徐々に煮詰まってきていたとはいえ、まだまだその時代ではなかった(その頃でさえ、たぶんアメリカでは5年程度、そして日本なら10年程度、早すぎた)。無視されるどころか研究費が全く当らないのである。そのためますますお金がかからない材料に流れて行くことになる。そして過去の生物学で大いに活用されてきたデータの利用である。なるべく楽してお金をかけず簡単に結論を得ようと言う訳である。学位さえ与えられれば良い!という割り切りもハッキリしていた。
ショウジョウバエの私の研究のスタートはこういうことであった。述べたように私は植物学出身である。とうとう動物の世界に足を踏み込んだ。実は哺乳動物は会社の中で早くから各種のもの(マウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌなど)を用い、また、その培養細胞は自由に使っていた。人の培養細胞もお手の物だった。なお、私はショウジョウバエの培養細胞も用いていたが、当時(1990年代)の日本で昆虫の培養細胞を用いている研究室は限りなくゼロ(たぶん、我々だけ)に近かった。その日本の後進性は驚くべき話である。理由は簡単である。教員が年功序列で高齢化しても代謝が遅くなかなか代わらないので、時代についていけないのである。特に1980~1990年代は高等生物領域で時代の変化が著しかった(日本の大学の高齢者のほとんどが微生物の分子生物学者だった)ので、こうなったのである。
しかし奇妙なことにそういう医学的薬学的研究の場合は、植物から来ようが動物からだろうと化学からだろうと誰も不思議に思わなかった。いわゆる応用研究という意識が強いせいだろう。ところが基礎生物学の世界になると非常に厳然とした境というか壁があった。植物学出身者がショウジョウバエの遺伝学に入るなど奇妙な印象だった。無い訳ではなかったが、特に私の場合はもう中年に近くなってからの転向で驚かれた。その私が昆虫を使うだけでなく、日本の昆虫の遺伝学者や生化学者がまだ誰も用いていなかった昆虫の細胞の培養を只一人やっていたのだから呆れた話である。
ただ、これは日本の中の話でアメリカではそんな垣根はゼロだった。そして私が転向したのはアメリカ時代の話である。だから可能だったので、日本だったら不可能だったろう。昆虫の培養細胞もアメリカ時代から使っていた。
実は細胞の培養というのは非常に費用のかかる実験なのだが、それは哺乳動物などでは培地に牛の胎児血清がいるからである(胎児の血清!非常に高価である)。そしてプライマリーカルチャーという動物から直接取り出した組織の培養は非常に困難だった(ある程度、細胞分裂すると増えなくなる)。ところがショウジョウバエの細胞培養には血清は不要で、極めて安価だった。かつ、いくらでもプライマリーカルチャーが可能あった。極端なことを言うと、生きたショウジョウバエの突然変異株を創ったり(あるいは貰い受けたり)すると、そのままそこから細胞を取り出すと、それで既に変異株の細胞が得られた。哺乳動物では考えられないことである。
キノコのときもそうだったが、昆虫にもこのような大いなる利点があった。にもかかわらず、国際的に、基礎生物学は流行している方向しか誰も興味を示さない傾向にあった。何故だかよく分からない。そうでなくとも研究費が不足する分野なのに(儲からないものに投資する人などいない。国だって同じである)、金のかかる皆がやる流行ばかりに走るのである。
もちろん私に取っては好都合だった。思う壷である上に、甘い汁を密かに吸った後でも何時までもライバルが非常に出来にくいのである。そして、何よりもましだったのはショウジョウバエを用いる限り、馬糞キノコよりは自分たちの研究の存在感を認めてもらえるのである。つまり学会の中で市民権があるのである。理由は簡単、昔から遺伝学の材料としてアメリカでは極めて重要視されてきており(モルガンやマラーの母国である)、日本でもそれを学んで持ち帰った者は多く、主流派の材料だったからである。ただし、その分子生物学は国際的にもあまりなかった。私の始めた1980年代には全くなかった。帰国した1990年には日本には当然だが全くなかった。主流な材料であるのにないのである。たちまち、私の研究室はショウジョウバエの遺伝学領域では代表的研究室の扱いになる。なにしろ昆虫細胞の培養(!)が出来るのである。そして2012年の今でも坂口と言えば、ショウジョウバエの分子遺伝学者というのが基礎生物学の世界では一番通りが良い(私、大学は“植物学”専攻だったんですよ)。
ハエ君、ありがとう。私の人生に付き合ってくれて!
つづく
発売中です


このような背景があったため、私が上記のような分野を始めた頃は何をやっても例がなく新しかったのである。その当時は私がこういう話をどのように主張しても無視された。私が天才的な才能の持ち主だったのではなく、天下の秀才達が“蔑まれた”“ちっこいちっこいマイナーな”領域などやりたくなかったせいである。このような話をしても、秀才達のほとんど全部が「フーン、そういうこともあるね。“面白そうだね”(鼻であしらう小馬鹿にした響きを伴う)、頑張ってやりなさいよ」というような反応だった。アメリカやカナダでも同じでしたね。
進歩の過程から見ても分子系の化学屋が優先しており、バクテリアや哺乳動物以外の生物屋は遥かに取り残されていた。化学屋にとっては複雑な高等生物をやることは遥かなる異分野だった。述べたように私は最初から分子生物学のスペシャリストのような訓練を受けた。そして、その下らなさを非常に感じて、徐々に顕微鏡系の形態学(いわゆる古典的な基礎生物学)に入って行った。人とは通常の逆のコースを進んだ。そのため最初から高等生物系それも何の役に立ちそうもない基礎生物系の材料に入って行ったのである。“ちっこいちっこいマイナーな”領域に興味が行った。基礎生物学上は、そこに起きる生物現象の説明が最も優先されるべきだ、と信じていた。
だから、私は何の疑いもなく早くからそこに入って行ったのである。只、それだけのことであった。ところが時代が少々早すぎた。1990年でさえ、徐々に煮詰まってきていたとはいえ、まだまだその時代ではなかった(その頃でさえ、たぶんアメリカでは5年程度、そして日本なら10年程度、早すぎた)。無視されるどころか研究費が全く当らないのである。そのためますますお金がかからない材料に流れて行くことになる。そして過去の生物学で大いに活用されてきたデータの利用である。なるべく楽してお金をかけず簡単に結論を得ようと言う訳である。学位さえ与えられれば良い!という割り切りもハッキリしていた。
ショウジョウバエの私の研究のスタートはこういうことであった。述べたように私は植物学出身である。とうとう動物の世界に足を踏み込んだ。実は哺乳動物は会社の中で早くから各種のもの(マウス、ラット、モルモット、ウサギ、イヌなど)を用い、また、その培養細胞は自由に使っていた。人の培養細胞もお手の物だった。なお、私はショウジョウバエの培養細胞も用いていたが、当時(1990年代)の日本で昆虫の培養細胞を用いている研究室は限りなくゼロ(たぶん、我々だけ)に近かった。その日本の後進性は驚くべき話である。理由は簡単である。教員が年功序列で高齢化しても代謝が遅くなかなか代わらないので、時代についていけないのである。特に1980~1990年代は高等生物領域で時代の変化が著しかった(日本の大学の高齢者のほとんどが微生物の分子生物学者だった)ので、こうなったのである。
しかし奇妙なことにそういう医学的薬学的研究の場合は、植物から来ようが動物からだろうと化学からだろうと誰も不思議に思わなかった。いわゆる応用研究という意識が強いせいだろう。ところが基礎生物学の世界になると非常に厳然とした境というか壁があった。植物学出身者がショウジョウバエの遺伝学に入るなど奇妙な印象だった。無い訳ではなかったが、特に私の場合はもう中年に近くなってからの転向で驚かれた。その私が昆虫を使うだけでなく、日本の昆虫の遺伝学者や生化学者がまだ誰も用いていなかった昆虫の細胞の培養を只一人やっていたのだから呆れた話である。
ただ、これは日本の中の話でアメリカではそんな垣根はゼロだった。そして私が転向したのはアメリカ時代の話である。だから可能だったので、日本だったら不可能だったろう。昆虫の培養細胞もアメリカ時代から使っていた。
実は細胞の培養というのは非常に費用のかかる実験なのだが、それは哺乳動物などでは培地に牛の胎児血清がいるからである(胎児の血清!非常に高価である)。そしてプライマリーカルチャーという動物から直接取り出した組織の培養は非常に困難だった(ある程度、細胞分裂すると増えなくなる)。ところがショウジョウバエの細胞培養には血清は不要で、極めて安価だった。かつ、いくらでもプライマリーカルチャーが可能あった。極端なことを言うと、生きたショウジョウバエの突然変異株を創ったり(あるいは貰い受けたり)すると、そのままそこから細胞を取り出すと、それで既に変異株の細胞が得られた。哺乳動物では考えられないことである。
キノコのときもそうだったが、昆虫にもこのような大いなる利点があった。にもかかわらず、国際的に、基礎生物学は流行している方向しか誰も興味を示さない傾向にあった。何故だかよく分からない。そうでなくとも研究費が不足する分野なのに(儲からないものに投資する人などいない。国だって同じである)、金のかかる皆がやる流行ばかりに走るのである。
もちろん私に取っては好都合だった。思う壷である上に、甘い汁を密かに吸った後でも何時までもライバルが非常に出来にくいのである。そして、何よりもましだったのはショウジョウバエを用いる限り、馬糞キノコよりは自分たちの研究の存在感を認めてもらえるのである。つまり学会の中で市民権があるのである。理由は簡単、昔から遺伝学の材料としてアメリカでは極めて重要視されてきており(モルガンやマラーの母国である)、日本でもそれを学んで持ち帰った者は多く、主流派の材料だったからである。ただし、その分子生物学は国際的にもあまりなかった。私の始めた1980年代には全くなかった。帰国した1990年には日本には当然だが全くなかった。主流な材料であるのにないのである。たちまち、私の研究室はショウジョウバエの遺伝学領域では代表的研究室の扱いになる。なにしろ昆虫細胞の培養(!)が出来るのである。そして2012年の今でも坂口と言えば、ショウジョウバエの分子遺伝学者というのが基礎生物学の世界では一番通りが良い(私、大学は“植物学”専攻だったんですよ)。
ハエ君、ありがとう。私の人生に付き合ってくれて!
つづく
発売中です