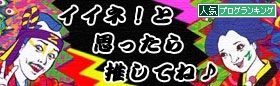【幕が上がる考察】小説と違う映画の素晴らしさ
<長文警報>
公開からもうすぐ一月。そろそろ「幕が上がる」について深く書いてこうかな。
ももクロちゃんにしか興味無くて、映画はどうでもいい人には面白くない記事です。
そういう人や、まだ映画見てない人はブラウザバックでお願いします。
さて、今回は映画と原作の違いについて語りたいと思います。

この映画版「幕が上がる」は原作から、設定やら話の流れやらキャラクターやら、
結構多くの変更点がある映画だと思います。
そしてそれは概ね上手くいき、素晴らしい映画になってるとは前にも書きました。
しかし、この映画版では原作から改変され、ボリュームダウンした部分があるのも事実。
特に、映画では原作で深く書かれている、
さおりの演出家としての成長、地区大会の失敗からのリカバリー、
銀河鉄道の夜の脚本を完成させて行く過程などの、演劇の細かい部分がバッサリと省かれている。
その辺を残念だとレビューを書いてる人も多くいました。
ただ私は、映画化においてはそれも仕方ないかなと思っています。
スキル的な部分を描こうとすれば説明的なセリフが多くなるし、
どうしても、批判的な意見の多かったさおりのモノローグを、更に多用する事になる。
そうなれば映画のテンポ自体が悪くなってしまいますし、2時間という尺に収めるのは難しくなるでしょう。
長くなればなるほど、演劇に興味が薄い層には、かなり退屈な映画になる危険性をはらみます。
なので映画ではその辺を軽く扱ってしまうのは仕方がない事です。
では、この映画版「幕が上がる」は、原作の小説版「幕が上がる」に比べると、
劣っているのかと言えばそんな事はありません。
むしろ映画化する事によって、小説版よりも優れた部分も多くあるのです。
この映画は、演劇のスキルアップ部分は大幅に省きましたが、
これだけだと物語の内容が小説より薄くなってしまう。
そこで脚本の喜安浩平さんは、その代わりに主人公さおりの精神的成長面に重きをおき、
より彼女と部員、先生のキャラクターを掘り下げ、大きな感動を巻き起こすことに成功しました。
そうするために、喜安氏はとある策をろうしていると考えられます。
映画版ではとあるキャラクターの設定が、原作から大きく改変されているのです。
それが主人公の高橋さおり。
原作のさおりは、吉岡先生との出会いによって大きく成長するものの、
実はその前からスーパー演劇部部長としての片鱗を見せています。
ゆっこやガルルから部長に勧められても、すんなり引き受けているし、
部員たちの特性を活かした演出を見事に施し、
新入生オリエンテーションの舞台を成功させ、多くの新入生部員の勧誘に成功しました。
その舞台を見ていた吉岡先生は、副顧問の依頼を受けた際に、
「ちっちゃいな目標、行こうよ全国大会」と、映画中盤のセリフをあっさりと言ってしまいます。
中西さんも、さおりの力を出会って早い段階から見抜き、自然と打ち解けます。
映画とは違い、全国大会を見に行くことを誘うのも中西さんの方からです。
なので部長になることを拒み、新入生オリエンテーションの舞台も失敗し、
自信を喪失して部長を辞めたいと思う、映画版のさおりとは偉い違いなのです。
つまり、映画でのさおりを小説版よりも有能には描かず、
むしろ自分に自信がもてない、コンプレックスのある存在として描くことにより、
より吉岡先生と出会ってからの心の成長を、大きく感じさせる作りになっているのです。
そしてそのような改変をすることによって、
映画では物語を、よりドラマチックに描くことに成功していると言えるでしょう。
小説版のさおりは、吉岡先生が辞めるという話を聞いた時、
もちろんショックは受けるのだけれども、映画版のように泣きながら立ち尽くすような事はない。
翌日には気丈に振る舞って、その後も部長としてやるべき事を果たしつつ、全国を目指します。
しかし映画版のさおりにとっては、吉岡先生は自分を救ってくれた神様と言える存在です。
彼女に裏切られる事は、さおりにとって天に見放された気分でしょう。
吉岡先生の手紙が読み上げられている時の表情を見れば、それは読み取ることができます。
しかし自分のつけてきた演出ノートと、滝田先生の言葉を受けて彼女は立ち直り、
映画のクライマックスともいえる、部員たちへの演説シーンへと繋がります。
このシーンで話すことは、この「幕が上がる」の主題ともいえる物。
小説ではこれを、さおりが部員たちの舞台を見ながら心のなかで悟ることで、
実際に言葉に表して、人に語ることはありません。
映画ではそれをさおり自らが部員たちへ語り、
吉岡先生を失い、呆然としている部員たちを結束させる、感動的なシーンとなっています。
これはさおりの実力を、原作より弱めに設定したことにより、彼女の成長を強調し、
吉岡先生への依存度を高めていたからこそ生まれた、原作を超える名シーンと言えるのです。
更にこの、さおりというキャラクター改変によって、
吉岡先生をも、小説版よりも魅力的に描く結果になっていると思います。
さおりが吉岡先生に言うセリフに、こんな物があります。
「責任なんて、とってもらわなくていいです。
私達の人生なんで。」
原作小説では、このセリフが発せられるのは、肖像画の公演が大成功し、
3年生だけ美術室に呼ばれて、ブロック大会に行けた場合の進路の話をした時です。
「人生変えちゃうかもしれないし、責任をもてない」
そう言った吉岡先生のあとに、さおりはほぼ即答しているのである。
これは小説版のさおりが、やはり早い段階で成熟した演劇部部長だからこそ、あり得る展開と言えます。
しかし映画版のさおりは、この時まだ演劇の楽しさに感化され始めたばかりの頃。
先生の問いかけに、即答することは出来ないでいました。
その問に答えを出せるのは、夏合宿の稽古が終わった後。
台本を書き終え、先生や部員たちからも評価を得て、稽古にも手応えを感じられた。
だからこそようやく、自信をもって答える事が出来たのでしょう。
この答えを言うタイミングがズレた事は、
吉岡先生の印象を大きく変える副作用を生んでいると思います。
小説版の吉岡先生は、合宿の辺りからそれを匂わす伏線はあるものの、
唐突に学校をやめるという展開が訪れます。
部員達の姿を見ることで感化されたと手紙には書いてあるけど、
ある意味とてもドライで、冷たい印象の去り方をしているのです。
だから辞めた後は、少しだけ彼女に触れる部分は有るものの、ほぼ物語に絡む事はない。
さおりとの繋がりが映画版程の強さがないため、
彼女の存在がその後膨らむような展開は特にありません。
しかし映画版だと、その印象は大きく変わってきます。
合宿終了、つまりは吉岡先生がオーディションに誘われた直後に、
さおりの「責任を取らなくていい、私達の人生なんで」という言葉を聞く。
その言葉は「女優としての人生」を諦めていた彼女にとって、
強烈なまでに胸に突き刺さり、感化された事は想像に固くありません。
なのでやはり、彼女が辞めることに唐突さはあるのだけど、
小説版ほどの冷たさを感じることは和らいでいるし、彼女の思惑も理解できる。
これがこの映画、幕が上がるのフィナーレを感動的にする伏線へとつながるのです。
映画版の最後のシーンは県大会の舞台の幕が上がるシーン、
そこには自信あふれるさおりと、部員たちの姿が映し出されると同時に、
初舞台に望む吉岡先生の稽古のシーンがかぶせられ、
さおりが演出ノートに書いた、読まれることのない先生への手紙がモノローグとして流れます。
1人の自立した人間として、表現者として、届くことのない「宇宙の果て」を目指す決意を語る高橋さおり。
それは愛すべき部員たちを捨て、同じく女優として宇宙の果てを目指しはじめた、
吉岡美佐子の姿にも重なっているのです。
宇宙の果てを目指すのは高橋さおりだけではなく、吉岡美佐子でもあるというダブルミーニング。
それがこの映画「幕が上がる」の結末を、より美しく、感動的なものに仕上げている。
さらに一度夢を諦めた吉岡美佐子が再び夢を追う姿が、
夢を諦めた我々大人達の心を、小説版よりも大きく突き動かすように、私は感じます。
このように、映画には小説版とは違ったキャラクター設定にすることで、
短時間で原作とは少し違った感動を味わえる、
とてもドラマチックな内容に仕上げる事に成功していると言えるでしょう。
起伏の少ないこの物語をこのような形に変えた脚本家、喜安浩平氏の力は本当に素晴らしいです。
この映画の成功の半分は、この人のおかげと言って過言ではないかもしれません。
これにももクロの5人と黒木華の名演、菅野祐悟氏のサントラ、本広克行監督の演出が加わることで、
素晴らしい映画として完成出来たのではないでしょうか。
私はこの映画版「幕が上がる」を、小説版に劣らない傑作と胸を張って断言できます。
ちなみに、劇中で演劇についての成長を、全く描いていない訳ではありません。
滝田先生の授業中に、さおりが演出ノートに、
イマイチだった銀河鉄道の夜のラスト部分を書き換えるアイディアを書いていたりするし、
ラスト付近での稽古では地区大会と違い、実際に書き換えられた方の台本で劇部が演じています。
それから地区大会での失敗の起点となったガルルと明美ちゃんの接触を防ぐため、
県大会での舞台では入り順が「明美→ガルル」から「ガルル→明美」になっていたり、
細かい所で修正が加えられていた事が匂わされています。
これは私が現時点で、8回もこの映画を見ているから気づいた小ネタです。
この映画は、そう言った細部までこだわって作られているんですね。
映画を一度見た皆さんも、是非ふたたび一度映画館に足を運んで、
ももクロちゃん達の名演と、製作者達のこだわりを、堪能してみては如何でしょうか。
公開からもうすぐ一月。そろそろ「幕が上がる」について深く書いてこうかな。
ももクロちゃんにしか興味無くて、映画はどうでもいい人には面白くない記事です。
そういう人や、まだ映画見てない人はブラウザバックでお願いします。
さて、今回は映画と原作の違いについて語りたいと思います。

この映画版「幕が上がる」は原作から、設定やら話の流れやらキャラクターやら、
結構多くの変更点がある映画だと思います。
そしてそれは概ね上手くいき、素晴らしい映画になってるとは前にも書きました。
しかし、この映画版では原作から改変され、ボリュームダウンした部分があるのも事実。
特に、映画では原作で深く書かれている、
さおりの演出家としての成長、地区大会の失敗からのリカバリー、
銀河鉄道の夜の脚本を完成させて行く過程などの、演劇の細かい部分がバッサリと省かれている。
その辺を残念だとレビューを書いてる人も多くいました。
ただ私は、映画化においてはそれも仕方ないかなと思っています。
スキル的な部分を描こうとすれば説明的なセリフが多くなるし、
どうしても、批判的な意見の多かったさおりのモノローグを、更に多用する事になる。
そうなれば映画のテンポ自体が悪くなってしまいますし、2時間という尺に収めるのは難しくなるでしょう。
長くなればなるほど、演劇に興味が薄い層には、かなり退屈な映画になる危険性をはらみます。
なので映画ではその辺を軽く扱ってしまうのは仕方がない事です。
では、この映画版「幕が上がる」は、原作の小説版「幕が上がる」に比べると、
劣っているのかと言えばそんな事はありません。
むしろ映画化する事によって、小説版よりも優れた部分も多くあるのです。
この映画は、演劇のスキルアップ部分は大幅に省きましたが、
これだけだと物語の内容が小説より薄くなってしまう。
そこで脚本の喜安浩平さんは、その代わりに主人公さおりの精神的成長面に重きをおき、
より彼女と部員、先生のキャラクターを掘り下げ、大きな感動を巻き起こすことに成功しました。
そうするために、喜安氏はとある策をろうしていると考えられます。
映画版ではとあるキャラクターの設定が、原作から大きく改変されているのです。
それが主人公の高橋さおり。
原作のさおりは、吉岡先生との出会いによって大きく成長するものの、
実はその前からスーパー演劇部部長としての片鱗を見せています。
ゆっこやガルルから部長に勧められても、すんなり引き受けているし、
部員たちの特性を活かした演出を見事に施し、
新入生オリエンテーションの舞台を成功させ、多くの新入生部員の勧誘に成功しました。
その舞台を見ていた吉岡先生は、副顧問の依頼を受けた際に、
「ちっちゃいな目標、行こうよ全国大会」と、映画中盤のセリフをあっさりと言ってしまいます。
中西さんも、さおりの力を出会って早い段階から見抜き、自然と打ち解けます。
映画とは違い、全国大会を見に行くことを誘うのも中西さんの方からです。
なので部長になることを拒み、新入生オリエンテーションの舞台も失敗し、
自信を喪失して部長を辞めたいと思う、映画版のさおりとは偉い違いなのです。
つまり、映画でのさおりを小説版よりも有能には描かず、
むしろ自分に自信がもてない、コンプレックスのある存在として描くことにより、
より吉岡先生と出会ってからの心の成長を、大きく感じさせる作りになっているのです。
そしてそのような改変をすることによって、
映画では物語を、よりドラマチックに描くことに成功していると言えるでしょう。
小説版のさおりは、吉岡先生が辞めるという話を聞いた時、
もちろんショックは受けるのだけれども、映画版のように泣きながら立ち尽くすような事はない。
翌日には気丈に振る舞って、その後も部長としてやるべき事を果たしつつ、全国を目指します。
しかし映画版のさおりにとっては、吉岡先生は自分を救ってくれた神様と言える存在です。
彼女に裏切られる事は、さおりにとって天に見放された気分でしょう。
吉岡先生の手紙が読み上げられている時の表情を見れば、それは読み取ることができます。
しかし自分のつけてきた演出ノートと、滝田先生の言葉を受けて彼女は立ち直り、
映画のクライマックスともいえる、部員たちへの演説シーンへと繋がります。
このシーンで話すことは、この「幕が上がる」の主題ともいえる物。
小説ではこれを、さおりが部員たちの舞台を見ながら心のなかで悟ることで、
実際に言葉に表して、人に語ることはありません。
映画ではそれをさおり自らが部員たちへ語り、
吉岡先生を失い、呆然としている部員たちを結束させる、感動的なシーンとなっています。
これはさおりの実力を、原作より弱めに設定したことにより、彼女の成長を強調し、
吉岡先生への依存度を高めていたからこそ生まれた、原作を超える名シーンと言えるのです。
更にこの、さおりというキャラクター改変によって、
吉岡先生をも、小説版よりも魅力的に描く結果になっていると思います。
さおりが吉岡先生に言うセリフに、こんな物があります。
「責任なんて、とってもらわなくていいです。
私達の人生なんで。」
原作小説では、このセリフが発せられるのは、肖像画の公演が大成功し、
3年生だけ美術室に呼ばれて、ブロック大会に行けた場合の進路の話をした時です。
「人生変えちゃうかもしれないし、責任をもてない」
そう言った吉岡先生のあとに、さおりはほぼ即答しているのである。
これは小説版のさおりが、やはり早い段階で成熟した演劇部部長だからこそ、あり得る展開と言えます。
しかし映画版のさおりは、この時まだ演劇の楽しさに感化され始めたばかりの頃。
先生の問いかけに、即答することは出来ないでいました。
その問に答えを出せるのは、夏合宿の稽古が終わった後。
台本を書き終え、先生や部員たちからも評価を得て、稽古にも手応えを感じられた。
だからこそようやく、自信をもって答える事が出来たのでしょう。
この答えを言うタイミングがズレた事は、
吉岡先生の印象を大きく変える副作用を生んでいると思います。
小説版の吉岡先生は、合宿の辺りからそれを匂わす伏線はあるものの、
唐突に学校をやめるという展開が訪れます。
部員達の姿を見ることで感化されたと手紙には書いてあるけど、
ある意味とてもドライで、冷たい印象の去り方をしているのです。
だから辞めた後は、少しだけ彼女に触れる部分は有るものの、ほぼ物語に絡む事はない。
さおりとの繋がりが映画版程の強さがないため、
彼女の存在がその後膨らむような展開は特にありません。
しかし映画版だと、その印象は大きく変わってきます。
合宿終了、つまりは吉岡先生がオーディションに誘われた直後に、
さおりの「責任を取らなくていい、私達の人生なんで」という言葉を聞く。
その言葉は「女優としての人生」を諦めていた彼女にとって、
強烈なまでに胸に突き刺さり、感化された事は想像に固くありません。
なのでやはり、彼女が辞めることに唐突さはあるのだけど、
小説版ほどの冷たさを感じることは和らいでいるし、彼女の思惑も理解できる。
これがこの映画、幕が上がるのフィナーレを感動的にする伏線へとつながるのです。
映画版の最後のシーンは県大会の舞台の幕が上がるシーン、
そこには自信あふれるさおりと、部員たちの姿が映し出されると同時に、
初舞台に望む吉岡先生の稽古のシーンがかぶせられ、
さおりが演出ノートに書いた、読まれることのない先生への手紙がモノローグとして流れます。
1人の自立した人間として、表現者として、届くことのない「宇宙の果て」を目指す決意を語る高橋さおり。
それは愛すべき部員たちを捨て、同じく女優として宇宙の果てを目指しはじめた、
吉岡美佐子の姿にも重なっているのです。
宇宙の果てを目指すのは高橋さおりだけではなく、吉岡美佐子でもあるというダブルミーニング。
それがこの映画「幕が上がる」の結末を、より美しく、感動的なものに仕上げている。
さらに一度夢を諦めた吉岡美佐子が再び夢を追う姿が、
夢を諦めた我々大人達の心を、小説版よりも大きく突き動かすように、私は感じます。
このように、映画には小説版とは違ったキャラクター設定にすることで、
短時間で原作とは少し違った感動を味わえる、
とてもドラマチックな内容に仕上げる事に成功していると言えるでしょう。
起伏の少ないこの物語をこのような形に変えた脚本家、喜安浩平氏の力は本当に素晴らしいです。
この映画の成功の半分は、この人のおかげと言って過言ではないかもしれません。
これにももクロの5人と黒木華の名演、菅野祐悟氏のサントラ、本広克行監督の演出が加わることで、
素晴らしい映画として完成出来たのではないでしょうか。
私はこの映画版「幕が上がる」を、小説版に劣らない傑作と胸を張って断言できます。
ちなみに、劇中で演劇についての成長を、全く描いていない訳ではありません。
滝田先生の授業中に、さおりが演出ノートに、
イマイチだった銀河鉄道の夜のラスト部分を書き換えるアイディアを書いていたりするし、
ラスト付近での稽古では地区大会と違い、実際に書き換えられた方の台本で劇部が演じています。
それから地区大会での失敗の起点となったガルルと明美ちゃんの接触を防ぐため、
県大会での舞台では入り順が「明美→ガルル」から「ガルル→明美」になっていたり、
細かい所で修正が加えられていた事が匂わされています。
これは私が現時点で、8回もこの映画を見ているから気づいた小ネタです。
この映画は、そう言った細部までこだわって作られているんですね。
映画を一度見た皆さんも、是非ふたたび一度映画館に足を運んで、
ももクロちゃん達の名演と、製作者達のこだわりを、堪能してみては如何でしょうか。