追記あり「そんな弱気でいいのか!」・響きの世界で常に勝負を挑んできた"男の歴史"に思いを馳せる
日付が変わったが、昨日やっと16曲をひと通り聴けた(笑)。
さて昨日は『Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD』のリリース日ということで、界隈はフラゲができた方々の感想で活況を呈している。特に今回は音質に言及している方々が多く、
"これはリマスタリングしてあるぞ!!!!"
"いや、既存曲は全く音質に変化はない。フラセボなのじゃないの??"
"いや、ミックスダウンからやり直しているぞ!!!!!"
などなど・・・・ etc。
だんだんと混沌としてきたような気もするが・・・・ 過去にこれに関連したエントリーで噛み付かれたこともあったっけ・・・・(苦笑)。
さらに最近ではサカナクションの山口一郎氏が出演する『サカナLOCKS!(TFM系)』でも、先週の放送でマスタリングについて、テーマとして取り上げられていたし。いろいろタイムリーかな・・・・
ということで、少し整理してみようと思いエントリーを書いている。
さて、皆さんはいろんなCDから音源を集めて、皆さんなりの "お気に入り・オリジナルCD" というのを作ったことはないだろうか。あるいはiTunesのプレイリストを使って、さまざまな音源から皆さんなりの "お気に入りのセットリスト" を作ったことはないだろうか。
実はそれが ある意味 "マスタリングみたいなもの" だったりするのだ(笑)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
○『マスタリング』とは
ミックスダウンの後、2ミックス(2ch)として出来上がった音源をメディア(CDなど)に収録するための原盤(マスター)を制作する作業のこと。
実際の作業は曲順の決定や変更や、クロスフェード作業(フェードイン・フェードアウトなど)、最終的な音源のレベルや音質(歪やノイズの除去)、音圧調整、曲間の編集とPQコードやISRCコード入力(曲の頭出し情報)などの作業を行う。
特に音圧調整で用いられる「コンプレッサー(Comp)」というエフェクターは、そのパラメーターによって大きく質感が変化するということが"仇"となって、使いこなしが極めて難しい事で有名。
マスタリングの目的は、基本的にアルバムなどの作品全体に統一感を引き出すために行われることが多い。
"パワーわんこ" による解釈より(笑)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
したがって、いろんなCDから音源を集めて "オリジナルCD" を作るというのは、ある意味『プリマスタリング』みたいなものだ(笑)。
それで、"オリジナルCD" を作った際にお困りになったことは皆さんないだろうか・・・・・ そう、
「 "前曲は音が小さい音源で、その次の曲は音が大きい音源を並べて" 、気持ち良く音楽を楽しんでいたら、曲が切り替わった瞬間に爆音が流れて、あわててボリウムを下げた・・・・」(苦笑)
ちなみに中田ヤスタカ氏が制作する音源は、他のアーティストと比べても音量・音圧が高めだ。したがって、オレの場合だとアコースティック系の音源を聴いていて、システムのボリウムを変えないで、中田氏の音源に切り替えて・・・・ 慌てたことは数え切れないほどだ(苦笑)。
もうお分かりだろうとは思うが、音の大きさは音源ごとに違うため、複数の曲を収録した場合は必ず音量・音圧もあわせて統一させなければならなくなる。
その際の音量・音圧の調整もマスタリングの工程に含まれるのだ
(最近では一般の方々がソフトウエアを用いて、お気に入りアーティストのCDを自らマスタリングを行うことも珍しくない。実はオレも以前は"オリジナルCD" を作る場合には、ソフトウエアを用いて音量・音圧の統一をオレ自身が行っていた。・笑)。
今回の『Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD』は、リミックスは2曲あるものの、ほとんどか既存楽曲を集めたコンピレーションアルバムである。
Perfumeはメジャーデビュー以降は、シングルやアルバムのすべての音源が、そのエンジニアリングも含めて、中田ヤスタカ氏が担当しているのは既に言うまでのこともないだろう。
そうなると「同一人物がエンジニアリングを行っているのだから、どのシングルやアルバムのどの音源も、同じ音量・音圧だろう」と短絡的に考えがちだが、実は機材の変遷なども影響してか、制作時期によって少しずつ変化していると感じる。
オレの聴感だと(システムのゲインでの確認では)、2011年にリリースされたアルバム『JPN』の音源を基準に考えると、『⊿(2009年)』や『GAME(2008年)』の音源は-1dB前後、『Perfume~Complete Best~(2006年)』の音源は-2dB前後という感じだ。
さらに今回リミックスされた「チョコレイト・ディスコ (2012-Mix)」と「MY COLOR (LTW-Mix)」は、『JPN』の音源と比較すると+1dB前後という感じだ。
ということは当然、最新の音源にあわせるだろうから、『LOVE THE WORLD』に収録された既存音源すべてにおいて音量・音圧の調整がなされているはずだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「中田 : コンピ(コンピレーション・アルバム)とかで、曲ごとにエンジニアやアレンジャーが違ったりして、1曲だけ聴く分には完璧なんだけど、アルバムとして並べたとき違和感があるようなときは、マスタリング・エンジニアってメチャクチャ重要だと思うんですよ。1曲だけバカみたいに音圧がでかいと困るし(笑)。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
しかし、コンピレーションアルバム制作の際にマスタリングをやり直したことが特別のことかと問われれば・・・・ まぁ、どのアーティストでも特にベストアルバムやコンピレーションアルバムを作る際は、必ず音量・音圧の調整は行う。したがって、特筆すべきことでもないとは思うが・・・・。
またファンの中には『LOVE THE WORLD』に収録された既存音源の音量・音圧の調整について"リマスタリング" と定義している方々もいらっしゃるが・・・・ 他のアーティストのベストアルバムやコンピレーションアルバムにおいては必ず行われる工程なので、それを特段にリマスタリングとは呼ばないことが多いと思う。(まぁ、作業自体はリマスタリング的なことをやってはいるのだが。)
またリマスタリングという場合は、既にリリースされているアルバムのマスタリングの工程をやり直すことを指すことが多く、この場合は音質の改善を狙っておこなわれることが多いと思う。
もし、ベストアルバムやコンピレーションアルバムにおいて、"リマスタリング作品" ということを大々的に打ち出していたら、それは "売らんがための宣伝文句" のような気がするなぁ・・・・ (苦笑)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「ライター : 中田さんのマスタリング作業についてはお聞きしていませんでした。どんなソフトを使っているのですか?」
「中田 : STEINBERG WaveLab ですね。まぁ、マスタリングは音を変えない前提でやっているですよ。マスタリングを考えてミックスするのって間違っていると思うし、何のためのマスタリングなのかってことですよ。」
「中田 : ミックスでマスタリングのための余白を残すんだったら、マスタリングのマスタリングが必要だって思うんですよ。わかります?」
「中田 : マスタリングは、曲を並べたときに "ちょっとこの曲の音量だけでかい" っていう部分だけ直すものであってほしいんです。曲を並べて、曲間を決めるだけの作業が本来のマスタリングだと思うんです。だから、僕もそういう方式でマスタリングを行っています。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
そういう意味では、今回の『LOVE THE WORLD』は2曲のリミックス作品以外は、取り立てて"リマスタリング" と謳うわけでもなく・・・・・ "徳間たん" も中田さんも本当に正直で、かなり全うな商売をしていると思う。本当に感心するなぁ・・・・ (どこの、だれかさんとは言わないが・・・・ 本当に正反対だなぁ・・・ これ・苦笑)。
さて、ファンの方々の中には、
「今回の既存音源は "マスタリングをやり直した" という程度ではない。既存音源はすべてミックス・ダウンからやり直したはずだ・・・」
と主張されている方もいらっしゃるようだが・・・・ それはやはりその音源によるだろうなぁ(苦笑)。また、各音色のバランスや音質を全く変更していなくても、音量・音圧だけを変えても、人間は音質が変わったように感じ取るし・・・・。まぁ、この辺は音響心理学が関連するところなので(笑)。
要するに中田氏は、当然コンピレーション・アルバム全体の響きに対する青写真があり、その統一感とトータルバランスを最大限に考慮して今回の制作に取り組んでいるはずだ。
したがって、例えば古い音源であったとしても、アルバムとしてのの親和性が高い音源は、音量・音圧の調整のみで音質に手を付けていない。逆に言えば、比較的新しい音源であったとしても、親和性が低いものはミックスダウンに立ち返って、EQなどの変更なども行っている可能性が高いとオレはその響きから感じている。
しかし、このようにDAWの出現でミックス・ダウンとマスタリングの垣根が取り払われつつあるのも事実だが・・・・
それを安易に "リミックス作品" と呼ぶことには、オレは抵抗がある(苦笑)。またそれを大々的に打ち出してプロモーションしているとするならば、それも "売らんがための宣伝文句" のような気がするのだが・・・・・(苦笑)。
*「ミックス・ダウン(トラック・ダウン)」とは、複数のトラックに収録された音源の個々のバランスや定位、エフェクト処理、EQ処理などを行い "2ミックス" と呼ばれるLR・2チャンネルの音源に集約する。マスタリングの前段階の作業。商業スタジオの場合は大規模で高価なミキシング・コンソール(卓)を用いて、作業を行う。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「ライター : 多くのレコーディングでは、ミックスとマスタリングは別工程で、"マスタリングを考えて、ピークから6dB余白を残してミックスダウンする" というエンジニアも居ますよね。」
「中田 : 音楽はマスタリングで完成するものじゃなくて、純粋にマスターを作るものだと思うんです。」
「中田 : でも、マスタリング・エンジニアに頼んで劇的に良くなるケースもあるにはある。何が変わったのか分からないけどすごく良くなったという場合はいいんですけど、初めから "ミックス・ダウンはこれくらいでマスタリングに任せるか" っていうのはやめたい。だって完成していないじゃん、それ。」
「中田 : でも、一人で曲を作ってアレンジしてミックスしてアルバムを完成させるなら、マスタリングは曲順と微妙な補正くらいしかするべきではない。まぁ、マスタリングのときに違和感があったら、僕はミックスに戻りますけどね。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
繰り返しになるがオレの主観では、今回の『LOVE THE WORLD』のコンピレーション・アルバムとしての統一感を最大限に考慮して、既存音源では音量・音圧の調整しか手を付けていないものもあれば、ミックス・ダウンまで立ち返って、EQなどを音質変更をかなり行った音源ものあると思う。
それが、どの楽曲なのか・・・・ それを探していくのも、音響的アプローチの "コンピレーション・アルバムの楽しみ方の一つ" なのだろう(笑)。
さて "マスタリングをやり直す = 音質が必ず改善される" とお考えの方々もいらっしゃるようだが、必ずしもそうとも言えない(苦笑)。
例えば、"アーティスト側が過去のアルバムに収録された音源の音質の"歪み感" に不満を感じていた" ということがあって、リマスタリングの際にその"歪み感" を取り除けば、アーティスト側の狙い通りということになる。
しかしアーティスト側は "歪み感" は演出上不可欠と考えていたにも関わらず、エンジニアが気を利かせて "歪み感" を取り除いてしまっても、それを "良い音質になった" とは言わないだろう。
そして今回の『LOVE THE WORLD』のリリースによって、少し気がかりなのは、
「『LOVE THE WORLD』に収録された音源のほうが、マスタリングがやり直されているのだから、絶対に音が良いはずだ。そうであれば過去のアルバムの音源はいらない、聴かない・・・・」
という風潮が、ファンの間でチラホラと見え隠れするような気がしないでもないのだが・・・・・ まぁ、オレの取り越し苦労なら良いけど(笑)。
ただしそういう風潮が本当にあれば、それは少し違うのではないかと思うのだ。
今回の『LOVE THE WORLD』の制作における中田氏の狙いは、あくまでも今回のコンピレーション・アルバムとしての統一感とトータルバランスを考え、その完成度を高めるためにマスタリングを行っている。
逆に言えば、例えば1曲だけを取り出して、その収録音源の持っている潜在能力を100%引き出すなら、もっと別のミックス・ダウンやマスタリングの手法や方向性になる可能性も当然あるのだ。
したがって過去にミックス・ダウンやマスタリングされた音源と、最新のミックス・ダウンやマスタリングされた音源に、その響きの方向性や傾向に違いはあったとしても、そこには優劣は存在しないのではないかとオレは考えている(確かに機材などの進化による優劣の差は発生する可能性は否定できないが。)
そして・・・・・
中田氏の作品作りに対する熱い思いと、そこに込めた気合と根性は過去も現在も変わっていない。
それよりもぜひ、最新音源と過去の音源を聴き比べて頂いて、むしろ過去の音源から当時の中田氏の熱い思いと、そこに込めた気合と根性、そしてその作品に投入した徒労に思いを馳せてやっていただければ、その音源たちも本望だとオレは思うのだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「ライター : 具体的な作業としては、2ミックスをCubase 5で書き出してWaveLab に並べていくのですか?」
「中田 : そうですね。そこで、"これちょっとなぁ" ってときにWaveLab上で何かをやるのは最終手段というかほとんどやらない。ちょっとだけ低音感が足りないんだったら、全体で持ち上げればいいけど、"キックのここが足りない" という場合は個別にEQをかけた方がいい。僕はミックスの段階にすぐに戻れる環境にいるからそれができる・・・・ 面倒くさいですけどね(笑)。」
「中田 : やっぱりミックスするんなら、完成品をちゃんと作りましょうよ、と言いたい。"この曲はマスタリング前なのでまだ完成じゃないんです"っていうセリフはあっちゃいけないと思うんです。」
「中田 : ミックス・エンジニアはマスタリングに遠慮しなくていいし、自信を持ってほしいですね。特にマスタリング用の余白は考えないようにしてほしい ・・・・マスタリング用に"ボーカル1dB上げバージョン"とか作るなっていう(笑)。完璧なバランスっていうのがエンジニアの中には絶対あるはずなので。」
「ライター : 一般のレコーディングの場合、ミックス・エンジニアとマスタリング・エンジニアのほかにプロデューサーやディレクターも居て、いろんな人の意見の中で落としどころを見つけなければいけない難しさもあるんでしょうけどね。」
「中田 : まぁそうなのですけど、そんな弱気でいいのかと(笑)。料理屋で味薄めと濃いめの2種類をセーフティーで用意するのと同じ感覚だと思うんですよ。"これだ!" っていうバランスがあるなら、それで勝負してほしいですよね。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
今回の『LOVE THE WORLD』も当然そうなのだが、過去の音源群も中田氏の絶妙なバランスで我々に勝負を挑んできた歴史が刻まれている。
過去の音源群も "一味違った響き" として、ぜひ楽しんでいただきたいと思う、今日この頃だ。
<○追記・15日am11:22>
"日本のマスタリングエンジニア界の名匠" と呼ばれる田中三一氏(奥田民生氏や佐野元春氏、JUDY&MARY、Boom Boom Satellitesなど数多くの作品のマスタリングを担当)が中田ヤスタカ氏と同様の発言をしていることが興味深い。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「田中三一氏 : 最近はミキシングエンジニアがマスタリングに立ち会うことも少なくなりましたし、逆に"どんなミックスがマスタリングしやすいですか?" って聞かれることもある。でも、そんなものはあり得ないんですよ。」
「田中三一氏 : マスタリングに向けてミックスするなんて、"音楽を作る" という観点からしても本末転倒だと思いませんか? 」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2012年9月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
このように音楽業界のプロの中でも、ミックスダウンやマスタリングなどは "ルーティンワーク化" された現状があるのを示唆しているのだと思う。
しかし・・・・ ミックスダウンやマスタリングは、あくまでもクリエーション(創造)の範疇なのだ。
しかしこのように "クリエーションという本質を深く理解している人物" は意外にも音楽業界の中でも少ないのかもしれない。そういうこともあって、中田ヤスタカ氏は『ミックスダウンで完璧な完成品を生み出してほしい』、『絶妙なバランスで勝負してほしい・・・・』と訴えているのだと思う。
これまではミックスダウンやマスタリングにはエンジニアが介在することで、アーティストの表現や演出意図が、ダイレクトにエンドユーザーの耳まで届かなかったこともあると思う。
しかし技術が進歩しDAWが生まれたことによって、アーティストが容易にエンジニアリングまで施せる時代となった。要するに "クリエーションという本質" にダイレクトに我々エンドユーザーが迫れる時代が到来したのだ。
そしてこれからは、ますますアーティスト自体が持っている "クリエーションの本質" がさらに問われていく時代になるのだと思う。
中田ヤスタカ氏が生み出す楽曲はけして完璧なものではなく、また中田氏が備えているミックスダウンやマスタリングのエンジニアリング技術も、プロのエンジニアが持っているノウハウと技術と比較すれば、それは劣るものかもしれない。
しかしこのように "クリエーションという本質を深く理解している人物" として見れば、中田ヤスタカ氏は抜きん出ていることは間違いないだろう。そしてそれは、日本においてかなり貴重な存在であることも浮き彫りになってくると思う。
その"クリエーションという本質を深く理解している人物" が作詞・作曲からエンジニアリングまでの最初から最後まで一貫して音源を作り、"絶妙なバランス" で我々エンドユーザーに勝負を挑んでくる。そして我々は、それを直接耳にすることができる・・・・・・
そのような音源を耳にできる時代に生まれたこと・・・・・
中田ヤスタカ氏と同じ時代に生まれたこと・・・・・
それを感謝したいと思った、今日この頃だ。
<○追記2>
*頂いたコメントに対するレスポンスなのだが、画像を掲載しかかったので、本文中に書くこととする。ご了承いただきたい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Choさん、コメントありがとうございます。画像を掲載したかったので、本文でのレスにさせていただきますね(笑顔)
早くも、スペクトラム分析しちゃったんですね(笑)。
いゃ・・・ 正直言いまして、あと1週間くらい聴感だけで分析してから、私もFFTをして科学的にその差を比較しようと思っていたのです。聴感トレーニングも兼ねて。人間は先入観があると、そのように感じちゃうものですからね(笑)。
でも気になって、データを見ちゃいました。もう聴感トレーニングにはなりません(苦笑)。
こういう分析を"宝探し的"に楽しんでいる方々もいらっしゃると思うので、その方々の足を引っ張らないように簡単に書きますね。
まず、響きは周波数特性だけでは語れませんが、今回はスペクトルなので、それだけに限定した話で考えください。
それでChoさんのお使いのソフトを私は使ったことがなかったので、念のために私も所有の別のFFTソフトでも分析しました。気になる楽曲だけオリジナル音源との比較分析を行ってみました(時間がなかったため全楽曲は行っていません)。
結果は、Choさんの測定データと傾向は似ているのですが、私の測定データとは結構、差異があって・・・・・・。これってPeak値をホールドした計測データなんでしょうか。私は一般的なMain値で実施してみました。
象徴的だったのは「GAME」だったので、分析結果をご紹介します。
*分析音源は「GAME」のもの。上はアルバム『GAME(2008年)』のスペクトラムで、下がコンピレーションアルバム『LOVE THE WORLD(2012年)』のスペクトラム
皆さんの宝探しの足を引っ張らないように、本当に少しだけ(笑)。
聴感でも一発で違いがわかるのはやはり「GAME」ですね。オリジナルはハイハットやクラッシュシンバルの音が耳に突き刺さるように襲ってきますが、LTW版ではそれが削られ、聴き心地が良くなっています。この傾向はスペクトルの波形にも反映されていますよね。
Choさんにご提供いただいたデータでは16kHz以降の帯域が極端に削られている楽曲がありました。
○Baby cruising Love
○シークレットシークレット
○Butterfly
○GAME
これは私の分析でも同様です。ただし16kHz以降の帯域って人間の耳ではほとんど識別できず、身体で感じるぐらいですから、ヘッドフォンなどでリスニングしている方々には分からない程度ですね。スピーカーでリスニングすれば雰囲気で感じられますが、"気のせい" と言われれば、そのように感じる程度だと。ただ、私はスペクトラム分析する前から少し気がついていました(笑)。
それで、中田さんが『LOVE THE WORLD』楽曲のいくつかにこのような処理を施したのかと推察すると、さまざまなことが考えられます。
まず新スタジオ、機材の変更などで、近々の音源や2曲のリミックス音源との親和性を図るというのもあると思いますが・・・・・。
この辺は皆さんの宝探しの足を引っ張らないように、もうしばらく経ってからにしますね。
では。パワーわんこでした(笑顔)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sound & Recording Magazine (サウンド アンド レコーディング マガ.../サウンド&レコーディング・マガジン編集部

¥980
Amazon.co.jp
Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD(初回限定盤.../Perfume

¥3,000
Amazon.co.jp
Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD/Perfume
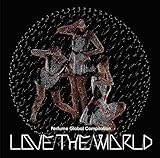
¥2,500
Amazon.co.jp
Sound & Recording Magazine (サウンド アンド レコーディング マガ.../リットーミュージック

¥1,000
Amazon.co.jp
さて昨日は『Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD』のリリース日ということで、界隈はフラゲができた方々の感想で活況を呈している。特に今回は音質に言及している方々が多く、
"これはリマスタリングしてあるぞ!!!!"
"いや、既存曲は全く音質に変化はない。フラセボなのじゃないの??"
"いや、ミックスダウンからやり直しているぞ!!!!!"
などなど・・・・ etc。
だんだんと混沌としてきたような気もするが・・・・ 過去にこれに関連したエントリーで噛み付かれたこともあったっけ・・・・(苦笑)。
さらに最近ではサカナクションの山口一郎氏が出演する『サカナLOCKS!(TFM系)』でも、先週の放送でマスタリングについて、テーマとして取り上げられていたし。いろいろタイムリーかな・・・・
ということで、少し整理してみようと思いエントリーを書いている。
さて、皆さんはいろんなCDから音源を集めて、皆さんなりの "お気に入り・オリジナルCD" というのを作ったことはないだろうか。あるいはiTunesのプレイリストを使って、さまざまな音源から皆さんなりの "お気に入りのセットリスト" を作ったことはないだろうか。
実はそれが ある意味 "マスタリングみたいなもの" だったりするのだ(笑)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
○『マスタリング』とは
ミックスダウンの後、2ミックス(2ch)として出来上がった音源をメディア(CDなど)に収録するための原盤(マスター)を制作する作業のこと。
実際の作業は曲順の決定や変更や、クロスフェード作業(フェードイン・フェードアウトなど)、最終的な音源のレベルや音質(歪やノイズの除去)、音圧調整、曲間の編集とPQコードやISRCコード入力(曲の頭出し情報)などの作業を行う。
特に音圧調整で用いられる「コンプレッサー(Comp)」というエフェクターは、そのパラメーターによって大きく質感が変化するということが"仇"となって、使いこなしが極めて難しい事で有名。
マスタリングの目的は、基本的にアルバムなどの作品全体に統一感を引き出すために行われることが多い。
"パワーわんこ" による解釈より(笑)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
したがって、いろんなCDから音源を集めて "オリジナルCD" を作るというのは、ある意味『プリマスタリング』みたいなものだ(笑)。
それで、"オリジナルCD" を作った際にお困りになったことは皆さんないだろうか・・・・・ そう、
「 "前曲は音が小さい音源で、その次の曲は音が大きい音源を並べて" 、気持ち良く音楽を楽しんでいたら、曲が切り替わった瞬間に爆音が流れて、あわててボリウムを下げた・・・・」(苦笑)
ちなみに中田ヤスタカ氏が制作する音源は、他のアーティストと比べても音量・音圧が高めだ。したがって、オレの場合だとアコースティック系の音源を聴いていて、システムのボリウムを変えないで、中田氏の音源に切り替えて・・・・ 慌てたことは数え切れないほどだ(苦笑)。
もうお分かりだろうとは思うが、音の大きさは音源ごとに違うため、複数の曲を収録した場合は必ず音量・音圧もあわせて統一させなければならなくなる。
その際の音量・音圧の調整もマスタリングの工程に含まれるのだ
(最近では一般の方々がソフトウエアを用いて、お気に入りアーティストのCDを自らマスタリングを行うことも珍しくない。実はオレも以前は"オリジナルCD" を作る場合には、ソフトウエアを用いて音量・音圧の統一をオレ自身が行っていた。・笑)。
今回の『Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD』は、リミックスは2曲あるものの、ほとんどか既存楽曲を集めたコンピレーションアルバムである。
Perfumeはメジャーデビュー以降は、シングルやアルバムのすべての音源が、そのエンジニアリングも含めて、中田ヤスタカ氏が担当しているのは既に言うまでのこともないだろう。
そうなると「同一人物がエンジニアリングを行っているのだから、どのシングルやアルバムのどの音源も、同じ音量・音圧だろう」と短絡的に考えがちだが、実は機材の変遷なども影響してか、制作時期によって少しずつ変化していると感じる。
オレの聴感だと(システムのゲインでの確認では)、2011年にリリースされたアルバム『JPN』の音源を基準に考えると、『⊿(2009年)』や『GAME(2008年)』の音源は-1dB前後、『Perfume~Complete Best~(2006年)』の音源は-2dB前後という感じだ。
さらに今回リミックスされた「チョコレイト・ディスコ (2012-Mix)」と「MY COLOR (LTW-Mix)」は、『JPN』の音源と比較すると+1dB前後という感じだ。
ということは当然、最新の音源にあわせるだろうから、『LOVE THE WORLD』に収録された既存音源すべてにおいて音量・音圧の調整がなされているはずだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「中田 : コンピ(コンピレーション・アルバム)とかで、曲ごとにエンジニアやアレンジャーが違ったりして、1曲だけ聴く分には完璧なんだけど、アルバムとして並べたとき違和感があるようなときは、マスタリング・エンジニアってメチャクチャ重要だと思うんですよ。1曲だけバカみたいに音圧がでかいと困るし(笑)。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
しかし、コンピレーションアルバム制作の際にマスタリングをやり直したことが特別のことかと問われれば・・・・ まぁ、どのアーティストでも特にベストアルバムやコンピレーションアルバムを作る際は、必ず音量・音圧の調整は行う。したがって、特筆すべきことでもないとは思うが・・・・。
またファンの中には『LOVE THE WORLD』に収録された既存音源の音量・音圧の調整について"リマスタリング" と定義している方々もいらっしゃるが・・・・ 他のアーティストのベストアルバムやコンピレーションアルバムにおいては必ず行われる工程なので、それを特段にリマスタリングとは呼ばないことが多いと思う。(まぁ、作業自体はリマスタリング的なことをやってはいるのだが。)
またリマスタリングという場合は、既にリリースされているアルバムのマスタリングの工程をやり直すことを指すことが多く、この場合は音質の改善を狙っておこなわれることが多いと思う。
もし、ベストアルバムやコンピレーションアルバムにおいて、"リマスタリング作品" ということを大々的に打ち出していたら、それは "売らんがための宣伝文句" のような気がするなぁ・・・・ (苦笑)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「ライター : 中田さんのマスタリング作業についてはお聞きしていませんでした。どんなソフトを使っているのですか?」
「中田 : STEINBERG WaveLab ですね。まぁ、マスタリングは音を変えない前提でやっているですよ。マスタリングを考えてミックスするのって間違っていると思うし、何のためのマスタリングなのかってことですよ。」
「中田 : ミックスでマスタリングのための余白を残すんだったら、マスタリングのマスタリングが必要だって思うんですよ。わかります?」
「中田 : マスタリングは、曲を並べたときに "ちょっとこの曲の音量だけでかい" っていう部分だけ直すものであってほしいんです。曲を並べて、曲間を決めるだけの作業が本来のマスタリングだと思うんです。だから、僕もそういう方式でマスタリングを行っています。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
そういう意味では、今回の『LOVE THE WORLD』は2曲のリミックス作品以外は、取り立てて"リマスタリング" と謳うわけでもなく・・・・・ "徳間たん" も中田さんも本当に正直で、かなり全うな商売をしていると思う。本当に感心するなぁ・・・・ (どこの、だれかさんとは言わないが・・・・ 本当に正反対だなぁ・・・ これ・苦笑)。
さて、ファンの方々の中には、
「今回の既存音源は "マスタリングをやり直した" という程度ではない。既存音源はすべてミックス・ダウンからやり直したはずだ・・・」
と主張されている方もいらっしゃるようだが・・・・ それはやはりその音源によるだろうなぁ(苦笑)。また、各音色のバランスや音質を全く変更していなくても、音量・音圧だけを変えても、人間は音質が変わったように感じ取るし・・・・。まぁ、この辺は音響心理学が関連するところなので(笑)。
要するに中田氏は、当然コンピレーション・アルバム全体の響きに対する青写真があり、その統一感とトータルバランスを最大限に考慮して今回の制作に取り組んでいるはずだ。
したがって、例えば古い音源であったとしても、アルバムとしてのの親和性が高い音源は、音量・音圧の調整のみで音質に手を付けていない。逆に言えば、比較的新しい音源であったとしても、親和性が低いものはミックスダウンに立ち返って、EQなどの変更なども行っている可能性が高いとオレはその響きから感じている。
しかし、このようにDAWの出現でミックス・ダウンとマスタリングの垣根が取り払われつつあるのも事実だが・・・・
それを安易に "リミックス作品" と呼ぶことには、オレは抵抗がある(苦笑)。またそれを大々的に打ち出してプロモーションしているとするならば、それも "売らんがための宣伝文句" のような気がするのだが・・・・・(苦笑)。
*「ミックス・ダウン(トラック・ダウン)」とは、複数のトラックに収録された音源の個々のバランスや定位、エフェクト処理、EQ処理などを行い "2ミックス" と呼ばれるLR・2チャンネルの音源に集約する。マスタリングの前段階の作業。商業スタジオの場合は大規模で高価なミキシング・コンソール(卓)を用いて、作業を行う。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「ライター : 多くのレコーディングでは、ミックスとマスタリングは別工程で、"マスタリングを考えて、ピークから6dB余白を残してミックスダウンする" というエンジニアも居ますよね。」
「中田 : 音楽はマスタリングで完成するものじゃなくて、純粋にマスターを作るものだと思うんです。」
「中田 : でも、マスタリング・エンジニアに頼んで劇的に良くなるケースもあるにはある。何が変わったのか分からないけどすごく良くなったという場合はいいんですけど、初めから "ミックス・ダウンはこれくらいでマスタリングに任せるか" っていうのはやめたい。だって完成していないじゃん、それ。」
「中田 : でも、一人で曲を作ってアレンジしてミックスしてアルバムを完成させるなら、マスタリングは曲順と微妙な補正くらいしかするべきではない。まぁ、マスタリングのときに違和感があったら、僕はミックスに戻りますけどね。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
繰り返しになるがオレの主観では、今回の『LOVE THE WORLD』のコンピレーション・アルバムとしての統一感を最大限に考慮して、既存音源では音量・音圧の調整しか手を付けていないものもあれば、ミックス・ダウンまで立ち返って、EQなどを音質変更をかなり行った音源ものあると思う。
それが、どの楽曲なのか・・・・ それを探していくのも、音響的アプローチの "コンピレーション・アルバムの楽しみ方の一つ" なのだろう(笑)。
さて "マスタリングをやり直す = 音質が必ず改善される" とお考えの方々もいらっしゃるようだが、必ずしもそうとも言えない(苦笑)。
例えば、"アーティスト側が過去のアルバムに収録された音源の音質の"歪み感" に不満を感じていた" ということがあって、リマスタリングの際にその"歪み感" を取り除けば、アーティスト側の狙い通りということになる。
しかしアーティスト側は "歪み感" は演出上不可欠と考えていたにも関わらず、エンジニアが気を利かせて "歪み感" を取り除いてしまっても、それを "良い音質になった" とは言わないだろう。
そして今回の『LOVE THE WORLD』のリリースによって、少し気がかりなのは、
「『LOVE THE WORLD』に収録された音源のほうが、マスタリングがやり直されているのだから、絶対に音が良いはずだ。そうであれば過去のアルバムの音源はいらない、聴かない・・・・」
という風潮が、ファンの間でチラホラと見え隠れするような気がしないでもないのだが・・・・・ まぁ、オレの取り越し苦労なら良いけど(笑)。
ただしそういう風潮が本当にあれば、それは少し違うのではないかと思うのだ。
今回の『LOVE THE WORLD』の制作における中田氏の狙いは、あくまでも今回のコンピレーション・アルバムとしての統一感とトータルバランスを考え、その完成度を高めるためにマスタリングを行っている。
逆に言えば、例えば1曲だけを取り出して、その収録音源の持っている潜在能力を100%引き出すなら、もっと別のミックス・ダウンやマスタリングの手法や方向性になる可能性も当然あるのだ。
したがって過去にミックス・ダウンやマスタリングされた音源と、最新のミックス・ダウンやマスタリングされた音源に、その響きの方向性や傾向に違いはあったとしても、そこには優劣は存在しないのではないかとオレは考えている(確かに機材などの進化による優劣の差は発生する可能性は否定できないが。)
そして・・・・・
中田氏の作品作りに対する熱い思いと、そこに込めた気合と根性は過去も現在も変わっていない。
それよりもぜひ、最新音源と過去の音源を聴き比べて頂いて、むしろ過去の音源から当時の中田氏の熱い思いと、そこに込めた気合と根性、そしてその作品に投入した徒労に思いを馳せてやっていただければ、その音源たちも本望だとオレは思うのだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「ライター : 具体的な作業としては、2ミックスをCubase 5で書き出してWaveLab に並べていくのですか?」
「中田 : そうですね。そこで、"これちょっとなぁ" ってときにWaveLab上で何かをやるのは最終手段というかほとんどやらない。ちょっとだけ低音感が足りないんだったら、全体で持ち上げればいいけど、"キックのここが足りない" という場合は個別にEQをかけた方がいい。僕はミックスの段階にすぐに戻れる環境にいるからそれができる・・・・ 面倒くさいですけどね(笑)。」
「中田 : やっぱりミックスするんなら、完成品をちゃんと作りましょうよ、と言いたい。"この曲はマスタリング前なのでまだ完成じゃないんです"っていうセリフはあっちゃいけないと思うんです。」
「中田 : ミックス・エンジニアはマスタリングに遠慮しなくていいし、自信を持ってほしいですね。特にマスタリング用の余白は考えないようにしてほしい ・・・・マスタリング用に"ボーカル1dB上げバージョン"とか作るなっていう(笑)。完璧なバランスっていうのがエンジニアの中には絶対あるはずなので。」
「ライター : 一般のレコーディングの場合、ミックス・エンジニアとマスタリング・エンジニアのほかにプロデューサーやディレクターも居て、いろんな人の意見の中で落としどころを見つけなければいけない難しさもあるんでしょうけどね。」
「中田 : まぁそうなのですけど、そんな弱気でいいのかと(笑)。料理屋で味薄めと濃いめの2種類をセーフティーで用意するのと同じ感覚だと思うんですよ。"これだ!" っていうバランスがあるなら、それで勝負してほしいですよね。」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2010年4月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
今回の『LOVE THE WORLD』も当然そうなのだが、過去の音源群も中田氏の絶妙なバランスで我々に勝負を挑んできた歴史が刻まれている。
過去の音源群も "一味違った響き" として、ぜひ楽しんでいただきたいと思う、今日この頃だ。
<○追記・15日am11:22>
"日本のマスタリングエンジニア界の名匠" と呼ばれる田中三一氏(奥田民生氏や佐野元春氏、JUDY&MARY、Boom Boom Satellitesなど数多くの作品のマスタリングを担当)が中田ヤスタカ氏と同様の発言をしていることが興味深い。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
「田中三一氏 : 最近はミキシングエンジニアがマスタリングに立ち会うことも少なくなりましたし、逆に"どんなミックスがマスタリングしやすいですか?" って聞かれることもある。でも、そんなものはあり得ないんですよ。」
「田中三一氏 : マスタリングに向けてミックスするなんて、"音楽を作る" という観点からしても本末転倒だと思いませんか? 」
『サウンド&レコーディング・マガジン 2012年9月号』より
-------------------------------------------------------------------------------------------------
このように音楽業界のプロの中でも、ミックスダウンやマスタリングなどは "ルーティンワーク化" された現状があるのを示唆しているのだと思う。
しかし・・・・ ミックスダウンやマスタリングは、あくまでもクリエーション(創造)の範疇なのだ。
しかしこのように "クリエーションという本質を深く理解している人物" は意外にも音楽業界の中でも少ないのかもしれない。そういうこともあって、中田ヤスタカ氏は『ミックスダウンで完璧な完成品を生み出してほしい』、『絶妙なバランスで勝負してほしい・・・・』と訴えているのだと思う。
これまではミックスダウンやマスタリングにはエンジニアが介在することで、アーティストの表現や演出意図が、ダイレクトにエンドユーザーの耳まで届かなかったこともあると思う。
しかし技術が進歩しDAWが生まれたことによって、アーティストが容易にエンジニアリングまで施せる時代となった。要するに "クリエーションという本質" にダイレクトに我々エンドユーザーが迫れる時代が到来したのだ。
そしてこれからは、ますますアーティスト自体が持っている "クリエーションの本質" がさらに問われていく時代になるのだと思う。
中田ヤスタカ氏が生み出す楽曲はけして完璧なものではなく、また中田氏が備えているミックスダウンやマスタリングのエンジニアリング技術も、プロのエンジニアが持っているノウハウと技術と比較すれば、それは劣るものかもしれない。
しかしこのように "クリエーションという本質を深く理解している人物" として見れば、中田ヤスタカ氏は抜きん出ていることは間違いないだろう。そしてそれは、日本においてかなり貴重な存在であることも浮き彫りになってくると思う。
その"クリエーションという本質を深く理解している人物" が作詞・作曲からエンジニアリングまでの最初から最後まで一貫して音源を作り、"絶妙なバランス" で我々エンドユーザーに勝負を挑んでくる。そして我々は、それを直接耳にすることができる・・・・・・
そのような音源を耳にできる時代に生まれたこと・・・・・
中田ヤスタカ氏と同じ時代に生まれたこと・・・・・
それを感謝したいと思った、今日この頃だ。
<○追記2>
*頂いたコメントに対するレスポンスなのだが、画像を掲載しかかったので、本文中に書くこととする。ご了承いただきたい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Choさん、コメントありがとうございます。画像を掲載したかったので、本文でのレスにさせていただきますね(笑顔)
早くも、スペクトラム分析しちゃったんですね(笑)。
いゃ・・・ 正直言いまして、あと1週間くらい聴感だけで分析してから、私もFFTをして科学的にその差を比較しようと思っていたのです。聴感トレーニングも兼ねて。人間は先入観があると、そのように感じちゃうものですからね(笑)。
でも気になって、データを見ちゃいました。もう聴感トレーニングにはなりません(苦笑)。
こういう分析を"宝探し的"に楽しんでいる方々もいらっしゃると思うので、その方々の足を引っ張らないように簡単に書きますね。
まず、響きは周波数特性だけでは語れませんが、今回はスペクトルなので、それだけに限定した話で考えください。
それでChoさんのお使いのソフトを私は使ったことがなかったので、念のために私も所有の別のFFTソフトでも分析しました。気になる楽曲だけオリジナル音源との比較分析を行ってみました(時間がなかったため全楽曲は行っていません)。
結果は、Choさんの測定データと傾向は似ているのですが、私の測定データとは結構、差異があって・・・・・・。これってPeak値をホールドした計測データなんでしょうか。私は一般的なMain値で実施してみました。
象徴的だったのは「GAME」だったので、分析結果をご紹介します。
*分析音源は「GAME」のもの。上はアルバム『GAME(2008年)』のスペクトラムで、下がコンピレーションアルバム『LOVE THE WORLD(2012年)』のスペクトラム
皆さんの宝探しの足を引っ張らないように、本当に少しだけ(笑)。
聴感でも一発で違いがわかるのはやはり「GAME」ですね。オリジナルはハイハットやクラッシュシンバルの音が耳に突き刺さるように襲ってきますが、LTW版ではそれが削られ、聴き心地が良くなっています。この傾向はスペクトルの波形にも反映されていますよね。
Choさんにご提供いただいたデータでは16kHz以降の帯域が極端に削られている楽曲がありました。
○Baby cruising Love
○シークレットシークレット
○Butterfly
○GAME
これは私の分析でも同様です。ただし16kHz以降の帯域って人間の耳ではほとんど識別できず、身体で感じるぐらいですから、ヘッドフォンなどでリスニングしている方々には分からない程度ですね。スピーカーでリスニングすれば雰囲気で感じられますが、"気のせい" と言われれば、そのように感じる程度だと。ただ、私はスペクトラム分析する前から少し気がついていました(笑)。
それで、中田さんが『LOVE THE WORLD』楽曲のいくつかにこのような処理を施したのかと推察すると、さまざまなことが考えられます。
まず新スタジオ、機材の変更などで、近々の音源や2曲のリミックス音源との親和性を図るというのもあると思いますが・・・・・。
この辺は皆さんの宝探しの足を引っ張らないように、もうしばらく経ってからにしますね。
では。パワーわんこでした(笑顔)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sound & Recording Magazine (サウンド アンド レコーディング マガ.../サウンド&レコーディング・マガジン編集部

¥980
Amazon.co.jp
Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD(初回限定盤.../Perfume

¥3,000
Amazon.co.jp
Perfume Global Compilation LOVE THE WORLD/Perfume
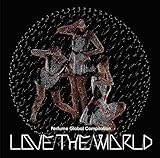
¥2,500
Amazon.co.jp
Sound & Recording Magazine (サウンド アンド レコーディング マガ.../リットーミュージック

¥1,000
Amazon.co.jp

