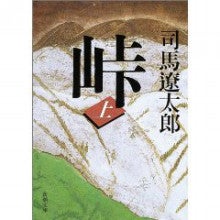「峠(上)」 司馬遼太郎 新潮文庫
越後長岡藩の下級藩士であった河井継之助は維新の動乱の中で家老にまで出世し、官軍と幕軍が戦闘を繰り広げる中、長岡藩をスイスのような武装中立の立場におき、両社を調停しようと試みます。しかし、結果論的には、長岡藩は幕府軍の一員として戦うことになり、戊辰戦争を通じて最も熾烈を極めた北越戦争により長岡藩は焼け野原となり最後のサムライと呼ばれた継之助もこの戦争の渦中に死亡します。
「峠(上)」は下級藩士の頃の河井継之助の人となりを豊富なエピソードを通じて描いたものになります。
雪深い越後長岡藩から江戸に留学し、ものごとの原理を知ろうと努める継之助の勉強方法は一風変わったものでした。司馬遼太郎氏は継之助の学問に対する姿勢を次のように表現しています。
その読み方も、かわっている。
単に読むのではなく、例の彫るような難筆でもって書写しているのである。
(ずいぶん、ご念の入った読み方だ)
と、佐吉もその点をおかしく思っている。
筆写などしていてはとほうもない時間がかかり、生涯多くの書物はよめまい。
「ではないでしょうか」と、ある日、きいてみた。
継之助は笑いもせず、これが本当だ、といった。
「おれは知識を掻きあつめてはおらん」せっせと読んで記憶したところでなんになる。知識の足し算をやっていることだけのことではないか。知識がいくらあっても時勢を救済し、歴史をたちなおらせることはできない。
「おれは、知識という石ころを、心中の炎でもって溶かしているのだ」
佐吉は、おかしかった。
なるほど、継之助の面構えは、石でも熔かしかねぬところがありそうである。もっとも熔かす、とは継之助のすきな陽明主義にあっては、知識を精神のなかにとかしきって行動のエネルギーに転化するということであろう。
継之助は客分となって佐久間象山や古賀塾に学び、さらに江戸の学問に飽き足らなくなった継之助は備中松山で藩の財政を立て直した山田方谷の教えを受けに旅に出ます。
山田方谷はのちに人にこのように語ったそうです。
「どうも河井はえらすぎる。えらすぎるくせにあのような越後のちっぽけな藩に生まれた。そのえらすぎることが、河井にとり、また長岡藩にとり、はたして幸福な結果をよぶか、不幸をよぶか」
河井も同様に自らを一国の宰相の器であると考えています。
「人間の才能は、多様だ」と継之助はいった。
「小吏にむいている、という男もあれば、大将にしかなれぬ、という男もある」
「どちらが、幸福でしょう」
「小吏の才だな」
継之助はいった。
藩組織の片すみでこつこつと飽きもせずに小さな事務をとってゆく、そういう小器量の男にうまれついた者は幸福であるという。自分の一生に疑いももたず、冒険もせず、危険の淵に近づきもせず、ただ分をまもり、妻子を愛し、それなりで生涯をすごす。
「一隅を照らすもの、これ国宝」
継之助は、いった。
叡山をひらいて天台宗を創設した伝教大師のことばである。きまじめな小器量者こそ国宝である、というのである。
「お兄様は?」
「お見かけのとおりさ」
どうみても、伝教大師が愛した小器量者ではない。
「大器量者?」
「そうとしか、おもえぬ」
この強烈な自負心。幕末の混乱の中、こんな男を藩士に持ってしまった長岡藩の運命はいったいどうなるのでしょうか?