昨日は、こんなシンポジウムに参加しました。
タイトル: NPO法人 いい会社をふやしましょう 創立記念シンポジウム 森と畑に「いい会社」
日時: 2012年12月15日(土) 14:00-16:30
場所: 東京都目黒区 東京工業大学蔵前会館
長いセッションでしたので、ある程度端折りながら。。。
最初に、NPO理事の江口さんから。
組織理念は、「いい会社をふやす」。会社に関わる多くの人の幸福に関わるから。対象にする人とは3つ。応援する人、経営者・社員、社会起業家。今後の予定としては、来月から「いい会社の理念経営塾」が予定されている。6/1には次回のシンポジウムも。一人ひとりの力は微力かもしれない。でも、無力ではない。「会社が変われば、社会も変わる」と考えている。
次は基調講演の大久保さん。
「いい会社をふやしましょう」 ~これからの日本を作る"いい会社"とは、"ほんものの人"とは何か~
「いい会社をつくりましょう」と、伊那食品工業のように社是にまであげているところは少ない。誰に聞いてもいい会社はいい、と言う。その「誰」というのは、客やパートナー、地域、株主まで含めるすべて。それが本質。一方、アナリストが「いい」というのは、規模であったり、ぎょうせきや配当。業績を上げて配当してても、その過程でたくさんの人を不幸にしていていはいけない。結局はマイナスの価値となる。こういう物は見えない。
鎌倉投信の鎌田さんや新井さんは、人間が目覚めたのである。行き詰まったところで。ずっとやってきたことで、こんな会社を増やしただろうか、と。前の会社を辞めた時は、今後は金融に触れない、というつもりだった。しかし、本来の金融を取り戻そうと鎌倉投信を立ち上げたのである。
伊那食品については、いつ行っても違う。社員の輝きが違う。ロビーにいるだけで、涙が出ることも。醸し出す雰囲気がいい。それも自然。素晴らしい企業というのは、社員が幸せ。生命が思う存分発揮している。関わる人すべてが幸せ。最近入社する人の中には、親に勧められて、という人が多い。なぜ親が勧めるかというと、人として立派になるから、と。地方企業でありながら、200倍以上の競争率となっている。なぜ会社が好きか、と聞くと、こんな答えが返って来る。「いい人ばかりだから」「先輩のようになりたい」「上司のようになりたい」。一方、大手で聞くと、「ああなってはいけない」とか「ギラギラしてる」と言う。最近では、「後輩のようになりたい」という人もいる。なぜなら、助け合っているから。思いやりを持って。実際、優秀な人が採用されている。優秀な人というのは、優しさに秀でた人。優しさというのは、人を憂うること。
毎朝、枯葉の掃除をしている。週末も自主的に、みんな出てくる。掃除というのは、五感が研ぎ澄まされるもの。基本的感性が磨かれる。
目が輝いていることと、職場の雰囲気がいいことの2つは作れない。働いている人が幸せを感じていない限り。目の輝きは作れない。表情はトレーニングできるが。
アフリカの戦闘地域で、幼い頃に真心を引っこ抜かれた人々のために学校、つまり職業訓練センターを作っているテラ・ルネッサンスの鬼丸さん。アイエスエフネットの渡邉さんは、2000人中800人の障がい者を採用している。匠カフェでは、10人以上の知的障がい者が働いている。テラ・ルネッサンスでは、震災後、福島、盛岡、仙台に事務所を置いている。職を作ることなしに再生しないと。お金を渡されても、人生の価値を見出せない。生きていないことになる。刺し子プロジェクトについても、10年スパンで考えている。やることがないと、避難所でフラッシュバックが起こる。自分で働くことで、笑顔が戻り。そのお金で、子や孫に何か買えると喜んでいる。
職を提供するのが企業。関わる人すべてが幸せになる。そんな企業が増えたら、という思い。経済が回らないと、国情不安となる。不幸な人を作ってはいけない。伊那食品工業では、社員からの要望で24時間勤務を始めたが、1ヶ月後、目の輝きが無くなったため、中止となった。
それができるのは、軸足を持っているから。社是社訓には通常、お客様や社員のことが書かれている。しかし、9割以上は無視している。
鎌倉投信は、いい会社をふやしましょう、と言ってきたが、彼らだけでは限度がある。そのために、NPOを作った。彼らがたくさん活躍できる会社が増え、職場が増え、幸せな人が増えるのがよいこと。最近はメンタル上行き詰まる人が多い。思いやりを持った会社では、そういう人は出てこない。働く人、1人1人がとてつもなく輝いている。彼らの笑顔がナチュラル。動作が美しく、表情が美しく、言葉が美しい。中から出てくるため。
ここに、「ほんものの人」とある。真心を引っこ抜かれたと思っていたが、人間性はなくならない。日本で震災が起こった、と聞いて、1日で5万円も集まった。愛情と思いやりを注がれて、出てきた。呼び水が必要だった。それも、たくさん。そして、恩を感じた。
いいものを表に出している人が「ほんものの人」。出していない人は、本物ではない。
次に、トビムシの竹本さん。
「ワリバシ(的なモノ)の可能性とこれからの林業」
(壇上で檜ネクタイをして) 檜は覚醒作用があるので、勝負ネクタイとも言える。トビムシもいい会社になりたい。
「ワリバシ(的なモノ)」というのは、割り箸だけでなく、本来的な意味で、ということ。「都市は物質的に豊か、地域は厳しく寂しい」「都市は自然を享受できない、地方に自然が豊か」と対比されるが、これは誤解。都市と森は同期している。「都市が厳しく寂しいなら、地方も厳しく寂しい」。都市の寂しい風景は、地方の寂しい風景と同意。自然に帰るというが、人が手を入れた所から人が離れるから寂しい。地方も、都市も。「都市(空間)が豊かなら、地方(の森)も豊か」。人工林は美しい。管理し、人が手を入れているから。
トビムシというのは、美しい森の中にいる。土がふかふかで、その中にいるのがトビムシ。人知れず支えている。そんな存在になりたい、と。理念として、地域の眠れる資産、その最たる森を支える。一世代では完結し得ないもの。垂直に、そして地方から都市へ出てきた人へも水平に思いを繋ぐ。
日本に普通にある森は、55歳、50歳の木が多い。もう少しすると、いい柱や床材になる。戦後一定期間経って、ハゲ山に植えていたもの。これから出てくる林業。その中で、プラスチックや鉄・非鉄が出てきて、木の需要が減ってしまった。このまま10年経つと、放置林では木が細く上へ伸びてしまうため、手遅れ林となり、ハゲ山になる。烈状間伐といって、バッサリ切ってしまって、ハゲ山になる可能性もある。今優性林であっても、いい木を先に切ってしまい、劣性林になって、ハゲ山になってしまう可能性もある。
日本の国土は、7割が森。うち4割が人工林。戦後、牛や馬のための草地だった所にも植えたため、最大の森林面積となっている。今やらなければならないことは、日本の木を使うだけでなく、劣性木間伐を続けること。細かったり、曲がっていたり、節があるもの。これは日本の森を取り戻すだけでなく、世界の伐採を減らすことにもなる。劣性間伐材については、ユカハリなどの商品となっている。50cm×10cmを5枚。通常の板は2mないと売買されないが、節などを除いて、50cm×10cmあればよい。これが、森の風景を作り、都市空間を豊かにしている。最近は、コグチタイルという製品もできている。こちらは、違う方向で木目を取り、強くなっているので、靴でもOK。お店などで。サクセスホールディングスでも使われており、木を使うことによって、湿度の調整ができる。さらに、割り箸も。これは21cmあればよい。香豊かで、色味があって、少し曲がっているかもしれない。そして、森や地域が豊かになる。
さらに、有機野菜の土も作っている。最近は、猫の手も借りたい、とペレットから猫砂も。猫砂繋がりで、さらにグッズも。これらがもっと売れ出したら、今度は人の手も借りたいとなるだろうが。
よく言うことだが、林は光のデザイン。もし水や養分が一定量なら、光が変数になる。ヒメホタルの写真。下層植生が豊かな所のみ見られる。こうなれば、都市の風景がキレイなはず。
すべて、つながりの(リ)デザインだと思っている。物質循環的繋がり。森ができないと、燃料も水もなくなる。林業の水域が豊かになると、中流・下流域も豊かになる。もったいないのではない。物流が細部に宿っているので、それぞれが分断されている。循環を取り戻すことで、持続性を担保できる。
檜は切って100年経つと最強になる。時間がかかるからこそある価値。昔に戻すのではなく、今しかできないことをやりたい。日々の生活の中で一票投票するように、ワリバシ的なモノを使う。声を上げることも。
休憩を挟んで、次は、マイファームの西辻さん。
「社会を変革する『自産自消』の農業」
選挙前で、戦闘モードになっていたが、2人の話で、アルファ波が出てきた。
農業についてであるが、野菜作りだけでなく、仕組み作りも行っている。自産自消のできる社会。野菜の旬を知るだけでなく、自然と生きることが大事だと気付いて欲しい。今の社会は効率化を求めているが、森の速度に合わせて生活することになる。野菜の成長する速度にも。自分たちを合わせていく。自然を前にすると、人は優しくなる。何気ない会話も、野菜の話でできるようになる。
福井県の出身。福井県と言えば、米どころ。子供の頃、減反政策で休耕地があった。なんてもったいない、と思った。私は農家ではない。家庭菜園をしていて、楽しいな、と思っていた。大人になって、事情は分かったが。
耕作放棄地をゼロにしたい。今、40万ha。5年で100ha、0.03%を直した。大学では、遺伝子組み換えの研究をしていた。最初は、そういう耕作放棄地を使って作りたいと思っていた。しかし、大学で先生に、なぜ遺伝子組み換えの研究をしているのか、と聞かれて答えられなかった。先生は、世界では何億人も飢えている人がいて、その人たちのために、生産性を増やすのだ、と。しかし、それよりも作る人を増やせばよいと思った。
農家さんは、食料を作るだけではない。心落ち着く地域の雰囲気も作っている。さらに発展させれば、観光産業もできるかもしれない。また、野菜作りをやってみたい人も増えている。農家さんは、知恵を持っているので、教育もできる。農家さんは、自然と人を結ぶ人言える。さらに、高齢化も進んでいるので、次の世代を作る必要もある。
マイファーム・アカデミーという専門学校を作った。平均年齢は20代。体験農園マイファームも83ヶ所に。畑師事業は、規制やしがらみがあって入りにくい事業の支援。
夏の過ちというものがある。東北へすべてかけてしまった。順位は付けられないが、今まで支えてくれた人たちは、となった。これが過ちでなかったというようにするのが私の仕事だが。
生きるって何かというと、生き生きと仕事すること。その仕組みを作る。先日NHKで放映されたビデオから。トマトの生産で、アルバイトが多い時には30人も。地元に雇用を落としたということで、町長も来た。
野菜を作っているのだが、見えないありがとうの価値がいっぱいある。それが人の間に絡み合う。今、通年の仕事はない。でも、恨むのではなく、自然流れだから、と言ってくれる。
仕組みを作る。それがうまくいくと、農家さんから紹介もされる。また、このトマトジュースを飲んでみたいと思うかもしれない。
先日新幹線から見ていた風景で。動物が少ないと思った。牧場を作れないか、と思った。新幹線から、羊やダチョウが見えてもいい。
昨日、マイファームの締め会で、農園コンテストがあった。83の農園で予選会をやり、昨日が本選。18もあるが。基本的には同じサービスだが、あとは管理人さん任せなので、そのアイディアのコンテスト。内緒で準備されていたものだが、とてもうれしかった。
最後に、パネルディスカッション。
「自分のあり方を見つめ、日本未来を考える」
鎌田: 塩害トマトについて。農業を再開するのに3年はかかると言われていたが、西辻さんは自分で調べて進めていた。竹本さんも同様。やるべきことをどう捉えるかが大事。その先に見えないものをどう見るか。そして、笑顔が大事。皆さん素敵な笑顔をしている。こちらから見ると何十年も苦労したように思えるが、楽しかったと言う。今も楽しいと言う。志を曲げなければ、人はついてくる。以降は、コーディネータを大久保さんにお任せして。。。
大久保: 竹本さんも、外資系コンサルティング会社から、無理だ、止めた方がいい、と言われているところに入っている。耕作放棄地は日本問題。林業も同じ。
竹本: 大久保さんは、会ってすぐにガハハと笑ってた。声がでかい人、というのが最初の印象。でも、そのおかげで、すーっと昔からの知り合いだったかのように話をした。初めて講演でも、最初に土を耕してくれる状態。やりやすかった。
大久保: なぜ林業?
竹本: 林業としての構造的問題は後から気付いた。養成法、環境法を作る人のアドバイスをしていた。社会的意識は高まっていた。でもやる人がいない。林業は関わらなければならない。しかし、地域が止まっていた。動かしていかなければならない。林業が必要。95%が林業なのに、横に置け、と言われていた。
大久保: 鰻は1匹を十何人で食べて…それは忘れるが。鹿は美味しかった。。。竹本さんの話からどう思う?
西辻: 林業と農業は繋がっていると言うが、本当にそうだと思う。最近、人糞を使うようにしたら、ほうれん草の葉先に環境ホルモンが出る。純粋な物は難しい。
大久保: 農家はすぐに農地を貸してくれるのか?
西辻: 最初は24才だった。若造として、何ができるのか、と言われた。実績は、と。ないからやりたいのに。思いを語り、積み立てありがとうを積み上げて、6ヶ月かかった。1個回ってきて、しっかりやっていれば繋がる。
大久保: 行く度に、髪も服も変えて。それでも失敗して。最終的には、酒飲んで酔っ払って、お前なら、となった。
竹本: 行政の課長職の前で、パネルをやったことがある。意見を聞かれ、西辻さんは「何もしないでください」と言った。その後、自分が「やっていただけることは何でも」と言って、場を温めた。(笑) 翌年になって、同じ状況で西辻さんは、「いろんなことを協力していただきたい」と。この1年の間に変わった。
西辻: もともと研究者肌で、1ヶ所だけ行きたいと思っていた。それに手がかかると、たくさんの人の手が必要だと気付いた。
竹本: 信頼関係の下で、腹に落ちたのでしょう。
大久保: 下に落ちるほど動く。一番は足。詳しくは考えてもらうとして…
西辻: 耕作放棄地に対する妄想。そこは野菜が作られていないだけでなく、営みがなく、景観が損なわれている。それだけを見ない。すると、発想が湧く。西宮で昨年、3つの農園があった。そこには、18農園あって、人が来ることで、息子が帰って来ることに。そうやって人が増え、お祭りが再開された。さらに、道路が渋滞するようになって、道が拡充された。
大久保: それは、文化が再生したということ。耕作放棄地は、文化が失われていたことに気付いた。農地や森林にいると、悪いことは考えられない。心が弱っていても、元気になる。大地や昨日エネルギーで、人は癒される。次は、製材所の話。
竹本: 1600人の村で、林業のみなので、製材所はあった。しかし、減ってしまい、家族でやっていた所のみに。会社が去った後で、大型製材を入れて、と。林業を知らないから、こうしたらいいと思っただけ。それが革命的と言われる。大島くんという家具職人。西洋の家具は西洋の木を使うが、日本の木を使いたいと。100年森構想に共感して。しかし、その時は、すぐに使える木がなかった。木はどこですか、と言われると、ほらそこにいっぱい。。。という状態。乾燥もできない状態。そのため、檜で家具を作る研究ができた、と言っている。分厚く、無骨になる物を改良したり、ニスまでも。100年後の風景に参加したことに。
大久保: もともと檜で家具は作らない。だからニスもなかった。彼は古文書を探した。そして、食べ物で作っているので、子供が舐めても大丈夫、と。お父さんかお祖父さんに「やってやれないことはない」と言われていたのだとか。鎌田さんから2人に。
鎌田: すっかり聴衆になっていたが。創業最初から、縁あって変わったことを始めた。今ある物でなく、妄想力というか。イマジネーションが幅広い。日本では、イノベーションというと技術革新と訳すが、本当は思考の革新。効率や費用対効果で見えなくなっている。認知時間に価値観を結び付けている。そういうキッカケを作っている。世の中を変えるのは、余所者・若者・馬鹿者と言うが、そのうちどれかではないか。
大久保: 時間の掛け方が違う。最近、お湯を沸かす時にはやかんを使うようにしている。利便性を追求すると、失われていく物がある。それをどう見るか。お茶を入れる過程楽しんでいる。
竹本: 知人が、1930年に横浜からサンフランシスコへ船で3ヶ月かかった。その間に、英語とダンスを学べたので、その後の社交界で困らなかった。今はニューヨークまで14時間。早くはなってるが、狭い箱に押し込められ。。。どう価値を捉えるか。3ヶ月を与えられたら何をするか考えること。
大久保: 今重要なのはボーっとすること。何を考えているわけでもなく。何も考えていないわけでもなく。それから、沖縄でのことを。
西辻: 耕作放棄地については、何がいいか仕掛けないといけない。沖縄の土は赤土だというので、食べてみた。いい土はチョコレートのように溶ける。また、毎日カルピスを飲んでるので、乳酸菌が多いせいか、大丈夫。
大久保: 地域からもダメと言われながら、今では地元の人も一緒にやっている。バックグラウンドには知識はあるが、しかし中心は彼らの思い。やらなきゃ、という力みはない。やりたいことをやっているだけ。海も山に繋がっている。活性化しているのが金融業。世の中繋がっている。。。山と農業、そして金融業も繋がった。皆さんはホームページで調べるだけでもよい。鎌倉投信のようなところは、金融業では異質。こういう人が活躍すれば、世界はよくなる。
以上です。
最後に鎌田さんから、下記の本の紹介がありましたので、貼り付けておきます。
マイファーム 荒地からの挑戦: 農と人をつなぐビジネスで社会を変える/学芸出版社

¥1,680
Amazon.co.jp
考えてみる/文屋
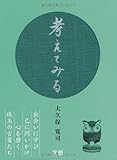
¥1,260
Amazon.co.jp
タイトル: NPO法人 いい会社をふやしましょう 創立記念シンポジウム 森と畑に「いい会社」
日時: 2012年12月15日(土) 14:00-16:30
場所: 東京都目黒区 東京工業大学蔵前会館
長いセッションでしたので、ある程度端折りながら。。。
最初に、NPO理事の江口さんから。
組織理念は、「いい会社をふやす」。会社に関わる多くの人の幸福に関わるから。対象にする人とは3つ。応援する人、経営者・社員、社会起業家。今後の予定としては、来月から「いい会社の理念経営塾」が予定されている。6/1には次回のシンポジウムも。一人ひとりの力は微力かもしれない。でも、無力ではない。「会社が変われば、社会も変わる」と考えている。
次は基調講演の大久保さん。
「いい会社をふやしましょう」 ~これからの日本を作る"いい会社"とは、"ほんものの人"とは何か~
「いい会社をつくりましょう」と、伊那食品工業のように社是にまであげているところは少ない。誰に聞いてもいい会社はいい、と言う。その「誰」というのは、客やパートナー、地域、株主まで含めるすべて。それが本質。一方、アナリストが「いい」というのは、規模であったり、ぎょうせきや配当。業績を上げて配当してても、その過程でたくさんの人を不幸にしていていはいけない。結局はマイナスの価値となる。こういう物は見えない。
鎌倉投信の鎌田さんや新井さんは、人間が目覚めたのである。行き詰まったところで。ずっとやってきたことで、こんな会社を増やしただろうか、と。前の会社を辞めた時は、今後は金融に触れない、というつもりだった。しかし、本来の金融を取り戻そうと鎌倉投信を立ち上げたのである。
伊那食品については、いつ行っても違う。社員の輝きが違う。ロビーにいるだけで、涙が出ることも。醸し出す雰囲気がいい。それも自然。素晴らしい企業というのは、社員が幸せ。生命が思う存分発揮している。関わる人すべてが幸せ。最近入社する人の中には、親に勧められて、という人が多い。なぜ親が勧めるかというと、人として立派になるから、と。地方企業でありながら、200倍以上の競争率となっている。なぜ会社が好きか、と聞くと、こんな答えが返って来る。「いい人ばかりだから」「先輩のようになりたい」「上司のようになりたい」。一方、大手で聞くと、「ああなってはいけない」とか「ギラギラしてる」と言う。最近では、「後輩のようになりたい」という人もいる。なぜなら、助け合っているから。思いやりを持って。実際、優秀な人が採用されている。優秀な人というのは、優しさに秀でた人。優しさというのは、人を憂うること。
毎朝、枯葉の掃除をしている。週末も自主的に、みんな出てくる。掃除というのは、五感が研ぎ澄まされるもの。基本的感性が磨かれる。
目が輝いていることと、職場の雰囲気がいいことの2つは作れない。働いている人が幸せを感じていない限り。目の輝きは作れない。表情はトレーニングできるが。
アフリカの戦闘地域で、幼い頃に真心を引っこ抜かれた人々のために学校、つまり職業訓練センターを作っているテラ・ルネッサンスの鬼丸さん。アイエスエフネットの渡邉さんは、2000人中800人の障がい者を採用している。匠カフェでは、10人以上の知的障がい者が働いている。テラ・ルネッサンスでは、震災後、福島、盛岡、仙台に事務所を置いている。職を作ることなしに再生しないと。お金を渡されても、人生の価値を見出せない。生きていないことになる。刺し子プロジェクトについても、10年スパンで考えている。やることがないと、避難所でフラッシュバックが起こる。自分で働くことで、笑顔が戻り。そのお金で、子や孫に何か買えると喜んでいる。
職を提供するのが企業。関わる人すべてが幸せになる。そんな企業が増えたら、という思い。経済が回らないと、国情不安となる。不幸な人を作ってはいけない。伊那食品工業では、社員からの要望で24時間勤務を始めたが、1ヶ月後、目の輝きが無くなったため、中止となった。
それができるのは、軸足を持っているから。社是社訓には通常、お客様や社員のことが書かれている。しかし、9割以上は無視している。
鎌倉投信は、いい会社をふやしましょう、と言ってきたが、彼らだけでは限度がある。そのために、NPOを作った。彼らがたくさん活躍できる会社が増え、職場が増え、幸せな人が増えるのがよいこと。最近はメンタル上行き詰まる人が多い。思いやりを持った会社では、そういう人は出てこない。働く人、1人1人がとてつもなく輝いている。彼らの笑顔がナチュラル。動作が美しく、表情が美しく、言葉が美しい。中から出てくるため。
ここに、「ほんものの人」とある。真心を引っこ抜かれたと思っていたが、人間性はなくならない。日本で震災が起こった、と聞いて、1日で5万円も集まった。愛情と思いやりを注がれて、出てきた。呼び水が必要だった。それも、たくさん。そして、恩を感じた。
いいものを表に出している人が「ほんものの人」。出していない人は、本物ではない。
次に、トビムシの竹本さん。
「ワリバシ(的なモノ)の可能性とこれからの林業」
(壇上で檜ネクタイをして) 檜は覚醒作用があるので、勝負ネクタイとも言える。トビムシもいい会社になりたい。
「ワリバシ(的なモノ)」というのは、割り箸だけでなく、本来的な意味で、ということ。「都市は物質的に豊か、地域は厳しく寂しい」「都市は自然を享受できない、地方に自然が豊か」と対比されるが、これは誤解。都市と森は同期している。「都市が厳しく寂しいなら、地方も厳しく寂しい」。都市の寂しい風景は、地方の寂しい風景と同意。自然に帰るというが、人が手を入れた所から人が離れるから寂しい。地方も、都市も。「都市(空間)が豊かなら、地方(の森)も豊か」。人工林は美しい。管理し、人が手を入れているから。
トビムシというのは、美しい森の中にいる。土がふかふかで、その中にいるのがトビムシ。人知れず支えている。そんな存在になりたい、と。理念として、地域の眠れる資産、その最たる森を支える。一世代では完結し得ないもの。垂直に、そして地方から都市へ出てきた人へも水平に思いを繋ぐ。
日本に普通にある森は、55歳、50歳の木が多い。もう少しすると、いい柱や床材になる。戦後一定期間経って、ハゲ山に植えていたもの。これから出てくる林業。その中で、プラスチックや鉄・非鉄が出てきて、木の需要が減ってしまった。このまま10年経つと、放置林では木が細く上へ伸びてしまうため、手遅れ林となり、ハゲ山になる。烈状間伐といって、バッサリ切ってしまって、ハゲ山になる可能性もある。今優性林であっても、いい木を先に切ってしまい、劣性林になって、ハゲ山になってしまう可能性もある。
日本の国土は、7割が森。うち4割が人工林。戦後、牛や馬のための草地だった所にも植えたため、最大の森林面積となっている。今やらなければならないことは、日本の木を使うだけでなく、劣性木間伐を続けること。細かったり、曲がっていたり、節があるもの。これは日本の森を取り戻すだけでなく、世界の伐採を減らすことにもなる。劣性間伐材については、ユカハリなどの商品となっている。50cm×10cmを5枚。通常の板は2mないと売買されないが、節などを除いて、50cm×10cmあればよい。これが、森の風景を作り、都市空間を豊かにしている。最近は、コグチタイルという製品もできている。こちらは、違う方向で木目を取り、強くなっているので、靴でもOK。お店などで。サクセスホールディングスでも使われており、木を使うことによって、湿度の調整ができる。さらに、割り箸も。これは21cmあればよい。香豊かで、色味があって、少し曲がっているかもしれない。そして、森や地域が豊かになる。
さらに、有機野菜の土も作っている。最近は、猫の手も借りたい、とペレットから猫砂も。猫砂繋がりで、さらにグッズも。これらがもっと売れ出したら、今度は人の手も借りたいとなるだろうが。
よく言うことだが、林は光のデザイン。もし水や養分が一定量なら、光が変数になる。ヒメホタルの写真。下層植生が豊かな所のみ見られる。こうなれば、都市の風景がキレイなはず。
すべて、つながりの(リ)デザインだと思っている。物質循環的繋がり。森ができないと、燃料も水もなくなる。林業の水域が豊かになると、中流・下流域も豊かになる。もったいないのではない。物流が細部に宿っているので、それぞれが分断されている。循環を取り戻すことで、持続性を担保できる。
檜は切って100年経つと最強になる。時間がかかるからこそある価値。昔に戻すのではなく、今しかできないことをやりたい。日々の生活の中で一票投票するように、ワリバシ的なモノを使う。声を上げることも。
休憩を挟んで、次は、マイファームの西辻さん。
「社会を変革する『自産自消』の農業」
選挙前で、戦闘モードになっていたが、2人の話で、アルファ波が出てきた。
農業についてであるが、野菜作りだけでなく、仕組み作りも行っている。自産自消のできる社会。野菜の旬を知るだけでなく、自然と生きることが大事だと気付いて欲しい。今の社会は効率化を求めているが、森の速度に合わせて生活することになる。野菜の成長する速度にも。自分たちを合わせていく。自然を前にすると、人は優しくなる。何気ない会話も、野菜の話でできるようになる。
福井県の出身。福井県と言えば、米どころ。子供の頃、減反政策で休耕地があった。なんてもったいない、と思った。私は農家ではない。家庭菜園をしていて、楽しいな、と思っていた。大人になって、事情は分かったが。
耕作放棄地をゼロにしたい。今、40万ha。5年で100ha、0.03%を直した。大学では、遺伝子組み換えの研究をしていた。最初は、そういう耕作放棄地を使って作りたいと思っていた。しかし、大学で先生に、なぜ遺伝子組み換えの研究をしているのか、と聞かれて答えられなかった。先生は、世界では何億人も飢えている人がいて、その人たちのために、生産性を増やすのだ、と。しかし、それよりも作る人を増やせばよいと思った。
農家さんは、食料を作るだけではない。心落ち着く地域の雰囲気も作っている。さらに発展させれば、観光産業もできるかもしれない。また、野菜作りをやってみたい人も増えている。農家さんは、知恵を持っているので、教育もできる。農家さんは、自然と人を結ぶ人言える。さらに、高齢化も進んでいるので、次の世代を作る必要もある。
マイファーム・アカデミーという専門学校を作った。平均年齢は20代。体験農園マイファームも83ヶ所に。畑師事業は、規制やしがらみがあって入りにくい事業の支援。
夏の過ちというものがある。東北へすべてかけてしまった。順位は付けられないが、今まで支えてくれた人たちは、となった。これが過ちでなかったというようにするのが私の仕事だが。
生きるって何かというと、生き生きと仕事すること。その仕組みを作る。先日NHKで放映されたビデオから。トマトの生産で、アルバイトが多い時には30人も。地元に雇用を落としたということで、町長も来た。
野菜を作っているのだが、見えないありがとうの価値がいっぱいある。それが人の間に絡み合う。今、通年の仕事はない。でも、恨むのではなく、自然流れだから、と言ってくれる。
仕組みを作る。それがうまくいくと、農家さんから紹介もされる。また、このトマトジュースを飲んでみたいと思うかもしれない。
先日新幹線から見ていた風景で。動物が少ないと思った。牧場を作れないか、と思った。新幹線から、羊やダチョウが見えてもいい。
昨日、マイファームの締め会で、農園コンテストがあった。83の農園で予選会をやり、昨日が本選。18もあるが。基本的には同じサービスだが、あとは管理人さん任せなので、そのアイディアのコンテスト。内緒で準備されていたものだが、とてもうれしかった。
最後に、パネルディスカッション。
「自分のあり方を見つめ、日本未来を考える」
鎌田: 塩害トマトについて。農業を再開するのに3年はかかると言われていたが、西辻さんは自分で調べて進めていた。竹本さんも同様。やるべきことをどう捉えるかが大事。その先に見えないものをどう見るか。そして、笑顔が大事。皆さん素敵な笑顔をしている。こちらから見ると何十年も苦労したように思えるが、楽しかったと言う。今も楽しいと言う。志を曲げなければ、人はついてくる。以降は、コーディネータを大久保さんにお任せして。。。
大久保: 竹本さんも、外資系コンサルティング会社から、無理だ、止めた方がいい、と言われているところに入っている。耕作放棄地は日本問題。林業も同じ。
竹本: 大久保さんは、会ってすぐにガハハと笑ってた。声がでかい人、というのが最初の印象。でも、そのおかげで、すーっと昔からの知り合いだったかのように話をした。初めて講演でも、最初に土を耕してくれる状態。やりやすかった。
大久保: なぜ林業?
竹本: 林業としての構造的問題は後から気付いた。養成法、環境法を作る人のアドバイスをしていた。社会的意識は高まっていた。でもやる人がいない。林業は関わらなければならない。しかし、地域が止まっていた。動かしていかなければならない。林業が必要。95%が林業なのに、横に置け、と言われていた。
大久保: 鰻は1匹を十何人で食べて…それは忘れるが。鹿は美味しかった。。。竹本さんの話からどう思う?
西辻: 林業と農業は繋がっていると言うが、本当にそうだと思う。最近、人糞を使うようにしたら、ほうれん草の葉先に環境ホルモンが出る。純粋な物は難しい。
大久保: 農家はすぐに農地を貸してくれるのか?
西辻: 最初は24才だった。若造として、何ができるのか、と言われた。実績は、と。ないからやりたいのに。思いを語り、積み立てありがとうを積み上げて、6ヶ月かかった。1個回ってきて、しっかりやっていれば繋がる。
大久保: 行く度に、髪も服も変えて。それでも失敗して。最終的には、酒飲んで酔っ払って、お前なら、となった。
竹本: 行政の課長職の前で、パネルをやったことがある。意見を聞かれ、西辻さんは「何もしないでください」と言った。その後、自分が「やっていただけることは何でも」と言って、場を温めた。(笑) 翌年になって、同じ状況で西辻さんは、「いろんなことを協力していただきたい」と。この1年の間に変わった。
西辻: もともと研究者肌で、1ヶ所だけ行きたいと思っていた。それに手がかかると、たくさんの人の手が必要だと気付いた。
竹本: 信頼関係の下で、腹に落ちたのでしょう。
大久保: 下に落ちるほど動く。一番は足。詳しくは考えてもらうとして…
西辻: 耕作放棄地に対する妄想。そこは野菜が作られていないだけでなく、営みがなく、景観が損なわれている。それだけを見ない。すると、発想が湧く。西宮で昨年、3つの農園があった。そこには、18農園あって、人が来ることで、息子が帰って来ることに。そうやって人が増え、お祭りが再開された。さらに、道路が渋滞するようになって、道が拡充された。
大久保: それは、文化が再生したということ。耕作放棄地は、文化が失われていたことに気付いた。農地や森林にいると、悪いことは考えられない。心が弱っていても、元気になる。大地や昨日エネルギーで、人は癒される。次は、製材所の話。
竹本: 1600人の村で、林業のみなので、製材所はあった。しかし、減ってしまい、家族でやっていた所のみに。会社が去った後で、大型製材を入れて、と。林業を知らないから、こうしたらいいと思っただけ。それが革命的と言われる。大島くんという家具職人。西洋の家具は西洋の木を使うが、日本の木を使いたいと。100年森構想に共感して。しかし、その時は、すぐに使える木がなかった。木はどこですか、と言われると、ほらそこにいっぱい。。。という状態。乾燥もできない状態。そのため、檜で家具を作る研究ができた、と言っている。分厚く、無骨になる物を改良したり、ニスまでも。100年後の風景に参加したことに。
大久保: もともと檜で家具は作らない。だからニスもなかった。彼は古文書を探した。そして、食べ物で作っているので、子供が舐めても大丈夫、と。お父さんかお祖父さんに「やってやれないことはない」と言われていたのだとか。鎌田さんから2人に。
鎌田: すっかり聴衆になっていたが。創業最初から、縁あって変わったことを始めた。今ある物でなく、妄想力というか。イマジネーションが幅広い。日本では、イノベーションというと技術革新と訳すが、本当は思考の革新。効率や費用対効果で見えなくなっている。認知時間に価値観を結び付けている。そういうキッカケを作っている。世の中を変えるのは、余所者・若者・馬鹿者と言うが、そのうちどれかではないか。
大久保: 時間の掛け方が違う。最近、お湯を沸かす時にはやかんを使うようにしている。利便性を追求すると、失われていく物がある。それをどう見るか。お茶を入れる過程楽しんでいる。
竹本: 知人が、1930年に横浜からサンフランシスコへ船で3ヶ月かかった。その間に、英語とダンスを学べたので、その後の社交界で困らなかった。今はニューヨークまで14時間。早くはなってるが、狭い箱に押し込められ。。。どう価値を捉えるか。3ヶ月を与えられたら何をするか考えること。
大久保: 今重要なのはボーっとすること。何を考えているわけでもなく。何も考えていないわけでもなく。それから、沖縄でのことを。
西辻: 耕作放棄地については、何がいいか仕掛けないといけない。沖縄の土は赤土だというので、食べてみた。いい土はチョコレートのように溶ける。また、毎日カルピスを飲んでるので、乳酸菌が多いせいか、大丈夫。
大久保: 地域からもダメと言われながら、今では地元の人も一緒にやっている。バックグラウンドには知識はあるが、しかし中心は彼らの思い。やらなきゃ、という力みはない。やりたいことをやっているだけ。海も山に繋がっている。活性化しているのが金融業。世の中繋がっている。。。山と農業、そして金融業も繋がった。皆さんはホームページで調べるだけでもよい。鎌倉投信のようなところは、金融業では異質。こういう人が活躍すれば、世界はよくなる。
以上です。
最後に鎌田さんから、下記の本の紹介がありましたので、貼り付けておきます。
マイファーム 荒地からの挑戦: 農と人をつなぐビジネスで社会を変える/学芸出版社

¥1,680
Amazon.co.jp
考えてみる/文屋
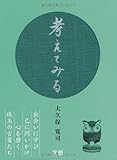
¥1,260
Amazon.co.jp