あれこれあって、なかなか落ち着いて読書する気分になれない。
それでも、なんとかようやくだが、ジョージ・エリオット著の『フロス河の水車場』(工藤好美・淀川郁子訳、『世界文学大系85』 所収、筑摩書房)を読むことができる(…もう、時間がなくてもとにかく手に取る!)。
ジョージ・エリオット(1819-1880)については、「英国女流作家探索-私だけの特別な一冊を求めて- 」の中の「George Eliot(ジョージ・エリオット)のプロフィール・作品・翻訳本の紹介 」が親切だし参考になる。
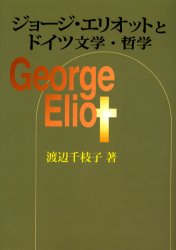
← 渡辺 千枝子 著『ジョージ・エリオットとドイツ文学・哲学 』(創英社)
少しは関心を持って詠んできたつもりだが、実際には『サイラス・マーナー』『ロモラ』(これは2回)を読んだだけ。まだまだ『ミドルマーチ』『ダニエル・デロンダ』『急進主義者フィーリクス・ホルト』『アダム・ビード』などの大作群が残っている。
『フロス河の水車場』だって、今から読むわけだから、実質、手付かずと言うべき作品だし。
ジョージ・エリオットについては、(日本語の)ネットの世界へのささやかな貢献(?)として、ジョージ・エリオット著『ロモラ』(工藤昭雄訳、集英社版 世界文学全集 40)からとして、下記の記事を提供している:
「「ジョージ・エリオット」解説
」
「「ジョージ・エリオット」作品について
」
ここでは、「George Eliot(ジョージ・エリオット)のプロフィール・作品・翻訳本の紹介
」の、簡潔で要を得た紹介を転記させてもらう:
Mary Ann Evansはナニートンで生まれ、1841年までそこで過ごす。文筆活動を始めた1856年、彼女の社会的立場が不安定だったためペンネームが必要だった。そこで、恋人のジョージ・ヘンリー・ルイス(妻子持ち)への敬意を込めて「ジョージ」とつけた。ルイスの死後、20歳も年下のジョン・ウォルター・クロスと正式に結婚したが、7ヵ月後ロンドンで息を引き取る。エリオットはフランス語、ラテン語、イタリア語、ヘブライ語、ギリシア語など語学が堪能で、広い教養を備えていた。当時ディケンズと並ぶ人気作家だった。ギャスケル夫人から多大な影響を受けている。
この中で、「エリオットはフランス語、ラテン語、イタリア語、ヘブライ語、ギリシア語など語学が堪能で、広い教養を備えていた」とある。
これだけでも凄いのだが、彼女に付いての情報を物色していたら、上掲の頁にもあるが、『ジョージ・エリオットとドイツ文学・哲学
』(渡辺 千枝子 著、創英社)なる本があることに今更ながら気がついた。
商品の説明の項には、「イギリスの女流作家として評価が高いジョージ・エリオット。その思想形成に最も大きな役割を果たしたとされるスピノザ、ゲーテ、フォイエルバッハなどドイツの文学者・思想家との結びつきに関する研究」とある。
スピノザ、ゲーテ、フォイエルバッハ!!
文学者だからって、文学者のみならず思想家の影響を受けたり何らかの結びつきがあっても別に変ではないが、それにしても、スピノザ、ゲーテ、フォイエルバッハである。
さらに、同じ頁の「レビュアー: カスタマー」氏によると、「ジョージ・エリオットの世界観形成に果たすドイツ哲学・文学の役割や『アダム・ビード』とスピノザ『エチカ』の関係、『フロス河畔の水車小屋』とG.ケラー『村のロメオとユリア』との関連、ゴットフリート・ケラーの『緑のハインリッヒ』など、本当に幅広くカバーした秀作である」だって。
これは、学生時代、一応は哲学科に籍を置いた者として見過ごすわけには行かない。
→ バールーフ・デ・スピノザ (画像は、「バールーフ・デ・スピノザ - Wikipedia」より)
今は上掲書を読んでいないし、うっかりしたことは言えないが、スピノザの『エチカ』を読む人物、「スピノザの『倫理学』などを訳 」す人物ということで、なんとなくだが思うことがある。
それは、「信兵衛の読書手帖
」の中の、「読書のおと(ジョージ・エリオット作品のページ)
」なる頁で見つけた記述に関係すること(以前にも、この頁は紹介したことがある。というか、参照させてもらったことがある)。
尤も、小生が未読の『ミドルマーチ』の項に見出した記述なのだが。
前後の脈絡を欠いての転記になるが、以下のような文がある:
エリオットには、サマセット・モームが指摘するように、その長所と同時に短所があります。モームはそれを「情熱が欠けている」と評しましたが、表現は大袈裟であるもののその通りであると感じます。
エリオットは作中人物の誰に対しても、温かさ、好意を示すことがありません。それだけ客観的に登場人物を描いていると言えますが、一方において誰一人として魅力的な人物を見出すことが出来ない、という不満もあります。
しかしながら、この作品の素晴らしさは、やはりエリオットが多くの登場人物を見事に客観的に描き分けていることにあると言えます。
「エリオットは作中人物の誰に対しても、温かさ、好意を示すことがありません」が、「しかしながら、この作品の素晴らしさは、やはりエリオットが多くの登場人物を見事に客観的に描き分けていることにあると言えます」という。
ある意味、矛盾した指摘。
が、ここにスピノザ『エチカ』を一枚、噛ませると、なんとなくイメージが浮んでくるものがある。
哲学者と言っても現実の政治への関心を深く持ち続け、現実を直視することを忘れず、「人間を自由にするものとしての神に対する愛を推奨」するが(以下、「バールーフ・デ・スピノザ - Wikipedia」を参照)、その実、「非人格的な神概念と、伝統的な自由意志の概念を退ける徹底した決定論」で、キリスト教神学者からも無神論者として非難された。
「精神の変化は身体の変化に対応しており、精神は身体から独立にあるわけではなく、身体も精神から独立となりえない」という発想からも分るように、スピノザは自由意志を認めない。
そして、「神を自然の働き・ありかた全体と同一視する汎神論の立場」。

← W・S・モーム/著『月と六ペンス 』(大岡玲/訳・解説、小学館) モームはジョージ・エリオットの作品を、「「情熱が欠けている」と評し」たというが。ちなみに、小生は、『月と六ペンス 』や『雨 』などを読み、感想文を書いたことがある。
ジョージ・エリオットに事寄せてみると、彼女は、徹底したリアリストなのだろう。この世の誰かが主人公という発想法は彼女にはありえなかったのではないか。たまたま誰かを便宜上、小説の主人公に仕立てたとしても、それはたまたま誰かにスポットを当ててみたに過ぎず、彼女にしたら他の誰でも良かったのではないか。
この世の誰もが、脚光を浴びて描かれるなら、一個の文学作品の主役足りうる世界が開示されうる。
ジョージ・エリオットに情熱が欠けていると、モームは指摘したとか(その典拠を確認していないので、前後の詳しい脈絡も何も分らないのだが)。
が、その真意はともかく、小生に言わせるなら、彼女は情熱が溢れすぎていた。誰彼に的を絞るにはあまりに横溢する情念がそれを許さなかった。客観的に登場人物を描き分けているというより、登場する誰彼は主役と同じように遇して描きこまないと気がすまない、そうした性分の結果なのではないか。
小生には上手くスピノザの哲学とジョージ・エリオットの文学的特徴とを重ね合わせたり、スピノザの哲学に共感することを示す典型的な箇所を示したりはできないが、小生の大雑把な直感が、ジョージ・エリオットとスピノザ、ああ、そうかもしれないね、なんて安直に納得してしまっていたりするのである。
