10月25~27日、東京農工大学科学博物館(旧 繊維博物館)(⇒リンク☆)において東京シルク展(⇒リンク★)が開催されました。
26日(土)、台風で朝から大風雨の中・・・シンポジウムを聴きに行って来ました


多摩シルクライフ21研究会代表・小此木エツ子先生の挨拶から始まりました。

お隣は、座長(兼パネリスト?)の古典織物研究家・中島洋一先生・・・魏志倭人伝や延喜式の記載から日本での養蚕や染織をひもとき、それらがどんな用途に使われてきたかのお話。また、先生のお仕事・海外美術館に残る倭錦の再生・『国家珍宝帳』の再生・出雲大社へ奉納した『遷宮の錦』・・などは当時の繭に近い品種で、糸にするのも染めるのも、当時に近づかないといけないご苦労など・・・こちらの先生のお話もとても面白かったです
基調講演は、メトロポリタン美術館終身名誉会員・梶谷宣子先生による『古来、自然と人で成してきた絹文化』と題して、先生がこれまでに出会って印象深かった古布・古裂類の紹介。(紀元前5000年頃の遺跡から発掘されたエジプト最古の亜麻布や、紀元前2700年頃(?)の中国の遺跡から発掘された平織絹布片・・等々)

世界各地の染色品は、古来身の回りにある繊維を使って発展していった。(葉脈繊維・靭皮繊維・樹皮・動物繊維・種子繊維など)古い布を見ていると、それらの繊維の長短や様々な性質によって、繊維がそうしか動かないからそうなった・・・ということが良くわかるのだそうです。
パネリストは、様々な角度から東京シルクに携わっていらっしゃる方々でした。

お写真には写っていませんが・・
大日本蚕糸会蚕業技術研究所前所長 ・ 井上元さん 「蚕品種の将来と展望」
写真右奥から・・・
養 蚕 家 ・ 小谷田昌弘さん 「蚕を飼う」
若手養蚕家 ・ 長田誠一さん 「八王子の養蚕」
撚 糸 業 ・ 森 博さん 「八兆式張り撚りと黒八丈染」
染 織 家 ・ 森久保雅子さん 「八王子・みさき手織工房と共に40年」
染 織 家 ・ 矢村璋子さん 「耐放射線素材で織る 仕上げは蚕」
呉 服 商 ・ 内海康治さん 「絹製品の新しい流通」


夫々に面白いお話が続きました

人気ブログランキングへ
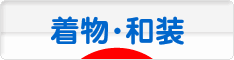
にほんブログ村 ← ブログランキングに参加中

26日(土)、台風で朝から大風雨の中・・・シンポジウムを聴きに行って来ました



多摩シルクライフ21研究会代表・小此木エツ子先生の挨拶から始まりました。

お隣は、座長(兼パネリスト?)の古典織物研究家・中島洋一先生・・・魏志倭人伝や延喜式の記載から日本での養蚕や染織をひもとき、それらがどんな用途に使われてきたかのお話。また、先生のお仕事・海外美術館に残る倭錦の再生・『国家珍宝帳』の再生・出雲大社へ奉納した『遷宮の錦』・・などは当時の繭に近い品種で、糸にするのも染めるのも、当時に近づかないといけないご苦労など・・・こちらの先生のお話もとても面白かったです

基調講演は、メトロポリタン美術館終身名誉会員・梶谷宣子先生による『古来、自然と人で成してきた絹文化』と題して、先生がこれまでに出会って印象深かった古布・古裂類の紹介。(紀元前5000年頃の遺跡から発掘されたエジプト最古の亜麻布や、紀元前2700年頃(?)の中国の遺跡から発掘された平織絹布片・・等々)

世界各地の染色品は、古来身の回りにある繊維を使って発展していった。(葉脈繊維・靭皮繊維・樹皮・動物繊維・種子繊維など)古い布を見ていると、それらの繊維の長短や様々な性質によって、繊維がそうしか動かないからそうなった・・・ということが良くわかるのだそうです。
パネリストは、様々な角度から東京シルクに携わっていらっしゃる方々でした。

お写真には写っていませんが・・
大日本蚕糸会蚕業技術研究所前所長 ・ 井上元さん 「蚕品種の将来と展望」
写真右奥から・・・
養 蚕 家 ・ 小谷田昌弘さん 「蚕を飼う」
若手養蚕家 ・ 長田誠一さん 「八王子の養蚕」
撚 糸 業 ・ 森 博さん 「八兆式張り撚りと黒八丈染」
染 織 家 ・ 森久保雅子さん 「八王子・みさき手織工房と共に40年」
染 織 家 ・ 矢村璋子さん 「耐放射線素材で織る 仕上げは蚕」
呉 服 商 ・ 内海康治さん 「絹製品の新しい流通」


夫々に面白いお話が続きました


人気ブログランキングへ
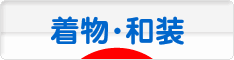
にほんブログ村 ← ブログランキングに参加中

