前回の記事 未読のかたは←こちらを読んでくださいね
もともと子供は感受性が豊かです。
想像力の塊ですし、
色んな可能性やパワーが無限に広がっている存在です。
そして大人になっても私たちは十分に想像力を働かせて生きています。
でもそれが自分であまり感じられない場合
もしかしたら 『感じないように』対処している癖が考えられます。
幼少期の何かが原因で自分の想像力や
何かを素直に感じることを恥じたり、許されない子供もいます。
そうやって大人になると、堅物で融通が利かなかったり、
普段の生活でも『遊び』が少なかったり
自分にとっての『喜び』が感じにくくなってしまうこともあります。
これが顕著になると
仕事や社会的には成功してるにも関わらず
『生きにくさ』や『喜びや幸福感の欠如』として現れたりもします。
前回お伝えしたように、子供は空気も察知します。
親や周囲の人の期待に応えようと自分をねじ曲げたり
自分以外を優先させたり
辛い状況下で
精神を保つために、生き抜くために
あえて『感じることをやめる』子供もいます。
(実際何も感じないのではなく、感じないように押し殺したり抑制したり、という具合に)
両親の不仲や、虐待を受けている子供、
機能不全の家庭で育った子供も
自分が想像力を働かせると、逆に辛さを感じる場合
(自分はモノを作るのが好きだけど、親がそれを良しとしない等も含め)も
『何も感じないようにすれば、辛くない=生きて行ける』ので
脳の中の対処機構が『感じることをストップしよう!』と働きます。
厳しいしつけや宗教などの制約が強くある場合も
たとえば『性』について想像をめぐらせることですらNGとされる環境では
そういう想像をするだけでも
「自分はなんて愚かなことを考えているのだろう、恥ずかしい
 」と
」と思ってしまう子供もいます。
こういう場合、
何かについて『恥』を感じる自分を『ダメだ』と思い込みますので
さらに精神の健全を悪化させる可能性が高いです。
対処機構の働き
これがあるお陰で無事その環境に適して乗り切れるわけです。
精神を保つために、もしくは
子供は自分の力だけで生きて行けませんので
環境に対処することで 『生き延びることができる』 んですね。
*ちなみに幼少期に形成されるその人の『思考』や対処機構は7、8歳頃までに完成し、それから40歳くらいまではその『思考』が続くと言われています。
なので、この『幼少期』がその後もずーっと人生に影響を及ぼすんです。
すごい事ですよね、考えてみると…

残念ながら、無意識で対処機構は働いてくれてますので、
本人は、『苦しい』とか自覚できるまで、そういう『癖』に
気づく事すらも難しい、となっているようです (。>0<。)
大人になっても、子どもの時の対処機構がそのままですので
自分の感覚をあえて感じにくくしている場合があります。
ムリに耐えて、自分の許容範囲以上に頑張って身体を壊したり
人から言われたことは出来るが、
自分であえて考えて行動するのが苦手だったり
何をすれば自分が楽しいか、よくわからなかったり
頭でっかちになってたり
何かや誰かを批評したり意見をいうことはできても、自分で何かを作り出すことが苦手 だったり
男性に多いケースでは
自分の『空虚』を仕事や優秀さで埋めようとしたりもします。
絵を描く事が好きだったAさんは
学校で賞を取った絵を父親に見せて「褒めてもらえる!」と思ったのに
「医者になるのに、絵なんか必要ない(`Δ´)」と一蹴されて
深く傷ついた経験がありました。
厳格な父親の元、頑張って勉強し
医者となり、社会的に成功しているのにも関わらず
なぜか虚しさがつきまとう。それが何故だかわからない。
こういうケースはいくらでもあります。
でも、大人の今でも自分の想像力を回復するのに
遅い ということはないと私は思っています。
回復まで、ちょっとした辛抱は必要かも、ですが。
次回は、想像力や感受性を取り戻すために
今でもできること について
私なりに少しお伝えできれば、 と思います

続きはこちら
皆さんの心がゆるーくなりますように(*^ー^)ノ
応援クリックお願いします☆↓
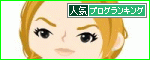
--------------------------------------------
セラピーはおもに東京の世田谷で行っています
心の不調や人間関係の疲れ、親御さんとの問題
自分自身を制限してしまう など
そういうものの原因は、ご自身の幼少期にあるかもしれません。
幼少期の原因を探るインナーチャイルドセラピーに限らず
その他のお悩みもお気軽にお問い合わせください。
セッションに関してはこちらをご覧ください
詳しいセッションのお問い合わせや疑問は
spitrekaori@@gmail.com
@を1つ削ってメールをおおくりください。
もしくはコメント欄に書いて頂いても大丈夫です
セッション希望の方は、お名前とご連絡先、
ご相談内容を簡単で結構ですのでご記入ください


