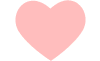平城宮跡資料館は今回展示内容を平城遷都1300年祭仕様にリニューアルしたそうです。
■奈文研ニュース No.33
(PDFファイル) 1/8 平城宮資料館の改修
No.36
(PDFファイル) 1/8平城宮資料館の改修(その2) 資料館見取り図あり
天平時代の役人の仕事部屋や 貴族の部屋などが再現されているとか。
平城京歴史館の復元遣唐使船の上でいろいろ講義しをしてくださったお爺ちゃんおすすめの釘も見なくちゃね^^
 ということで佐伯門を入って左手の「大極殿には行けない」という張り紙があるゲートを通ります。
ということで佐伯門を入って左手の「大極殿には行けない」という張り紙があるゲートを通ります。
真っ直ぐに抜けた先が多分バス停の「二条町」大極殿はこの平城遷都1300年祭の期間は仮の塀で囲われていて入り口が南門になっているので入れないんですね。 お祭りが終わったらどうなるのかはわからいですけど。
資料館の方に歩いていく途中で仲の良さそうなご夫婦とすれ違いました。
ご主人がモグモグと何か食べながら歩いていて、ポロポロ胸にこぼしてるのを奥さんがハタハタと払ってあげているのです。
イタズラっぽい目でウチを見ながら
ご主人「しかせんべい、うまいね」
ウチ「!?」
奥様「いやぁ~ね、鹿せんべいじゃないでしょw」
ご主人「しかせんべい、しかせんべい」
ウチ「?!?!?!?!?」
奥様「オホホホw違うんですのよ、ねえあなた、ってもうもうwww」
しかせんべい・・・甘くないよね・・・っていうか味付けないはずだし・・・・美味しくないはず・・・???
疑問符を頭上に出しながらウチはおふたりを見送ったのでした。
お、大極殿が見える
資料館の入り口にはちゃんとスロープがありました。
スロープを歩いて行く人が多かったです。

階段ちょっと段が高いかな?
開館時間は9:00~17:30(最終入館17:00)
*ただし5/10以降変更ありとのこと。
平日 9:00~16:30(入館は16:00まで)
土日祝 9:00~17:30(入館は17:00まで)の予定らしいです。

入り口ではボランティアさんによる無料のガイドの時間が貼り出されています。
ロビーには大きくて座り心地のいい椅子もありましたよ。

ガイドさんについて行った人たちが居なくなってガランとしたお手洗い前。
このつい立ての向こうがトイレなんですね。
いよいよ展示室に入っていきます。まず目に飛び込んでくるのが大きなジオラマです。
■奈文研ニュース No.34 4/8 発掘調査ジオラマと遺構の記録 この人達はまさか1300年後に同じような建物が復元されるなんて思ってもいないだろうなーw

発掘中のシーン

最後に復元された遺構で憩う(や、韻w本当は遺構じゃなくて遺跡かな?)現代の私たちのシーン
~・~
解説してくださるボランティアさんの博学ぶりにも脱帽。
~・~
手で少しずつ掘ってるんですよね・・・ジオラマの向かい側の壁にもびっしりとパネル展示があって 年表や棚田嘉十郎翁の活躍などがわかるようになっていました。
このガイダンスコーナーの解説の方も詳しかったですよ!
そして大きな大極殿と南門の模型とわかりやすいモニター解説のある部屋を抜けるといよいよお部屋の復元のブロックに。
*官衙(かんが)とは役所とか官庁という意味だそうです。
要は役人の仕事部屋。櫃(ひつ)には巻物がぎっしり!
この櫃も正倉院展で見たことがあるような?
■宮内庁:正倉院 主要宝物自動鑑賞 (最下段)27古櫃(こき)
櫃(ひつ)が書類キャビネットなんですね。

紙と筆で書類を作成したり木簡を作ったり。
 木簡はナイフで削って文字を消すので消しゴム替わりが「刀子(とうす)」という小型のナイフだったらしい。
木簡はナイフで削って文字を消すので消しゴム替わりが「刀子(とうす)」という小型のナイフだったらしい。
■奈良国立博物館 第59回正倉院展 主な出陳宝物 北倉9 小三合水角鞘御刀子
より

ピカピカの刃物は展示されていないけど 錆びた刀子で削ったという設定で置いてある削りカスに字が見えるのがなんだかリアル。

木簡は簡単な出勤簿や荷札などとして使われてたようで 展示室には長屋王の屋敷跡から出た木簡も展示されていました。
アワビですってアワビ!!!
|
前に書いたけど、平城宮跡会場音声ガイド によると
「平城宮は地下水位が高いので木簡を腐らせるバクテリアが活動出来ずに沢山の木簡が残ってきた」
んだそうです。
平城宮跡内を歩きながら
「大和西大寺駅に来るまでの線路脇に『伏見中学校』があったやろ、伏見はもともとは伏水、掘ったらすぐに水が湧く土地によくつけられる地名なんや。京都にもあるやろ」
って言ってたおじいさんが居てはったけどほんまかな?
あ、脱線してしまったw
言いたかったのは、
「木簡は水浸しの状態で1300年間残ってきたので保存は水に浸した状態でされている」
ということ。だから平城宮跡資料館に展示されてる乾いた木簡は多分レプリカなんだろうなって思ってったんだけど・・・・
ってあらー?
乾かしても文字が見にくくならない保存技術が開発されてる!!!!!!
(財)滋賀県文化財保護協会 調査員のおすすめの逸品 No.19
カップラーメンの乾燥技術が応用されてるんだって!![]()
これ奈良県でも導入されてるのかな?
■平城宮跡の散歩道 2008.7.21に書かれた 「発掘された木簡は、こうして処理される! 」に工程写真がありました。
2年後の今はどうなってるんでしょうね。
■平成13年11月3日に行われた 第89回奈良文化財研究所公開講演会 古代の証人「木簡」を次の世代へ(PDFファイル) . 埋蔵文化財センター・高妻洋成さん
によると保存処理に時間がかかるので(長いものだと二年!)やはり沢山の木簡が水漬けの状態でで保存処理を待っているそうです。資料の最後に今回の平城遷都1300年祭でリニューアル展示してあったのと同じ壊れた文書箱や硯の載った黒ずんだ片足の机の写真があったので やっぱりあれは・・・・
大遣唐使展に長屋王木簡が展示されてたのであっちが本物?
それともどちらもレプリカ??
奈良国立博物館の大遣唐使展の出品一覧 を見ると本物を2枚ずつ 1~2週間ほどで入れ替えて出展してるようです。それだけデリケートな物でしょうね。
デスクと椅子でお仕事して、書類いっぱい作ってるって
お役人さんのお仕事は1300年前とそんな変わってない?w
発掘品展示ケースにあった木靴。靴履いてたんだね。
宮殿復元コーナー
正倉院御物のレプリカで当時の皇族貴族の生活を再現したコーナーです。

こちらも絨毯の上にベッドが置かれた洋風で今風な室礼。

ただしスノコ状のベッドの上には畳が置かれていたようで畳屋さんが熱いサイトを立ち上げておられました。
■能登畳店 現存する最古の畳 日本最古の畳の在り処 御床畳残欠 御床
後ろに立っている屏風は
鳥毛帖成文書屏風
という王羲之の書体の上に鳥の羽を植えつけてある正倉院御物の屏風の複製品。
内容は
種好田良易以得穀 種好く田良きは、以て穀を得易し。
(良い田んぼに好い種を蒔けば沢山収穫しやすい)
君賢臣忠易以至豐 君賢に臣忠なるは、以て豐に至り易し。
(賢い王様と裏切らない家来だったら国は豊かになりやすい)
諂辭之語多悦會情 諂辭の語は、悦び多く情に會ふ。
(おべっかとかごますりの言葉は 聞くと嬉しいし受け入れやすい)
正直之言倒心逆耳 正直の言は、心に倒らひ耳に逆らふ。
(正直なアドバイスは受け入れにくいし聞きたく無い)
正直爲心神明所佑 正直を心と爲せば、神明の佑くる所あり。
(真っ正直に生きれば天の助けもあるものだ)
禍福無門唯人所招 禍福は門無し、唯だ人の招く所なり。
(わざわいも幸福もここから入ってくると決まった門のようなものはなくて
どちらもただその人の行いが招くものだ)
父母不愛不孝之子 父母は不孝の子を愛さず。
(親孝行をしない子供を両親は愛さない)
明君不愛不益之臣 明君は不益の臣を愛さず。
(きちんとした王様なら役に立たない家来を愛さない)
清貧長樂濁富恒憂 清貧は長く樂しみ、濁富は恒に憂ふ。
(貧乏でもガツガツしないで清らかな気持ちで居られるなら長く楽しく暮らせるけれど
賄賂を取ったり権力闘争したりお金をかき集めようと企んでる人の心はずーっとイライラしてる)
孝當竭力忠則盡命 孝當さに力を竭すべく、忠則ち命を盡す。
(親に従うのには全力を尽くすように、王様に従うのには命を尽くす)
君臣不信國政不安 君臣信ぜざれば、國政安からず。
(王様と家来に信頼関係が無くて国政がちゃんとするはずが無い)
父母不信家閨不睦 父母信ぜざれば、家閨睦まじからず。
(両親が不仲なら家がちゃんとするはずがない)
■参考サイト 斎藤拙堂研究会 百五十一回例会 『鐵研餘滴甲集』 巻四から
「玄徳失箸」「鳬毛屏風銘 」「小松内府像」の三編を講読
()内はウチのいい加減なざっくり意訳なので恥ずかしい><。
要するに聖武天皇は
「ちゃんと夫婦仲良しかい?
親孝行してるかい?
権力や金に執着してないかい?
お前の家来はちゃんとしてるか?
お前は家来に信用してもらえる王様なのか?
お世辞ばっかり言う奴を重用したりしてないか?
ちゃんと苦言を受け入れてるか? ・・・etc」
という戒めの書かれた屏風を側に置いて暮らしてたんですね。
その隣は書斎を再現してあるのかな。文机と文箱 奥の棚には巻物が。

文机の奥にある巻物を読む専用の台「書几(しょき)」は現代にはないものですよね。
手前の黒い肘掛にもたれて読んだらしいです。

正倉院御物にある碁盤
と双六盤を模しているように思われます。吉備大臣が唐で日月を封じ込めたのはこんな双六盤だったのかも?w
琴は六弦(琴柱が6個)に見えるので和琴ですね。
木材の色を変えて螺鈿の燕尾模様を表現してあってこれはこれでステキ。
■錦絵に描かれた音楽 音楽のある風景 「正倉院の楽器」
図12
本物ソックリに復元した劉宏軍氏のサイトには復元品のカラーの写真
があります。
*上海万博で演奏会を開かれたそうです!CDを買えば天平の音色が聴けるんですね。
碁盤・双六盤・和琴ともに螺鈿などの装飾が省かれたシンプルな仕上がり。天平時代の本物は螺鈿の貝がゆらゆら揺らめく灯明の明かりに映えてさぞ美しかったでしょうね。
壁際の屏風は有名な「鳥毛立女屏風
(とりげりつじょのびょうぶ)」のレプリカ。意外に小さかったです。本当は表装されていて絵の周りにある錦の幅分大きかったかも。
ちなみに青地の花柄の絨毯に見えるのは 花氈(かせん)と呼ばれるフェルト状の敷物です。
この花氈については ハンドメイドの方でまた書きますね。
黒漆塗りのシックな食器が低い膳台に幾つも並べられていて中には鴨肉のローストとかアワビとかご馳走がいっぱい!
白瑠璃瓶(ピッチャー)

白瑠璃碗
■よみがえれ現代のシルクロード 正倉院の宝物
より
正倉院に伝わった「白瑠璃の碗(はくるりのわん)」は副葬品として土に埋められることがなかったので世界にたった一個だけ 作られた当時のままの輝きで今も存在しているんだそうです。
■石原美術 古美術及び物故作家 最下段 ササン朝ペルシア白瑠璃碗より
なぜなら昔の砂から焼いて作ったペルシャガラスの器は土中に埋められてしまうと成分が変化して表面に薄い銀の膜が張ってしまったり、長く土中にあると還元作用でもとの砂の成分に戻りかけて 透明じゃなくなってしまったりするからだそうです。
日本の大阪にある 安閑天皇陵出土のガラス器は白瑠璃の碗にそっくり。上の2段のカットがまん丸だけど。
■東京国立博物館 館蔵品詳細 ガラス碗
(がらすわん)より

ペルシャの出土品もそっくりな形だけれどもう透明ではなくなってしまっています。
■写真でイスラーム 白瑠璃の碗とペルシア
より テヘラン国立博物館蔵カットグラス
欲しいなと思って探すと正倉院ガラス器のレプリカを売っているお店発見!
こんなレプリカで飲むお酒はきっとおいしいんでしょうね。
■東京ヴェリエ Top>企画事業>復元品>「正倉院ガラス器 」
☆★正倉院のガラス器の復元をされたガラス作家 由水常雄氏のサイト
*由水常雄氏は1992年に東京ガラス工芸研所:発行 東京ヴィリエ:発売
「パート・ヴェールの技法」という本を出版されています。
バックに立っているのは
クイズの答えは次回です~~
*遺跡クイズです !
また別にUPしますねー
ん~~~ 何食べてたのか気になる~~w