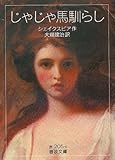そういえば見たことなかった…と、古い映画ながらも見てみましたのは
リチャード・バートン、エリザベス・テイラー主演の「じゃじゃ馬馴らし」。
原作は(言わずと知れた?)シェイクスピア
であります。
スカパーなどで古い映画が放送される時に、
今のご時勢にこの表現はどうよ?的なところがでてきますがご容赦ください…
てなふうな画面が出てくることがありますですね。
往年の東宝喜劇あたりなぞはさしずめセクハラおやじの軍団のようでもあり。
翻ってこの「じゃじゃ馬馴らし」ですけれど、
全く話を知らないままに見ましたですが、いやはや驚きましたですね。
こういうのを「DV」って言うんでないのと思ったりもしたですよ。
パドヴァのお金持ちバプティスタには二人の娘がおり、
妹ビアンカの方はおとなしくて可愛らしいところから求婚者が絶えない状況。
これに対して姉ケイト(エリザベス・テーラー)はといえば、口をひらけば悪口雑言、
身を翻せば乱暴狼藉、そのじゃじゃ馬ぶりは広く知れわたり、男性には悉く逃げ出すばかり。
そんなところへ、
持参金さえ詰まれるのなら全く構わないという御仁ペトルーチオ(リチャード・バートン)が現われ、
脅し賺しのあれこれを弄して父親からもケイトからも結婚の約束を取り付けてしまう。
結婚式も早々にケイトを自らの屋敷に連れ帰る途上から
すでに妻を手懐ける作戦に出るペトルーチオ。
ですが、その手法たるや居丈高に相手を捻じ伏せるようでもあって、
そりゃあ実に酷いものだなと。
この辺の感覚は現代は元より、この映画が撮られた1960年頃でも(今ほどではないにせよ)
違和感を抱く人はいたろうと考えると、シェイクスピアの時代が今とは
随分かけ離れた感覚であったのかと思ったり。
だもんですから、原作とこの映画の間にどれほどの違いがあるのか無いのか、
気になったので戯曲「じゃじゃ馬馴らし」を(今回は岩波文庫版で)手にとってみたのでありますよ。
そうしますと、ペトルーチオとケイトとの関係は
基本的に原作をなぞっているのだなと分かりましたですが、ペトルーチオという人物は
映画で見る以上に、持参金付きならどんな女性でも構わない度合いが強い、
そして相手がじゃじゃ馬と聞いたときにその対処法を「鷹の訓練方法」に擬えて語っている
てなことも見つかる。
つまり、ペトルーチオという人物がはから女性を金づる(つまりはモノ)、あるいは
手懐けられるべき鷹(つまりは動物)とも見ていて、ヒトとは考えていないとも言えそうです。
だからこそ、ケイトへの対し方は(ケイトを当然にヒトと見ている側からすれば)
この上なく惨いものになるわけですが、こうした一貫性はペトルーチオが
逆に手懐けやすい人物にもしているようで。
ケイトの人物像や心理の動きは原作でも情報が少なく、推測するしかないのですけれど、
その手懐けやすさに付け込むコツを早々に気が付いたのではないですかね。
要するに「従って見せる」というコツを(こうしたことが婦人の鑑のように思われた時代もあったかと)。
原作にもあるところですが、夫妻で妹ビアンカの結婚式に向かう場面で
真っ昼間に空を見上げてペトルーチオは「きれいな月だ」という。
ケイトが太陽だと言うと、ペトルーチオは結婚式には行かないと言い出す。
結局のところ、ケイトがペトルーチオの言うことに肯定すれば満足し、
そうでないと「お家へ帰る」とだだをこねているのと一緒。
これは見透かされて当然でありますね。
こうしてみれば、あらゆる場面で
ケイトがさも夫に従順になった(じゃじゃ馬が馴らされた)と見えて、そう見えることに
嬉々としているペトルーチオはとんだ道化の役回りを振られていると言えるのではなかろうかと。
特に最後の部分でケイトが夫に対して従順であることの徳を語る長台詞を、得々として聞くあたり。
まあ、そんなふうに考えることもできるわけですが、
映画の場合は場面描写が視覚的である分、インパクトが強く、
ペトルーチオの振る舞いが刺激的にもなってしまうのではなかろうかと。
そうであればこそ、演出がすごく大事な要素になってくる話なのでしょう。
演出という点では、映画では省かれていた序幕の存在、
そして序幕に対して入れ子の関係の劇中劇として演じられていた「じゃじゃ馬馴らし」の
話が終わると、序幕の結びはどこへやら、ただちに全編の幕が引かれるという構成も、
演出がうまくなされないとちぐはぐなものになってしまうようにも思われます。
(ただし、シェイクスピアの時代、入れ子の中身の終結でお終い…という芝居もあったようです)
難しい芝居なのだと思いますね。
あまり上演されないのもやむなしというべきでありましょうか…。

![じゃじゃ馬ならし [DVD]/エリザベス・テイラー,リチャード・バートン,シリル・クザック](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51AlXX092PL._SL160_.jpg)