| この項目では、国家について説明しています。大陸については「オーストラリア大陸」を、その他の用法については「オーストラリア (曖昧さ回避)」をご覧ください。 |
- オーストラリア連邦
- Commonwealth of Australia
-

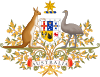
(国旗) (国章) - 国の標語:なし
- 国歌:アドヴァンス・オーストラリア・フェア

-
公用語 英語 首都 キャンベラ 最大の都市 シドニー 独立 イギリスより
1986年3月3日[2]通貨 オーストラリア・ドル (AUD) (A$) 時間帯 UTC 不明(DST:-75から+93) ISO 3166-1 AU / AUS ccTLD .au 国際電話番号 61 - 註1 : 国歌は公式には『アドヴァンス・オーストラリア・フェア』であるが、女王や総督が臨席する場合には『女王陛下万歳』が用いられる。
オーストラリア連邦(オーストラリアれんぽう、英語: Commonwealth of Australia)、またはオーストラリア(Australia)は、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成りオセアニアに属する国。日本では、豪州(ごうしゅう)とも呼称される。メリノ羊が放牧されている。
目次
1概要
2国名
3歴史
3.1先史 - 人類の移動、居住、氷河期の終焉
3.1.1更新世の地球環境、人類の移動
3.1.2人類の居住以降
3.1.3氷河期の終焉
3.2ヨーロッパ人の到達以後
4地理
4.1動植物
4.2環境問題
5政治
5.1地方自治
5.1.1概要
5.1.2全国の地方自治体数
5.1.3地方行政区画
6軍事
7国際関係
7.1日本との関係
7.2MIKTA
8地方行政区分
8.1州
8.2その他の特別地域
8.3主要都市
9経済
9.1基本情報
9.2産業
10国民
10.1民族
10.2言語
10.3人名・婚姻
10.4宗教
10.5保健
10.6教育
10.7人種差別問題
10.8難民
11文化
11.1芸術
11.1.1演劇
11.1.2舞踏
11.2メディア
11.3映画
11.4文学
11.5音楽
11.6料理
11.7スポーツ
11.7.1ラグビー
11.7.2クリケット
11.7.3競馬
11.7.4サッカー
11.7.5バスケットボール
11.7.6モータースポーツ
11.7.7競泳
11.8世界遺産
11.9ナショナルカラー
11.10祝祭日
12脚注
13参考文献
14関連項目
15外部リンク
概要
オーストラリアの総面積は世界第6位である。近隣諸国としては、北にパプアニューギニア・インドネシア・東ティモール、北東にソロモン諸島・バヌアツ、南東にニュージーランドがある。
2014年、同国の一人当たりの国民所得は世界第5位であった[6]。同国は国際連合、G20、イギリス連邦、ANZUS、経済協力開発機構 (OECD)、世界貿易機関、アジア太平洋経済協力及び太平洋諸島フォーラム加盟国である。
18世紀末期における最初のイギリスの植民までの少なくとも4万年の間[7][8][9]、おおよそ250の言語グループに分類される言語話者の先住民が居住してきた[10][11][12]。彼らの食文化ブッシュ・タッカーは1970年代から注目された。
1606年におけるオランダ人探検家によるヨーロッパのオーストラリア大陸発見後、1770年にイギリスが同大陸の東半分を領有主張し、1788年1月26日からニューサウスウェールズ州の植民地に初めて流刑を通じて定住が開始された。その後の数十年間で同大陸の調査が行われ、人口は着実に増加し、さらに5つの自治王領植民地が設立されていた。
19世紀前半にメリノ種の牧羊が普及した。1859年に持ち込んだウサギが牧草を食ってしまい、羊毛生産量を減じた。バサーストに始まったゴールドラッシュの開拓者に食わせる肉が必要だった。19世紀後半には鉄道が敷設されてゆき、あのケーブル・アンド・ワイヤレスが陸揚げを果した。経済は羊毛からジリ貧となって、義賊ネッド・ケリーが出た。彼はメルボルン万国博覧会の期間中に処刑された。ベアリング恐慌がオーストラリアにも響いて1893年5月頭バンクホリデーに陥った。
1901年1月1日、6つの植民地が連合し連邦を形成後、6つの州及びその他特別地域から成る連邦議院内閣制及び立憲君主制の役割を果たす安定した自由民主主義の政治体制を維持してきた。2,360万の人口は、高度に都市化された東部の州及び沿岸部にかなり集中している[13]。パリ講和会議には、首相ヒューズが全権代表として参加した。太平洋の旧ドイツ領諸島の帰属については、日本と激しく争った末に、赤道を挟んで北側を日本が、南側をオーストラリアがC式委任統治領として確保することで妥結した。また、日本が提案した人種平等案(国際連盟規約への人種差別撤廃条項挿入)に対してはカナダと共に反対し、これを阻止した。ワシントン会議では蚊帳の外に置かれたが、1925年には太平洋問題調査会がホノルルで発足、1961年まで活動した。
1950年、フランク・フェナー博士(Frank Fenner)が指揮する調査のあと、野ウサギを駆除するため粘液踵症ウイルス(天然痘の遠い親類)が撒かれた。半年足らずで蔓延し、個体数を二度と繁栄できない数にまで減らした。
1960年代と1970年代は激動期であった。羊毛主体であった産業構造は鉱業主体となった。この間にまずポセイドン・バブルが起きた。それから国際的に遅れて変動為替相場制をとった。また、この期間にオーストラリア系銀行は日本・香港・マレー半島を除く極東地域で支店数を増やした。1961年にたった12店舗であったのが1978年に528店舗となり、これほどの急展開を諸外国の銀行に見ることはできなかった[14]。1986年、ロイズ銀行がスタンダードチャータード銀行に買収をしかけたとき、主役のロバート・ホームズ・アコート、HSBCの包玉剛、メイバンクのクー・テクバ、以上の三人が阻止に成功した[15][16]。ロバートの出身はイギリスのヘイツベリー(Heytesbury)男爵の閨閥であるが、ヘイツベリーは19世紀初期の腐敗選挙区であった。ホワイトナイトを演じたロバートは、スタンダードチャータード銀行のトップ・マネジメントに迎えられた[17]。クー・テクバはスタンダードチャータード銀行の重役を辞めた[16]。一番上の息子邱万福(Khuu Ban Hock)はブルネイ国立銀行(National Bank of Brunei)元会長であったが、同行で金融犯罪に手を染め折り悪く有罪を認めていた[18][19]。ブルネイ国立銀行はクーが王族と出資割合7対3で1965年に創立したが[20][21]、ブルネイ通貨委員会の設立が2年後であるのと比べて早い。この1986年にはHSBCと懇意の李嘉誠が万科城市花园别墅(Vanke City Garden)を中国光大グループに売却し内部者取引として非難を浴びているが[22]、2000年Powercor Australia を買収[23]、2013年PA親会社の南オーストラリア電力の持つ利権をめぐって税務署と衝突し[24]、2017年1月現在も電力事業の買収を続けている[25]。2014年7月、マレーシア・インドネシア・ベトナム各国政府高官と関係する汚職について、過去のものを含むあらゆるメディアがオーストラリア政府の命令で検閲を受けていたことが、オーストラリア準備銀行筋でウィキリークスの公開により明らかとなった(英語による詳細)。この翌年にマレーシアで1MDB をめぐる汚職が報道され、パナマ文書が捜査に活用された。
国名