- 新世界より 上/貴志 祐介
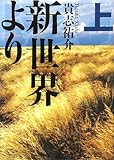
- ¥1,995
- Amazon.co.jp
- ¥1,995
- Amazon.co.jp
遠未来、日本。激減した人類は呪力と呼ばれる超能力を手に入れ、牧歌的な生活を謳歌していた。
しかし、それは閉じられたユートピアに過ぎず、一歩町の外に出れば、悪夢のような生物が闊歩している。
グロテスクなまでに二極化された世界はどうして作られたのか?
作品解説。
ナウシカを書こうとしたら漂流教室になってしまいました。
おわり。
で、全てが言い表せる話。
世界観はすごく好みだけど、あまりにグロテスクすぎる点と、記号的なキャラクターという点
以上2点において、好きじゃない。
遠未来だけど、昭和初期みたいなレトロな雰囲気、
呪力(=魔法、超能力)を学校で習う、というゲーム的な面白さ、
なおかつ、そこに妖怪話のように、奇妙な生物を盛り込み、
その冒険がやがて、世界の根幹の秘密に関わっていく。
うーん。
山盛りだくさん。面白い。お腹いっぱい。
これでキャラクターが生きてさえいれば…!
物語の骨子は、性悪説で、人の憎悪と争いという業によって、人類のみならず、世界が改変されてしまいました。
というもの。
だけど、主人公たちが勇気を忘れず、真実にもめげず、頑張って世界をよりよくしていきます!
まだまだ、人間には絶望しないぞ、きらきら!
というメインテーマがありつつ、あくまで作者目線=世界構成は、限りなくグロテスク、という。
物語の要素としては、
1、ハリー・ポッター的な、異能力を学校で習うという、エンタ要素
2、図書館戦争に代表されるような、”本て素晴らしいのよ”メッセージ
3、マン・アフターマンで描かれた、とんでも生物
4、手塚治虫時代の超能力少年漫画要素
5、遠未来だけど、昭和初期(ALLWAYS)ぽく仕上げたら面白いんじゃない?=団塊の世代、以降ターゲット
6、戦略ゲームの要素
7、大人対こども
という、とても元ネタや狙いが分かりやすいもの。
作者は40代なので、おそらく、子供時代に冒険活劇漫画に憧れ、
その憧れを維持したまま、今流行りの要素(1,2)、現代っこに好まれる要素(6,7)をぶち込みつつ、
同世代、少し上世代にも通じる要素(4,5)も混ぜた高等技。
それを、きちんと消化して自分のものにし、
破綻なく最後までぐいぐい読ませる構成、ストーリーテリングが、このひとのすごい才能。
この分厚さ、説明的過ぎるという難点を持ちながらも、先の展開で興味を引き、
セクシー要素も随所に織り交ぜてサービスしながら読ませるのはさすがエンタ作家。
だがあざとい。
作家には二種類居て、天性の作家と、努力してなった作家とがいるけど、
このひとは後者。
書き始めの頃は相当文章下手だったんだと思う。
やけに説明的だったり、まるで機械を組み立てたような、構成立てといい。
だけど、不断の努力と、話を纏め上げる力で、結局は売れっ子作家になったんだろうな。
ずば抜けたセンスがあるから作家になれるわけじゃないんだよね。
本も結局は商品だから、誰でも読みやすく、心惹かれる要素をどれだけ練り上げて、
読者に親切に作れるかが、筆で食ってく作家に一番必要だと思う。
んで、このヒトはエンタ作品として、素晴らしい技術を手に入れた、と。
話がずれた。
気に入らない要素ナンバーワンについて。
あまりにグロテスクすぎる物語背景。
絶対的な性悪説。
まさに、”万人の万人に対する戦い”をホラーにしました、とう成り立ちが気に入らない。
特に、凄惨な惨殺の歴史を延々紡いでいくシーンは、本当に必要があったのか?と首を捻ってしまう。
人間は放っておいたら憎みあい、殺しあう存在で、
無意識においても世界を歪めてしまう絶対悪だ、っていうのが骨子なんだけども、
そこまで酷くしなくても…と思ってしまう。
業魔の存在や、漏れ出した呪力でグロテスクに作り変えられた悪意の具現化、
更に、化鼠の存在。
むしろ、その発想に吐き気がする。
人間が貪欲で、人類以外にはぞっとするほど冷酷で、というのは分からなくはないけど、
そもそも、そういう発想が出てくること自体が問題だと思うから。
個体間で殺しあうのは人間以外も同じだし、その根本は生存競争で、
生存競争として許される範囲を超えた、憎悪と殺し合いが、性悪説の論拠なんだろうけど、
女王を頂く社会形勢の生物を、人間の倫理基準に照らして”気持ち悪い”と言い切ってしまう発想を
作者が持っていることが根本的な問題だと思う。
それを主人公にあえて言わせることによって、”所詮人間なんて、エゴイスティックでグロテスクな存在”
ということを表したかったのかもしれないけど。
”人類てこんなにグロテスクな、悪意に満ちた存在なんだよ”と、
警鐘を鳴らしているつもりかもしれないけど、
その前に、そういう発想を持ってしまうこと自体が、そのグロテスクな想像の根幹だとなんで気付かないんだろう。
そう、受け入れられない違和感の一番の要素はここ。
作者はこの物語を作りあげることによって、
人間てグロテスクなんだよ。罪深いんだよ。
それを、僕が教えてあげるよ!人間は理性で持って、常に改革していかなくちゃいけないんだ。
といったメッセージを発してる。
けど、そういう発想をしてしまうこと自体が問題だとはちっとも気付いていないようで、イヤ。
ナウシカだったら、
人間は闇に瞬く一筋の光だ!みたいな、
グロテスクだけど、それすらも生きるっていうひとつの形で、苦しみながら、傷つけ、傷つきながらも
それでも生きていこうするから美しい、
って結論だからこそ、人の心を打って、残る物語に昇華されてるわけだけど、
これは、
人間てグロテスク。
で終わっちゃってるから、単なる漂流教室。ホラーエンターティメントで終わってしまってる。
まぁ、漂流教室も面白いし、けなげに頑張るこどもらが、結構希望だったりしていい作品なんだけども。
主眼が、モンスターホラー+人の心ってグロテスク!だからね…
んで、それを和らげるためにキャラクター配備がなされてるわけだけど、ここに更に問題が。
キャラが死んでる。
物語を運ぶ要素以上の働きが無い。
魅力が無い。
愛情と、強さを体現しなくちゃならない主人公はとにかく気が強く、理詰めで人を説き伏せ、
人より優位に立たなくちゃ気がすまない性格で、
他のキャラは、気が強いけど頭の足りない美少女、完璧超人だけど早逝する美少年、
ほら吹きだけど、いざという時は頼りになる幼馴染、凡庸な引き立て役。
この、一言紹介できる性格を少しもはみ出ない記号的人物ばかり。
物語に必要な役割としては十分なんだけど、人間を読みたい、という基本的欲求を満たすには役不足。
初期のポリゴンアニメのキャラみたいな感じ?
まぁ、キャラクターを描けるというのは、それこそ天性の才能だから、
そこまで求めるのは酷かもしんないけど、
話が面白いからこそ、更に上を求めて欲してしまうわけで。
主人公の要素としては、ナウシカ的な、強く猛々しいけども、限りなく優しい、
そんなものを目指したらしいのは分かるんだけど、
時には人を説き伏せ、時には誰よりも頭が良く、
なのに肝心なところでいきなり頭が悪くなるという、よくわからない存在に。
”悲しみを乗り越えられる、しなやかな心の持ち主”
というのがコア要素なんだけども、だったらそれはエピソードで語るべきなのに、
周りが”でもあなたは強いから”と説得する、という方法で語ってしまっていて、
台無しに。
はたして、この主人公がとても好きです、勇気付けられました、というひとはどれだけいるんだろう?
世界観はとても面白かったけど、
以上2点の大問題で、この作者の本は読むのを止そう、と思ってしまった。
