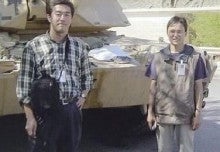『週刊文春』(2003.12.11)
総力特集「新聞・テレビが絶対に報じない」
「イラク外交官テロ全真相」
特集の最後:
「独占入手!絶筆:故奥克彦参事官が死の直前に書いたイラク復興への思い」
人間は死に直面した時、脳細胞の記憶の箱が次々と開けられ、そこから様々な映像が飛び出すという。故奥克彦・外務省参事官は、襲撃現場から病院へ搬送されてから亡くなったと伝えられている。チクリットの犯行現場で意識がなかった、というが、もしかすかにでもあったとすれば、遥か日本と約八千キロ離れたかの地で倒れた彼の脳裏には、いったいどんな映像が浮かんでいたのだろうか――。
〈(紛争後における軍隊の役割について―イラクの実例から)〉
そして、その仕上がり間近の原稿の内容について、奥氏自身、こう綴っていたという。
〈イラク復興に関与しているアメリカ軍を中心とした各国の戦闘要員である軍隊が、ポスト・コンフリクト(地域紛争後)において果たしている役割、例えば民政部門の復興への関与について、私が見た、体験したイラクでの実例を挙げながら解説する予定。その上で、今後のイラク復興の方向付けについての意見を展開します。イラクでは、連合暫定施政当局(CPA)よりも、むしろ軍関係者が治安維持という分野を越えて、さまざまな分野に関与している。つまり、軍が事実上の「行政」を取り仕切っている。こういったイラクの実例は、これまで国連のPKOが行われたコソポ、東ティモール、またアフガニスタンと比べてもまったく異質なるものである。これからも起きるであろう紛争後の社会の安定、経済発展を考えるうえでは、さまざまな示唆を提示していることをお伝えしたい。
******************************
もう、15年も前に尊い命をイラクの地に吸われた「奥参事官」の思い。
しかし、いまだ日本は、「積極的平和主義」と言っただけで、
マスコミがつつき放題に非難する。
国連による全面統治が必要だといった“きれい事”ではすまされない。
イラクという国家のシステムが、実態として何によって安定が保たれているのか、
その現実に立った上での「イラク復興」を考えなければならないことを彼は強調していた。
そして国連だけで行うことの限界を知り、軍という組織を抜きにしてすべてが語れないという
“本当の現実”を伝えたかったのではないか、と私は見る。
国連をもっとも良く知る彼だからこそ、その“現実”を語れたのだ。
さらに、日本人こそ現実と真正面から向き合わなければならない
――それを言いたかったのではないか――。
彼をよく知る関係者は、派遣先のサマワを駆け巡った奥氏にとっての、
国際社会への日本の責任としての自衛隊派遣の意義
――アメリカ軍支援とは別の復興支援部隊としての意義がそこに説かれているはずだ、と語る。
いまこそ、「奥参事官」の「思い」に立ち返る必要があるのではないですか?