カウンセリングを語る(上) (講談社プラスアルファ文庫)/河合 隼雄

***
「私も本を書いておるわけですが、
思いますのは、本を書くときは、
どうしても典型的なことを書くわけですね。
非常に典型的な、
しかもうまいこといった話を書くんです。
ところが、
そのようにうまくいく典型的な人は
非常に少ないんです。
(by 心理療法家 河合隼雄)
***
「こうすれば、こうなる」
という因果律に現代人は縛られている。
河合先生は、いろいろな本で
因果律の危うさを指摘してきました。
例えば、ある少年が事件が起こす。
その少年が片親だったとする。
すると、マスコミはすぐに
「片親だから少年は事件を起こしたのでは」と、
因果関係で結びつけ、裁いてしまう。
片親が「原因」で、少年の事件が「結果」です。
「そんなアホな話があるか」
と、河合先生は憤る。
人はもっともっと
様々なものを背負って生きていて、
たったひとつの要因らしきものをとりだして
「事件が起きた」とさわぐのは、
そうしたほうが、わかりやすいからであり、
因果律は「わかりやすい」がゆえに
人をとりこにして、
つまり、不可解な複雑なものから
巧妙に目を背けるそれらしき理由となり
私たちを楽にさせてくれます。
人は易きにながれる。
さまざまな本に書かれてある
典型的な例もまたそれと同じで、
典型的な例が提示され
「こうすればうまくいきます」
と言われ、もしその通りになならないと
著者を批判する人もいるし、
人によっては、
著者のことを無能よばわりすることもある。
特に「人」のことに関しては、
「こうして問題が解決した」という典型例が、
別の人にとって典型例となりえいないのは、
時間も場所も、まして「人」も違うわけで、
「40代の中間管理職と20代の部下の関係」
といった時に、会社が違うだけで、
どれだけ違う要素がその問題に入り込んでくるかを
そういわれれば、私たちは、
容易に想像することができます。
ただ、本を読み、典型例として説明されると、
いとも簡単に「我が事例に応用可能である」と
過度に思い込み、それでうまくいかないと、
短絡的に「著者が悪い」となってしまう。
トイレ掃除すると仕事がうまくいく、
金運がアップする、
と本に書かれている。
そうなる人もいれば、
そうならない人もいるのが現実です。
典型例に縛られず、
典型例が典型例とならないことに腹をたてず
自分でよくよく考え、
淡々と努力をつづけていくことが大事なのかな、
と、書くと、
これまたそれが典型例かと責められそうですけど(笑)
「今日の言葉」の深いところにあるものは、
真実は実のところ、
自分自身が知っているということかなと思います!
松山淳
〈個人セッション〉4月の予定
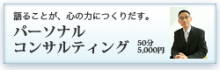
50分 5,000円~
★5,000人を越えるリーダーたちが読んでいるメルマガ!
『リーダーへ贈る108通の手紙』
