
¥1,995
Amazon.co.jp
ウィリアム・コッツウィンクル(内田昌之訳)『ドクター・ラット』(河出書房新社)を読みました。
河出書房新社の、ちょっと奇妙な雰囲気が漂う作品を集めたシリーズ「ストレンジ・フィクション」の中の一冊です。
いやあ、これはなかなかの問題作ですね。でも、ぼくはこういうの嫌いじゃないです。まさに「ストレンジ・フィクション」にふさわしい一冊だと思います。
ぼくが単純に「好き」ではなく、「嫌いじゃない」と言わざるをえないのは、この小説が何ともグロテスクで、クレイジーな物語だから。
人間に捕えられ、繁殖させられ、残酷な実験をされているねずみたち、そして世界中の動物たちが、次第に人間に対して暴動を起こすようになるんですね。
単純に人間の支配から逃れようというのとは少し違っているんですが、ともかく、動物たちみんなが、一つの場所を目指して大移動をしていきます。
そんな動物たちに同調しないねずみが一匹いまして、それが物語の主人公ドクター・ラット。
自身も手術で睾丸を切り取られ、迷路の実験で狂気に追いやられていながらドクター・ラットは、人間の立場に立ち続けます。
死こそ解放なり、というのがわたしのスローガンだ。わたしは仲間のラットたちのためにできるだけのことをして、最高の助言をあたえている。結局のところ、最終溶液(五パーセントのホルマリン)は死であり、死こそ解放なのだ。
(4ページ、本文では「最終溶液」には「ファイナル・ソルーション」のルビ)
人間の立場とはつまり、実験によってねずみを傷つけること、もしくは或いは結果的に殺してしまうことは残虐な行為ではなく、科学の進歩のために必要なことだという立場です。
さて、物語はほとんどが一人称で進んでいきますが、その視点の持ち主は章ごとに違います。
大体ドクター・ラットと、その他の動物たちに大別できて、ドクター・ラットの部分は繋がった一つの物語なので、わりと読みやすいです。
その他の動物たちの章は、章ごとに様々な動物の一人称で紡がれていきます。
鮮烈な印象がありながらも非常に断片的なので、こちらはドクター・ラットの章に比べて、多少読みにくい感じはあります。
ただ、極端なことを言ってしまえば、ドクター・ラットの独白以外の部分は、大まかな流れさえ分かっていればよいので、雰囲気だけつかめれば大丈夫です。
人間の実験の残酷さがグロテスクなぐらいに強調されていますし、何と言っても頭の狂ったねずみが主人公の物語ですから、好き嫌いの分かれる小説であることは間違いありません。
しかしながら、何とも不思議な印象の残る小説なんです。
動物たちの大移動は、地球の最後を描いたいわゆるパニックものにとてもよく似ていて、たとえば、ローランド・エメリッヒ監督の『2012』とかの、あの感じです。
2012 エクストラ版 [DVD]/キウェテル・イジョフォー,ジョン・キューザック
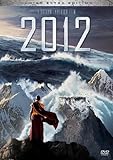
¥2,980
Amazon.co.jp
『2012』は、地殻変動により地球が滅びゆく中で、唯一生き残るための手段である宇宙船に乗り込むために奮闘するという物語。
『ドクター・ラット』は突如現れた危機を描いた物語ではありませんが、一つの目的のためにみんなで同じ行動をするという点で、とてもよく似ています。
動物たちは大きな賭けに出たわけです、すべてを得るか、すべてを失うか。
この物語を動物側から描けば、宇宙人の侵略に対抗する人間の物語と同じような物語構造になったはずです。自分たちを虐げる存在に立ち向かう物語。
或いはそれとは逆に、この物語を人間側から描けば、突如現れたゾンビに襲われるホラー映画のように、不気味な存在と戦っていく物語になったはずです。
しかし、この小説の主人公は、人間ではなく、かといって動物側でもない、頭の狂ったねずみ、ドクター・ラットでしたね。
人間VS動物の物語ではあるんですが、それがドクター・ラットという奇妙な存在から描かれることによって、単純な物語構造の小説とは一線を画した物語になっているんです。
それだけに、単に動物愛護を訴えた物語とは明らかに違っていて、分析しきれない不思議な感情が、心に残ります。
作品のあらすじ
こんな書き出しで始まります。
コロニーで、わたしはドクター・ラットと呼ばれている。この研究室にはとても長くいて、とても念入りに調べられてきたので、当然ながら、ほかのラットたちがみんなつけている耳の内側の刺青以外にもしるしをあたえられている。(3ページ)
研究室で、仲間のねずみたちが体の一部分を取り除かれるなど、残酷な実験をされる時、古くからいる〈わたし〉は、「彼らが世界規模で果たす重要な役割について理解させて」(6ページ)やります。
実際のところ、人間の科学技術の発展について、ねずみには理解など出来ませんし、理解できたところで恐怖は去らないのですが。
ある時、仲間のねずみがおかしなことを言い出しました。何だか変な気分がするというんですね。
〈わたし〉はそのねずみが大量の食事を詰め込まれる実験をされているねずみだと知っていますから、二週間後には死んでいるであろうことも分かっています。
しかし、〈わたし〉とねずみとの会話は噛み合いません。そのねずみは自分に起こったことは、肉体的な問題でも、精神的な問題でもないと言いました。
「肉体でもなく精神でもない? ぼうや、ほかになにがあるというのだね?」
「ぼくの魂です」
「腎石灰化と骨粗鬆症、きみを悩ませているのはそれだよ。すこしばかり体が過敏になっているのかもしれん」
「いいえ、ドクター、ぼくはずっと奥深くにある部分のことをいっているんです」
「8号フランス式ゴム製カテーテルが届かないほど奥深くということかね?」
「もっと、もっと奥深くです」
「きみは博学なマッド・ドクターであるわたしにむかって、ラットには人間のまだ知らない部分があるといっているのかね?」
「ぼくの光です、ドクター、ぼくの内側にある光・・・・・・」
「・・・・・・それは直腸をとおして挿入された・・・・・・」
「ぼくは自分の内側に光の泉を見たんです。ドクター、ぼくたちはその泉から生まれたんです」(14~15ページ)
その頃、野犬たちがある「匂い」に釣られて走り始めます。夢中になって走る内に、すっかり忘れていた昔からの、本能的な感覚を取り戻していきます。
研究室でも、犬やねずみたちが同じようになんだか変な気分になって、騒ぎ出すようになりました。一人〈わたし〉だけが、こう叫びます。
人間が我々を飢えさせたり、傷つけたり、自由に扱えるのは、人間が「聖なる輝きを宿している」からであり、我々「動物には魂がないのだ!」(28ページ)と。
ラジオからは、迷子になった犬についての放送が流れます。ご主人の元へ帰ろうと迷う犬も中にはいますが、多くの犬たちは、支配者など初めからいなかったのだと、もう気付いています。
「踊れ、犬たちよ、踊れ! 種族全体が妄想から解放されたのだ」(50ページ)と。犬たちは走り続け、食肉加工場に送られるはずだった牛たちは、家畜囲いを突破します。
監獄のような暮らしをしている豚は、自分たちを救う存在についての噂を聞き、色々と考えた結果、「わたしはわたしだ!」(75ページ)と、自分が実在しているということに初めて気が付きました。
ようやく自我を獲得し、新しい光が見えた来たような気がした豚ですが、無残にも人間によって吊り上げられ、ソーセージを作るために体を切り裂かれて・・・。
有名な作曲家のサー・ジェイムズ・ジェフリーズは、船の上から、クジラに音楽を聴かせる実験を試みます。サー・ジェイムズは、クジラが優れた音楽家だと思っているから。
船の上のオーケストラがサー・ジェイムズの「深海への賛辞」を奏でました。
それからしばらくして、クジラたちはそれぞれのパートに分かれて、その曲をそのまま歌い始めたのです。サー・ジェイムズは驚愕します。
サー・ジェイムズは、こんなにも素晴らしい歌の達人たちを、自分たち人間が殺し続けて来たことに涙し、また、その歌に心震わせます。
しかし、捕鯨船が銛打ちのために場所をあけろと言って来て・・・。
サバンナでは、鷲がすべての動物に呼びかけ、集会のために、動物たちは大移動を始めます。小鳥から、巨大な象までがその場所を目指して行くのです。
年老いた猿と、若いチンパンジーは集会についての話をします。
「じゃあ、よく聞けよ、おいぼれ猿。おれたちが集まる理由はひとつしかない」
「わたしの耳はきみの話を聞こうとしてキノコのように突きだしているぞ、若者よ」
「大勢の仲間が集まって、おのおのの思考の流れをひとつに融合させるときがやってきたんだ。この森にいるすべての生き物も、はるか遠くの森にいる生き物もひとつに融合する。鷲たちがそこらじゅうに知らせを届けているんだ」
「それで、この融合の目的は? どうか教えてほしい、わたしの耳は象の耳なみに大きくなっているぞ」
「おれたちが集結すれば、人間もやってくるだろう。人間はおれたちみんながひとつの生き物だと気づいて、おれたちを殺すのをやめるだろう。それは突然のすばらしい認識となるはずだ」(142ページ)
移動し続ける動物たち。一方、ドクター・ラットである〈わたし〉は、「断頭術は胎児や生まれたばかりのラットから血液を摂取するには最適の手段だ。この生まれたばかりの革命の頭も切り落としてやらなければ」(96ページ)と反逆者たちの中に潜り込んで・・・。
はたして、動物たちは旅の果てに一体何を目にするのか? そしてドクター・ラットの運命はいかに!?
とまあそんなお話です。一人反乱に加わらないドクター・ラットと、新しい何かに目覚めた動物たちの物語。
かなり興味深い場面は、ドクター・ラットの濡れ場です。
研究室の混乱の中で、メスのねずみに迫られるんですが、ドクター・ラットは去勢されているので、当然行為に及ぶことが出来ません。
「ハニー、どうしたっていうの!」雌は急に身を引いて、ふだんどおりに、わたしの態勢を崩させる。(中略)わたしにできるのは専門家らしくメモをとることだけだ。いずれ〈サイエンス・トゥデイ〉に掲載されたら、より息の長い満足感が得られることだろう。
雌はじっとわたしを見つめる。「ハニー、あなたひょっとして・・・・・・」
「わたしは博学な教授に対して恩義がある――誕生後しばらくして受けた去勢実験で手を貸りたのだ。教授の手助けと大学の協力がなければ、この論文が完成することはなかっただろう」
「でも、あたしは体がうずうずしているのよ、ダーリン。あたしに必要なのはそれをしてくれる立派なラットなの」
「不毛な快楽だ、ほんの一瞬で消えてしまう」
(187ページ、本文では「それをしてくれる」に傍点)
ドクター・ラットは常に狂った存在として描かれますが、何がどういう風に狂っているのか、この場面からよく分かります。
つまり、人間の勝手な実験によって去勢されてしまったわけですが、それを恨むどころか、かえって感謝しているわけですね。これは狂っていないと出来ないことです。
そして狂っているからこそ、生殖という「不毛な快楽」ではなく、論文執筆という「より息の長い満足感」に喜びを感じることが出来るわけです。
以上の特徴的な事柄は、こんな風に言い換えることが出来るかと思います。
ドクター・ラットは動物らしさを失い、科学的な知識を元に、すべてを合理的に考えるからこそ、狂っているのだと。
他の動物たちが、何かに導かれるように動いていく一方で、一人だけ動物に魂を認めないのもドクター・ラットでした。
「動物らしさを失い、科学的な知識を元に、すべてを合理的に考え」て、鶏や豚、クジラなど、動物たちに特別なものを認めない存在が、ドクター・ラット以外にもいますよね。
そう、もちろん我々人間です。ドクター・ラットがもし狂っているのだとしたら、我々人間はどうなんでしょう?
残酷な実験や、動物が殺される様を描いて、動物愛護を訴えるだけの物語ではなく、そうした深いテーマを持った作品でもあります。
グロテスクで、クレイジーで、読者を選ぶ小説ですが、興味を持った方は、ぜひ読んでみてください。
明日も「ストレンジ・フィクション」から、アヴラム・デイヴィッドスン 『エステルハージ博士の事件簿』を紹介します。