
¥1,890
Amazon.co.jp
ジョゼ・サラマーゴ(雨沢泰訳)『白の闇〔新装版〕』(NHK出版)を読みました。
ジョゼ・サラマーゴは本についている著者略歴によると、ポルトガルの国民的作家だそうで、1998年にはノーベル文学賞を受賞しています。
それほど有名な作家であるにもかかわらず、日本での知名度はほとんどないといってよくて、唯一知られているのがこの『白の闇』でしょう。しかも『ブラインドネス』というタイトルで映画化されてようやく認知されたという状況だろうと思います。それはぼくにとってもそうです。
この翻訳が基本的には英語に訳されたものからの翻訳ということからも、ポルトガルの文学との距離を感じずにはいられません。これはこの本だけの問題ではなくて、外国文学の中でもどちらかと言えばマイナーな国の文学では、英語やフランス語など、他の言語に翻訳されたものからの翻訳ということがよくあります。
重訳ではなく、原語からの翻訳が望ましいことは言うまでもありません。しかし、研究者や翻訳者が不足しているなど様々あって、現実問題としてなかなか難しい部分があるのかもしれませんね。
最初にこの作品の映画化作品『ブラインドネス』について触れます。
ブラインドネス スペシャル・エディション(初回限定生産2枚組) [DVD]/ジュリアン・ムーア,マーク・ラファロ,アリス・ブラガ
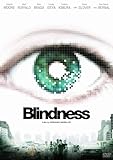
¥4,179
Amazon.co.jp
『ブラインドネス』は多少話題になりましたので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。伊勢谷友介と木村佳乃も出演していますよ。
ある時、車を運転中に1人の男性(伊勢谷友介)の目が見えなくなるんです。それが普通の失明だったなら、真っ暗になるはずなんですが、真っ白になります。そしてその目の見えなくなる病が、人から人へ伝わっていって・・・。
とまあそんな映画なんですが、ぼくはリアルタイムでは観ていませんでした。なぜかというと、なんとなくゾンビ映画のように、人々がパニックになる様を描いた映画だろうと思っていたからです。でも実は全然違うんですけどね。
ところで、みなさんはゾンビものはお好きですか? ぼく自身はあまりゾンビものは好きではないんですが、よく一緒に映画を観る人がホラー好きで、無理やり色々観させられました。ええ、ぼくも抵抗を試みましたよ。ホラーなんかいやだようと。でもいつも無駄な抵抗で終わりました。
ゾンビ映画の中で、ちょっと面白かったのが、『ショーン・オブ・ザ・デッド』です。
ショーン・オブ・ザ・デッド [DVD]/サイモン・ペッグ,ケイト・アシュフィールド,ルーシー・デイヴィス
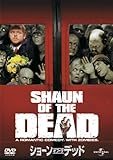
¥1,500
Amazon.co.jp
ゾンビもののパロディでありコメディなんですが、この中で一番面白かったのは、親友がゾンビになってしまったらどうするか? という問題に対する答えがユニークなところです。
普通は解毒剤のようなものを探すか、止むを得ず撃ち殺すかの2択だと思うんですが、どうしたと思います? 興味のある方は『ショーン・オブ・ザ・デッド』をどうぞ。
『ブラインドネス』をどのような映画として宣伝するかは難しかったと思います。ただぼくを含めて一般の人は「どうせパニックものでしょ」と勘違いして観ずに終わり、パニックものが好きな人は観ても、「なんじゃこりゃ、おもてたんとちがうー」という感じだったろうと思います。
ぼくは映画と小説がある場合、いつもどちらかと言えば原作小説の方をおすすめしてきましたが、この場合、映画も相当いいです。もちろんささいな相違点はありますが、ほとんど忠実に映画化されていると言ってよいと思います。小説が苦手な人は、ぜひ映画を観てみてください。
ただぼくがここで言う「相当いい」というのは、面白いとか、おすすめとかそういう意味とは少し違います。一言で言うと、衝撃作です。トラウマになりそうなくらい、人間の醜さとか、汚らしさみたいなものをあぶり出した作品です。そしてそれだけに深く深く考えさせられる物語です。
訳者あとがきでも多少触れられていましたが、似た印象の作品として、ゴールディングの『蝿の王』があります。共通しているのは、ある程度閉鎖された空間で、自然と生まれる人間の力関係、そしてある種の熱狂の恐ろしさを描いているということ。
『ブラインドネス』はパニックものではありません。ではどんな物語かというと、目が見えなくなった人が、元々は精神病院だったところに隔離されるんです。人から人に移る病なので、そこから出ようとすると監視している兵士に撃ち殺されてしまいます。
一番最初に車の運転中に目が見えなくなった人、その人を車で家まで送り届けてあげた人、目医者、目医者の待合室で出会ったサングラスの娘、子供、眼帯をした老人などが、その精神病院だった建物に集められます。
人から人へ。段々目の見えない人は増え、次々とこの建物に送られてきます。ベッドは足りず、食糧も足りなくなってきます。目が見えないので、トイレに行くのも一苦労で、至るところが汚れていきます。それでもみんなで助け合えば、平和な暮らしができるはずですよね。ところがそうはならないんです。
あるグループが暴力で食糧を占拠し、他のグループに金目のものを要求します。やがてその要求はエスカレートしていきます。怖ろしや怖ろしや。がくがくぶるぶる。要求に従わなければ、当然みんな餓死してしまうわけです。
目の見えないという条件はみんな同じであり、そしてある種の理想論では、人間はみんな自由で平等のはずです。しかし、ここで生まれてしまった圧倒的な力の差、理不尽な要求。同じ状況に陥ったら、ぼくらは一体どうすればいいのか? という問いを投げかけ続ける問題作です。
閉鎖された空間で、人間心理の怖ろしさを描いた怖るべき物語なんですよ。人間の醜さ、怖ろしさ。
そしてこれは単にたまたま起こった特殊な出来事を描いたということのみならず、ある意味において、ぼくらの生きる現実世界の縮図になっているわけで、それを考えるとより一層背筋がぞっとする部分があります。
作品のあらすじ
ここからは主に小説について書いていきます。
小説には特徴が2点あります。会話が鍵カッコ(「 」)で描かれていないこと。地の文に溶け込む形式になっています。それから、登場人物が「医者の妻」などと書かれ、名前が書かれていないこと。
たとえばこんな感じです。元精神病院の建物に新しい人々がやってきた場面。
病室で目覚めたら失明しており、その運命を嘆きはじめたとたん、いっしょにいた親族や友人に別れを告げるいとまももらえず、目の見える人びとに即刻追いだされたというわけだ。医者の妻が言った。あなた方が自分たちで数えて。名乗り合うのがいちばんいいから。失明した患者たちは身じろぎもせず、ためらっていたが、だれかが行動を起こさなければならないと、二人の男が同時に話しだし、ありがちなように二人とも黙りこんだ。すると三人目の男が口をひらいた。一番。そこで黙った。つづけて名前を言うのかと思ったが、つぎに男が口にした言葉は、警察官です、だった。医者の妻は思った。名前を言わなかった。この人もここでは名前がなんの意味も持たないことを知ってるんだわ。(69~70ページ)
もしかしたら、多少読みづらい文章かもしれません。全編こんな感じです。苦手そうだなあと思った方で、それでも物語に興味があるなら、映画をぜひ観てみてください。
名前が出てこないというのは、物語内でなんの意味も持たないからということだけではなく、血の通った個性的なキャラクターとしてよりも、もう少し漠然とした寓意性のあるキャラクターとして描きたかったからだろうと思います。
つまり役割のようなものは指し示しているけれど、どういう人間かを具体的に描写せずに、ぼくら読者が入り込みやすいように作られているのだろうということです。
1台の車が交差点で青信号なのに止まっているところから物語は始まります。鳴らされるクラクション。どうしたんだと運転手の元に人びとが集まっていくと、目が見えないと言うんです。「なんにもない、まるで霧にまかれたか、ミルク色の海に落ちたようだ」(9ページ)という運転手。
この男は親切な男に車で家まで送ってもらい、妻と一緒に目医者に行きます。目が見えなくなった原因は分かりません。そして親切な男、目医者の待合室で会った人びとの目が次々と見えなくなっていきます。
朝目覚めると、目医者の目も見えなくなってしまっています。目医者はすぐさま隔離されることになるんですが、目医者の奥さんは、自分も目が見えなくなったと偽って、車に乗り込みます。そうして運ばれていったのが、元精神病院だったといわけです。
事態の説明をする音声がスピーカーから人工的に流れ、ベッドがただ無造作に並んでいる建物。やがて、お互いに少しずつ関わりのある人びとがやってきます。一番最初に目が見えなくなった男、その男を送ってやった男、目医者の待合室にいたサングラスの娘、斜視の子どもなど。
全員目が見えない中に、1人だけ実は目が見えている人がいます。そう、目医者の妻ですね。この目医者の妻が物語の中心人物になります。陰日向にみんなを支える役目を果たすわけです。その中で迷いが生まれ、苦しんでいく部分があります。
色々大変なことはあるけれど、なんとかやっていく生活。ところが、あるグループが食糧を占拠したことから、事態は大きく変化していきます。
男は腕を上げて、もう一発撃った。またもや漆喰のかけらが床に降った。それからおまえ、と拳銃を持ったならず者が言った。おまえの声は忘れないぞ。わたしもその顔はね、と医者の妻が答えた。(155ページ)
果たして物語はどんな展開を迎えるのか!?
人間の怖ろしさが描かれた小説です。この物語は実は、目の見えない恐怖を描いたものなのではなく、そもそもぼくらの目はちゃんと見えていたのか、ということを問いかけているわけです。
内容が内容なだけに、若干トラウマになる可能性があるので、拳をぎゅっと握りしめて、ある程度の覚悟をしてから読むなり観るなりしてみてください。面白いかどうかはおいておいて、心揺さぶられる物語であることは間違いないです。
おすすめではないですが、おすすめです。
おすすめの関連作品
リンクとして、映画を1本、小説を1冊紹介します。
まずは同じように閉鎖された空間の人間心理を描いた傑作として、ラース・フォン・トリアー監督『ドッグヴィル』です。
ドッグヴィル プレミアム・エディション [DVD]/ニコール・キッドマン,ポール・ベタニー,クロエ・セヴィニー
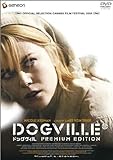
¥4,935
Amazon.co.jp
これは不思議な映画で、地面に線が書かれただけで、それが建物などを表しているんです。逃げてきた女を町の人びとがかくまう話ですが、徐々に人間の怖ろしさのようなものが浮かび上がってくる物語です。これもどちらかといえば衝撃作の領域にある映画ですが、そういった意味で非常に面白いです。
続いては小説。目の見えない人物を描いた傑作と言えば、ジッドの『田園交響楽』でしょう。
田園交響楽 (新潮文庫)/ジッド

¥340
Amazon.co.jp
詳しいあらすじはそちらの記事を参考にしてみてください。こちらも深く考えさせられるものがあります。
明日は、ブラジルのミュージシャンであり作家のシコ・ブアルキの『ブダペスト』を紹介する予定です。月末が近づいて、ようやく〈その他の国の文学月間〉らしくなってまいりました。