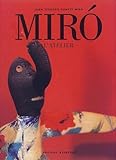先にスペイン語絡みでジョアン・ミロの名前に触れましたけれど
、
そんな時に図書館でふと目に飛び込んできたのが、「ミロのアトリエ」という一冊です。
1956年、バレンシアの沖合いに浮かぶマジョルカ島に作られたミロのアトリエ。
そのアトリエの様子を写した写真集に、
ミロの言葉の引用と美術史家でもあるミロのお孫さんの回想が添えられた仕立てになっていました。
こんな立派なアトリエを構えていたのか…と思えば、それは功なり名を遂げた後のミロであって、
その前には当然のように無名時代の苦労があるわけですね。
例えば、1919年3月に初めてパリで出たミロが、たびたびのパリ滞在で経験した生活のようす。
ミロ自身の回想に語ってもらいしょうか。
ぼくは、今ではピカソが私蔵している《スペインの踊り子の頭部》や《手袋の置かれたテーブル》などを描いた。ひどくついらい時期だった。窓ガラスは割れていたし、蚤の市で43フランもしたストーブはさっぱりだった。
…家事は自分でやった。ひどく貧乏していたので、週に一度しか昼食をとれず、ほかの日は乾燥いちじくで我慢したし、チューインガムを噛んでしのぐこともあった。
貧しい、寒い、腹減った…というありさまがよく分かるわけですけれど、
こんな時代にミロが抱いた夢のひとつが、アトリエだったのですね。
どこかに落ち着けることになったら、ぼくの夢は広々としたアトリエを持つことだ。採光とか北からの光線とかといったことはどうだっていい。それよりも、カンヴァスをいっぱいに並べるだけのスペースが欲しい。なにしろ、仕事をすればするほど、いっそう仕事がしたくてたまらなくなる。彫刻もやりたいし陶芸も、それに印刷機を入れて版画もやってみたい。
そのことだけを励みに頑張ったわけでもないでしょうけれど、
見知らぬ人の街であったパリで、いろいろな人との出会いからだんだんと交友も広がっていったようです。
ぼくはトゥルラック街22番地のフュザン荘にアトリエを借りた。ここはトゥールーズ=ロートレック やアンドレ・ドランも住んでいたことがあるし、ピエール・ボナール は今もここにアトリエを構えている。この時期、ここにはポール・エリュアールやマックス・エルンスト をはじめ、セーヌ街のベルギー人画家フーマンス、ルネ・マグリット 、アルプらが住んでいた。
こうした志しで結びつく若者たちの街であったのでしょうね、パリというところは。
小説家として飛躍するちょっと前のヘミングウェイ
もミロに会いに来て、絵を買ってくれたのだそうです。
それが、この「農園」という作品。
当時、ヘミングウェイ以外は誰もこの絵を理解しようとしなかったと言われることもあるだけに、
ミロとしては嬉しかったんですはないですかね。
それに、後年のミロらしいシンプルさとは異なって、ずいぶんと描きこまれていますけれど、
それはそれで刺激的な印象を残すものだったりはします。
ぼくはテーブルの一つに陣どって、壁の絵に目を走らせた。死んだウサギを描いた板絵があった。雉の絵もあったが、やっぱり死んだ雉だった。それと、死んだ鴨を描いた絵もあった。どの絵もみんな色調が暗く、いぶしたようにくすんでいた。
「日はまた昇る」の中でこんなふうに壁にかかった絵の描写を差し挟むことで
その場の雰囲気を伝える手段としたヘミングウェイは
絵が好きだったのかもしれませんね、もちろんそれ以上にスペインが。
とまれ、逆境を乗り越えて、ミロは念願のアトリエを持つのですが、これが1956年。
つうことは、ミロは63歳になっていました。
これはもううれしくてうれしくて、しょうがなかったでありましょう。
アトリエの写真を見ると、大きな空間をそれこそ自由に、誰のじゃまもされることなく使って制作もし、
こまかい収集品(ミロはとにかくいろんなものを拾ってきたらしい…)の置き場にも使っていたことが分かります。
ミロの孫で美術史家のジュアン・テオドーロ・プニェット・ミロの回想です。
ミロにとってこの空間は神聖だった。ここは瞑想と孤独と創造の場であり、この中では自分の息づかいや、熟考するために座るロッキングチェアーのきしみしか聞こえなかった。
老境に至ってようやくたどり着いた至福の地であったことでしょうね。