死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う/森達也

¥1,680
Amazon.co.jp
☆☆☆☆
今月読みたい本リストに書いた本1冊目読破です。
タイトルどおり本書は死刑を題材にした本ですが、ある程度客観的な見地から学術的な議論をしているモノを希望される方には期待はずれな内容だと思います。その代わり、漫然と存在している死刑について考えてみたい、触れてみたい、かき乱されてみたい、と考えている方には絶好の本だと思います。まあこの辺は森達也フォロワーであればいつもどおりのことですが。
さてこういった本は通常、死刑制度存置派、廃止派どちらかに軸足を置きながら、相対する考え方に突っ込みをいれ、またその論に逆に突っ込みを入れられといった弁証法的な展開をして自説の優位性を示すのが定番です。しかし本書では作者自身が立場を明示せずにアッチコッチと振り回されながら様々な議論を展開していきます。
例えば死刑を言い渡され執行までの期間の間に自身を見つめなおし心から改心する受刑者は少なくないといいます。彼らは再審請求することも無いので決して演技ではありません。心から反省し改心し、時に被害者遺族が彼らの死刑取り消しを訴えることすらあります。
心から罪を悔いた人間を殺す必要が何処にあるのだろうか?しかし彼らは死刑に直面したからこそ自身の行いを悔いたのであってそれこそが死刑の効用であるといえるのかもしれません。しかし本人が悔い改め、遺族の応報感情すらも満たされてしまった時、彼らを殺す意味と権利は何処にあるのか?
例えば、通常死刑は受刑者に苦痛を与えない方法で行われます。アメリカでは絞首刑から電気椅子に電気椅子から薬物に死刑方法が変遷していきました。この理由は受刑者が安楽に死ねる形を追求した結果によるものです。死刑は拷問ではありません。公開処刑や死刑者に強い痛みを伴う刑罰を与えないという点には多くの方が同意されると思います。ところで、死刑制度存置派がよって立つ根拠の最も大きなものの1つに遺族の応報感情を満足させ得るための社会的機能である、という論理があります。これは多くの人にとって納得のいくものであると思います。でも良く考えてみてください。当然と思えるこの2つ論理は互いに矛盾します。遺族の応報感情を満足させるためならば、拷問に処した上で彼らの目の前で公開処刑すべきだとも言えると思います。
「死刑は遺族の応報感情に報いるために必要なもの」とする割りにはそれを阻害するようなシステムがとられているのが現状です。だったら「死刑は遺族の応報感情に報いていないのだから必要ないのじゃないだろうか?」勿論これは極論だし、暴論です。(本編でもここまでの書かれ方はしていません。あくまで分りやすい事例として挙げさせていただきました。)
死刑は多くの矛盾を抱え込んだ制度です。作者はそこに様々な思いを馳せます。時にそれは暴論です。しかし法律に関しては素人である森達也が抱く疑問や葛藤は同じ素人である私たち読者にも伝播します。こういった数多くの疑問と矛盾を元刑務官、弁護士、被害者遺族、ジャーナリスト、そして死刑確定囚でありながら冤罪が証明され出所することが出来た日々死におびえていた死刑囚など多様な人々にぶつけます。
本書は死刑が持つ社会的効果や原理原則論から執行方法まで、体系的にこと細かには書かれていません。構成も論文的に1つ1つ積み上げられたものではなく、執行方法の話をしていたと思っていたら被害者遺族の話が出て来て、また執行方法の話に戻ったりと死刑を学ぶにはあまり良いテキストではありません。しかし死刑に携わった様々な人間の言葉が実態が作者の辿った思考そのままに揺さぶられながら書かれており、読み進めるうちに読者自身も混乱しながら死刑を考えることになります。
死刑を学ぶという観点からは評価の出来ないテキストです。しかし死刑を考えるにはこれ程の良書は少ないだろうと思います。
日本の死刑システムを非常に判り易く描きながら、素晴らしいエンタメ作品に仕上げた「13階段」もお奨めです。
13階段 (講談社文庫)/高野 和明
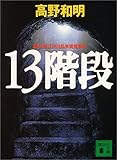
¥680
Amazon.co.jp

¥1,680
Amazon.co.jp
☆☆☆☆
今月読みたい本リストに書いた本1冊目読破です。
タイトルどおり本書は死刑を題材にした本ですが、ある程度客観的な見地から学術的な議論をしているモノを希望される方には期待はずれな内容だと思います。その代わり、漫然と存在している死刑について考えてみたい、触れてみたい、かき乱されてみたい、と考えている方には絶好の本だと思います。まあこの辺は森達也フォロワーであればいつもどおりのことですが。
さてこういった本は通常、死刑制度存置派、廃止派どちらかに軸足を置きながら、相対する考え方に突っ込みをいれ、またその論に逆に突っ込みを入れられといった弁証法的な展開をして自説の優位性を示すのが定番です。しかし本書では作者自身が立場を明示せずにアッチコッチと振り回されながら様々な議論を展開していきます。
例えば死刑を言い渡され執行までの期間の間に自身を見つめなおし心から改心する受刑者は少なくないといいます。彼らは再審請求することも無いので決して演技ではありません。心から反省し改心し、時に被害者遺族が彼らの死刑取り消しを訴えることすらあります。
心から罪を悔いた人間を殺す必要が何処にあるのだろうか?しかし彼らは死刑に直面したからこそ自身の行いを悔いたのであってそれこそが死刑の効用であるといえるのかもしれません。しかし本人が悔い改め、遺族の応報感情すらも満たされてしまった時、彼らを殺す意味と権利は何処にあるのか?
例えば、通常死刑は受刑者に苦痛を与えない方法で行われます。アメリカでは絞首刑から電気椅子に電気椅子から薬物に死刑方法が変遷していきました。この理由は受刑者が安楽に死ねる形を追求した結果によるものです。死刑は拷問ではありません。公開処刑や死刑者に強い痛みを伴う刑罰を与えないという点には多くの方が同意されると思います。ところで、死刑制度存置派がよって立つ根拠の最も大きなものの1つに遺族の応報感情を満足させ得るための社会的機能である、という論理があります。これは多くの人にとって納得のいくものであると思います。でも良く考えてみてください。当然と思えるこの2つ論理は互いに矛盾します。遺族の応報感情を満足させるためならば、拷問に処した上で彼らの目の前で公開処刑すべきだとも言えると思います。
「死刑は遺族の応報感情に報いるために必要なもの」とする割りにはそれを阻害するようなシステムがとられているのが現状です。だったら「死刑は遺族の応報感情に報いていないのだから必要ないのじゃないだろうか?」勿論これは極論だし、暴論です。(本編でもここまでの書かれ方はしていません。あくまで分りやすい事例として挙げさせていただきました。)
死刑は多くの矛盾を抱え込んだ制度です。作者はそこに様々な思いを馳せます。時にそれは暴論です。しかし法律に関しては素人である森達也が抱く疑問や葛藤は同じ素人である私たち読者にも伝播します。こういった数多くの疑問と矛盾を元刑務官、弁護士、被害者遺族、ジャーナリスト、そして死刑確定囚でありながら冤罪が証明され出所することが出来た日々死におびえていた死刑囚など多様な人々にぶつけます。
本書は死刑が持つ社会的効果や原理原則論から執行方法まで、体系的にこと細かには書かれていません。構成も論文的に1つ1つ積み上げられたものではなく、執行方法の話をしていたと思っていたら被害者遺族の話が出て来て、また執行方法の話に戻ったりと死刑を学ぶにはあまり良いテキストではありません。しかし死刑に携わった様々な人間の言葉が実態が作者の辿った思考そのままに揺さぶられながら書かれており、読み進めるうちに読者自身も混乱しながら死刑を考えることになります。
死刑を学ぶという観点からは評価の出来ないテキストです。しかし死刑を考えるにはこれ程の良書は少ないだろうと思います。
日本の死刑システムを非常に判り易く描きながら、素晴らしいエンタメ作品に仕上げた「13階段」もお奨めです。
13階段 (講談社文庫)/高野 和明
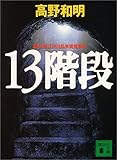
¥680
Amazon.co.jp