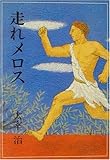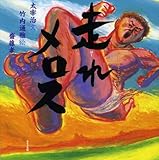■世に不祥事の種は尽きまじ・・・
~メロスvs五右衛門vs孫子!?~
♪石川や 浜の真砂は 尽きるとも 世に盗人の 種は尽きまじ
石川五右衛門の辞世に詠んだとされる歌です。
砂浜の砂粒が無くなったとしても、盗人はいなくならない!との「当時の国王:豊臣秀吉に対する」宣言です。
尽きないのは「盗人」だけではありません。
「盗人」だけでなく、その組織として専門家として「ありえない」・・・引き起こされる「不祥事」もなくならないのでしょうか。
原発・・・。政界、官界、角界、企業、教育現場・・・そこかしこです。
「不祥事の種は尽きまじ」
危険な物質を取り扱う原発、安全に妥協は、許されない「はず」でした。甚大な犠牲がでました。
食品、即、中毒につながるので衛生管理に妥協は、許されない「はず」でした。
大衆への娯楽であり国の伝統でもある角界、不正はありえない「はず」でした。
企業の情報を開示するにあたって「粉飾」はありえない「はず」。
また、企業のオーナーが会社のお金を私用することもありえない「はず」。
指導、道を説く立場の教員による生徒に対する醜聞ありえない「はず」。
個人情報の情報漏えい(利益目的の売却、システムの不備・・・)。
未公開情報での不公正取引・・・。
それだけではありません。先月も今月も、先週も昨日もそして今日も・・・「不正・不祥事」のニュースが続きます。
明日も、明後日も、来週も、来月も来年も、そうなのでしょうか。
多くは、「個人」の問題として処理されています。「特定の個人が間違いをしでかしました。」と組織を守ります。
確かに、個人の素養・・・倫理観や間違い、ミスも一因でしょう。
果たしてそうでしょうか。
つねづね、その組織の問題点を見逃してはならないと考えるのです。
その個人が断罪され償いを求められうことは当然のことです。
一方でそれを引き起こした組織内の歪んだ「ストレスを蓄積する構造」を分析しなければなりません。
多くのケースで、組織に原因があると考えられます。
組織の問題。もちろん、これがすべてであるとは考えません。それも一因(部分)です。しかし、ラインの問題点の影響の大きさを指摘したいのです。
ラインとは、その「しでかした人物」、上席者、そのまた上席者、さらに上席者、そして組織のトップです。
ラインに「専横者」の存在。「専横」はパワーハラスメントも含むのですが、100%合致しません。パワーハラスメントで定義されていることに該当しない専横が存在します。専横に組する側に対して組みしない側の「組織内冷遇感」の蓄積、蔓延。
専横者がTOP層である場合は、致命的です。
TOPの専横のもとには、その一派の専横がみてとれます。
専横のTOPに「守られている」心理から引き起こされるラインの「専横」です。その専横が、直接的、間接的に「不正」「不祥事」を引き起こします。
いずれにしても、「専横者」に周囲のものが、反論、指摘、意見具申することが少なくなるのです。自浄機能が損なわれます。
太宰治の「走れメロス」の主人公「メロス」になれる人物は稀です。
メロスの正義感。
その異常を象徴する、「やけに寂しい」町、口を閉ざす「若い者」から「老爺」。
町は、「組織」。そして、若年から壮年までの口を閉ざす構成員・・・。
王の保身、そしてメロスの反論(指摘)!
冒頭の2文、今の時代に響きます。
------------------
メロスは激怒した。
必ず、かの邪知暴虐の王を除かなければならぬと決意した。
メロスには政治がわからぬ。メロスは、村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしてきた。
けれども邪悪に対しては、人一番に敏感であった。
今日未明メロスは村を出発し、野を越え山を越え、十里離れたこのシラクスの市にやって来た。
メロスには父も、母もない。十六の内気な妹と二人暮しだ。
この妹は、村のある律儀な一牧人を、近々、花婿として迎えることになっていた。結婚式もま近なのである。メロスは、それゆえ、花婿の衣装やら祝宴のごちそうを買いに、はるばる市にやって来たのだ。まず、その品々を買い集め、それから都の大路をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの市で、石工をしている。その友を、これから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから、訪ねて行くのが楽しみである。歩いているうちにメロスは、町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて、町の暗いのはあたりまえだが、けれどもなんだか、夜のせいばかりはでなく、市全体が、やけに寂しい。のんきなめロスも、だんだん不安になてっきた。道であった若い衆をつかまえて、何かあったのか、二年前にこの市に来た時は、夜でもみなが歌を歌って、町はにぎやかであったはずだが、と質問した。若い衆は、首を振って答えなかった。しばらく歩いて老爺に会い、今度はもっと、語勢を強くして質問した。老爺は答えなかった。メロスは両手で老爺の体をゆすぶって質問を重ねた。老爺は、辺りをはばかる低声で、わずかに答えた。
「王様は、人を殺します。」
「なぜ殺すのだ。」
「悪心を抱いている、というのですが、だれもそんな、悪心を持ってはおりませぬ。」
「たくさんの人を殺したのか。」
「はい、初めは王様の妹婿様を。それからご自身のお後継ぎを。それから、妹様を。それから、妹様のお子様を。それから、皇后様を。それから、賢臣のアレキス様を。」
「驚いた。国王は乱心か。」
いいえ、乱心ではございませぬ。人を、信ずることができぬ、というのです。このごろは、臣下の心をも、お疑いになり、少しくはでな暮らしをしている者には、人質一人ずつさし出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて、殺されます。今日は、六人殺されました。」
聞いて、メロスは激怒した。「あきれた王だ。生かしておけぬ。」
メロスは単純な男であった。買い物を、背負ったままで、のそのそ王城に入って行った。たちまち彼は、巡邏の警史に捕縛された。調べられて、メロスの懐中からは短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは、王の前に引き出された。
「この短剣で何をするつもりれあったか。言え!」
暴君ディオニスは静かに、けれども威厳を持って問いつめた。その王の顔は蒼白で、みけんのしわは、刻みこまれたように深かった。
「市を暴君の手から救うのだ。」
とメロスは悪びれずに答えた。
「おまえがか?」
王は憫笑した。
「しかたのないやつじゃ。おまえには、わしの孤独がわからぬ。」
「言うな!」
とメロスは、いきり立って反駁した。
「人の心を疑うのは、最も恥ずべき悪徳だ。王は、民の忠誠さえ疑っておられる。」
「疑うのが、正当の心構えなのだと、わしに教えてくれたのは、おまえたちだ。人の心は、あてにならない。人間は、もともと私欲のかたまりさ。信じては、ならぬ。」
暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。
「わしだって、平和を望んでいるのだが。」
「何のための平和だ。自分の地位を守るためか。」
今度はメロスが嘲笑した。
「罪のない人を殺して、何が平和だ。」
---------------------------
世の犯罪、不祥事、不正・・・露見するのは、氷山の一角なのです。
組織を構成する人々のモチベーションが著しく低下していると「不祥事」は続きます。
その原因は行き着くところ、専横するTOPにある場合が多いのです。
TOPは言います、「個人の問題である(組織に問題はない)」と。
外面が良くても「邪知暴虐の王」なのです。それは、どの組織においても「王」以外の皆がよく知るところです。
一方、不祥事組織に所属する多くの構成員は、穏やかなる「メロス」です。引き起こされた不祥事に失意失望、怒りを覚えていることでしょう。
しかし、
「露見」に至れば、解決の入り口に立つことができます。
「怒り」を「喜び」に転ずることが・・・。「慍(いきどお)り」を、「悦び」に転ずることができる・・・そうすることが大切だと。
「怒りは以て復た悦ぶべく、慍(いきどお)りは以て悦ぶべき」これは、中国古典の「孫子」一節です。
中国の五行の哲学でも、「木:怒」→「火:喜」→「土:思」→「金:悲」→「水:恐」→はじめの「怒」への循環を示しています。
怒りから喜びが生まれ、喜びから思う心が生まれ、思う心から悲しみ生まれ、悲しみから恐れが生まれ、恐れから怒りが生まれます。
①引き起こした組織のそれをキッカケとした課題解決力。
②受け止める市民としての厳しい目(不正を許さぬ世論)。
「露見」は「邪知暴虐なるもの」を除く「入り口」です。
ーーーーー