TOTO IV~聖なる剣(期間生産限定盤)/TOTO
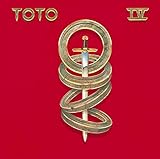
¥1,080
Amazon.co.jp
あ、もちろんこのバンドも、
これでトトと読むのだけれど、
カナで表記されることは
滅多にないので、
本稿でもそのひそみに倣い
a-ha(♯121)や
AC/DC(♯135)と同様、
例外ではありながら
基本このTOTOの表記のまま
行かせていただくことに
しておりますので念のため。
さて、僕らなんかは
80年代のアメリカのシーンは、
このバンドによって
幕を開けたのではないかくらいの
認識だったのだけれど、
実はTOTOの人気というのは、
アメリカ本国よりもむしろ、
日本とヨーロッパでの方が
当時から一貫して高いのだそうで。
ギタリストのS.ルカサー自身、
自分たちが続けていられるのは
この両地域のおかげだ
みたいなことを
発言してもいるらしい。
ヨーロッパはともかくとして、
日本での認知度が
当初からもう十分にあったのは
ひょっとしてこの
名前のせいだったのかなあ、と
まあ今回こんな記述を見つけ、
思わずそんなことまで
考えてしまったりもした次第。
今はちょっと趣も変わって
きているよなあとも思うけれど、
当時はたぶん、
トイレに行ったことのある人なら、
誰でも必ずこの表記を
目にとめていたはずである。
もちろんこのバンド名、
あの東洋陶器さんに
由来している訳では決してない
――はずだと思う。
バンド側からの説明もなんだか、
二転三転しているみたいで、
ラテン語のALLからというのが、
まあ一番座りがいいかなあと
個人的には思うのだが、
それが確実なところだという
訳でもないらしいのが
やや悩ましいところではある。
さて正直にいって
僕自身はこの方たちに関しては
すごくはまったということが、
今に至るまでないまま来ている。
きちんと耳を通しているのは
ジャケットを掲げた82年の代表作、
『聖なる剣』の邦題で紹介された
TOTO Ⅳと、それから
90年発表のベスト盤のみである。
このベスト盤が実は、
ちょっといわくつきというか、
バンドのキャリアの上では、
ある種の瘤みたいなものに
なってしまってもいるのだが、
まあこの詳細は後から触れる。
さて、このTOTOが
AORの雄ボズ・スキャッグスの
アルバムのレコーディングに
招集されたことがきっかけで、
結成されたグループだというのは
たぶん有名な話だろうと思うのだが、
でもどうやら、
オリジナル・メンバーのうちの
ほとんどが
実は高校時代からの
知己だったのだそうで。
その頃も一緒にバンドを
組んでいたそれぞれが
スタジオ・ミュージシャンとして
キャリアを積んだところで、
前述の現場で再会し、
また一緒に音出そうか、みたいな
ノリになったのだということらしい。
ハイ・スクール時代の友人が、
この時まで揃って
音楽を諦めずにいたのみならず、
誰もが押しも押されぬプロへと
成長していたところが、
実はすごいのかもしれない。
そういう経緯でできあがった
グループであるから、
彼らの演奏は、
デビュー時点からすでに
無茶苦茶上手かった。
荒削りという形容が
当たる時期などまったくない。
個人的にはあるいは逆に
その辺りが、
心酔し切れなかった理由かも
しれないよなあと、
まあ今となればちょっとだけ
思わないでもなかったりする。
だから、こんなの売れて
当たり前だよなみたいに、
斜にかまえていたところは
絶対なかったともいい切れない。
実際78年のデビュー作からもう
Hold the Lineなる
トップ5ヒットが生まれてもいる。
浜田省吾さんの作品(♭54)を
扱った時に多少触れてもいるけれど、
とりわけギターの
スティーヴ・ルカサーの名前は、
随所で耳に入ってきたものである。
ところがその後の数年間、
思いがけずもこのTOTOは
とりわけ本国米国では
苦戦を強いられていたらしい。
2ndアルバムHYDRA所収の99が、
CMに起用されるなどしていたし、
顔文字の元祖みたいな
3rdアルバムTURN BACKの
ジャケットなんかも
あの頃よくレコード・ショップで
大々的に展開されていたので、
そんなことは当時はまったく
思いもしなかったのだけれど、
セールス的にはここまでは
残念ながら下降の一途だったと
いってしまっていい
状態だった模様である。
その苦境を一変させたのが、
前述の82年発表の四枚目、
『聖なる剣』ことTOTO Ⅳだった。
まず最初に
リード・オフ・シングルだった
Rossanaが2位にまで上昇し、
シングル・チャートでの
自己最高位を更新すると
もう一曲のトップ20ヒットを挟み、
今回表題にしたAfricaが
ついにバンド初のトップを獲得する。
さらには次のシングルとなった
I Won’t Hold You Backも
些か地味目なバラードながら
最高位10位を記録するヒットとなり、
自ずとアルバムは売れ続け
ついには翌年のグラミーで
一気に6部門を
制覇するに至ったのである。
ちなみにルカサーはこの時、
アルバム・オブ・ザ・イヤーは
前回(♯151)触れたフェイゲンの
THE NIGHTFLYが
獲るものだろうと
直前まで思っていたのだそうで。
いや、これはまったくの余談だが。
いずれにせよ82年から
翌83年にかけてのこの時期
このTOTOというバンドが
アメリカのロック・シーンを
牽引していたことは
たぶん断言して間違いがない。
さて、彼らのサウンドを
何よりも特徴付けているのは、
ニュアンスの異なった音作りと
演奏スタイルとを誇る二人の
鍵盤奏者の存在と、そのバランス、
そしてそれを支える
ちょっと普通では真似のできない
テクニカルなドラミングであろう。
さらには、上のグラミーで、
ベスト・エンジニアド・レコーディングを
受賞していることからも明らかなように、
録音の上手さというか、
スタジオ・ミュージシャンならではの
音質や細部への
こだわりみたいなものが、
彼らのアルバムを
同時期のほかの諸作品から
圧倒的に際立たせていたのだと思う。
デジタル・シンセサイザーを
商業ベースに乗せ
使いこなすことに成功したのは、
彼らが最初だといっていいらしい。
もちろんギター、ベースまでも含めた
確固たる個々の演奏技術を背景にして
ジャズやあるいは、
当時の用語でいうところの
クロスオーバーまでを含めた
様々なジャンルへの嗜好と
それをロックへと
適合させるセンスという意味では
このTOTOに勝るバンドは
ほとんど見当たらないだろう。
実際この人たちの作り出す音は
時に鋭利過ぎるほど美しい。
聴いている方が
不意に理由のよくわからない
緊張を強いられてしまうくらい、
なんというか、隙がない。
――ああ、そうか。
僕はだから、だいたいが
文章を書きながら
音楽をかけることが常なので、
集中力をそっちに
持って行かれてしまうと
正直あまり好ましくないから、
このTOTOの作品を
長時間にわたって
かけておくことが
できないのかもしれない。
いや、かといって
いつも愛聴盤といって
ここで紹介している
アルバム群の音がすかすかだと、
いいたい訳では決してないのである。
いうなればこのTOTOの作品の場合
完成度の高さと呼ぶべきものが、
どこかで突き抜けて
しまっているのである。
そういった部分への
畏敬といったら少し違うが、
それに似た気持ちが
どこかで起きてしまうことは
どうやら否めない気がする。
それこそ正座して
聴くべきなんじゃないかみたいな、
そんな気持ちが起きてくる場面が
多々あったりするのである。
それでも今回の
ピックアップであるAfricaは
そういう意味では少しだけ
手触りが柔らかいのでは
なかろうかとも思う。
しかしこれがいつ聴いても、
本当に不思議な曲なのである。
タイトルからもすでに
十分明らかであるように
このトラックが
描き出そうとしている光景は、
彼ら自身のそれまでやあるいは
以降までも含めた楽曲群はもちろん、
巷間数多ある
普通のポップ・ソングとも
はっきりと一線を画している。
なるほどこの曲に内在する
プロットみたいなものを
無理やりにでも抽出すれば、
アフリカにいる主人公が
同地にやってくる恋人を
待ちわびている景色が
浮かび上がってくるのかもしれない。
しかしこの曲の本質は
たぶんそういうことではないと思う。
聴く側が否応なく
感じ取ってしまうのは、
ひどく手垢のついた言い回しになるが、
未開の大陸に広がる大自然と
それが象徴する原初みたいなものへの
穏やかで本能的な畏怖である。
で、それを基本的には
音だけで再現できて
しまっているところが
やっぱり途轍もなくすごいのである。
リリクスなんて聞かなくても、
それがびしびし伝わってくる。
だから、アプローチの異質さが
そのまま曲の力強さに
繋がっていった好例だといえよう。
バンド唯一の
全米トップワンというのも
十分に頷けてしまうのである。
ちなみに同曲のソングライターである
デヴィッド・ペイチと
ジェフ・ポーカロの二人は、
最初はアルバムへの収録は
見送る結果になっても
仕方がないくらいにも
実は思っていたのだそうで、
なるほどこの時までこのTOTOが
たぶん最も得意としていた
ある種宇宙的なアプローチとは、
曲調もサウンドの手触りも
明らかに異なっているし、
実際の収録もなんだか
ボーナス・トラックみたいな扱いで、
アルバムの一番最後に据えられている。
もちろんバンド内で
当時どんな話し合いが行われて、
こういう形に落ち着いたのかは
僕には皆目わからないのだが、
でもこの時の英断が、
TOTO Ⅳの栄光に
繋がったことは
九分九厘間違いがない訳で、
そう考えると巡り合わせというのは
やはり不思議なものだよなあと
改めてつくづく思ったりもしてしまう。
なお同曲に関しては、
コーラスとサイド・ギターに
イーグルス(♯150)のベーシスト、
ティモシー・B.シュミットが
どうやら参加している模様。
まあ、こちらも余談ではありますが。
さて、しかしながら
このTOTO Ⅳの後、
活動開始からの
専任ヴォーカリストであった
ボビー・キンボールが
バンドを抜けてしまい、
それからTOTOはしばし、
シンガーに苦労することになる。
80年代の後半の時期
Pamelaなどのヒット曲で
バンドに参加していた
ジョセフ・ウィリアムスは、
なんとあの映画音楽の巨匠、
ジョン・ウィリアムスの
息子さんだったのだそうなのだが、
この彼が三人目の
ヴォーカリストだった。
そして前の方で触れたベスト盤が
その次の一応4代目となる
ジャン・ミッシェル・バイロンなる
アフリカ系のシンガーの
イントロデューシングを兼ねていて
四曲の当時の新録音が
併せて収録されていたのだが、
どうやら実はこの企画、
レコード会社側からの
ほとんどゴリ押し
みたいなものだったらしい。
まあ大方Africaの
ヒットを持つこのTOTOが
本当にアフリカ人の
フロント・マンを持てば
それは必ず話題になって
くれるはずだろうみたいな
極めて安直な発想だったの
ではないかとも思うのだが、
結局このバイロンは、
バンドのメンバーと
まったくもってうまくいかず
ほとんど同作品の
録音期間だけしか在籍せずに
終わってしまう。
それ故この一枚、ベスト盤と
銘打っているのにも関わらず、
さほどヒットしていないどころか、
バンドがライヴで
取り上げることさえ稀な楽曲が
四曲も紛れ込んでいるという
非常に居心地の悪い編成に
なってしまっているのである。
これはA&Rの失態だよなあ。
なお、11年にバンドは
初代のキンボールと一緒に、
THROUGH THE
LOOKING GLASSという
キャリア初のカヴァー集を
発表してもいるようである。
この中でこれも前回の
スティーリー・ダンの記事の中で
最後の方に名前だけ出した
Bodhisattvaや、あるいは
ハリスンのビートルズ時代の
While My Guitar~なんかも
取り上げているらしいので、
ちょっと興味なくもなかったりする。
ではそろそろ締めの小ネタ。
今回は正直ネタに困ったので、
このAfricaの
カヴァー・ヴァージョンを
いろいろと探してみました。
まずたぶん本邦では
一番有名だろうと思われるのが、
94年の小室哲哉さんによる、
TRUE KISS DESTINATIONの
デビュー曲であろうかと思われる。
うーん。
外野なのでまた
勝手なことをいうけれど
当時最初に見かけた時も、
いやずいぶんと、
難しい曲に挑んだものだなあ、なんて
ほとんど余計なお世話でしかない
ことを考えたものだったのだが、
今回改めて耳を通してみて、
なんというか、
やはり曲のテーマそのものが
ダンス・ミュージックとは
相当相性が悪いのかなあ、と
そんなことを痛感した次第。
何よりもどうせやるのなら、
サビにもちゃんと
日本語詞をつけて
挑んで欲しかったなと思う。
かなり難しそうだけれどね。
ま、外野なのでご容赦ください。
それからドヴァイ出身の
カール・ウルフなる
この人はアイドルでいいのだろうか、
そういう方が、
08年にやはり果敢にこの曲に
挑んでこそいるのだが、
こちらもまた普通に
単なるヒップホップでしか
ないような仕上がりで、
原曲の持つ深遠さからは
正直ほど遠く感じられた。
まあそれでもこの録音、
この方の世界進出の
足がかりにはなったのだそうで、
楽曲の力だよなあ、と改めて思う。
そして昨15年には、
アメリカはオハイオ出身の
AFFIANCEなる
ヘヴィメタル・バンドが
わざわざ南アフリカで
レコーディングを敢行して
同曲を発表したりもしている。
あのイントロのラインを
ヘヴィメタのギターでやると
さていったいどうなるか、
おおよその向きには
結構すぐ察しがつくのでは
ないかとも思われるけれど、
だいたいその通りの出来です。
歌始まると、すっかりメタルだし。
こんなもんだろうな、という
予測の域を出るものでは
残念ながら決してなかった。
だからもうこの辺りで
やっぱりこればっかりは
そう簡単には
原曲越せるものではないよなあ、と
改めてそう思い始めたところで、
すごいの見つけてしまいました。
PERPETUUM JAZZILEという
こちらはスロヴェニアの
コーラス・グループだそうで。
これ、何人いるんだ?
百には届いていないと思うけれど、
二十や三十では絶対おさまらない。
そしてこの人たちが、
基本は伴奏なしのアカペラで、
つまりはほぼ人間の肉声だけで、
全編を再現しているのである。
リズム・パターンも
上の三曲とは違って
原曲のそれを忠実に
なぞってこそいるのだけれど、
もちろんこれも、
ヴォイス・パーカッションで
ほぼ全編を処理している。
いや、ちょっとびっくりしました。
まず開幕からして、
フィンガースナップだったり、
あるいは全員で腿を叩いたりして、
アフリカの雨音の再現を試みて、
雰囲気を醸し出している。
しかも照明の点灯とともに、
メンバーが壇上でジャンプして、
落雷まで演出している。
そしてリズム・パターンが
それこそ呪術の光景のように
染み込むように始まってくると、
ほどなくあの印象的な
木管っぽいシンセのラインが、
スキャットによって再現される。
もうなんか、
引き込まれっぱなしであった。
曲がそもそも持っていた
プリミティヴな
エネルギーみたいなものが、
このスタイルで演奏されることで
より一層ヴィヴィッドに、
むしろ暴力的なまでに鮮明に、
描き出されてくる気がしたのである。
間奏のあの
ちょっとだけ符割りの多い
シンセのラインとかもう
ただ圧巻である。
いや、かなり新鮮でした。
これ生で見てみたいわと本気で思った。
まあスロヴェニアなんて場所から
百人近くを招聘することは
相当難しいだろうから、
どなたか、合唱でこの
Africaを披露することを
考えていらっしゃる
合唱部なり合唱団なりの
代表者の方がもし
どこかにいらっしゃいましたら、
是非ご連絡下さい。
なんとかして見に行きます。
距離によっては
参加したいくらいかもしれません。
それこそ頑張って
日本語詞考えてみてもいい。
いや、ちょっと大袈裟だけれど
そのくらいのインパクトがありました。
ネタに困ったおかげで
こんな発見もあるものなんだなあと、
ちょっと感動して思わずCDを
入手してしまいもしたくらい。
そしたらこの人たち
ヴァン・ヘイレン(♯135)の
Jumpとかも取り上げていて、
これもまた個人的に大受けでした。
あのキーボードのパターンが
女性コーラスで
いきなり迫ってくるの。
大体ご想像いただけるのでは
ないだろうかと思います。
いや本当、大層面白かったです。
しかし振り返ってみれば
今回の小ネタはとりわけ、
ずいぶんとワールドワイドな
展開になったものである。
それもまた、
このAfricaという曲そのものが
何か簡単には手の届かない
そういう領域へ
踏み込むことに成功している、
その証拠なのだと思います。