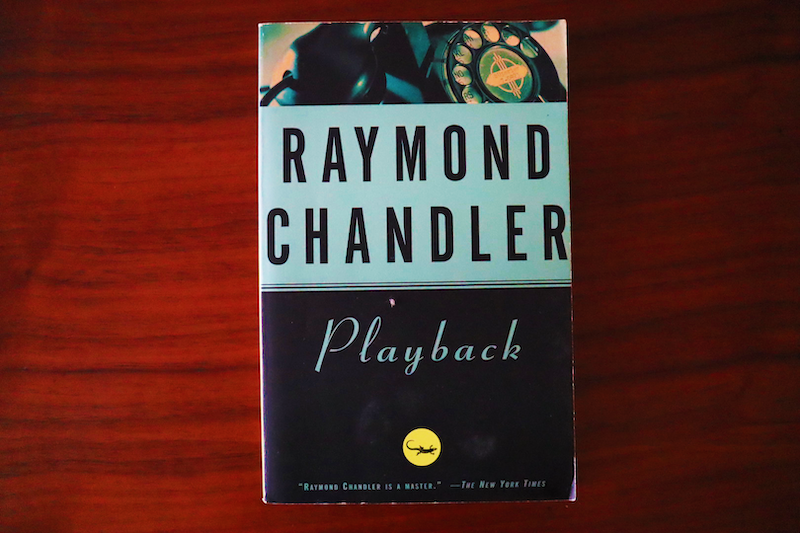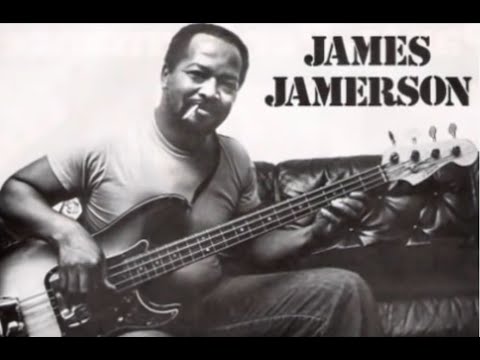JR総武線浅草橋駅は骨組みなんかに古レールを使っていることで有名。
ホームが外に張り出す、いわゆるキャンティレバー方式のホームとか。
建築マニア、てっちゃん心を刺激する。
浅草、好きやわ。

安吾な日本文化私観
坂口安吾は、国民精神総動員の御先棒を担いだ文士だ。
戦時中の体制は、国民精神の総動員のためのスローガンとして「ぜいたくは敵だ」という、バラック以外の建築を事実上禁止した。
ちなみにバラックとは、トタンや有り合わせの木材、破壊されなかった建築物を組み合わせ、雨露をしのぐ程度に建てられた家屋。
これではそっけないので、今和次郎らが「バラック装飾社」を設立し、商店などのバラック建築をにぎやかにデザインして街を彩ったという。
終戦後には、外地からの引き揚げ者も多く、建物疎開跡の空き地などの土地に不法に建てられたバラックが多数に上った。
色々な街で興行された闇市の商店も、その1つである。闇市から発展したアメ横、秋葉原電気街、新宿ゴールデン街などの店舗の中には、当時のバラックを思わせるような狭い間口で奥行きの無い店が見られるという。
閑話休題。
さて「ぜいたくは敵だ」という、このスローガンを受けて安吾は
「京都、奈良のお寺がみんな焼却しても日本の伝統は微動だにしない。必要ならば新たに作ればいいだけだ。バラックで結構。なんとかなる。必要ならば公園をひっくり返してバラックを立てればいい。菜園にしてもいい。それでも我々の文化は健康である」
と語っていたという。

ベネチアは運河の街
ベネチアは運河の街で有名だが、徒歩以外は基本船移動。
「家族ゲーム」の家庭教師・吉本が船でやってくる感じ(笑)。
自動車通行は公的用途以外は基本NG。
旧市街はもれなく全面禁止だという。
また運河には手すりもガードレールもない。
そう、雨の日には水面と道路の高さが=になるという、あれだ(笑)。
香川、岡山の用水路とおんなじだ。
マジあぶないって。

原田芳雄宅で松田優作と桑名正博がケンカして、桑名瞬殺だったとのこと。
「優作っ!!」て呼び捨てにしたことが原因らしいが、普段から呼び捨てにさせていたと聞くが(笑)。
まあ、相手悪いで。
で、みゅうじと、、なぜか松尾貴史を連れて速攻退散したらしい。