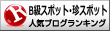前回から引き続いて、群馬県の綿貫観音山古墳とその出土品を訪ね歩いています。
古墳を後にして、古墳から南へ約1kmほどのところにある、群馬県立歴史博物館へ来ました。
いよいよ、出土品とご対面です。
銅水瓶
企画展示室に入っていきなり、この出来栄えの水瓶。
時代を考えてください。古墳時代ですよ。
度肝を抜かれました。
「中島さんじゃないけど、いい仕事してんな~。」
蓋に着いたピンセットのようなものは、蓋が外れないようにするためのもの。
芸が細かい。中国に副葬品として出土している例があるそうですが、国内では類例がありません。
中国ですよ、大陸ですよ。
この時代に海を渡ったかもしれない品だと思うと、感動します。
続いては…
獣帯鏡
銅鏡。鏡です。
「このくらいなら、国立博物館でいっぱい見るよ。」
と思っていたら、韓国で出土した鏡や滋賀県の古墳から出土したものと同型鏡(模様が一致している鏡。鋳型も一緒のものは同笵鏡といい、少し意味が違うので注意。)なんだとか。
なんか壮大な話じゃないですか。
踏み返し鏡(元の鏡から粘土型を取って鋳返した鏡)ってやつだそうで。
だから模様がぼやけた感じなのか。
さらに続きます。
金銅鈴付大帯
こんな帯、見たことない。
こんな帯を腰に閉めたら、腹が擦られ痛そうですけどね。実用品ではないのかな。
ただ、こんな装飾品が出土するのも驚きですよ。状態もいいですし。
鈴がつく例はこれだけだとか。鈴ってこの時代から、形が変わらないんですね。
馬具もあります。
金銅環状鏡板付轡
馬具です。轡(くつわ)ですね。
この時代、馬を所有するのはステータスを表わすものだったみたいなので、こういうものが出ること自体、埋葬者の地位の高さがうかがわれるんですよね。
しかも金銅製というのは珍しいでしょう。錆びの塊りと化した轡しか見たことありませんから。
実際に使われた可能性があるそうです。
馬の食み跡らしい傷があるし、手綱と見られる革帯の一部や織物の切れ端も残ってます。
そして…
金銅心葉形杏葉
馬の装飾品ですね。
忍冬唐草文が特徴的ですね。
やはり緑青や錆がなく、豪華な飾り馬が想像できますね。
さらに、鞍も出土しているのです。
鉄地金銅張鞍金具
鞍の金具です。唐草文を彫金で表現していて、丁寧な仕事ですね。
似たようなものは奈良の藤ノ木古墳出土品がありますが、写真でしか見たことありません。
今回も、比較のために藤ノ木古墳出土品の一部が来館して展示されてましたが、鞍金具はありませんでした。
見たかったなぁ…。
そして今回、一番感動したのが…
金銅花弁形鈴付雲珠・辻金具
これなんです。
同じようなものを見たことがありません。
写真でアップにしてるからサイズがわかりにくいかもしれませんが、小さいです。
手のひらより小さいサイズ。
よく残ったものだと思いませんか?
それもそうですが、作業が細かい。
小さな金属の薄い板なんぞ、よく敲き出したものだ。
また、続いてのこれも驚きました。
金銅歩揺付雲珠・辻金具
飾り金具も折れることなく、よく残されたものだと驚きました。
馬に着けて、飾り馬に仕立ててたのでしょうね。
岩手県の盛岡市に「チャグチャグ馬っ子」という行事がありますね。
実際に見たことはないんですが、あんな感じになるのでしょうか。
直刀も3振り展示されていました
直刀(奥から銀錯龍文捩り環頭太刀・金銀装頭椎太刀)
飾太刀です。
金具や刀身はわかりますが、鞘が残るのは珍しいですよね。
これもまた豪華、というか精緻、というか、細かな仕事がなされています。
銀錯龍文捩り環頭太刀・柄頭
1振りは環頭太刀。柄頭の飾り金具です。
「半円形にした捩(ねじ)り環」を付けた柄頭、も初耳です。
銀錯龍文捩り環頭太刀・鞘口
そして、鞘口の飾り金具には龍でしょうか、銀象嵌の細かな模様が刻まれているんです。
彫金もされていますよ。
銀錯龍文捩り環頭太刀・鞘尻
同じような模様の鞘尻金具です。
とにかく豪華な太刀拵(こしらえ)ですよね。
金銀装頭椎太刀・柄頭
もう1振りは頭椎太刀。上の写真は柄頭です。
金銀装頭椎太刀・鞘口
頭椎太刀の鞘口の部分。
鞘に巻かれている糸などもほとんど腐らずに残っていて、自然条件の偶然が重なった結果に感謝です。
鉄兜(竪矧板鋲留式突起付冑)
衝角付冑はあちこちで見かけますが、こんな突起がついた冑は見たことがありません。
竪矧板鋲留式の冑だそうで、突起がついたものは韓国には出土例があるようですが日本ではやはり、ほとんどないそうです。
埼玉古墳群の将軍山古墳で例があるそうですが、見た覚えがありません。
しかも完形の出土品は、国内ではこれが唯一だとか。
鉄胸当
上の冑に付いていた眉庇との説もあるそうですが、鉄製の胸当とされています。
これも国内での出土例はほとんどなく、完形で出土したのはここだけだとのこと。
鉄臑当
臑当(すねあて)だそうです。
今まで豪華な装飾を施したものばかり見たので、急に地味な錆だらけの鉄製品になってガッカリされたかもしれません。
しかしこの鉄製品、価値があると思います。
こんな状態がいい武具の出土はハッキリ言って珍しい。
臑当の構造がわかる出土状態なんて、本当に重要なんですよ。
こんな細い鉄製の板(小札)を連ね、革紐で綴ったものがあったなんて。
既に古墳時代にこんな加工ができる技術があったんですね。
綿貫観音山古墳出土品は、これだけではありません。
当時の葬送儀礼が伺われる形象埴輪が数多く出土しています。
これらもこの度の国宝指定に含まれています。
次回は、綿貫観音山古墳出土の埴輪類を紹介します。
--------
参考文献:
『綿貫観音山古墳のすべて』国宝決定記念 第101回企画展、群馬県立博物館(2020)
ブログが気に入ったらクリックをお願いします