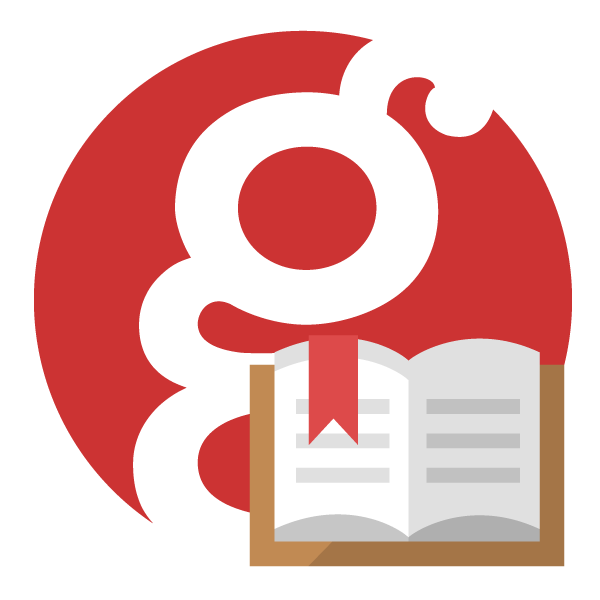十一年前にも書いていますが、多くの人が言う「見立て」は本当に「見立て」なのか?という疑問はあり、疑義を投げています。また、三年前にnoteでもこんな文章を書いています。
ここでは「取り上げ」という言葉で代用していますが、実はしっくり来ていませんでした。
モヤモヤを抱えながらも、色々と精力的に取り組んでまいりましたが、ひょんなことから「あ! これだ!」となったのが「見做し」です。
それは湯相・湯音の言葉に同じ漢字が存在するのはあまり好ましくないということから、湯音の「無音」は「無声」の方がいいのでは?と考え、それならば、湯相の「無風」は何がいいか?と調べていたときのことでした。
辞書にはこうあります。
では、見立てはどう書いてありますでしょうか?
み‐たて【見立て】 の解説
とあります。
簡単に言うと見立ては、趣向であり、茶会の趣旨でなければならず、「ブレスレットを蓋置にすることが趣向となるかどうか?」が肝腎になるということです。
趣向になるというのは「物語が附随して、情景の一部になっているかどうか?」ですから、蓋置として用いることは「景色の一部になっているとは言えない」と私は考えます。
つまり、ブレスレットを蓋置に用いることは【見做し】であると言えるのです。
ですが、例えばこのブレスレットが故人の持ち物、あるいはそれと同型だったり、故人から頂いたものであったらどうでしょう? その故人を偲ぶ会に用いることは、物語が附随しますので、【見做し】であったとしても、単なる代用ではないことになり、【物語】のある素敵な道具組みとなると思います。
これは、【見立て】という言葉を安易に使うな!という警鐘であり、日本語の誤用を改めさせたいという危機感を持っています。
ご納得いただけましたら是非、【見做し】と使っていただきたいものです。