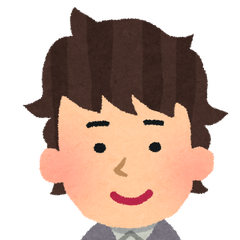今回の臨時議会では、「専決処分の是非」を審議する以前に、まず控訴理由を審議し、控訴の是非の判断がなされるのは当然のことです。
したがって、この審議の中でポイントになるのは、原点である「恫喝発言はあったのか、なかったのか」ということです。
まず、ここを抑えたうえで、控訴理由について審議が進んでいきます。
さて、「恫喝発言はあったのか、なかったのか」の議論においては、押さえておくことがあります。
前号でも指摘しましたが、当時議員であり当事者でもあった12人の議員についてです。
この12人の議員は、市長と山根議員の発言を直接聞いています。
そして、当時の議会の調査に応じ、「威圧的と感じる発言=恫喝発言はなかった」と確認しています。
つまり、12人の議員は、「恫喝発言はなかった」ことを知っているのです。
当時の議長であった山本優議員は、1審の公判でも「恫喝発言はなかった」と証言されています。
そして、当然のことながら1審判決でも、「恫喝発言はなかった」と判断され、「名誉棄損」が認められています。
「恫喝発言はなかった」ことを知っている12人の議員は、
① 市長が「恫喝発言はあった」として控訴し、市民の税金を使って裁判を継続することを許すのでしょうか。
② 山根議員への執拗な個人攻撃をよく知っているにもかかわらず、「市長に恫喝発言はあったと信じるに足りる事情があった」として、「市長の行為は名誉棄損にならない」として、控訴を許すのでしょうか。
控訴は安芸高田市の代表者である市長が行いますが、その是非を決めるのは議会の権限ですから、専決処分が行われていても、議会に控訴の是非の判断が問われることは当然のことです。
事ここに至って、市長はどんな理由をもって控訴の正当性を説明するのでしょうか。
「恫喝発言はあった」とする市長に、12人の議員がどんな振る舞いをするのでしょうか。
その後議員になった3人が、今回の判決をどう受け止め、どんな議論をするのでしょうか。
市民の皆さん、2月14日の臨時議会に注目しましょう。
〔注〕真実相当性
名誉棄損で、損害賠償等を免れることができる場合があります。
これを、名誉毀損の免責三要件と言います。簡単に書けば、次の3点があります。
1 公益性・公共性
2 真実性
3 真実相当性
真実相当性は、摘示した名誉毀損事実が、「「真実」だと思ったことに相当である」場合に、損害賠償等を免責するための要件です。
しかし、真実相当性は、証明可能な程度の厳しい真実性が要求されます。
したがって、この審議の中でポイントになるのは、原点である「恫喝発言はあったのか、なかったのか」ということです。
まず、ここを抑えたうえで、控訴理由について審議が進んでいきます。
さて、「恫喝発言はあったのか、なかったのか」の議論においては、押さえておくことがあります。
前号でも指摘しましたが、当時議員であり当事者でもあった12人の議員についてです。
この12人の議員は、市長と山根議員の発言を直接聞いています。
そして、当時の議会の調査に応じ、「威圧的と感じる発言=恫喝発言はなかった」と確認しています。
つまり、12人の議員は、「恫喝発言はなかった」ことを知っているのです。
当時の議長であった山本優議員は、1審の公判でも「恫喝発言はなかった」と証言されています。
そして、当然のことながら1審判決でも、「恫喝発言はなかった」と判断され、「名誉棄損」が認められています。
「恫喝発言はなかった」ことを知っている12人の議員は、
① 市長が「恫喝発言はあった」として控訴し、市民の税金を使って裁判を継続することを許すのでしょうか。
② 山根議員への執拗な個人攻撃をよく知っているにもかかわらず、「市長に恫喝発言はあったと信じるに足りる事情があった」として、「市長の行為は名誉棄損にならない」として、控訴を許すのでしょうか。
控訴は安芸高田市の代表者である市長が行いますが、その是非を決めるのは議会の権限ですから、専決処分が行われていても、議会に控訴の是非の判断が問われることは当然のことです。
事ここに至って、市長はどんな理由をもって控訴の正当性を説明するのでしょうか。
「恫喝発言はあった」とする市長に、12人の議員がどんな振る舞いをするのでしょうか。
その後議員になった3人が、今回の判決をどう受け止め、どんな議論をするのでしょうか。
市民の皆さん、2月14日の臨時議会に注目しましょう。
〔注〕真実相当性
名誉棄損で、損害賠償等を免れることができる場合があります。
これを、名誉毀損の免責三要件と言います。簡単に書けば、次の3点があります。
1 公益性・公共性
2 真実性
3 真実相当性
真実相当性は、摘示した名誉毀損事実が、「「真実」だと思ったことに相当である」場合に、損害賠償等を免責するための要件です。
しかし、真実相当性は、証明可能な程度の厳しい真実性が要求されます。