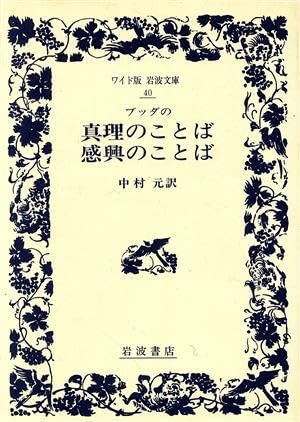ブッダが説く苦しみの終滅と安らぎ
『(1)苦しみと(2)苦しみの原因と(3)苦しみの止滅と(4)それに至る道とをさとった人は、一切の悪から離脱する。それが苦しみの終滅であると説かれる』
(《ブッダの真理のことば 感興のことば》中村元・訳、岩波書店、1978年)
今回も《感興のことば》第二六章『安らぎ(ニルヴァーナ)』から引用となります。
苦しみを感じることには、なにか原因があるのだとするならば、その原因を知ることは大切なことです。
仏教的には、執着や欲望といった、煩悩が苦しみの原因であるとされています。
ただ、ひと口に煩悩といっても、その実際の内容は、ひとによって異なることもあると思います。たとえ社会のうちで生活をしている人々でも、できるだけ多くのことを求めない、というこころがけを意識することによって、過剰に世間の評価や物質的な価値観にとらわれないで生きることができるようになります。
非認知スキル(感情を処理する能力)について、マシュマロをつかった心理実験があります。子どもを待たせておいて、長い時間マシュマロを食べないで、ほかのことをして待っていることができる子どもほど、社会的な能力が高い、という実験です。
そのマシュマロ・テストは、欲望の対象に気をとられずに、なにかほかのことで気をまぎらすことができれば、自己の感情をうまくあつかいやすくなる、ということを意味しています。マシュマロがあっても食べることを許されないという状況は、ブッダがいう『(2)苦しみの原因』に該当するわけです。べつのことをしてマシュマロに気をとられないようにする、ということは『(3)苦しみの止滅と(4)それに至る道』にあてはまります。
たとえば、私は、たまに空腹のときに読書をしたり、音楽を聞いたりすることがあります。そういったことに意識を向けているときには、空腹など、あまり気にならないものです。食事については、あまり我慢しすぎるわけにはいきませんけれども、たまにするぶんには、自制心の訓練にはなると思います。
🔻参考文献