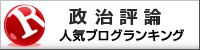【新日本ファクトチェックセンター】

前回記事(その253)の続きで、現在の日本の政局の考察を。前回記事は以下。
■都議選で自公が【歴史的大惨敗】
先日6月22日の東京都議選では、参政党の躍進、共産党やれい新の不振などの話題もあったが。
今回の記事で注目したいのはやはり自公が【歴史的大惨敗】をしたという点。
 「今回の都議選で自民党の獲得議席数は【過去最低議席記録を更新】ということですから、まさに【歴史的大惨敗】ですねぇ」
「今回の都議選で自民党の獲得議席数は【過去最低議席記録を更新】ということですから、まさに【歴史的大惨敗】ですねぇ」
うむ。自民党は過去にも【大逆風】の時期は何度もあり、政権交代を許したり都議選で第一党の座から陥落したり、大ピンチは幾度もあった。
今回、そうした「過去の大ピンチ」のケースを更に下回る獲得議席数で【過去最低議席記録を更新】した訳で、衝撃的な大惨敗と言える。
そして、メディアの報道や自民党の事前調査でも『自公のこれほどの大惨敗』を予想していたところは【ほぼ皆無】と言っていいのではないだろうか。
 「立民や国民民主党や維新なども支持率等は伸び悩んでますしね」
「立民や国民民主党や維新なども支持率等は伸び悩んでますしね」
たとえば6月20日の以下記事などが事前予想の典型例だった。
「進次郎劇場」で一転! 都議選、参院選とも自民に楽観ムード…それでも“次の首相候補1位”が本当の首相になれない理由
2025/6/20 集英社オンライン
>自民は第一会派を維持できるか微妙ではあるものの、今のところ、『小池ブーム』が起きて都民ファーストの会が圧勝した2017年ほどの惨敗は回避できそうです。
>さらに、7月20日の投開票が有力視されている参院選の情勢調査でも「自公で非改選を合わせ過半数は確保できそうだ」との見方が広がり、永田町の自民党議員や関係者は一気に安堵のムードに包まれている。
>「永田町の自民議員や秘書たちと話していると、『裏金問題は終わった』『進次郎農水相の登場で雰囲気が変わった』と、楽観ムードが漂っていて驚いた」(自民地方議員)
 「つまり【事前予想に反しての自公の歴史的大惨敗】という点は明らかですね」
「つまり【事前予想に反しての自公の歴史的大惨敗】という点は明らかですね」
 「事前の【自民は微減程度で済みそうだ】という楽観ムードから一転、まさかこれほどの大惨敗になるとは」
「事前の【自民は微減程度で済みそうだ】という楽観ムードから一転、まさかこれほどの大惨敗になるとは」
当然、石破首相はこの【歴史的大惨敗】の責任を取る必要があるだろう。
 「今回、自民党の歴史にワースト記録として名を残すほどの超大惨敗の結果だった訳ですから、当たり前です」
「今回、自民党の歴史にワースト記録として名を残すほどの超大惨敗の結果だった訳ですから、当たり前です」
■この【予想外?の大惨敗の原因は何か?】
で、この【予想外?の大惨敗の原因は何か?】という点を考察してみると。大きくは以下2つになるだろう。
①【進次郎効果】は既にかなり薄れている
②有権者の石破内閣に対する強烈な不信感
順に考察すると。
■①【進次郎効果】は既にかなり薄れている
今年の5月21日に進次郎が農水大臣に就任してから、既に1ヶ月以上経過している。
 「センター長の、進次郎農水大臣への評価は、どんな感じなのでしょうか?」
「センター長の、進次郎農水大臣への評価は、どんな感じなのでしょうか?」
上記の就任後最初の10日間、つまり「5月の間」の進次郎の行動については「概ね評価できる内容だった」とワイは考えている。
この間、彼がやってきたことはほぼ『コメ価格高騰への対策』のみ。
 「自ら『コメ担当大臣』を自称してましたしね」
「自ら『コメ担当大臣』を自称してましたしね」
進次郎のこの10日間の施策は、完璧でも満点でもなかった。しかし【それまでの石破内閣(&岸田内閣)がコメ価格高騰に対して1ミリも問題解決できていない、異常なまでの超無策・超無能だった】ことと比較すればだいぶマシであり、及第点はつけていい。
何より、『短期間で一定の効果を出した』点は評価できる。つまり【スピード感】こそが進次郎の一番の【売り】だったと言える。
 「【兵は拙速を尊ぶ】みたいな感じですかね」
「【兵は拙速を尊ぶ】みたいな感じですかね」
そしてそれは進次郎自身も自覚的に行動していたことのようで。以下記事。
小泉農相、元農相の苦言に反論 備蓄米「党に諮れば大胆な判断できず」
>元農相の野村哲郎氏は前日の5月31日、随意契約による備蓄米放出を党農林部会に諮らなかったことに苦言を呈した。これについて小泉氏は「大臣がやることなすこと一つ一つを党に諮っていたら、誰が大臣になってもスピード感をもった大胆な判断が出来ない」と反論した。「大臣の裁量内で決められることは私は党に諮らず決める。ご指摘があれば国会の中でいただく」と述べた。
小泉進次郎大臣が農政改革に言及「農水部会長と大臣は決定的に違う」「生産者と消費者が一致するコメ価格はどこなのか」
>「まず部会長と大臣というのは決定的に違う。部会長は中間管理職的なところがある。その中間管理職的立場でできる範囲内と、大臣という行政のトップとして権限を持ってできることは自ずと違うので、今回大臣として決定できること、そして決定するからこそ自分が責任を取れることは躊躇なくやれることはやりたいと思っている」と応じた。
 「【農水行政のトップ】である【農水大臣】という立場だからこそ、農政改革等の対応に【スピード感】を持って取り組める、という点を進次郎自身が語っているのですね」
「【農水行政のトップ】である【農水大臣】という立場だからこそ、農政改革等の対応に【スピード感】を持って取り組める、という点を進次郎自身が語っているのですね」
うむ。
で、こうした施策により5月中にも『随意契約による5キロ2千円前後の備蓄米』が売り出され、6月頭には店頭のコメ価格も多少は下がりはじめ、世論も当時は概ね進次郎に好意的だった。
 「『だった。』って過去形なんですか?」
「『だった。』って過去形なんですか?」
進次郎が【スピード感を持ってコメ対策に取り組めた】のは、ほぼ『最初の10日間』のみであって。6月に入って以降は、【売り】であるスピード感は実はほとんどなくなって急ブレーキが掛かっている。
 「そう言えば、6月以降に進次郎が実現した『新施策』ってほとんどないような?」
「そう言えば、6月以降に進次郎が実現した『新施策』ってほとんどないような?」
 「何故なのでしょうか?」
「何故なのでしょうか?」
進次郎自身は『随意契約による備蓄米販売だけでは不十分』だと当然認識はしていて、『二の矢、三の矢』と続く施策を矢継早にスピード感を持って繰り出すつもりであったように見える。
が、それはできなくなってしまった。
 「できなくなった? どういうことでしょうか?」
「できなくなった? どういうことでしょうか?」
具体的に言えば、6月頭時点で【農政改革に関する体制変更】が行われた。以下記事。
石破首相「コメ増産で安定供給」 閣僚会議が初会合、高騰の検証指示
2025/6/5 日本経済新聞
>2026年6月ごろに一定の取りまとめを目指す。
 「コメに関する関係閣僚会議の初会合? これは何でしょうか?」
「コメに関する関係閣僚会議の初会合? これは何でしょうか?」
つまりだな。
5月の時点では『農政改革はあくまで農水省の管轄』であり、『小泉農水大臣はその農水省のトップ』だったから、【農政改革の決定権を持つトップ】はあくまで『小泉農水大臣』という体制で行われていた。だからこそ当時の進次郎は(党に諮らずに)スピード感のある施策遂行を実現できた。
それは前述の記事でも進次郎が自ら発言していた通り。
ところが、6月に入って石破政権は【農政改革は『米の安定供給等実現関係閣僚会議』で行う】と宣言・決定してしまった。
つまり農水行政の中でも農政改革は【専門のプロジェクトチーム(上記会議)の管轄とする】という体制になってしまった。しかも最悪なことに、このプロジェクトチームのトップ(議長)に石破茂を据えてしまった。
これにより農政改革の【トップとしての決定権】は完全に石破茂に奪われ、進次郎はこの【プロジェクトチーム(会議)の一メンバー】に過ぎない形になった。
進次郎がスピード感を持って農政改革の『二の矢、三の矢』を矢継早に繰り出そうとしても、
『農政改革の検討はこのプロジェクトチームで検討する、というルールになっている。その一メンバーに過ぎない小泉氏が独断専行で勝手に決定・実施するなどは明確なルール違反だ!まずはこのチーム(会議)にきちんと諮って正式な手続きを踏みたまえ!』
と言われてしまう体制にシステムが変わってしまった。
 「え!それって、野村哲郎・元元農相ら農水族が主張していたような『党に諮らない限り何も決められない』旧態依然のやり方に後退してしまったのでは!?」
「え!それって、野村哲郎・元元農相ら農水族が主張していたような『党に諮らない限り何も決められない』旧態依然のやり方に後退してしまったのでは!?」
まさにその通り。そこが本件の肝であって。
そしてこのプロジェクトチーム?は、前述の記事の通り『2026年6月ごろに一定の取りまとめを目指す』などと言っている【スピード感皆無の組織】であり。
 「取りまとめって1年後じゃないですか!? なるほど、6月に入ってから進次郎の『施策実現』から急速にスピード感が失われて【口先だけで実現が伴わず】みたいな大減速状態になってしまったのは、この【悪しき体制変更】が原因なのですね」
「取りまとめって1年後じゃないですか!? なるほど、6月に入ってから進次郎の『施策実現』から急速にスピード感が失われて【口先だけで実現が伴わず】みたいな大減速状態になってしまったのは、この【悪しき体制変更】が原因なのですね」
状況証拠から見る限り、まず間違いないだろうな。
この【悪しき体制変更】を主導したのも、十中八九は森山幹事長ら『農水族』だろう。
無能過ぎる石破茂は森山幹事長に対してはひたすら言いなりなので、「農政改革プロジェクトチーム」のトップに石破茂を据えておけば、農水族側が【進次郎によるスピード感のある決定&施策遂行】をいつでも自由に合法的に阻止できる体制、が構築されてしまった、と言える。
 「6月以降の進次郎改革のスピードに急ブレーキが掛かったのには、実はこうした事情があったのですね」
「6月以降の進次郎改革のスピードに急ブレーキが掛かったのには、実はこうした事情があったのですね」
うむ。
結果、6月下旬の今になってもコメの価格は6月頭からさほど変わっていない。期待されたほどには平均価格が下がっていない。
『二の矢、三の矢』は『実現』ベースではほとんど何も実施されておらず、5月時点で既に実施していた『随意契約による備蓄米販売』(一の矢)以外、進次郎は結果的には何も実現できていない。
結果、最近は世論も既に『進次郎ブーム』にやや飽き始めている印象で。それが都議選の結果(大惨敗)にも繋がっているのではないだろうか。
 「『①【進次郎効果】は既にかなり薄れている』というのは、そういう話なのですね
「『①【進次郎効果】は既にかなり薄れている』というのは、そういう話なのですね
うむ。長くなったので、続きはいずれ(おそらく次回)。