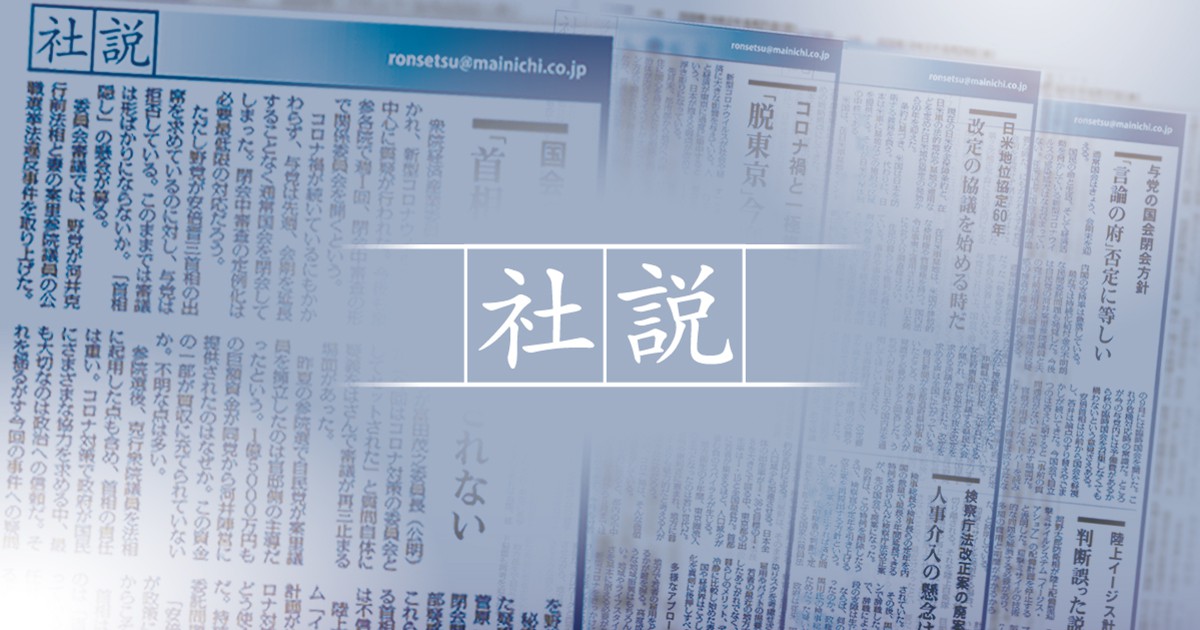-
空虚にして虚無なる「AI兵器規制論」-①【朝日社説】戦後78年 AIと戦争 平和守る責任は人間にある 他
核兵器はじめとして、各種兵器を禁じたり制限したりする条約ってのは、現時点でも結構ある(*1)。有名なところでは「核兵器禁止条約」「クラスター爆弾禁止条約」「対人地雷禁止条約」ってところ、だろうか。ハーグ陸戦協定だかジュネーブ条約だかは「軍用銃弾には鉛玉禁止」としており、軍用銃弾は「完全被甲 フルメタルジャケット」と呼ばれる、多くの場合銅製の「被甲(カバー、と言えば良いか)」で覆われ、命中時の銃弾の変形や飛散を防止している、ってのも「有名な兵器規制」であろう。
だが、左様に「兵器規制(禁止/制限)」ないし「兵器規制/禁止/制限条約」を列挙してみると、「有効であるモノは実は相当な少数派である」ことに、否が応でも気づくだろう(*2)。
核兵器もクラスター兵器も対人地雷も、批准する国が少ない等で「禁止する条約”も”ある」ってのがせいぜいな所(*3)。案外遵守されているのが「軍用銃弾の鉛玉禁止」だが、コレとて散弾銃の軍用使用の事例が数多あることや、炸裂弾が禁じられていない事を考えると、「他の兵器禁止/制限条約よりは大部マシ」ながら、「抜け穴は、相応にある」とするべきだろう。
とうの昔に失効しているが、「海軍休日」を実現した一連の「海軍軍縮条約」こそは、世界三大海軍国(日米英)が揃って批准し、相応に遵守し、「人類史上最も成功した兵器制限条約」と言えそうであり、その後、「一連の海軍軍縮条約以上に成功した、兵器制限条約は無い」状態であり・・・核兵器、クラスター兵器、対人地雷については「条約もある」だけ状態である。
因みに、一連の海軍軍縮条約が期限に至って失効したのは、大戦間期。もう80年以上前の話、だ。
で、だ。核兵器もクラスター兵器も対人地雷も「禁止条約だけはあるが、この体たらく」であると言うのに、今度は「殺人ロボット」などと俗称される「AI兵器」を、禁止なり制限なりしろと、朝日と毎日社説に掲げている。
まあ、朝日と毎日が「社説に掲げる主張」って事は、それだけで「どうせろくなモノじゃあるまい。」って予想/邪推も湧くのだが・・・
①【朝日社説】戦後78年 AIと戦争 平和守る責任は人間にある
②【毎日社説】'23 平和考 AI兵器と戦争 「第2の核」にせぬ英知を
- <注記>
- (*1) 「軍艦年鑑」として昔から有名なJane年鑑の一つが、「兵器禁止条約年鑑」になっていたりする。
- (*2) 無論、気づかない間抜けや、気づいても見て見ぬフリをする輩は、相応に居る。
- (*3) 分けても、「核兵器保有国がタダの一国も批准していない、核兵器禁止条約」こそが、「最も効果の薄い兵器禁止条約」であろう。
- その「効果の薄さ」は、「例え我が国が批准することになっても、大差は無い。」と、断定断言出来る。
- 「唯一の核兵器被爆国が、核兵器禁止条約を批准することに、意味/意義がある。」というのは、感情論・人情論・浪花節であって、論理/ロジックではない。
- ハッキリ言えば、嘘だ。願望ではあるかも知れないが、虚言・虚偽・妄想だ。
(1)①【朝日社説】戦後78年 AIと戦争 平和守る責任は人間にある
戦後78年 AIと戦争 平和守る責任は人間にある
https://www.asahi.com/articles/DA3S15718384.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年8月17日 5時00分
list
2
写真・図版
インフラ施設のそばにある集合住宅はロシア軍のドローンによる攻撃を受け、市民が犠牲になった。行方不明者の捜索やがれきの撤去作業が続いていた=2022年10月、キーウ、高野裕介撮影
[PR]
戦争は、科学技術の進歩とともに変化を遂げてきた。
78年前に日本が敗れた大戦もそうだった。各国は軍用機の性能向上や爆弾の威力の強化にしのぎを削った。原子爆弾の開発に知の最先端が動員された。
それは現代のウクライナでも変わらない。
ウクライナ軍は、人工衛星が提供する高速ネット回線を介し、戦車や装甲車、ドローン(無人機)などが敵情報を共有しながら、ロシアの侵略と戦っていると伝えられる。
かたやロシア軍は、衛星からの位置情報を妨害電波で攪乱(かくらん)する手法を用いて対抗する。
さながら科学の先端の競い合いと化したような戦いが、繰り広げられている。
■人の手を離れる戦い
弓矢から銃、大砲、爆弾、ミサイルへ。歴史を顧みれば、兵器は生身の人間同士が相対せずとも遠方から攻撃できるかたちで発達してきた。死傷者が血を流す姿が見えにくくなり、殺す側の罪悪感は薄れた。
兵員の損失を抑え、しかも民間人の巻き添えを最小限にできるとの触れ込みで、1991年の湾岸戦争以降、精密誘導兵器での「ピンポイント爆撃」が多用されるようになった。
戦争の態様は、戦場から遠く離れて遠隔操作する、一種のゲームと化した。
人間と機械の境目はあいまいになり、今、人工知能(AI)に注目が集まる。
AIを兵器に使えば、人間に委ねられていた意思決定の速度は格段に早まる。AI兵器が自律的に判断することで、遠隔で操作する必要さえなくなる。
戦争のありようを一変させる技術として、AIが火薬、核兵器に続く「第3の軍事革命」とも称されるゆえんである。
自軍兵士の危険が軽減され、人的ミスが減って民間人被害も回避できるとの理由から、「人道的」という評価すらある。
そうだろうか。
■利かなくなる歯止め
戦争を始めるハードルは下がるだろう。AIには、人を殺すことへのためらいも、殺される恐怖心もない。
正確とされたピンポイント爆撃だが、アフガニスタンでは病院や民家などへの誤爆が相次いだ。AI兵器に誤作動や暴走の危険はないと、どこまで言いきれるだろうか。
特に懸念されるのは、情報の収集や判断が人の手を離れることで、責任の所在がわからなくなる事態だ。だれも責任を負わなければ、戦闘のエスカレートを防ぐ歯止めは失われる。
まるで人間が書いたかのような文章や、本物と見分けがつかないニセ画像もAIで簡単に作り出せるようになった。誤情報や偏見を拡散して緊張をあおったり、選挙に介入して政治をゆがめたりすることも可能だ。
技術革新で平時でもネットを通じたインフラ攻撃が可能になったことも相まって、平時と戦争の境界もますますぼやけていく。そんな世界に人々は安心して暮らせるだろうか。
先月、国連の安全保障理事会が、AIに関する初の会合を開いた。グテーレス事務総長が「いま行動しなければ、現在と未来の世代への責任を放棄することになる」と述べ、AIが自動で敵を殺傷する兵器を規制する国際ルールづくりを訴えたのは当然だ。
各国は人類の存亡にもかかわる問題との危機感を共有し、合意点を見いだしてほしい。
■変わらぬ戦場の実相
戦争の本質とは何か。
原爆のキノコ雲の下では、焼かれたり吹き飛ばされたりして息絶えた多くの市民がいた。戦後も原爆症に苦しんだ。
ウクライナの戦場で起きていることから学べることも、少なくない。砲弾が正確に命中した先には生身の人間がいる。ロシアのドローンやミサイルが発電・水道施設を狙い撃ちし、酷寒の真冬に暖房が止まる。原発が軍事目標となり、穀物倉庫や輸出拠点も攻撃された。
領土を奪うために非情な殺し合いも辞さないのが戦争だ。戦いを続けられないよう生産拠点やインフラ、街を破壊する。いくら技術が進んでも、この現実が変わることはあるまい。
食料やエネルギーの自給率が低く沿岸部に原発が林立する日本は、その脆弱(ぜいじゃく)さを自覚し、戦場にしないための一層の努力が求められる。
かつて、原爆開発に携わった科学者たちは、核兵器に警鐘を鳴らした。国を挙げてAI開発にしのぎを削る時代、科学技術の利点だけでなく、そのリスクにも通じた専門家には声を上げる責任があろう。
市民の側も為政者や専門家に任せきりにせず、先端技術の利用について関心を持ち、発信すべきだ。SNSや機械翻訳など技術の利点も生かし、国を超えた連帯につなげたい。
そもそも、戦争を始めるのはAIではなく、人間である。人類の新たな災厄にしないためにも、平和を守るという強固な意思が欠かせない。
(2)②【毎日社説】'23 平和考 AI兵器と戦争 「第2の核」にせぬ英知を
’23平和考 AI兵器と戦争 「第2の核」にせぬ英知を
https://mainichi.jp/articles/20230818/ddm/003/070/093000c
注目の連載
オピニオン
朝刊3面
毎日新聞 2023/8/18 東京朝刊 English version 1658文字
核兵器をしのぐ脅威になるのではないか。そんな懸念が強まる。急速に進む人工知能(AI)の兵器化である。
ウクライナの戦場では、装甲車が疾走し、砲弾が飛び交う。ロシア部隊と繰り広げる総力戦は過去の大戦に重なる。
一方、新たな様相も見せる。最先端のテクノロジーを駆使した兵器が大量投入されている。その中核が無人機・ドローンだろう。
爆発物を搭載したカメラ付きの小型無人機を遠隔操作し、標的に衝突させる。ロシア、ウクライナ両軍が多用する最新兵器だ。
それを機能させるためにAIが使われている。地理情報や偵察動画と衛星画像を組み合わせ、敵の位置を特定する。
攻撃後、誤差を検証し、更新した情報がAIに反映される。その繰り返しにより、攻撃の精度は向上していくという。
ウクライナは自前の無人機の製造に乗り出し、ロシアは対抗して量産を加速する。激しさを増す「ドローン戦争」の現状だ。
人間が介在しない怖さ
これは「AI戦争」の始まりに過ぎない。その未来図を元米海兵隊大将で米ブルッキングス研究所長を務めたジョン・アレン氏は、戦略立案から兵器のボタンを押すタイミングまで機械が決める「ハイパー戦争」と表現する。
鳥のように群れをなしたり、魚のように潜行したりして攻撃する自律型ドローンの開発が進む。
AIの利用は兵器にとどまらない。認証情報を迅速に割り出してシステムに侵入し、重要インフラを停止させる大規模なサイバー攻撃を仕掛けることもできる。
偽情報を大量に拡散して人心を惑わし、社会不安を引き起こして統治機能を壊滅させるツールにもなりうる。
AI兵器は火薬、核に次ぐ「第3の軍事革命」と言われる。それがどういう結果をもたらすのか。「驚くべき技術の飛躍がどこへつながるか、AI設計者ですら見当がつかない」。グテレス国連事務総長が示す危機感が、未知なる戦争の恐ろしさを物語る。
未来を憂慮し、米国の非営利団体が今春、AIがもたらす「人類滅亡のリスク」に警鐘を鳴らした。「パンデミックや核戦争と並ぶ世界的な優先課題だ」と議論を喚起する声明に署名した専門家や企業トップは350人を超える。
AI兵器を「第2の核」にしないためにはどうすればいいか。真剣な議論を始める必要がある。
開発の停止を求める声がある。だが、気候変動対策や食糧生産の効率化など利点も多い技術の進歩を止めることはできないだろう。
問題はAI兵器のリスクをどう管理するかだ。何より重要なのは、使用する際には人がその責任を負う仕組みをつくることだ。
制御不能に陥ったり、誤作動を起こしたりすることは否定できない。国際人道法が禁じる民間人や民間施設への攻撃を回避するためには、人による制御を条約などで定める必要がある。
規制の枠組みが必要だ
とりわけ人類に破滅的な影響を与える核兵器システムへの搭載は禁じるべきだ。その合意に向けた努力が核保有国には求められる。
戦争における民間の影響力はかつてなく高まっている。ウクライナ軍は敵の配置について、商業衛星の画像を分析する米大手AI企業の情報を参考にしている。
そうした標的情報は、別の米宇宙企業の高速衛星通信網を介して瞬時に現場の指揮官や兵士に送られているという。
戦況を左右する企業の協力のあり方や責任の取り方をどう考えればいいか。議論は十分ではない。
核兵器がそうであるように、持てる国と持たざる国に世界を分断する恐れもある。少数の技術大国が独占する「AI覇権」だ。
規制もなく、大国が好き勝手に高度なAI技術を操るなら、世界の格差は広がり、国際協調は後退するに違いない。
原子力技術を管理し検証する国際原子力機関(IAEA)のような世界的な規制の枠組みを創設することも一案ではないか。
1945年夏。広島に原爆を投下した米軍パイロットは初めて見る光景に驚いた。とてつもない大爆発と湧き上がるきのこ雲。「なんてことをしたんだ」と日誌に走り書きした。
技術の進歩が悲劇につながらぬよう、人類の英知を結集する必要がある。
-
(3) モノの美事に「ナニも主張していない」、空虚な作文
否、「駄文の見本」であろう。
上掲①朝日社説も、上掲②毎日社説も、「AI兵器の脅威と恐怖」を再三煽っているが、煽るだけで、其れを如何すれば規制できるかを全く論じること無く、
①1> 平和を守るという強固な意志が欠かせない。
②1> 技術の進歩が悲劇につながらぬよう、人類の英知を結集する必要がある。
と、何れも最終パラグラフを「締めている」のだが・・・「精神論に逃げ込んでいる。」「気合いをかけている、だけ。」としか、私(ZERO)のような「異教徒」には思わない。
ポエムやアジテーションやシュプレヒコールならば、それでも良かろうが、曲がりなりにも「新聞社の社説」でこのザマだから、呆れるほか無いな。
端的に言えば、朝日の言う「平和を守るという強固な意志」も、毎日の言う「技術の進歩を悲劇に繋げない、人類の英知の結集」も、「全くと言って良いほど、期待できない」し、「期待するべきではない」。
そりゃぁ中には左様な「強固な意志」を持つ人も、「人類の英知を結集仕様」という人も、居ないでは無いかも知れないが、「どうせ大した数にはならない。」。
精々の所、「平和を愛する諸国民」と同数程度でしか無かろうよ。
それでも、何らかの方策なり具体策なりが示されていれば、まぁだ意味/意義のある言説かも知れないが、そんなモノはまるで無く、唯、精神論が結論なのだから、呆れる。
婉曲表現で言えば「理想主義的」と言えるのかも知れないが・・・「青臭い書生論」ったら、「書生に失礼に当たる」レベル、だと思うぞ。