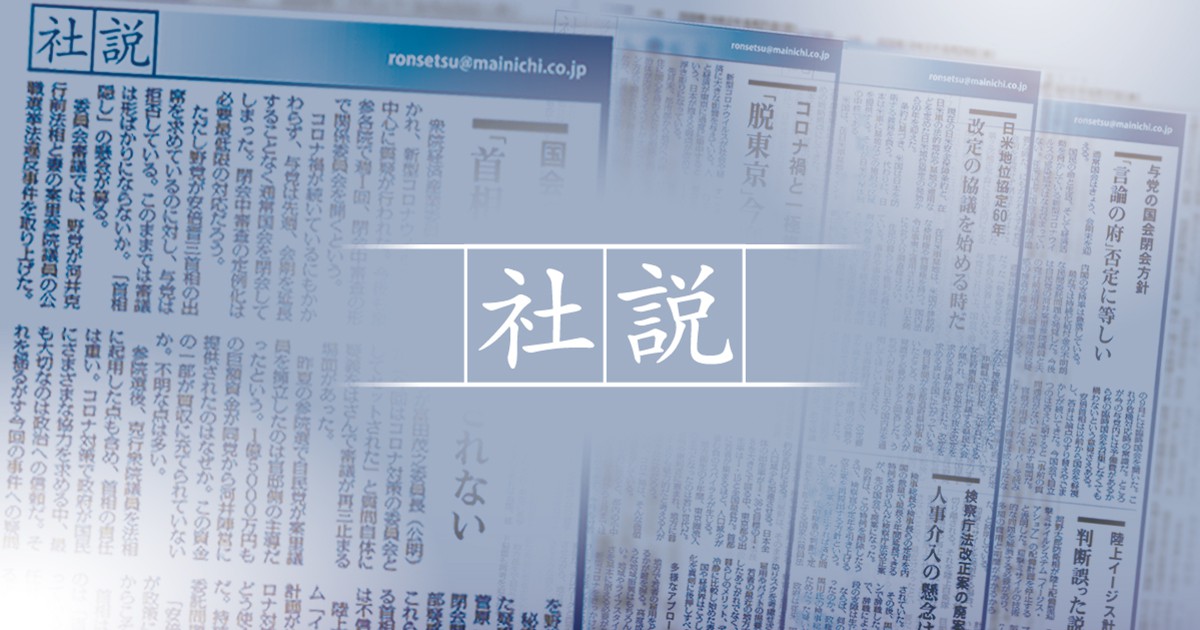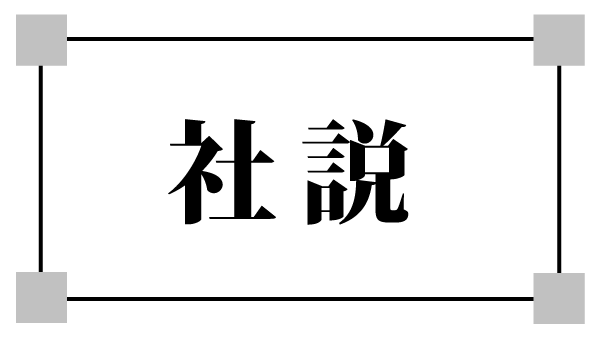-
日米首脳会談社説に見る、アカ新聞どもの焦り
日米の外相&防衛相(相当)会談(「外務・防衛担当閣僚会合」なぁんて、便利な表現もあるんだな。)である「日米2+2会談」に続いて、日本の岸田首相と米国のバイデン大統領との首脳会談が実施され、昨年末の「防衛三文書見直し」も受けて、アカ新聞どもが一寸した騒ぎになっている。下掲するのはアカ新聞各紙の社説で在り、そのタイトルを列挙すると、以下の通りである。
- ①【朝日社説】日米首脳会談 国民への説明 後回しか
- ②【毎日社説】日米首脳会談 緊張制御する安保戦略を
- ③【東京社説】日米首脳会談 対中緩和への外交も語れ
- ④【沖縄タイムス社説】[安保大変容:日米首脳会談]懸念深まる軍事一体化
- ⑤【琉球新報社説】日米首脳会談 国民不在の暴走やめよ
なぁんと言うか、「アカ新聞どもの焦り」が目に浮かぶ様な社説タイトルで在るな。願わくば、その「アカ新聞どもの焦り」が、「中共の焦り」で在り、「ロシアの焦り」であることを、期待するぞ。
☆
(1)①【朝日社説】日米首脳会談 国民への説明 後回しか
https://www.asahi.com/articles/DA3S15527864.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2023年1月15日 5時00分
厳しさを増す安全保障環境に、日米がより緊密に連携して対処するのはもっともだ。ただ、国民的議論のないままに決まった日本の安保政策の大転換を前提に、同盟強化にひた走るなら、国の防衛に不可欠な国民の理解と支持は広がるまい。
岸田首相が米ワシントンで、バイデン大統領と会談した。首相は1カ月前に安保3文書を改定し、敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有や防衛予算の「相当な増額」を決めたことを伝え、大統領は全面的な支持を表明した。首相は米国製の巡航ミサイル「トマホーク」の購入についても話したという。
首相は昨年5月に東京で開かれた首脳会談で、敵基地攻撃能力の「検討」と、予算の相当な増額への「決意」を、大統領に表明していた。いわば、その約束を果たした形だが、いずれも国内ではきちんとした説明はなく、年末ぎりぎりになって結論だけ示されたのが実情だ。
首相は会談後に米大学院で行った講演で、自身の「決断」を、吉田茂首相の日米安保条約締結、岸信介首相の安保改定、安倍晋三首相の集団的自衛権行使の一部容認に続く、「歴史上最も重要な決定の一つ」と自賛した。しかし、その重みにふさわしい議論と検討が尽くされたとは、とても言えない。
バイデン政権は昨年10月に策定した国家安全保障戦略で、同盟国にも軍事力の強化を促し、自国の抑止に組み込む「統合抑止」を打ち出した。日本の政策転換はこれに呼応するもので、米側が歓迎するのは当然だ。
ただ、両国がその行動を「最大の戦略的挑戦」と位置づける中国との関係をめぐっても、日米の利害が常に完全に一致するわけではない。米国の方針に一方的に引きずられることなく、主体的な判断を貫く覚悟が首相にあるのだろうか。
首相は講演の中で、ロシアの侵略と戦うウクライナ国民を引き合いに、「国民一人一人が主体的に国を守る意志の大切さ」を強調した。安保3文書改定後の記者会見でも同じことを述べた。国の針路にかかわる方針転換に理解と納得を得る努力を後回しにしたままで、この言葉が国民に響くとは思えない。
専守防衛を空洞化させる敵基地攻撃能力の保有が、かえって地域の不安定化や軍拡競争につながらないか。自衛隊が「盾」、米軍が「矛」という同盟の役割分担はどう変わるのか。「倍増」される防衛関連予算の財源もあやふやだ。こうした数々の疑問や懸念に、岸田政権はまだ正面から答えていない。
23日から通常国会が始まる。今度こそ首相は逃げずに、徹底した議論に臨むべきだ。
(2)②【毎日社説】日米首脳会談 緊張制御する安保戦略を
日米首脳会談 緊張制御する安保戦略を
https://mainichi.jp/articles/20230115/ddm/005/070/087000c
朝刊政治面
毎日新聞 2023/1/15 東京朝刊 859文字
日米首脳会談は、軍備増強を続ける中国への危機感を背景に、同盟の一体化を一段と深化させることを確認するものとなった。
ロシア、北朝鮮の動向を含め、安全保障環境が厳しさを増す中、抑止力を強化することは必要だ。だが、その内容が日本の防衛や地域の安定にとって最適なのか、外交的側面がおろそかになっていないか。懸念が募る。
日本は昨年末、安全保障関連3文書の改定で、相手国のミサイル発射拠点をたたく反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有を決めた。
それからわずか約1カ月。岸田文雄首相にとっては、就任後初のワシントン訪問でもあった。防衛力の抜本的強化と、防衛費の大幅増額の方針を説明し、バイデン大統領の支持を得た格好だ。
昨年5月の東京での会談で、首相は防衛費の「相当な増額」へ決意を示した。その際の「約束」への回答を示したことも意味する。
大統領は今回の会談の冒頭、「日本の歴史的な防衛費増額と新たな国家安全保障戦略を踏まえて、日米の軍事同盟を現代化していく」と語った。「日米同盟の現代化」は共同声明でも強調された。
現在の同盟のままでは、中国による東・南シナ海での一方的な現状変更の試みや、台湾海峡を巡る緊張、北朝鮮の核・ミサイル開発の進展に対応できないとの危機感があるのだろう。
しかし、日本が反撃能力を保有すれば、自衛隊は防衛力としての「盾」に徹し、米軍が打撃力としての「矛」を担うという従来の同盟の役割分担を変更することになる。日本が「矛」の役割を一部担い、専守防衛の原則が変質しかねない。
軍事力には軍事力で対抗するという発想ばかりが目立つことも問題だ。共同声明は、外交への目配りが乏しく、最後に日米豪印や東南アジア諸国連合(ASEAN)などとの協力に簡単に言及しただけだった。軍事的抑止と外交は、安全保障の両輪だ。にもかかわらず、地域の緊張を緩和するための戦略が見えてこない。
通常国会が今月下旬から始まる。安全保障政策の大転換を米国に説明した後、与野党で議論するというのは順序が逆転している。徹底した審議が不可欠だ。
(3)③【東京社説】日米首脳会談 対中緩和への外交も語れ
日米首脳会談 対中緩和へ外交も語れ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/225874?rct=editorial
2023年1月18日 07時57分
岸田文雄首相とバイデン米大統領との首脳会談が行われ、共同声明で日米軍事協力の「深化」を誇示した。軍備拡張を続ける中国をけん制する狙いだが、軍事に偏った対応は対立を煽(あお)ることになりかねない。日米両政府には緊張緩和に向けた外交戦略も示すよう求めたい。
ワシントンで初めて行われた岸田・バイデン会談の主要テーマは中国だった。共同声明は中国による「ルールに基づく国際秩序と整合しない行動」を批判し、台湾問題の「平和的解決」を促した。
しかし、中国との対話には言及せず、日米の軍事協力ばかりが強調された。外交軽視である。
バイデン氏は、防衛力を抜本的に強化する日本政府の方針を「称賛」。日本が保有を決めた敵基地攻撃能力(反撃能力)の開発・運用でも「協力を強化」し、日米両国の「安全保障同盟はかつてなく強固」とも明記した。
自衛隊と米軍は協力を進めてきたが、これまでとまったく異なるのは、専守防衛という「盾」に徹してきた自衛隊が敵基地攻撃能力を持つことで、米軍が担ってきた打撃力という「矛」の役割を一部担うようになることだ。
憲法九条に基づく専守防衛は形骸化し、日本周辺地域の軍拡競争にも拍車をかけるだろう。
バイデン政権は中国を「唯一の競争相手」と位置付け、中国との覇権争いを最優先課題とする。昨年末、南シナ海上空で米中の軍用機が異常接近するなど、対立が軍事衝突に発展する懸念もある。日米の軍事一体化が進めば、日本も参戦することになりかねない。
相手国を威嚇する「戦狼(せんろう)外交」を強める中国との対話には困難が伴うが、相手の意図を正確に読み取るには重層的な意思疎通が欠かせない。まずは林芳正外相、ブリンケン国務長官がそれぞれ計画する訪中実現が急務だろう。
首相が、増税を伴う安保政策の大転換を国会で説明する前に、バイデン氏に報告したのは順序が逆だ。米国の支持で政策転換を既成事実化する意図があるなら看過できない。野党は二十三日召集の通常国会で厳しく追及すべきだ。
(4)④【沖縄タイムス社説】[安保大変容:日米首脳会談]懸念深まる軍事一体化
[安保大変容:日米首脳会談]懸念深まる軍事一体化
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1088577
2023年1月16日 7:42
米軍基地・安保
集団的自衛権の行使容認に道を開いた安倍晋三元首相の「共に戦う同盟」路線を深化させたような首脳会談だった。
岸田文雄首相とバイデン米大統領がホワイトハウスで会談した。
岸田首相は反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有決定と防衛予算の増額を伝え、バイデン氏は「歴史的だ」と称賛した。
両首脳の共同声明では、これら日本の取り組みについて「日米関係を現代化するものとなる」と位置づけた。
会談に先駆けて実施された日米安全保障協議委員会(2プラス2)では、対米協力をにらみ、自衛隊陸海空部隊の「統合司令部」創設が取り上げられた。
バイデン政権では原子力空母を日本海に展開させ、自衛隊や韓国軍と連携する「統合抑止力」も浮上している。
米国は、もはや自国だけでは中国や北朝鮮を抑えられない。
「現代化」や「統合」という言葉は、日米の防衛協力が全く新たな段階に入ったことを示している。
首相は、自律飛行し敵を攻撃する米国製の巡航ミサイル「トマホーク」の購入も伝えた。
反撃能力の保有が閣議決定されたのは国会閉会後で、わずか1カ月前である。国民的な議論もないまま軍拡路線に突き進む首相の姿勢は、あまりに前のめりすぎる。
■ ■
日米の軍事一体化の背景にあるのが、東アジアの安全保障環境に対する強い危機感だ。
共同声明ではロシアによるウクライナ侵攻や、中国や北朝鮮の軍事行動を挙げ「あらゆる力または威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対する」と強調した。
中国の海洋進出や、北朝鮮のミサイル発射は周辺の緊張を高めており問題だ。しかし、日米による抑止力強化も地域の緊張を高めている。
批判された中国や北朝鮮がさらなる挑発行動に走る危険性は高い。軍事力に軍事力で対抗するだけでは「安全保障のジレンマ」に陥りかねない。
2プラス2では、米軍嘉手納弾薬庫の共同使用で一致。自民党内には下地島空港を国管理にし、軍事利用する案も出ており、懸念が高まっている。
■ ■
念頭に置くのは「台湾有事」だが、この間、際立つのは軍事強化だ。緊張緩和の外交や、有事の際の住民保護などの議論はほとんど見えない。
首相は会談後の講演で、「昨年、私は外交・安全保障政策で二つの大きな決断を行った」として、安保政策を大きく転換したことを説明した。一方で、国民や県民への説明はいまだに十分とは言えない。
23日から始まる通常国会では、安全保障特別委員会の設置を求めたい。防衛増税や日米同盟の在り方、沖縄の負担軽減について徹底的に議論すべきだ。
(5)⑤【琉球新報社説】日米首脳会談 国民不在の暴走やめよ
日米首脳会談 国民不在の暴走やめよ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1646906.html
2023年1月15日 05:00
社説
mail_share
岸田文雄首相はバイデン米大統領とホワイトハウスで会談し、日本の防衛力強化や防衛費増額の方針を説明、バイデン氏はこれを称賛した。両首脳は他国領域のミサイル基地などを破壊する日本の敵基地攻撃能力(反撃能力)開発と運用に向けた協力で一致し、同盟深化への決意を示した。
岸田政権は先月、敵基地攻撃能力保有の明記など防衛力を強化する安保関連3文書を閣議決定し、安保政策を大転換した。専守防衛を逸脱する内容だ。2023年度から5年間の防衛費を現在の1・5倍の約43兆円に増やす方針だ。
バイデン氏に伝えられたこれらの内容は国会で議論されておらず、国民から理解を得ているどころか反発も強い。にもかかわらず、米国に「約束する」のは、国民への背信行為で、断じて許されない(*1)。岸田政権は国民不在の独断的な暴走をやめるべきだ。
重要なのは、日本の敵基地攻撃能力保有や防衛費増額が米国の要求であることだ。岸田首相が国民を置き去りにしたまま、米国の要求に応えた形である。乱暴極まりない。
首相の唐突な方針表明に世論は反発している。共同通信社が先月実施した全国電話世論調査によると、43兆円の防衛費増額方針について賛成は39・0%に対し反対は53・6%。防衛力強化のための増税については支持30・0%に対し不支持は64・9%。この増税を巡る首相の説明に関し「不十分だ」と答えた人が87・1%で、「十分だ」の7・2%を大きく上回った(*2)。
両首脳が表明した「同盟深化」は危険もはらむ。「民主主義国」を中心とした国際秩序が中国やロシアなどによって脅かされているとの危機感を背景に両国への対抗姿勢を鮮明にした。国際社会の分断を回避する道筋を示すどころか、むしろ対立をあおる形だ。
中ロに北朝鮮を加えた国々との軍拡競争によって「安全保障のジレンマ」を自ら招く形といえる。軍備増強で自国の安全を高めようと意図した政策が、想定する相手国にも軍備増強を促し、実際には双方とも衝突を避けたいにもかかわらず、結果的に衝突の恐れが高まる状況だ(*3)。今回の首脳会談の結果は、東アジア地域で安全保障のジレンマを決定的にしたともいえる。
この地域で緊張が高まり有事が起きれば、真っ先に標的にされ被害を受けるのは、急速に軍備強化が進む南西諸島だ。有事の際の住民保護計画は不十分で、戦闘が長引けば実行は不可能だろう。配備予定の攻撃型ミサイルを撃ち合えば、甚大な被害をもたらす。絶対に避けるべきだ。
列島に点在する原発を狙われれば日本は致命的な事態に陥る。住民保護は脆弱であることを肝に銘じるべきだ。重要なのは有事をいかに回避するかだ。この議論が決定的に不足している。対立ではなく衝突回避のための国際協議の枠組み構築など安定的な関係を生む外交戦略(*4)が必要だ。
- <注記>
- (*1) [国民の認可無しに政府の方針を外国に表明できない]ってのは、どう考えても「首脳会談の否定」でも在れば、「政府の外交権の否定」でもある。
- (*2) 「世論調査で政策を決定する」と言うのは、少なくとも一面、大衆迎合の人気取りであり、衆愚政治への入口である。
- 都合の良いときだけ、世論を引っ張り出して、「世論に従え」ってやぁガル。「敵基地攻撃能力を、世論の6割が支持」って結果は、無視しやぁがる癖に。
- (*3) 結構なことではないか。軍拡競争に至らず、一方的に軍拡不戦敗する事は、回避できたのだから。
- (*4) 外交は、弾丸を使わない戦争ですが、何か?
(6) 一方その頃、韓国のアカ新聞は・・・
☆
1.【ハンギョレ社説】日本の軍事大国化を追認した米、北東アジアの軍拡競争が懸念される
日本の軍事大国化を追認した米、北東アジアの軍備競争が懸念される
登録:2023-01-16 02:03 修正:2023-01-16 08:19
https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/45648.html
米国のバイデン大統領と日本の岸田首相が13日(現地時間)、米ワシントンのホワイトハウスで、首脳会談の開始にあたって握手を交わしている=ワシントン/ロイター・聯合ニュース
「敵基地攻撃能力(反撃能力)」を保有し、5年内に防衛費を2倍に拡大するという日本の計画を、米国が公式に追認した。日本は戦後70年あまりにわたって維持してきた「専守防衛」原則を事実上廃棄し、軍事大国化していくうえでの心強い援軍を確保した。米日同盟が中国の挑戦に対抗して露骨に軍事協力を強化したことで、北東アジアで軍拡競争が加速することが憂慮される。
米国は11~13日(現地時間)、ワシントンで日本と外交・防衛相による「2プラス2」会談と首脳会談を相次いで行い、日本の反撃能力の保有と大々的な軍備拡張に強い支持を表明した。米国のバイデン大統領は「日本の歴史的な防衛費支出の増大と新たな国家安保戦略を基盤として、我々の軍事同盟を現代化している」と述べた。また米日の首脳は共同声明で、「日本の反撃能力及びその他の(軍事的)能力の開発及び効果的な運用について協力を強化するよう、閣僚に指示した」と述べた。さらに、米国製トマホークミサイルを日本が数百発購入すること、沖縄駐留の米海兵隊を連隊規模に拡大するとともに、機動性を強化して活動半径を広げることに合意した。
米日のこのような動きは、「米国は攻撃(矛)、日本は防衛(盾)」という第2次世界大戦以降の役割分担が根本的に転換されつつあることを意味する。中国の軍事的挑戦という新たな環境に対応しようというものだが、結果的に北東アジアは各国の軍拡競争の悪循環に陥るとみられる。軍拡競争は緊張を高め、偶発的な衝突の可能性を高める。このような状況は決してどの国にとっても好ましいものではない。
朝鮮半島は地政学的位置上、大国同士の軍事力競争の最大の被害国になり得るだけに、このような時こそ韓国の役割が重要だ。韓国は、大国の間に立つ仲裁者となることはできないだろうが、少なくとも北東アジアで偶発的な衝突が発生しないようにする装置を主導的に作っていかなければならない。冷戦時代に欧州諸国が欧州安保協力機構(OSCE)を創設し、冷戦的対決を緩和し共存を達成したように、東アジア版安保協力機構の創設がそのような方法になりうるだろう。そのような点で、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領がこのところ独自の核武装の可能性に言及し、日本の軍事大国化の動きを容認するような発言をしたことは、非常に憂慮される。米日の軍事力強化に調子を合わせるのではなく、外交力を総動員して緊張を管理しうる方法を早急に模索してもらいたい。
(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/1075773.html
韓国語原文入力:2023-01-15 18:43
訳D.K
-
(7)矢っ張り、アカ新聞は、チョウセンジン並みだな。
国家安全保障の基本は、軍事力だ。外交も、同盟も、軍事力在っての話で在り、「軍事力抜きの外交」も「軍事力抜きの同盟」も、基本的には骨抜き、虚構、絵空事。「軍事力抜きの同盟」なんてのは、原語矛盾に近い(*1)。
戦争は、弾丸を使う外交。
外交は、弾丸を使わない戦争。
戦争も外交も、国益追求の手段で在り、目的は、国益だ。
朝日も毎日も東京も、「日本の防衛方針転換について、日米首脳会談で『米国に報告』するより先に、国会で国民に説明すべきだ/説明すべきだった。」と主張しているが、「国民への説明」は別に国会に限ったことではない。「日本の防衛方針転換」ならば、岸田首相も相応に表明しているし、その路線は「国防三文書の公的改訂」という形にこそならなかったモノの、先々代の首相たる安倍晋三元首相以来の「既定路線」ですら、あろうが。
岸田首相の「防衛方針転換説明」が、十分か否かというのに議論の余地はあろうが、モリカケ桜はじめとする「出来損ないスキャンダルの追及しか能が無い」事をここ数年立証実証し続けている今の野盗共、もとい、野党共相手には、「何を如何何遍説明しようが、無駄であろう。」と言うことは、十分予想できる。
仮に日米首脳会談に先立って国会が開かれ、岸田首相と日本政府が日本の防衛方針転換について説明したとしても、あの夜盗共、もとい、野党共(*2)は、「納得」なんか絶対にせず、議決したところで「強行採決だ!」「議論は不十分(*3)だ!!」と騒ぎ、アカ新聞どもは、日米首脳会談後であっても「日本の防衛方針転換について、国民は納得してない!!」と主張したであろう事は、賭けても良いぐらいだ。
言い替えようか。あの野盗/夜盗/野党共を相手にして、「我が国の防衛方針」を幾ら期間をかけて説明(それは、恐らく、議論にすらならない。)しようが、「国民的議論」になんかならない。良い処、「疑惑ハサラニ深マッター」のリフレインで終わるだろう。
従来従前の、モリカケ桜学術会議の様に、な。
まあ、そんな野盗/夜盗/野党共ばかりを、国会議員として選出し続けている、有権者たる日本国民に、左様な「惨状」の責任の一端は、あるのだけどね。
衆院選挙に「当時憲政史上最多の衆院議席数」を獲得して華々しく「政権交代」を果たしたその時の「連立予定三党共通公約」に、「安全保障」って項目が「皆無であった」民主党、社民党、さきがけ の「なれの果て」共に、未だに国会議席を与え続けていると言う事自体が、「常軌を逸している」と思うんだがね。
ま、あ・の・鳩山由紀夫(*4)率いる、あ・の・民主党に、「当時憲政史上最多の議席数」を与えて政権与党に祭り上げたのも、他ならぬ日本国民であるから、その程度の「狂気」は、「当たり前」とも、言い得るのだがね。
- <注記>
- (*1) かつての、片務的な日米同盟=日米安保条約が、「軍事力抜きの同盟」に近いモノがあったが、そりゃ米国が日本に「軍事力の無い状態」を強制したという「負い目があった」からで在り、極々珍しい「同盟関係」である。
- (*2) 日本維新の会ぐらいは、未だマシな対応をする、かなぁ?程度。国民民主党だって全く当てに出来ないし、立憲民主党なんざ共産党並みに論外だ。
- (*3) ウーン、あの野党共が真っ当に「議論している」所ナンざぁ、国会であろうが国会外であろうが、トンと見た覚えが無いんだが。
- (*4) 当時、鳩山由紀夫の気違いぶりは「余り知られていなかった」のは事実だが。かく言う私(ZERO)も「訳の判らぬ胡散臭い奴」とは思っていたが、気違いとは知らなかった。