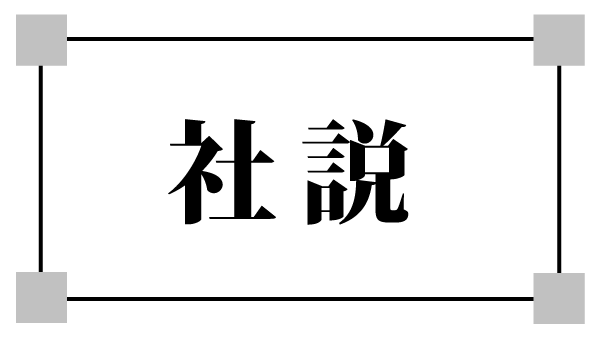-
最早、「明らかなる敵」ではないか?-【沖縄タイムス社説】[米即応部隊配備へ]機能強化認められない &【琉球新報社説】沖縄に離島即応部隊 負担軽減の道理に反する
沖縄二紙の軍事忌避軍人差別平和ボケ安保白痴は、既に再三弊ブログで指摘し記事にしてきた所。その「沖縄二紙の軍事忌避軍人差別平和ボケ安保白痴」が「完全なる自発的な善意に基づくモノ」と考えるよりは、「日本侵略を狙い、宣言公言している中国共産党の手先となり、日本侵略の尖兵となっている。」と考える方が「安全側である」ことも、仮に「完全なる自発的な善意に基づくモノ」であったとしても「日本侵略を狙い、宣言公言している中国共産党の手先となり、日本侵略の尖兵となる」のと「効果として、影響として、同程度である」事も、何度か記事にしている。
ああ、「日本侵略を狙い、宣言公言している中国共産党」って表記を否定する向きもあるだろうな。だが、「尖閣諸島(中国名:魚釣島)は、中国の核心的利益」と公言宣言しコレを撤回していない以上、「中国共産党が、日本侵略を狙い、宣言公言している。」事に、疑義の余地は無い。
だが、「それでも沖縄二紙の記者の大半は、日本国籍を有する日本国民に違いない。」と考える私(ZERO)は、「沖縄二紙の軍事忌避軍人差別平和ボケ安保白痴」は「完全なる自発的な善意に基づくモノ」である、少なくとも「可能性」を、幾許なりとも「内心期待して」居たのだが・・・どうも、その「期待」は、「虚しいモノ」でありそうだ。
前述の通り、「沖縄二紙の軍事忌避軍人差別平和ボケ安保白痴」は「完全なる自発的な善意に基づくモノ」であろうが、無かろうが、「実害として大差は無い」のだけどね。
- ☆【沖縄タイムス社説】[米即応部隊配備へ]機能強化認められない
- ☆【琉球新報社説】沖縄に離島即応部隊 負担軽減の道理に反する
(1)【沖縄タイムス社説】[米即応部隊配備へ]機能強化認められない
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1086205
2023年1月11日 6:55
米軍基地・安保
はてなブックマーク
バイデン米政権は沖縄に駐留する海兵隊の一部を数年以内に改編し、離島防衛に備えて対艦ミサイルを装備した即応性のある「海兵沿岸連隊(MLR)」を配備する方針を固めた。南シナ海や東シナ海で海洋進出を強める中国への抑止力を高め、周辺地域で有事の対処力を強化する狙いがある、という。
自衛隊による南西諸島の軍備強化が進む中、米軍まで、さらに機能強化が進めば県民の基地負担が一層増す。そして何より、基地が集中することで沖縄が再び戦争に巻き込まれることを強く危惧する。
MLRは1800~2千人規模となる見込みで、敵のミサイルの射程圏内で機動的に対応する能力が特徴。敵のミサイル攻撃をかわしながら部隊を分散し、複数の離島で、対艦ミサイルなどの拠点を確保する新戦略「遠征前方基地作戦(EABO)」を実行する。
すでに米軍は、伊江島補助飛行場やうるま市の浮原島などで訓練を実施している。
キャンプ・ハンセンの第12海兵連隊(砲兵)、シュワブの第4海兵連隊(歩兵)の改編が検討されている。
MLRが配備されても、沖縄全体で海兵隊を約1万人とする米軍再編計画に変更はないとされる。一方で訓練の激化が想定される。
■ ■
昨年12月、EABOに基づく演習が沖縄本島北部で実施され、東村高江の県道70号でライフル銃などで武装して歩く米兵の姿が確認された。
同演習では、敵国が沖縄に侵入し、占拠されたダムを奪還するなど、具体的な戦略を想定していた。
沖縄が戦場となることを前提とした訓練は、すでに始まっている。
加えて自衛隊は、第15旅団の「師団」への増強を図り、奄美から宮古、石垣島まで、地対艦、地対空ミサイルの部隊配備を進める。勝連分屯地にも地対艦ミサイルが配備される。新たな部隊配備は米軍の新戦略と呼応している。
MLRの配備は、11日に開催予定の日米外務・防衛閣僚による安全保障協議委員会(2プラス2)で確認する方向だ。
日本の動きは、米国の戦略への過剰な適用にみえる。台湾有事を前提とした「日米VS中国」の対立が強まり、急速に進む軍拡路線に危機感が募る。
■ ■
反撃能力(敵基地攻撃能力)を明記した「国家安全保障戦略」は、安全保障上の目標を達成するため「第一に外交力」を挙げている。
しかし、地域の緊張を和らげる外交はほとんど見えない。
中国から攻撃された場合の住民へのリスクの説明も乏しい。自衛隊の強化や米軍のMLRの配備は、沖縄県の理解を得ぬまま進められ、専守防衛を巡る安保政策の議論は国会で圧倒的に不足している。
13日には、日米首脳会談が開かれる。両首脳には長期的な中国との協調を見据えた、外交戦略についても具体的な協議を進めてもらいたい。
前の記事へ
(2)【琉球新報社説】沖縄に離島即応部隊 負担軽減の道理に反する
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1644731.html
2023年1月11日 05:00
社説
mail_share
米政府が在沖米海兵隊を改編し、離島有事に即応する「海兵沿岸連隊(MLR)」を創設する方針だ。基地負担軽減の道理に反し、到底容認できない。
沖縄の負担軽減の名目で、海兵隊約9千人のグアムやハワイへの移転で日米が合意している。訓練についても国内の演習場への分散移転が進められてきた。
「台湾有事」を見据えて対処戦術を特化した部隊を創設するのは、機能強化にほかならない。負担軽減どころか強化一辺倒であり、県民を不安に陥れるものだ。
沖縄に置くMLRは、ハワイの部隊と同程度の2千人前後の規模とされる。このため、約1万人の海兵隊員を沖縄に残す米軍再編計画に変更はないとの見立てがある。数字のまやかしではないのか。
仮に人員の帳尻を合わせたとして、離島侵攻を想定した戦術を展開する部隊を置くことは機能の強化ではあっても軽減とは言えない。
南西諸島周辺の緊張の高まりを理由とした配備強化は自衛隊も同様だ。那覇市の陸自第15旅団は師団へと格上げされる。安保関連文書への敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有明記に伴い、長射程ミサイルの県内配備も想定される。
陸上自衛隊は離島防衛専門部隊「水陸機動団」を創設した。自衛隊と米軍の一体化によって訓練も激しくなり、離島奪還を想定した共同訓練も県内で実施されている。
これらの軍備強化は中国の離島侵攻を想定している。南西諸島への配備強化の動きは、中国をより刺激することにしかならない。
有識者からは軍事的な衝突の回避に向けた提言が相次いでいる。その多くが抑止力強化偏重の安全保障戦略を疑問視し、軍事力によらない新たな秩序やシステムの構築で地域の安定の実現を提唱するものだ。こうした知見こそ平和国家たる日本が追求すべき方向性である。
沖縄へのMLR創設は、11日の日米安全保障協議委員会(2プラス2)で確認する見通しだという。既に日米外務・防衛当局者の間では確認済みということだ。
国民への説明抜きに、まずは米国と協議して推し進める姿勢は日本の安全保障政策に一貫している。在沖基地の整理縮小をうたったのは日米特別行動委員会(SACO)合意である。その本質が負担軽減ではなく、県内移設による機能強化にあることは、普天間飛行場や那覇軍港の返還条件で示されてきた計画などからも明らかだ。
「台湾有事」の危機感の高まりに乗じて事を進める政府の姿勢は、もはやあからさまに南西諸島の軍事拠点化を一気に進めているようにしか見えない。
沖縄の負担軽減名目で訓練移転を受け入れてきた全国の自治体への説明もないままだ。国会の場を含め、全国民に説明する必要がある。
-
(3)「基地負担」なんぞ、オマケだ。「些事」だ。「道理」な、訳が無い。
「兵力を増強」しても、「装備を更新して強化」しても、「基地負担増」とは言い得るだろうさ。上掲沖縄二紙社説は、「沖縄への離島即応部隊配備」を、「基地負担増である」として、反対して見せている。他に解釈のしようは、在りそうに無い。
かかる沖縄二紙の「沖縄への離島即応部隊配備反対社説」が、「沖縄二紙が、日本侵略を狙い宣言公言している中国共産党の手先であり、日本侵略の尖兵となっている」事の証左・証拠とは、断言断定はしかねるだろう。
だが、かかる沖縄二紙の「沖縄への離島即応部隊配備反対社説」が、「日本侵略を狙い宣言公言している中国共産党の手先や、日本侵略の尖兵」と「利害が一致している」事には、一寸疑義の余地が無い。一般的に「基地負担軽減」とは「基地の弱体化、基地駐屯部隊の弱兵化」を意味するから、そりゃぁ「利害も一致」しようというモノだ。
諄い様だが繰り返すと、沖縄二紙は「日本侵略を狙い宣言公言している中国共産党の手先であり、日本侵略の尖兵となっている」と考える方が、「安全側」である。
まあ、単に「安全側である」ばかりでは、感覚的・感情的に「済まなくなっている」のも、事実だけどね。
Parabellum 戦いに備えよ。