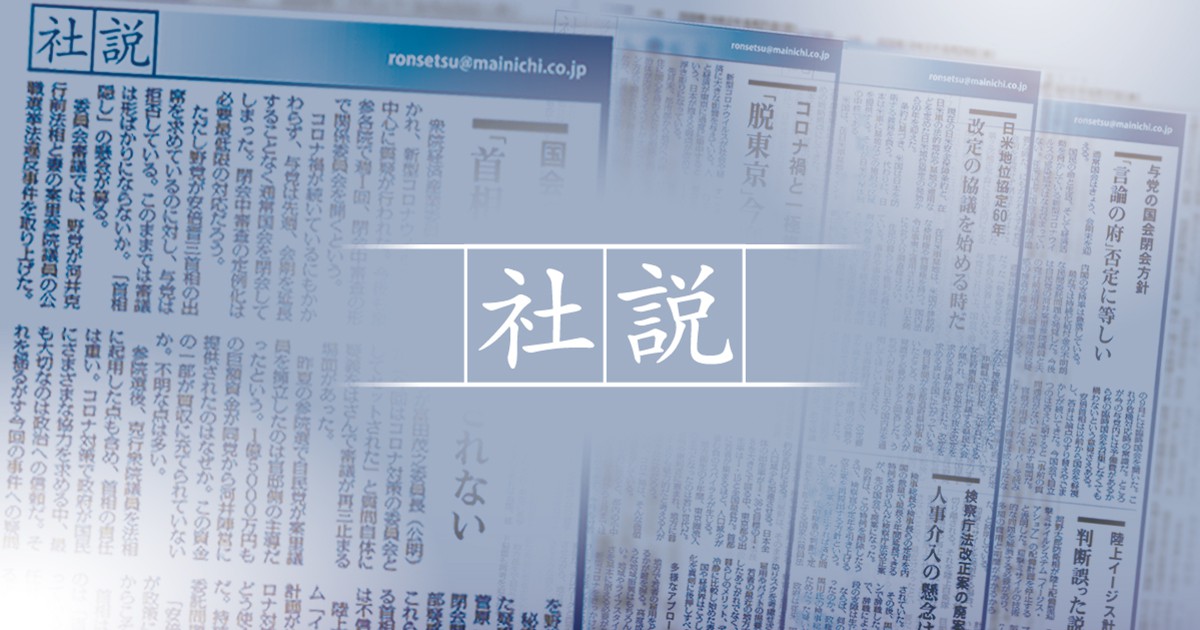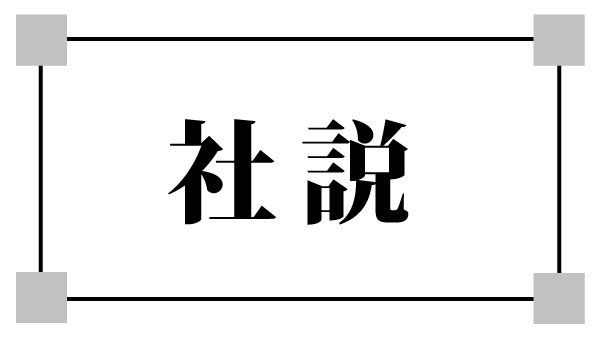-
「こういう人達に、負けるわけにはいかない!」ー安倍元首相国葬翌日のアカ新聞社説
先行記事にした通り、安倍元首相国葬に対して、毎日新聞が国葬前日に「岸田首相の責任は重いぃぃぃっ!」って社説を掲げた上、国葬当日には東京新聞が「静かな追悼が妨害されたぁぁぁぁッ(*1)」と主張する社説を掲げ、どちらも「負け犬の遠吠え」社説としか思えず、私(ZERO)は呆れ返ってたのだが、なぁんと、安倍元首相国葬翌日には、アカ新聞どもが挙ってこぉんな社説を掲げてやぁガル。
①【朝日社説】安倍氏「国葬」 分断深めた首相の独断
②【毎日社説】安倍元首相の「国葬」 合意なき追悼の重い教訓
③【東京社説】「安倍政治」検証は続く 分断の国葬を終えて
④【沖縄タイムス社説】「安倍氏の国葬」国会の検証が不可欠だ
⑤【琉球新報社説】反対大勢の国葬実施 決定過程の検証が必要だ
- <注記>
- (*1) イヤ、妨害しているのは、お前ら「国葬反対者」だろうが。
(1)①【朝日社説】安倍氏「国葬」 分断深めた首相の独断
https://www.asahi.com/articles/DA3S15429404.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年9月28日 5時00分
安倍元首相の「国葬」で、追悼の辞を述べる岸田首相=2022年9月27日、東京都千代田区の日本武道館、代表撮影
[PR]
本来なら、選挙中に凶弾に倒れた元首相を静かに追悼する場とすべきところを、最後まで賛否両論が渦巻く中で挙行した。社会の分断を深め、この国の民主主義に禍根を残したというほかない。異例の「国葬」を決断した岸田首相の責任は、厳しく問われ続けねばならない。
国内外から4千人以上が参列して、安倍元首相の国葬が営まれた。一般向けの献花台には、早朝から多くの人が列をつくった。一方、反対する集会やデモ行進も各地で行われた。
首相経験者の葬儀は、内閣と自民党の合同葬が定着しており、約5年の長期政権を担った中曽根元首相もそうだった。同じ形式だったら、世論の反発はここまで強くなかったかもしれないが、首相は法的根拠があいまいで、戦後は吉田茂の1例しかない国葬を選んだ。
戦前の「国葬令」では、「国家に偉勲ある者」が、天皇の思(おぼ)し召(め)しである「特旨」によって国葬の対象となった。天皇主権から国民主権に代わった戦後の民主主義の下で、国葬を行おうというのに、国民の代表である国会の理解を得る努力なしに、首相は国葬を独断した。
安倍氏が憲政史上最長の8年8カ月、首相の座にあったのは事実だが、その業績への賛否は分かれ、評価は定まっていない。強引な国会運営や説明責任の軽視、森友・加計・桜を見る会などの「負の遺産」もある。
政権基盤の強化に向け、安倍氏を支持してきた党内外の保守派へのアピールを狙い、国葬に違和感を持つ世論の存在に思いが至らなかったとすれば、首相による国葬の「私物化」と評されても仕方あるまい。
首相は追悼の辞で、安保・外交分野を中心に安倍政権の業績をたたえ、集団的自衛権の一部行使に道を開いた安保法制や特定秘密保護法の制定などを挙げた。しかし、これらは、強い反対論があるなか、数の力で押し切って成立させたものだ。国葬が安倍政権に対する評価を定め、自由な論評を封じることがあってはならないことを、改めて確認したい。
国葬への反対は時がたつほど強まった。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と自民党政治家との関係が次々と明らかになり、その要として安倍氏の役割に焦点があたったことが影響したに違いない。
数々の疑問や懸念を抱えた国民を置き去りにしたまま、国葬は行われ、社会の分断にとどまらず、国民と政治との溝を広げることになった。その距離を縮め、信頼回復の先頭に立つのは、国葬を決めた首相以外にない。週明けに始まる臨時国会への対応が試金石となる。
(2)②【毎日新聞社説】安倍元首相の「国葬」 合意なき追悼の重い教訓
https://mainichi.jp/articles/20220928/ddm/005/070/119000c
注目の連載
オピニオン
朝刊政治面
毎日新聞 2022/9/28 東京朝刊 English version 1611文字
参院選の遊説中に銃撃され亡くなった安倍晋三元首相の「国葬」が、厳戒下で営まれた。
首相経験者としては戦後2例目となり、1967年の吉田茂元首相以来55年ぶりである。
三権の長や海外の要人ら4000人以上が参列し、会場外の献花台には長い列ができた。岸田文雄首相は弔辞で、「開かれた国際秩序の維持増進に、世界の誰より力を尽くした」と功績をたたえた。
凶弾に倒れた故人を悼む機会を設けること自体には、異論は少ないだろう。
しかし、国葬反対の声は日を追うごとに高まり、毎日新聞の直近の世論調査では約6割に上った。一部の野党幹部が参列せず、反対集会も開かれた。
分断招いた強引な手法
岸田首相は当初「国全体で弔意を示す」と説明したが、幅広い国民の合意は得られず、かえって分断を招いた。
その責任は、国葬という形式にこだわり、強引に進めた首相自身にある。
そもそも政治家の国葬には、明確な基準や法的根拠がない。そうであれば、主権者である国民を代表する国会が、決定手続きに関与することが不可欠だったはずだ。
だが、首相は「暴力に屈せず、民主主義を守る」と言いながら、国会に諮らず、閣議決定だけで実施を決めた。議会制民主主義のルールを軽視し、行政権を乱用したと言われても仕方がない。
国葬には約16億6000万円の国費がかかり、国会の議決を経ない予備費からも支出される。
「安倍氏をなぜ国葬とするのか」という根本的な疑問は、最後まで解消されなかった。
歴代最長の通算8年8カ月間、首相を務めた安倍氏だが、退陣してまだ2年で、歴史的な評価は定まっていない。森友・加計学園や「桜を見る会」などの問題も未解明のままだ。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との深い関わりが発覚したことが、反対論に拍車をかけた。自民党議員と教団の重要な接点となっていた疑いが浮上している。
ところが岸田首相は、安倍氏が死去したことを理由に調査を拒んでいる。閣僚や自民党議員に対する調査も不十分だ。疑念にふたをしようとする姿勢に、国民の不信が深まった。
批判の高まりを受け、「弔意を強制するものではない」と首相は繰り返した。自治体や教育委員会などに対する弔意表明の協力要請も見送った。
無理を通そうとした結果、国葬色は薄れて、名ばかりのものとなった。
実施決定から約1カ月半後に、ようやく開かれた衆参両院の閉会中審査は、わずか計3時間にとどまった。首相の答弁は説得力に欠けた。
国葬を強行した手法は、首相が掲げる「聞く力」や「丁寧な説明」とは程遠い。かつて安倍・菅両内閣が独断で物事を決め、異論に耳を傾けなかったことに対する反省はうかがえない。
前例にしてはならない
一連の経緯から浮かび上がったのは、政治家の国葬は、価値観が多様化する現代になじまないということだ。
戦前・戦中には、皇族だけでなく、軍功があった人物も国葬とされ、国威発揚の手段に使われた。その反省から、旧国葬令は敗戦直後に廃止された。
吉田元首相の国葬の際にも、基準の曖昧さや法的根拠の欠如が問題となった。
このため75年の佐藤栄作元首相の葬儀は、内閣・自民党・国民有志の「国民葬」として行われた。80年の大平正芳元首相以降、内閣と自民党による「合同葬」が主流となってきた。
国民の理解を得て、静かに故人を送る環境をどう整えるのか。半世紀以上にわたり、首相経験者の国葬が行われなかったのは、対立や混乱を避けるための政治的な知恵だった。
にもかかわらず岸田首相は、国葬の実施について「時の政府が総合的に判断するのが、あるべき姿だ」と強弁した。それでは、恣意(しい)的に運用される恐れがあり、特定の政治家への弔意を国民に強いることにもつながりかねない。
そうした事情への配慮を欠いたことが、追悼の環境を損ない、分断を深めてしまった。前例とすることがあってはならない。
今回の国葬の重い教訓である。
(3)③【東京社説】「安倍政治」検証は続く 分断の国葬を終えて
https://www.tokyo-np.co.jp/article/205085?rct=editorial
2022年9月28日 07時06分
故安倍晋三元首相の国葬がきのう東京・日本武道館で行われた、代表撮影。故人への敬意と弔意を表す国の公式行事として国葬が行われたとしても、国葬実施により国民は分断され、安倍氏の歴史的評価も定まったわけではない。「安倍政治」の検証作業は私たち自身が続ける必要がある。
安倍氏は二〇一二年十二月の衆院選で首相に復帰し、二〇年九月に体調不良を理由に内閣総辞職した。第一次内閣の一年間と合わせると通算八年八カ月、首相の座にあったことになる。この間、私たちの暮らしや、社会や政治はよくなったのだろうか。
まず検証すべきは大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略という「三本の矢」からなる安倍氏の経済政策「アベノミクス」の功罪だ。
第二次内閣発足間もない一三年に始まったアベノミクスが当初、国内経済に強い刺激を与えたことは事実だろう。金融緩和と財政出動で金融市場に大量の投資資金が流れ込み、株価は回復。多くの企業が財務環境を好転させた。
しかし、利益を内部留保にため込んだ企業は人件費に回さず、給与は今に至るまで伸びていない。経済格差も広がっている。
アベノミクスが描いた「投資活性化による利益が賃上げを促し、消費が伸びる」という好循環は結果として実現しなかった。
最大の理由は、外国人観光客の増加以外に、効果的な成長戦略を見いだせなかったことだろう。
◆政策縛るアベノミクス
岸田文雄首相はアベノミクスを事実上継承し、野放図で場当たり的な財政出動と緩和一辺倒の金融政策を続ける。それは結果として政策の手足を縛り、日本経済の懸念材料となっている円安・物価高に対する政府・日銀による政策の選択肢を狭めている。
私たちの暮らしにとって、アベノミクスは「功」よりも「罪」の方がはるかに大きい。
安倍氏の後継政権である菅義偉前首相、岸田首相は国葬での追悼の辞で、いずれもアベノミクスに言及しなかったが、これまでの経済政策を検証し、改めるべきは改めることが、政策の選択肢を広げる第一歩ではないか。
「安倍一強」の定着とともに発覚した森友・加計両学園や「桜を見る会」を巡る問題ではいずれも安倍氏ら政権中枢に近い人物や団体の優遇が疑われ、公平・公正であるべき行政は大きく傷ついた。
側近議員や官僚による安倍氏らへの「忖度(そんたく)」が横行し、森友問題では財務省は公文書改ざんに手を染め、改ざんを指示された担当者が自死する事態にもなった。
桜を見る会前夜の夕食会を巡っては、安倍氏は国会で百回以上の虚偽答弁を繰り返した。日本の議会制民主主義の汚点でもある。
しかも、これらの問題はいずれも真相解明に至っていない。安倍氏が亡くなっても不問に付さず、解明に努めるのは国会の責任だ。
安倍氏を中心として、自民党議員と旧統一教会(世界平和統一家庭連合)との密接な関係も明らかになった。反社会的な活動をしていた団体が政権与党の政策決定に影響を与えていたのではないか、と有権者は疑念を抱いている。
この際、安倍氏や前派閥会長の細田博之衆院議長を含め、教団との関係やその影響を徹底調査することが、政治への信頼回復につながるのではないか。
◆憲法や国会を軽んじて
安倍内閣は、歴代政権が違憲としてきた「集団的自衛権の行使」を閣議決定で容認し、安全保障関連法の成立を強行した。時々の政権が国会での議論の積み重ねを軽視し、憲法を都合よく解釈する姿勢は、立憲主義を揺るがす。
岸田首相も歴代政権が否定してきた敵基地攻撃能力の保有に踏み切ろうとしている。憲法に基づく臨時国会の召集要求に応じない姿勢も、安倍氏と変わらない。
安倍氏は、街頭演説で抗議の声を上げた有権者に「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と言い放ったことがある。
世論が二分される中で行われた国葬は、国民を分断することで、賛否の分かれる政策を進めてきた安倍政治の象徴でもあろう。
ただ、こうした安倍政治は、国政選挙での度重なる自民党勝利の結果である。有権者の政治への諦めや無関心が低投票率となり、政権に驕(おご)りや緩みを許してきたとは言えないだろうか。安倍政治の検証は同時に、私たち主権者の振る舞いを自問することでもある。
(4)④【沖縄タイムス社説】[安倍氏の国葬]国会の検証が不可欠だ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1031973
2022年9月28日 06:56
安倍晋三元首相の国葬が、国内外から約4200人が参列して東京の日本武道館で営まれた。葬儀委員長の岸田文雄首相ら三権の長のほか、友人代表の菅義偉前首相が追悼の辞を述べた。
当初見込まれた最大6400人の参列者数からは大幅に減った。国葬を巡り世論の賛否が二分されたことなどが影響したとみられる。
海外からはハリス米副大統領、インドのモディ首相、オーストラリアのアルバニージー首相ら元職を含め50人近い首脳級が参列した。ただ、先進7カ国(G7)の首脳は結局一人も参列せず、政権が強調した「弔問外交」は期待したほどの成果は得られなかった。
国葬会場に程近く設けられた一般向け献花台には夕方まで多くの人たちが並んだ。
一方で、会場周辺では数千人規模の抗議集会も開かれ、国葬に賛成する市民と反対する市民との間では小競り合いもあった。
県内でも那覇市や沖縄市、宮古島市などで国葬に抗議する集会が行われた。集まった市民らは、安倍政権が民意を顧みず名護市辺野古の新基地建設を強行してきたことなどに触れ「沖縄を踏みつけてきたのが安倍元首相」などと反対の声を上げた。
国葬を巡って表面化したのは社会の対立と分断でもあった。
法的根拠が曖昧で、政府として国葬を執り行う説得力のある理由も示せなかった結果、共同通信が行った世論調査では、国葬への反対は約60%を占めた。
■ ■
安倍氏自身、銃撃事件の背景となった世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係が取り沙汰されたことも国葬への支持が揺らいだ一因だろう。自民党は旧統一教会と党所属国会議員との関係を巡り調査を行ったが、不徹底な上、安倍氏を調査対象から外したことで、岸田首相への不信感が高まった。
岸田首相は、国葬実施について国会に諮る時間は十分あったはずだが「行政権の判断」としてそうはしなかった。
安倍氏の国葬を行うとの判断を急いだ背景には、安倍氏を強く支持してきた保守派の存在があったとされる。
ただ、そうした政治的な判断で16億6千万円という多額の国費支出を伴う国葬に対し批判が集まったのは当然とも言える。
その結果、内閣支持率は政権発足後最低水準となっている。
■ ■
10月3日には臨時国会が召集される予定だ。
国会の場で国葬決定の経緯について検証する必要がある。岸田氏はなぜ安倍氏の国葬が必要だと判断したのか、自らの言葉で説明を尽くすべきだ。また、今後の国葬が政権の都合で行われたとみられないためにも、この国会でのルール作りは不可欠だ。
国葬を実施する対象や条件を明示し、事前に国会の承認を必要とするなど、プロセスを明示することが根拠の一つとなる。
国葬の「強行」が残した禍根に向き合わなければならない。
(5)⑤【琉球新報社説】反対大勢の国葬実施 決定過程の検証が必要だ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1591192.html
2022年9月28日 05:00
社説
mail_share
国民の約6割という根強い反対の中、安倍晋三元首相の国葬が執り行われた。法的根拠のほか、決定過程や財政支出の在り方を含め、疑問は拭えない。国葬の実施は憲法に抵触するとも指摘されてきた。
立憲主義や国民主権など、戦後の日本が追求してきた民主主義の理念にも反する。実施によって終わりということでは済まされない。政府は国会での審議はもちろん、後世の評価に向けて検証する場を設けるなど、実施の責任を全うする必要がある。
国葬の歴史に詳しい中央大の宮間純一教授は「国葬は大日本帝国の遺物。誰か一人を追悼して国としてのまとまりを高めようという思考は戦後日本の民主主義、自由主義とはなじまない」と指摘した。戦前の国葬が国民を戦争に動員する政治的意図に利用されてきた背景があるからだ。
実施については事前に国会には諮らず、閣議決定で押し切った。のちに国会に説明したが、基準や財政支出の是非については議論は不十分なままだ。
経費は運営や会場設営に約2億5千万円、警備、接遇費を含めると16億6千万円に上る。国民の代表である国会での十分な審議を経ずに税金を投入する。理解は得られていない。共同通信の全国世論調査は「反対」「どちらかといえば反対」が60.8%。長野県の信濃毎日新聞の県民調査は反対が68%、賛成16%。福島民報などの県民調査は反対66%に賛成21%だった。
財政負担以外にも表現の自由、内心の自由との整合はどうなるのか。この点も国会での論議は全く足りていない。
戦前は国葬について定めた勅令の「国葬令」があったが、戦後の憲法制定によって失効した。つまり、国葬の実施には法的根拠がない。
であるならば、実施に当たっては立法との関連を国会で審議するのが筋だが、その手順を踏まなかった。「国の儀式」は内閣府の所掌事務であることから、「新たな根拠法は必要ない」との論理だ。法に基づいて執行する立場の政府が、その根拠を必要ないとするのはあまりに無理がある。
事は国論を二分する重要問題だ。緊急性があったと思えないが、国会説明は後回しだった。立法府軽視の批判は免れず、立憲主義にも反する。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と政治、特に自民党との親和性が銃撃事件で問題化した。当初は個々人の問題としていたが、支持率低下などによって党は調査にようやく踏み切った。国葬実施には問題の幕引きの意図があるのではないかとの見方もあるが断じて許されない。
岸田文雄首相は国葬実施で「民主主義を守る決意を示す」と言ったが、その理念からはかけ離れている。民主主義に資するというのであれば、実施決定に至る経緯など全てを明らかにして検証する、それしか策はない。
-
(6)早い話が「こういう人達」
何のことはない。モリカケ桜に始まって、学術会議も統一教会ももう「ネタが古くなってきた」と見て、新たなネタが「安倍元首相国葬決定」って事、らしいや。法的根拠も決定の経緯も、既に十分に明らかなんだが、例によって例の如くの「疑惑ハサラニ深マッター」をやるつもりなんだろう。
だけどなぁ、こんどは一体、どんな「疑惑」なんだろうねぇ。どんな「決定過程」でも何らかのイチャモンをつけてやろう、って魂胆かな。モリカケ桜よりは「世論の反応が良い」と見て、アカ新聞どももバカ野党も「張り切っている」ってことか。
報道機関たるべきマスコミとしても、政治的主体たるべき野党としても、そんな「出来損ないスキャンダル追及による、現政権攻撃」ってのは、自殺自滅以外の何物でもないんだがな。
まあ良いさ。安倍元首相がいみじくも評した通りの、「こういう人達」である。そんな「こういう人達」であるが故に、益々「負けるわけにはいかない」よなぁ。
そうでしょう。安倍総理。