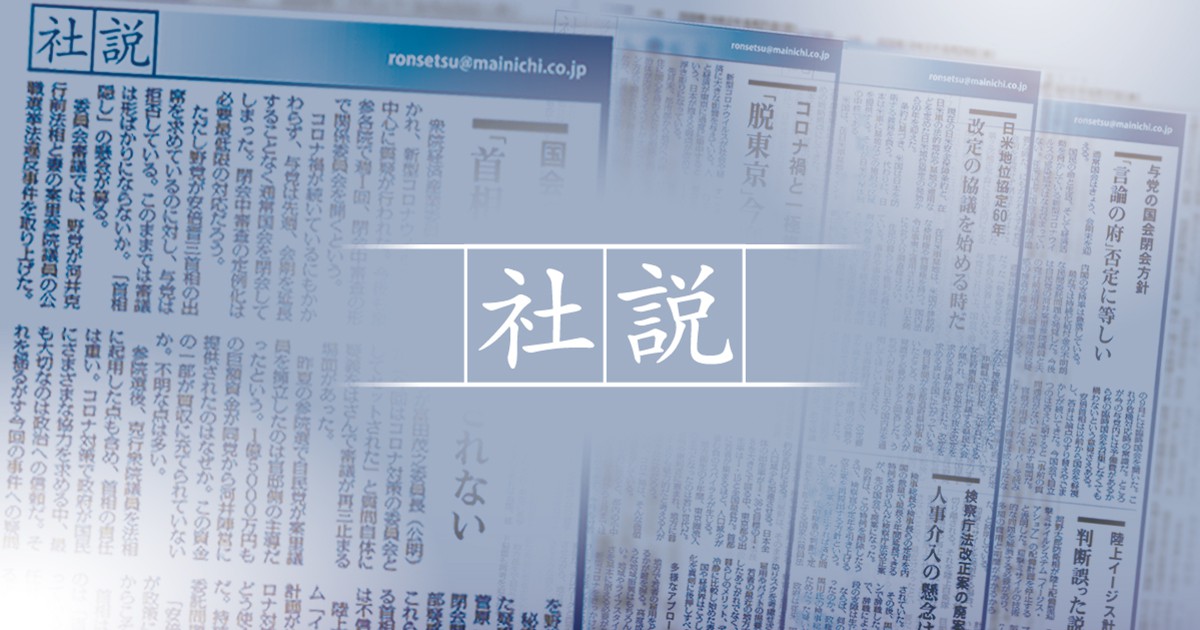-
防衛費、2%で、この騒ぎ。-「骨太の方針として、防衛費倍増示唆」に対する、アカ新聞社説の右往左往
何度か書いた覚えがあるが、「馬鹿が、馬鹿を晒しているのを見るのは、楽しいモノだ。」。今回は、日本政府の「骨太の方針(*1)」として「経済財政運営と改革の基本方針」が閣議決定され、この中で「(防衛費の)5年以内の強化」と明記の上、「北大西洋条約機構(NATO)諸国が国内総生産(GDP)比2%以上を目指している」とも明記された、と言うので、アカ新聞どもの社説がこんなことになって居る。
これ即ち、「馬鹿が、馬鹿を晒している」状態であり、実に「楽しいモノ」である。
①【朝日社説】骨太の方針 防衛費の膨張が心配だ
②【毎日社説】規律なき骨太方針 首相の姿がかすむ一方だ
③【東京社説】防衛費2%方針 「倍増ありき」の危うさ
⑤【琉球新報社説】「骨太方針」決定 防衛費増ありきは問題だ
④の沖縄タイムスは、該当する社説無し。
- <注記>
- (*1) この表記は、好かんのだがね。方針ってのは、方針であるが故に、「骨太である」のが本来にして王道。骨細でフラフラしたり、折れたりするのは、「方針」とは言わない。
(1)①【朝日社説】骨太の方針 防衛費の膨張が心配だ
①【朝日社説】骨太の方針 防衛費の膨張が心配だ
骨太の方針 防衛費の膨張が心配だ
https://www.asahi.com/articles/DA3S15318247.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年6月8日 5時00分
骨太の方針を決めた経済財政諮問会議・新しい資本主義実現会議合同会議で、発言する岸田文雄首相(左から2人目)=2022年6月7日午後5時41分、首相官邸、上田幸一撮影
【1】 防衛費をはじめとする歳出の拡大に歯止めがかからなくならないか。きのう閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)からは、こんな不安が拭えない。
【2】 骨太の方針は、翌年度の予算編成の大枠にあたり、政府の重点政策を挙げつつ、財政健全化に向けた考え方を示してきた。今回も「財政健全化の旗を下ろさず、これまでの目標に取り組む」と記し、国と地方の基礎的財政収支を25年度に黒字化する目標を維持した。
【3】 25年度には、団塊世代全員が75歳に達し、医療費などの公費負担が一段と膨らむ。それまでに、借金依存の財政運営から脱する意義は大きい。コロナ禍を経ても企業業績は堅調で、税収は増えている。目標を維持するのは当然の判断だ。
【4】 一方で、見過ごせない問題がある。目標達成の前提になる歳出抑制を形骸化させかねない表現が加わったことだ。
【5】 従来の骨太では、社会保障経費の伸びを高齢化による自然増の範囲内に、その他の経費は3年間で計1千億円の伸びに抑えるとしてきた。今回も、この方針自体は変えなかったが、決定前日の自民党との調整で「ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない」との文言が入った。抑制の例外を認めるかのような表現だ。
【6】 歳出を増やすべき「重要な政策」があるのは否定しない。ただ、その際はその分の財源を同時に議論すべきだ。歳出拡大だけを言うのでは「財政運営」の名に値しない。
【7】 とくに懸念するのは、安倍元首相らが国内総生産の2%以上にするよう求める防衛費の扱いだ。この「重要な政策」の一つとして念頭にあるとされる。
【8】 ロシアのウクライナ侵略が起きたなかで、あるべき防衛の姿を考えることは当然だ。ただ、適切な予算は、装備など必要な経費を積み上げて検討すべきで、「2%」のように総額ありきの議論は筋違いである。
【9】 安倍氏は「政府は日本銀行とともに、お札を刷ることができる」など財政規律を軽んじる発言も連発している。骨太が「防衛力を5年以内に抜本的に強化する」としながら財源には触れず、歳出の別扱いにする余地までつくったのは、安倍氏らに配慮したためだろう。
【10】 1947年施行の財政法は、赤字国債の発行を禁じている。野放図な借金が身の丈を超えた軍事予算の拡張を許し、悲惨な戦禍を招いた反省からだ。政府の借金は、すでに未曽有の規模に膨れあがっている。このうえ歯止めなき国債発行を続けて、際限のない軍拡競争を招くようなことは、あってはならない。
②【毎日社説】規律なき骨太方針 首相の姿がかすむ一方だ
https://mainichi.jp/articles/20220608/ddm/005/070/093000c
規律なき骨太方針 首相の姿がかすむ一方だ
毎日新聞 2022/6/8 東京朝刊 English version 876文字
【1】 防衛と財政は国の根幹をなす重要政策だ。岸田文雄首相が自らの考えを明確に示さないまま、方向が決まっていく流れは危うい。
【2】 岸田政権で初めての「骨太の方針」が閣議決定された。
【3】 ウクライナ危機で増額論が浮上した防衛費では、原案になかった「5年以内の強化」を打ち出した。「北大西洋条約機構(NATO)諸国が国内総生産(GDP)比2%以上を目指している」との記述も注釈から本文に格上げした。
【4】 これまでGDP比1%程度にとどまっていた防衛費を5年以内に倍増させたい思惑がうかがえる。原案の提示後、安倍晋三元首相らの主張に押される形で修正した。
【5】 安全保障環境の変化に応じた防衛力の整備を検討するのは必要だろう。ただ数値ありきではなく、専守防衛との整合性などを丁寧に議論していくことが欠かせない。「骨太」がなし崩し的な増額にお墨付きを与えるようでは問題だ。
【6】 財政に関しても、健全化目標の時期が明記されなかった。
【7】 政府は基礎的財政収支という指標を2025年度に黒字化する目標を掲げてきた。従来は「堅持」としていた表現を「これまでの目標に取り組む」と後退させた。財政規律が骨抜きにされかねない。
【8】 背景には、予算の大幅な拡大を求める積極財政派の安倍氏らの動きがある。防衛費を増やしても国債で賄えばいいと唱えている。
【9】 国と地方の借金は計1200兆円規模と危機的状況にある。高齢化が進む中、将来世代へのつけを膨らませるのは無責任だ。
【10】 本来、首相のビジョンが問われる大事な局面である。にもかかわらず指導力を発揮していない。
【11】 防衛費については「相当な増額を確保する決意」をバイデン米大統領に伝えた。だが国民には財源も含めて詳しく説明していない。
【12】 財政でも以前は健全化を訴えていたが、「骨太」策定では、積極派の主張を大幅に受け入れた。
【13】 看板政策に掲げる「新しい資本主義」も、アベノミクスと代わり映えしない内容になった。存在感はかすむ一方である。
【14】 参院選を前に最大派閥を率いる安倍氏の影響力を意識しているのならば、あまりに内向きだ。どのような国家を目指すのかを国民に明示する必要がある。
(3)③【東京社説】防衛費2%方針 「倍増ありき」の危うさ
③【東京社説】防衛費2%方針 「倍増ありき」の危うさ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/182243?rct=editorial
防衛費2%方針 「倍増ありき」の危うさ
2022年6月8日 08時02分
【1】 政府が経済財政運営の指針「骨太の方針」を閣議決定し、防衛力を五年以内に抜本的に強化する方針を明記した。防衛費を国内総生産(GDP)比2%程度に増額することを念頭に置いたもので、現在の1%から「倍増ありき」の方針は、防衛力整備の歯止めを失う危うさをはらんでいる。
【2】 骨太の方針は防衛力強化の理由に、ロシアのウクライナ侵攻やインド太平洋地域での力による一方的な現状変更で安全保障環境が厳しさを増していることを挙げ、北大西洋条約機構(NATO)加盟国が国防費の目標としているGDP比2%以上を例示した。
【3】 二〇二二年度の防衛費は約五兆四千億円でGDP比は1%弱。これを2%に増やすと年五兆円以上が新たに必要になる。
【4】 岸田文雄首相は、防衛力強化について「国民の命や暮らしを守るには何が必要なのか、具体的に現実的に議論し、しっかり積み上げる」と数値目標の設定に慎重な見解を繰り返し示してきた。
【5】 骨太の方針に、積算ではなく、数値目標を盛り込んだのは、政権基盤を安定させるため、防衛費の大幅な増額を求めていた安倍晋三元首相に配慮したからだろう。
【6】 ただ防衛力の抜本的強化が何を意味するのか、必ずしも明確ではない。仮に防衛費を五年間で五兆円以上増やすことになれば、年間一兆円以上も積み増し続けることになる。明確な防衛戦略もなく、過剰あるいは不要な装備品を大量に買い込むことにならないか。
【7】 政府は、「国家安全保障戦略」「防衛計画の大綱(防衛大綱)」とともに、防衛装備調達の五カ年計画である「中期防衛力整備計画(中期防)」を年内に改定する方針で、防衛費倍増方針がどう反映されるか注視する必要がある。
【8】 防衛費増額の財源をどう手当てするのかも不透明だ。自民党内では国債を発行して充てるべきだとの意見が強いが、「戦時国債」発行で軍備拡張を推し進めた過去の過ちを繰り返すべきではない。
【9】 そもそも他国を防衛する義務がない日本の防衛費を、相互防衛義務を負うNATO加盟国と同列に扱う合理性はない。防衛費の増額は逆にアジア太平洋地域の安定を損なう要因になりかねない。
【10】 節度ある防衛力の整備に努めるのはもちろん、外交にも力を注ぐことこそが、国民の命と暮らしを守ることになるのではないか。
⑤【琉球新報社説】「骨太方針」決定 防衛費増ありきは問題だ
「骨太方針」決定 防衛費増ありきは問題だ
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1530428.html
2022年6月9日 05:00
社説
mail_share
【1】 岸田政権で初の経済財政運営の指針「骨太方針」が閣議決定された。だが、岸田文雄首相が目指す国家像とリーダーシップが見えない。
【2】 財源健全化が後退し、歳出増を伴う施策が並ぶ。特に防衛費は保守派の「圧力」で大幅増額を見込む内容に修正された。必要額を積み上げた結果ではなく最初から防衛費増額ありきは受け入れられない。軍事費を特別扱いした戦時中を想起させ、看過できない事態だ。
【3】 「骨太」の焦点だった財政健全化では安倍晋三元首相率いる自民党の積極財政派に配慮した。国と地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化を目指す時期を削除してしまった。さらに「政策の選択肢を狭めることがあってはならない」との文言を加えることで、歳出拡大の余地を残した。
【4】 歳出拡大の一例が防衛費である。政府原案は「防衛力を抜本的に強化」と表記していたが、最終的に大きく変更した。ロシアのウクライナ侵攻を機に増額論が高まり、原案になかった「5年以内の強化」を書き加えた。北大西洋条約機構(NATO)加盟国が目標とする、国内総生産(GDP)比2%以上という記載を、脚注から本文に格上げした。
【5】 防衛費の上限をGDP比1%にとどめた1976年の閣議決定を覆す思惑があるのだろう。安倍氏ら保守派の圧力に屈したと言われても仕方あるまい。
【6】 GDP比を2%に倍増すると5兆円規模の予算が必要になる。どこに財源があるのか。今回の「骨太」は財源を明らかにせず、無責任のそしりを免れない。
【7】 国家の借金に当たる「国債残高」は2021年度末で1千兆円を突破した。それでも安倍氏は「防衛費確保のための国債発行」を訴えている。その国債を「政府の子会社」(安倍氏)と位置付ける日銀に購入させるのだろうか。
【8】 既視感がある。日中戦争と太平洋戦争の戦費は戦時国債で調達した。国民に国債を無理矢理買わせ、足りない分は日銀が直接引き受けた。調達した資金は臨時軍事費特別会計に組み込まれ、敗戦まで帝国議会に報告されることはなかった。軍にとって都合のいい財布だ。戦時国債は敗戦によって紙くずになった。
【9】 5兆円あれば、大学の授業料や小中学校の給食費を無償化できる。1人当たり年金の支給額を増やすことも、消費税を現行10%から8%に引き下げることも可能だ。
【10】 一方、「骨太」は「強い沖縄経済」の実現を掲げ、沖縄振興策を「国家戦略として総合的・積極的に推進する」と明記した。
【11】 だが、沖縄経済の最大の阻害要因である基地の負担軽減に触れなければ画餅に終わってしまう。名護市辺野古の新基地建設や防衛費増額の先に、沖縄が再び戦場になる危険性が高まる。県民の命と暮らしを守らない「骨太」では困る。
-
抽出 アカ新聞各紙が「防衛費増額に反対する理由」
<理由1> 「倍増ありき」だから。①【8】③見出し【1】⑤見出し
<理由2> 歳出の拡大に歯止めが利かなくなるから。①【1】【4】②【7】
<理由3> 歳出拡大には財源論が必要だから。/赤字国債を財源とする案があるから。②【13】③【8】⑤【6】【7】
<理由4> 1947年発行の財政法は、赤字国債を禁じているから。①【10】
<理由5> 際限のない軍拡競争を招きかねないから。①【10】
<理由6> 「専守防衛」との整合性を議論すべきだから。②【5】
<理由7> 財政規律が骨抜きになりかねないから。②【7】【9】
<理由8> 岸田首相の強い指導力が見られないから。/安倍元首相の強い影響が見られるから。②【13】【14】③【5】⑤【5】
<理由9> 過剰・不要な装備を買う恐れがあるから。③【6】
<理由10> NATOは相互防衛義務があるが、日本は専守防衛だから。③【9】
<理由11> 軍事費を特別扱いした戦時中を想起させるから。⑤【2】【8】
<理由12> 防衛費増額分の予算は、他のことに使えるから。⑤【9】
-
<理由2> 歳出の拡大に歯止めが利かなくなるから。
-
<理由3> 歳出拡大には財源論が必要だから。/赤字国債を財源とする案があるから。
-
<理由4> 1947年発行の財政法は、赤字国債を禁じているから。
-
<理由7> 財政規律が骨抜きになりかねないから。
この4つの理由は、「財政的理由」と括ることが出来よう。平たい話が、「金がないから、防衛費増額反対。」という主張。
国の予算である以上、財政に関わることは不可避で在り、予算増額なのだから財政悪化/赤字化の方向であることも不可避だろう。これは、全ての予算増額について言えることで在り、防衛費増額とて例外ではない。
だが、「財政悪化/赤字化を許容するレベル」は、予算増額の種類によって大いに異なろう。で、防衛費増額ってのは、我が国の安全保障に直結した予算増額で在り、我が国の危急存亡にさえ関わることがある予算増額である。従って、防衛予算増額の「財政悪化/赤字化を許容するレベル」は、高い。多分、国家としての最高レベルであり、「ちょっとやそっと国が傾くぐらいの財政悪化/赤字化は、許容されるべきレベル」ともなり得る。「赤字国債を発行して財源に充てる」ことも、「財政規律の例外とする」ことも、政治判断として十分ありうることだ。
無論、その「赤字国債を発行して財源に充てる」「財政規律の例外とする」等の議論をし、判断し、決断を下す事は大変重要であり、それこそ正に「国会に於ける予算審議の真骨頂にして存在意義」である。が、「赤字国債発行禁止」や「財政規律」を理由に「防衛予算増額の議論も国会審議も許さない」と言うのは、本末転倒とは言わぬまでも、「角を矯めて牛を殺す」暴論ではあろう。
アカ新聞各紙が上記4つの「財政的理油」で「防衛予算増額に反対する」のには、(珍しく)相応に理がある。だが、「増額される防衛予算を含めて、予算は国会の審議を経て成立・執行される。」のであるから、その過程で「財政的理由による防衛費増額反対」を議論すれば、済む話。「政府の予算案の段階での、防衛予算増額」に反対できる理由ではない。
-
<理由12> 防衛費増額分の予算は、他のことに使えるから。
この<理由12>は、「財政的理由=金がないから防衛費増額反対」に準じたモノであり、「防衛費増額する金があるなら、他へ廻せ。」という主張。言い替えれば、「予算配分として、防衛費増額よりも優先すべきモノがある。」って主張だ。
これまた、「一見尤もらしい主張」であるが、同時に「大抵の予算増額反対に利用・活用できる主張」でもある。それだけに、「それだけでは、説得力に欠ける」理由でもあろう。ああ、「防衛予算増額=悪」と短絡思考して考える安保白痴の平和ボケは、この限りではないか。
上記<理由12>を掲げる琉球新報は、その安保白痴・平和ボケと表裏一対の軍事忌避・軍人差別で「一部では有名」であるが、
⑤1> 5兆円あれば、大学の授業料や小中学校の給食費を無償化できる。
⑤2> 1人当たり年金の支給額を増やすことも、
⑤3> 消費税を現行の10%から8%に引き下げることも可能だ。
として、「授業料/給食無償化」「年金増額」「消費税減税」を「防衛費増額より優先すべき予算」として挙げている。多分、俗耳に入りやすく、一般受けしそうな項目を選んだのだろう。
だが、私(ZERO)に言わせるならば、「矢っ張り安保白痴の平和ボケ」である。
防衛費が直結しているのは、我が国の安全保障だ。安全保障政策に失敗すれば、国が滅びることだってある。国が滅びたら、少なくとも「授業料/給食費無償化」も「年金増額」も、意味を成さない(*1)。
従って、防衛費増額の可否は、先ず(琉球新報が忌避し、差別し、それ故に大いに不得意としている)安全保障上の観点から論じるべきであり、「授業料/給食費無償化」「年金増額」「消費税減税」等と同列において予算の正否を論じるのは、良く言っても大衆迎合論。普通に考えれば「亡国に至る可能性さえある暴論」であろう。
尤も、「日本の亡国」こそ正に、琉球新報の目的である可能性は、相当に高そうだが。
- <注記>
- (*1) ああ、「消費税減額」も「意味を成さない」が、「消費税そのものを徴税されなくなる」可能性があるので、「減税ではなくなる(そもそも、税金を取られなくなる)」可能性がある。
-
<理由9> 過剰・不要な装備を買う恐れがあるから。
この<理由9>も「財政的理由=金がないから防衛費増額反対」に準じたモノと言えそうではある。言えそうではあるが・・・ナンとも情けない理由であろう。「防衛予算を要求する防衛省や自衛隊も、防衛予算を審議する国会も、随分と舐められ、馬鹿にされたモンだ。」と言うところ。要は、「防衛予算を増額すると、無駄遣いするから、反対。」って主張だ。
「自衛隊、防衛省、国会を、ガキ扱いした」反対理由である。少なくとも「国会軽視」と非難されて然るべき反対理由であろう(*1)。
この<理由9>も、前述の「財政的理由」と同様に、「買い込む装備品の過剰・不要は、国会での予算審議を通じて議論すれば済む話」であり、「政府の予算案において、防衛予算を増額する」ことに反対できる反対理由ではない。
あ、「今の野党が無能で少数で、国会の予算審議で真面な議論が出来ない。」のは、無能な野党と、少数しか選出しない有権者の責任であり、「国会の予算審議を軽視する理由」にはならないぞ。
- <注記>
- (*1) 防衛省や自衛隊は、軽視されても、それだけでは罪にならない。多分。
-
<理由5> 際限のない軍拡競争を招きかねないから。
-
<理由6> 「専守防衛」との整合性を議論すべきだから。
-
<理由10> NATOは相互防衛義務があるが、日本は専守防衛だから。
この三つの「防衛費増額反対理由」は、「政治的理由」と分類出来そうだ。左様分類は出来るが・・・揃いも揃って屁理屈ばかりだな。
先ず<理由10>は、今回「防衛費倍増方針」のベースとなった「NATO加盟国はGDP比2%以上の国防費が目標である」のに対する「NATOと我が国では条件が違う」って主張であり、それを「相互防衛義務のNATOと、専守防衛の日本」で対比させているのだが・・・実に好都合な点だけに絞った対比だな。
NATOが対峙しなければならないのは、ロシア一国だ。これに対し我が国は、中国とロシア、北朝鮮と、対峙しなければならない国が(少なくとも)3つある。「相互防衛義務のNATOと、専守防衛の日本」と言う対比だけでは、「条件の違い」が、判る訳がない。
かてて加えて、「専守防衛の方が、防衛費は安く上がる。」と言うのは、かなりの程度思い込みだ。「攻撃的兵器を保有しなくて良い」点では「安く上がる」様に思えるが、弾道ミサイルと弾道ミサイル防衛では、弾道ミサイル防衛の方が技術的にも高度で、値段も高い。少なくとも弾道ミサイルについては「専守防衛よりも、大量報復戦略の方が、安く付く」ことは、ありうるのだ。
更には、上記<理由6>とも関わって来るが、防衛予算は先ず第一に我が国の安全保障、我が国の主権・領土領空領海及び我が国民の生命財産を如何に守るか、と言う視点で議論されるべきであり、「専守防衛」だろうがナンだろうが(*1)、「我が国の安全保障上、有害」と判定されれば、「従来の方針を改め、専守防衛を止めるべき」なのである。
言い替えれば、優先すべきは我が国の安全保障であり、その為の防衛費増額である。その防衛費増額が「専守防衛と整合しない」ならば、「専守防衛方針を改める」だけの話。従って、上記<理由6>「「専守防衛」との整合性を議論すべきだから、防衛費増額反対。」ってのは、矢っ張り「角を矯めて牛を殺す暴論」・・・と言うよりは、これこそ正に「本末転倒」と評すべきだな。
「専守防衛との整合性を議論する。」のは良いさ。だが、我が国の安全保障上必要となった防衛費増額を「従来方針である専守防衛と整合しない」として否決するならば、それは「本末転倒」というモノ。専守防衛は従来従前の我が国の防衛方針ではあるが、それは我が国の安全安泰に資する、少なくとも「邪魔にならない」範囲であるべき、だろう。
上記<理由5>は「際限のない軍拡競争を招きかねないから、防衛予算増額反対。」な訳だが・・・ある種の敗北主義だな。
「軍拡競争」。結構ではないか。「軍拡競争にすら至らない、軍拡不戦敗」よりは、余程良い。
大体、我が国が対峙すべき核大国の片割れである中国は、もう20年以上も軍事費二桁爆増を続けて来たのだから、我が国の「軍拡競争参戦」は、遅いと言うことはあっても早いと言うことは無い。
言い替えるならば、我が国は覚悟を持って、「対中国軍拡に参戦すべき」なのである。またそれは、対ロシアでも対北朝鮮でも有効であろう。
- <注記>
- (*1) この「ナンだろうが」には、大抵のことが入る。何しろ、我が国の危急存亡に関わるのだから、「非核三原則」だろうが「平和主義」だろうが「日本国憲法」だろうが、存否を含む議論の対象から、外すべきではない。
-
<理由8> 岸田首相の強い指導力が見られないから。/安倍元首相の強い影響が見られるから。
・・・今回上掲アカ新聞社説から抽出した「防衛予算増額反対理由」の内、ほとほと呆れ果てたのが、この<理由8>である。「岸田首相の強い指導力が見られない。」なぁんて一見尤もらしい「反対理由」を挙げているが、「安倍元首相が防衛費増額を主張しているのだから、岸田現首相は(当然)これに反対すべきだ。」って主張だか思想だか信仰だかが背景にあっての、この<理由8>であり、「防衛費増額も、アベガワルイ。」と言う「アベガー理論」の発露・発現である、らしい。
そりゃ安倍政権は長期政権で、安倍晋三氏は近年希に見るほど長いこと首相の座にあり、その「安倍首相在任時代」を通じてバカ野党とアホマスコミは「アベガー!アベガー!!」吠えていたんだけどさ。習い性となって「アベガー」しか出来なくなったのではないか?そりゃ、言論人としても、政治家としても、自滅だろう。
念のために書いておこう。今般の防衛費増額は、防衛費増額として議論すべきであり、その背後に「黒幕」安倍元首相が居ようが居まいが、岸田現首相の指導力が見えようが見えまいが、「防衛費増額」とはナンの関係もない。
従って、上記<理由8>は、「防衛費増額に反対する理由」として不当であり、議論するに値しない。
-
<理由11> 軍事費を特別扱いした戦時中を想起させるから。
これもヒドいよなぁ。此処で言う「戦時中」とは、先の大戦=大東亜戦争の事を指す。第2次世界大戦という押しも押されもしない総力戦の真っ只中の交戦国で「軍事費を特別扱い」しなかった国なんぞ、あるモノかよ。アメリカ合衆国は「第2次大戦直後には、世界のGDPの過半を占めた」ぐらいの「無慈悲なまでの工業力」を誇ったが、そのアメリカ合衆国でさえ第2次大戦下では「軍事費を特別扱いした」事は間違いない。
言い替えれば、少なくとも総力戦の「戦時中」に「軍事費を特別扱い」するのは、当たり前。非難するには当たらない。
で、今回の防衛費増額は、「GDP比2%」でしかない。従来従前の我が国防衛費と比べれば「増額ではある」が、「GDP比2%」は「NATO諸国の国防費目標値」でもある。「グローバルスタンダード」とは言わないまでも、先ず「常識的な線」であり、「特別扱い」と言うさえ憚られ様。(むしろ、GDP比1%と言う従来の我が国防衛費こそ、逆の意味で、「特別扱い」である。)
況んや、総力戦たる大東亜戦争下の「軍事費の特別扱い」を「想起させる」として同一視してみせるとは、イチャモンとは言われないかも知れないが、「印象操作」ではあろう。
以上から、上記<理由11>は、「琉球新報社説担当記者の感想」ではあろうが、それだけであり、「防衛費増額反対理由としては、不当である。」。
-
<理由1> 「倍増ありき」だから。
でまあ、上掲アカ新聞社説の見出しにもなっているのが、この<理由1>なんだが・・・・
-
「1%ありき」と、何が違う?
「忘れた」とは言わせないぞ。我が国の防衛費ってのは随分と長いこと「1%ありき」だったんだ。それも、大した根拠もないままに、だ。余りにも「1%ありき」なモノだから、「GDPは、防衛費の100倍とする!」ってブラックジョークが(極一部には)あったぐらいだ。
それでも、「人事院勧告に従って給与を上げたら、防衛費が1%を越えてしまったぁぁ!軍国主義化だぁぁぁっ!!!」とアカ新聞らが騒いでいた一頃に比べると「年度当初予算で1%の枠に入っていれば。補正予算追加での1%突破は、可」ぐらいまで「防衛費のGDP比1%枠」の適用は緩和された様だが、「1%ありき」は残り続けた。
今度の「骨太の方針」で「防衛費2%の枠」が示されているが、これには「NATO諸国の国防費目標値」という、なかなか説得力ある「指標」が付いている。これに対し前述の通り(<理由10>)東京新聞は「NATOと我が国の相違」を「防衛費増額反対理由」に挙げている訳だが、「防衛費増額の原案としての、NATO加盟国目標値並みのGDP比2%」と設定し、議論を始めることに、なんの問題があろうか。
「防衛費の総額ではなく、中味を議論すべきだ。」と言うならば、それこそ正に、国会に於ける防衛予算審議の意味と意義である。
「防衛費の総額を決めるとはケシカラン!」と主張する輩には、従来従前の「1%枠」を、しっかりキッチリ、説明して貰おうではないか。
以上を以て、アカ新聞各紙の「防衛費増額反対理由」は、殆ど議論するに値しない、と言える。QED。