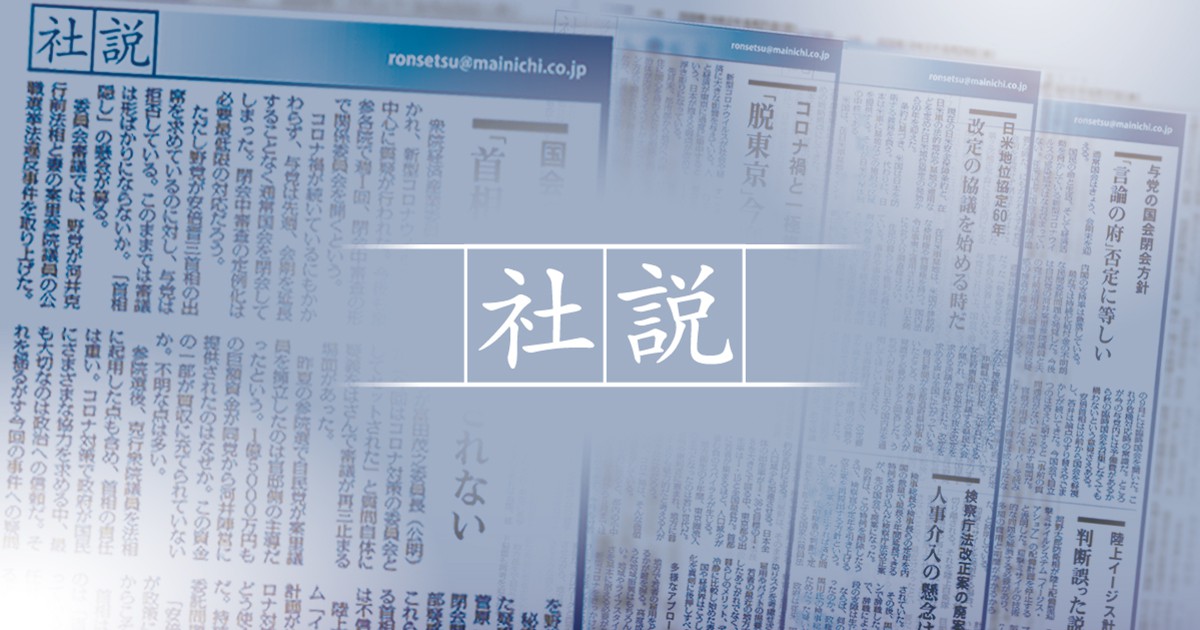-
銃は、自らの手にあるべきだ。ー【朝日社説】銃社会の米国 人命を守る民主主義を 他、アカ新聞各紙の「銃規制を訴える社説」に欠けている視点
タイトルにした「銃は、自らの手にあるべきだ。」と言うのは、フランスの大統領(当時)であったシャルル・ド・ゴールの決め科白である「剣は、自らの手にあるべきだ。」を捩ったモノ。「銃」と「剣」の違いはあるが、何れも「武器である」と言う点は共通しており、何れも「武力の象徴」である。ド・ゴールはこの決め科白で以て「フランス独自の核武装」を表明しており、ド・ゴールの言う「剣」とは、「独自の核兵器の象徴」である。
で、だ。「フランスの国家としての独自核武装路線」と、「アメリカ人としての自己防衛Self Deffence意識」とを、全く同列に置くのは無理があるが、相通じるモノは在ろう。「アメリカ人としての自己防衛Self Deffence意識」と言う、ある意味「アメリカの伝統と歴史」を無視して「アメリカでの銃規制」を主張したって、ほぼ無意味無反響無影響、だと思うんだがなぁ。
①【朝日社説】銃社会の米国 人命を守る民主主義を
②【毎日社説】米国の小学校乱射事件 いつまで悲劇が続くのか
③【東京社説】米国の銃犯罪 なぜ規制に踏み出さぬ
☆
①【朝日社説】銃社会の米国 人命を守る民主主義を
銃社会の米国 人命を守る民主主義を
https://www.asahi.com/articles/DA3S15306582.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年5月27日 5時00分
シェア
ツイート
list
ブックマーク
0
メール
印刷
写真・図版
乱射事件が起きた米テキサス州ユバルディの小学校の前で25日、肩を組んで寄り添う人びと=ロイター
[PR]
安全な学びの空間であるべき教室が、銃による殺戮(さつりく)の場となる惨劇がまた米国で起きた。
テキサス州の小学校で男が銃を乱射し、児童19人と教員2人が死亡した。容疑者は地元に住む18歳で、教室に1時間近く立てこもり、警官に射殺されるまで凶行に及んだという。
大勢が犠牲になる乱射はこれまでも繰り返されてきた。大きく報じられずとも、銃が絡む事件は各地の教育現場で「日常」となっている現実がある。
「うんざりだ」。バイデン大統領はそう嘆く。怒りを共有する米国人は少なくないだろう。だが、それは子の命を守れない政治の無策にも向けられていることを忘れてはならない。
背景には、人口を上回る4億の銃が社会にあふれる実態がある。しかもテキサスなど多くの州で、戦場で用いられるような銃が厳格な審査もなく販売されている。
今回の男も殺傷力の高い銃を合法的に購入したという。18歳の若者がなぜ単独で購入できたか。取引でどんなやりとりがあったのか。疑問は尽きない。
たしかに合衆国憲法は、市民が武装して自衛する権利を規定している。しかし、それは独立と自由を勝ち取った建国後まもない当時の理念にもとづくもので、善良な市民への攻撃が許されるはずもない。
今までも乱射事件のたびに購入審査の厳格化や高性能銃の販売規制などを求める世論が盛り上がった。だが、何を守るべきかという冷静な議論を欠いたまま、銃規制の是非ばかりが争点となり、有効な解決策は置き去りにされてきた。
さらに懸念されるのは、自分と異なるアイデンティティーや信条を持つ相手を敵と見なす風潮が近年の米国で強まっていることだ。アジア系など特定人種への憎悪犯罪が横行し、妊娠中絶問題など価値観をめぐる問題で市民同士がいがみあう。
銃が蔓延(まんえん)する社会に、非寛容が広がる恐ろしさが浮き彫りになる事件も多い。最近、ニューヨーク州の食料品店で白人至上主義を標榜(ひょうぼう)する若者が起こした乱射事件では、死傷者のほとんどが黒人だった。
格差の拡大や価値観の多様化など分断の原因は複雑だ。しかし、意見や立場の違いを超えて共存をめざすどころか、対立をあおることで支持を固める手段と堕した今の政治のありようこそ、改める必要がある。
米国は民主体制の利を世界に説くのであれば、足元の民主主義も見つめ直すべきだろう。理不尽な暴力におびえずに学べる社会をどう築くか。違いを超えて知恵を絞り合う協働を、その第一歩としてほしい。
-
「自らの手にある銃が、民主主義を守る。」革命権とは、そう言う事だろう。
「差別主義者や犯罪者の手にある銃が、民主主義を脅かす。」ならば、尚のこと。「自らの手にある銃が、自らの命と民主主義を守る。」と考えるのが、多分「伝統的・保守的(ひょっとすると、相当に一般的)なアメリカ人」であろう。
アメリカに住んだことも無く、実は行ったことすら無い私(ZERO)が、アメリカ及びアメリカ人について斯様に断定断言できる/してしまうのは、私(ZERO)が「随分昔から西部劇ファン」で在り、「西部劇を通じてアメリカ及びアメリカ人を(相応に)理解している(と思っている)」から。そりゃ、西部劇なんてジャンルの映画は、本家本元であるアメリカですら絶滅危惧種状態であるし、そんな「過去のフィクションエンタテイメント」が21世紀のアメリカ及びアメリカ人にどれ程影響しているかは、大いに疑義の余地がありうるが、事「銃社会アメリカ」と「アメリカにおける銃規制(が、全くと言って良いほど普及しないこと)」に関する限りは、「西部劇に見られるアメリカ及びアメリカ人のメンタリティ」と言うのは、大いに参考になる、と思えてならない。
無論、西部劇というのは精々が「史実をベースにしたフィクション」で在り、「史実をベースにすらしていない西部劇(*1)」もあれば、「ベースとした史実からしてかなり怪しい西部劇(*2)」もある。
だが、肝腎なことは、「西部劇がどの程度フィクションで、どの程度史実に基づいているか。」ではないだろう。恐らくは、「史実をベースにした」が故の「西部開拓時代」というある種の「建国神話」であるのが西部劇で在り、極言すれば「魂の故郷」とも言い得よう。
その「アメリカ人の魂の故郷」とも言い得る(多分)西部劇の本質の一つは、「力による正義の肯定」で在り、更には、「正義を裏付ける力が、政府や他人では無く、自らの手にあること。」であると、私(ZERO)は理解している。クリント・イーストウッド演じるハリー・キャラハン刑事が「ダーティー・ハリー」シリーズで最後にモノを言わせるのは大型回転式拳銃スミス&ウエッソンM29 44マグナム(と、その後継者達)であるし、チャールズ・ブロンソン演じるポール・カージーがDeath Wishシリーズにて正義を執行するのは、「靴下に小銭を詰めた棍棒・ブラックジャック」から徐々にエスカレート・大型化・大威力化していく銃火器だ。ダーティー・ハリーシリーズやDeath Wishシリーズは、西部劇ではないが、「力による正義の肯定」という点では「西部劇の末裔」と言えよう。
①1> たしかに合衆国憲法は、市民が武装して自衛する権利を規定している。
①2> しかし、それは独立と自由を勝ち取った建国後間もない当時の理念にもとづくもので、
①3> 善良な市民への攻撃が許されるはずもない。
等と、上掲朝日社説は主張するが、「その善良な市民が武装していれば、差別主義者や犯罪者も、そうおいそれとは手が出まい。」と言うのが、全米ライフル協会の主張であるし、「市民が武装して自衛する権利」の現代的意義でもある。おそらくは、相当部分のアメリカ人の意見でもあろう。
なればこそ、銃乱射事件が生起する度に、「銃規制を求める声」が一方で大きくなるモノの、他方で「銃の売れ行きが良くなる」と言う、「極めて冷徹な現実」がある。
- <注記>
- (*1) チャールズ・ブロンソン主演の「ホワイト・バッファロー」なんて、殆ど怪獣映画である。
- ブロンソンが演じるのは、実在の人物・バッファロー・ビルなんだけどね。
- (*2) ジョン・ウエイン主演・監督・制作の「アラモ」は、アメリカのテキサス併合の契機となった「アラモ砦の戦い」と言う史実をベースとしている。が、種々「史実とは異なる」事が知られている。
- 私(ZERO)の大好きな映画、なんだけどね。
②【毎日社説】米国の小学校乱射事件 いつまで悲劇が続くのか
米国の小学校乱射事件 いつまで悲劇が続くのか
https://mainichi.jp/articles/20220529/ddm/005/070/051000c
朝刊政治面
毎日新聞 2022/5/29 東京朝刊 843文字
米国の宿弊がまたも惨劇をもたらした。
南部テキサス州の小学校で、教室に立てこもった18歳の男が銃を乱射し、児童や教員ら20人以上を殺害した。
事前にソーシャルメディアで襲撃を予告していたという。国境警備隊に撃たれて死亡し、現場からは殺傷力の高い軍用の半自動小銃が見つかった。
ダンス好きの男の子やバスケットボールに熱中する女の子らの将来が瞬時に奪われ、児童を守ろうとした女性教師が犠牲となった。
10年前には26人が殺害される小学校乱射事件があった。なぜ悲劇は繰り返されるのか。
事件が起きるたびに銃規制強化を求める声が上がるが、遅々として進んでいない。背景には、米国社会の根深い対立がある。
合衆国憲法は市民に自衛のための武装を認めている。規制賛成派は、そうであっても戦場で使われるような銃は護身の範囲を超えており、制限すべきだと主張する。
規制反対派は、銃そのものは「悪」ではないと反論する。凶悪な犯罪者から身を守るための手段であり、種類によって制限を加えるべきではないという立場だ。
問題は、対立のはざまで政治が身動きできないでいることだ。
規制を支持する民主党は、銃購入者の身元調査を拡大し、厳格化する法案の可決を目指すが、見通しは立たない。
規制に反対する共和党が、再発防止の最善策は教職員に銃を持たせ、訓練を実施することだと主張し、妥協を拒んでいるからだ。
そもそも、大量殺傷を可能にする武器を10代の若者が合法的かつ容易に入手できることが、尋常ではない。その規制なしには悲劇が繰り返されるだけではないか。
衝撃は世界に広がっている。欧州諸国の政府首脳らは「ひどい話だ」「ぞっとする」と驚きの声をあげた。ロシアや中国は米社会の深まる分断を民主主義の衰退の表れと指摘している。
米国では人口を上回る4億丁の銃が流通する。銃問題は、「米国の常識」が世界には非常識に映る典型的な事例である。
人権尊重をいくら叫んでも、足元の人権侵害に無策のままでは、国際社会の信頼は得られまい。
③【東京社説】米国の銃犯罪 なぜ規制に踏み出さぬ
米国の銃犯罪 なぜ規制に踏み出さぬ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/180362?rct=editorial
2022年5月30日 07時35分
悲劇のたびに銃規制が叫ばれながら、いつの間にか立ち消えになる。そんな繰り返しは終わりにしなければならない。米南部テキサス州の小学校で起きた銃乱射事件。今度こそ米社会は再発防止へ踏み出すべきだ。
事件では十九人の児童に加え、児童を守ろうとした女性教師二人も犠牲になった。報道によると、その一人イルマ・ガルシアさん(48)は虫の息で児童を抱き締めているところを警官に発見された。
伴侶の死がショックだったのだろう。事件の二日後、ガルシアさんの夫も心臓発作で亡くなり、四人の子どもが残された。
犯人の十八歳の少年が所持していたのは殺傷能力の高い半自動小銃「AR15」である。二〇一七年にネバダ州ラスベガスで五十八人が死亡した史上最悪の銃乱射事件でも使われた。
バイデン大統領は「こんな銃を十八歳の少年が店頭で買えるなんて、間違っている」と述べたが、こうした殺傷能力の高い武器は全面的に禁止すべきである。
米国では総人口よりも多い四億丁の銃器が流通しているという。銃規制を目指す民間団体によると、年間で自殺を含めて四万人余が銃で命を落とす。
しかもコロナ禍が本格化した二〇二〇年、銃の販売数は二千万丁を超えて過去最多を記録した。コロナ禍による治安悪化への懸念が指摘されている。
米憲法修正第二条は「規律ある民兵は自由な国家の安全に必要であり、国民が武器を保有し携行する権利は、これを侵してはならない」として、自衛のための銃の所持を認めている。
銃規制反対派はこの憲法条項を盾にするが、警察機構が整備されていなかった建国当初とは時代が違う。
ロビー団体である全米ライフル協会の反対も壁になっている。政界に及ぼす影響力は強く、銃購入者の身元調査の厳格化といった規制の立法化は進まない。
バイデン氏は「こんな事件は世界のよその土地ではめったに起きない」と嘆いた。米社会はその異常ぶりを自覚する必要がある。
-
(4)> 警察機構が整備されていなかった建国当初とは時代が違う。 警察を解体しちまう様な地方都市があるのに、かね?
先述の通り、「銃乱射事件が生起する度に、銃の売れ行きが良くなる。」と言う極めて冷厳な事実がある一方、章題に挙げた通りマイアミ警察の様に「人種差別的行動で黒人容疑者を死に至らしめた」廉で「警察解体」なんて事態が起こりえる(*1)のが、現代アメリカである。
21世紀の今日、アメリカの警察機構が200年以上前の建国当初よりも(基本的に)整備されているのは事実だ。だがそれは、「市民自身の自己防衛を不要とする」には不十分な地域が相当部分である(と、推定できる)。更には、その「不十分な警察機構」さえ、(どうにも私(ZERO)なんそには理解不能な理由で(*2))「解体し、無くなってしまう」事がありうるのが、現代アメリカである。
「銃は、自らの手にあるべきだ。」と、ド・ゴール張りの考えに、現代アメリカ人が傾倒するのは、理の当然ではなかろうか。
アメリカ自身が、その歴史と伝統の上で、押しも押されもしない「実際に銃社会である」と言う冷厳たる事実もある。我が日本がアメリカとは対極にある様な「銃規制の厳しい、銃なき社会」であるから、想像しがたいのも無理なかろうが、「既に銃社会であるアメリカが、ちょっとやそっと銃規制したぐらいで、銃なき社会になる、訳が無い。」事も、先述の「西部劇を魂の故郷とする、市民防衛・自己防衛の伝統と現実」の他にも、考慮せねばなるまい。現存する銃の内、銃規制で規制できるのは、「合法的に登録されている銃」ばかりで在り、「非合法で未登録の銃」は、ほぼ規制されない。
以前にも書いたが、「米国を銃規制(*3)などで銃なき社会に近づけよう。」とするならば、一つには「市民が武装し自己防衛する必要がないだけの高い治安」を実現する必要があり、もう一つには「合衆国憲法に明記された武装権・革命権との整合・妥協」が必要だろう。
「革命は銃口から。」とは毛語録だが、「政府の不正を、武力で正す、革命権」は、「武装した市民」が前提となる。その「市民の武装」は、少なくとも警察、ひょっとすると軍隊に対抗出来なければならない。「政府の不正を武力で正す」のには、それほどの「武力」が必要であり、徒手空拳や刀槍では事足るまい。革命権そのものが、アメリカの建国理念、「イギリスの植民地から、武力革命で独立した」歴史に根差しているのだから、そうおいそれと「取り上げる」事も「弱体化する」事も、ままなるまい。相応の議論と何らかの妥協が必要だろう。
それでも、「革命権」の方は言ってみれば「覚悟一つ」で決まる話だ。より問題なのは「市民の自己防衛が不要な高い治安」の方であろう。先述の通り(章題にもしたとおり)「警察解体」なんて動きも(一部では)在るぐらいだから、「警察予算を増やし、警官を増員した」ぐらいで、即座に治安が高まる訳ではない・・・いや、正直なところ、アメリカで「市民の自己防衛が不要な高い治安」を実現したならば、その時の大統領は「合衆国史上最高の大統領」と言われることは間違いなさそうだが、それだけにこれは難事で、「一体どうすれば実現するか」私(ZERO)なんぞは途方に暮れるぐらい。
即ち、アメリカにおいて、「市民の自己防衛が不要な高い治安」は、(少なくとも)当面実現しない。
「銃なき社会に近づける」事を当面諦めれば、「革命権/武装権との妥協」や「市民の自己防衛不要な高い治安」は不要だろう。だがその場合、「現状とさして変わらない銃社会における銃規制」に止まる。その銃規制による「銃乱射事件防止効果」は、在るにはありそうだが、限定的なモノに止まるだろう。
一部には、「学校での銃乱射事件を防止するため、教師が武装すべきだ。」って論があるそうだ。一見暴論とも思える議論だが、「法的一律の銃規制」は「教師や生徒の非武装化の方向」でもあるのだから、「学校での銃乱射事件を、誘発ないし被害拡大する可能性」も、決して「頭ごなしに否定」すべきモノではあるまい。言い替えれば「教師武装化論」と言うのも、「相応に理がある」のである。
「銃乱射事件は悲惨だから、アメリカは銃規制しろ。」と主張するのは、一見尤もらしく、正義漢面も出来、「カッコ良い」主張でもあろう。だから、上掲アカ新聞ばかりか、産経新聞まで、似た様な社説を掲げている。
だが、「銃社会アメリカ」という冷厳な事実は、ちょっとやそっとの「銃規制」では「銃なき社会に近づく事すらない。」と言うことでも在る。また、先述の通り「合衆国憲法に明記され、建国理念にも深く関わる武装権/革命権」と「一般市民の武装無しには覚束ない治安」は、「銃なき社会に近づくことすら許容しがたい」という事実。言い替えれば、「銃社会を銃なき社会にすることは、絶対善ではない。」と言うこと。それらをすっ飛ばして、或いは無視して、「アメリカも銃規制を!」って主張は、かなり無責任だと思うぞ。
その無責任は、上掲アカ新聞ばかりではなく、産経新聞も、だけどな。
- <注記>
- (*1) 今回調べて見ると、マイアミ警察は何とか解体は免れた様だが・・・実際に警察解体に至ってしまった、事例も在る、と判明した。
- (*2) マイアミ警察が解体されそうになったのは「組織ぐるみの人種差別」を疑われたから、ナンだが・・・・仮にマイアミ警察が組織を挙げて人種差別をしていたとして、為すべき事はマイアミ警察改革では無いのか?新たに「新マイアミ警察」を立ち上げる、と言うのもあるかも知れないが、「警察解体」って選択肢は、どうにも理解しがたい。
- 「市民自身の自己防衛意識の究極的発露」と、理解すべき、なのだろうか。
- (*3) だけでは、無理だと思うが・・・国民意識の抜本的変更が必要だろう。
- その過程で「西部劇の流通・公開禁止」なんて事も、想像できてしまう。Death Wishシリーズなんぞも、ご禁制の品にされそうだな。