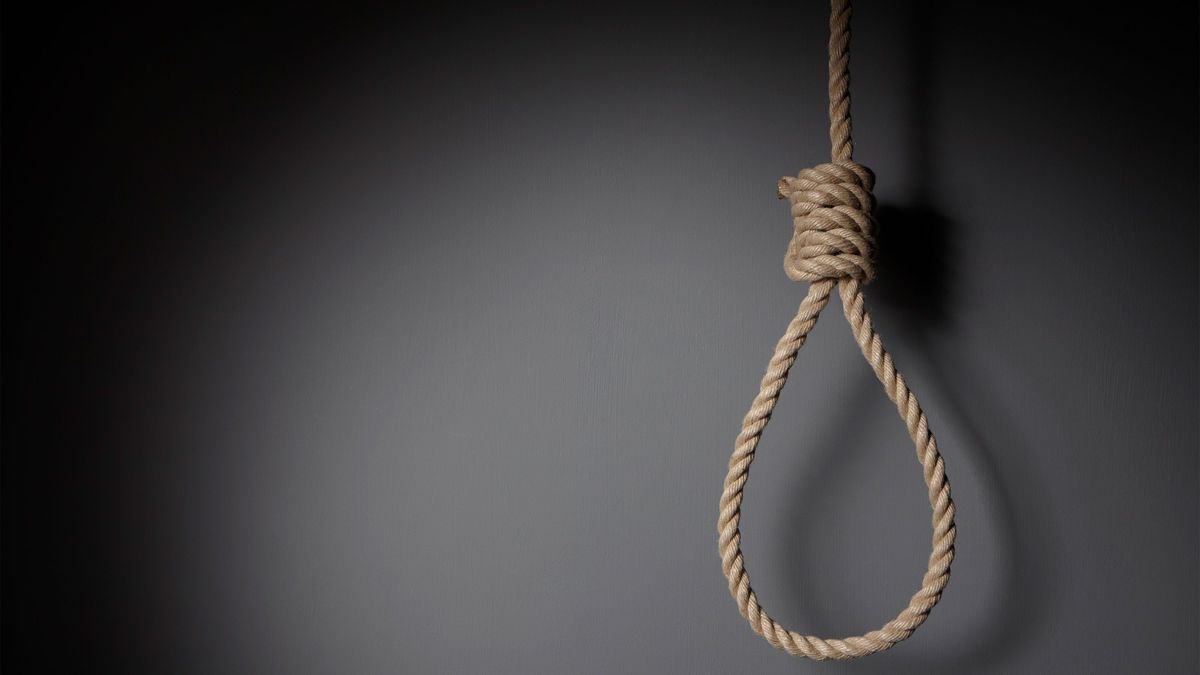-
「死刑制度を廃止して幸福になろう。」って、宗教だろう。-【プレジデント】殺人犯を死刑に処するのは当たり前・・・そんな考え方に幸福学者が「不幸になるだけ」と反論するワケ
弊ブログで幾つか記事にした通り(と言っても、大分前だと思うが・・・・)、私(ZERO)は我が国の死刑制度を「かなり積極的に肯定」している。「死刑制度廃止がEU加盟の条件だ。」とか、「死刑制度を廃止した国は増加している(って説は、かなり怪しいのだが・・・)」とか、聞いた/読んだ処で、「だから何?我が国が我が国の死刑制度を維持継続する上で、何の支障にもなるまい。」と答える。喩え、「我が国以外の全ての国が死刑制度を廃止した。」としても、それは「我が国が我が国の死刑制度を廃止する」理由には、少なくとも直接的には、なり得まい。「我が国が我が国の死刑制度を廃止する理由」が「外国では廃止しているから。」と言うのは、実に恥ずかしい限りのロジックであろう。
平安時代には我が国でも「死刑は実施されなかった」ってのも何処かで読んだが、だからと言って我が国が「平安時代の昔に戻って死刑を執行しなくなる」のが「正しい」とも「より良い」とも、全く思えない。
再三繰り返すとおり、「我が国の死刑制度の存廃」は、「死刑制度を存続させている日本」と、「死刑制度を廃止してしまった日本」と言う「二つの日本の未来像」の優劣良否で判定すべきで在り、「何人を如何に残虐に殺そうが、死刑になる事は無く、精々が終身刑で、生涯国に喰わして貰える(*1)」日本が、「ヘタすると死刑にされる可能性がある」日本よりも、「良い」とか「優れている」とか「より理想に近い」とか、全く思えない。「より人道的である」とは辛うじて評せるかも知れないが「それは、一面的な対死刑囚向きの人道的で在り、対被害者や、対社会と言う点では、逆に非人道的ではないか。」と反論/反駁したくなる。
「”万死に価する罪”というモノがあるのに、”一死もてすら償わず、償えない”等と言うことが、正しい訳が無い。」と、世界中に相応の数の「死刑制度廃止国」が在り、下掲記事にある「幸福学者」含めて我が国内にも相応の数の「死刑制度廃止論者」があることを承知の上で、私(ZERO)は主張するものである。
- <注記>
- (*1) 左様な国が、「死刑制度廃止国」として、現存しているのは承知しつつ。
【プレジデント】殺人犯を死刑に処するのは当たり前・・・そんな考え方に幸福学者が「不幸になるだけ」と反論するワケ
https://president.jp/articles/-/57782
https://president.jp/articles/-/57782?page=2
https://president.jp/articles/-/57782?page=3
https://president.jp/articles/-/57782?page=4
https://president.jp/articles/-/57782?page=5
いずれ死ぬ運命ならば、許し、罪を償わせたほうがいい
PRESIDENT BOOKS
前野 隆司
前野 隆司
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授
凶悪な殺人犯にはどんな刑罰を与えるべきなのか。慶應義塾大学の前野隆司教授は「人は死んだらなにも残らない。ならば、加害者を許し、罪を償わせるべきだ。報復手段としての死刑は、社会の平和につながらない」という――。
※本稿は、前野隆司『ディストピア禍の新・幸福論』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
絞首刑のロープのイメージ写真=iStock.com/xefstock※写真はイメージです
存続、廃止について答えが出ない死刑制度
誰もが最後は死ぬのなら、いま生きている期間は、いずれやってくる死を恐れながら監獄で待つのと大差ないのではないか。
誰だって、今日明日にも死ぬかもしれない。
わたしたちは、いつ死刑執行されるかもわからない毎日を暮らす虚むなしい存在なのではないか――。
死について考えるとき、関連する問題として、社会制度としての死刑の存在がある。
存続・廃止をめぐって世界中でいろいろな議論があり、日本でも世論が大きく分かれがちな問題、それが死刑制度だ。
死刑の最大の目的は「犯罪抑止」
死刑が求刑されるような事件のニュースに触れて、感情的に「許せない」と感じる人は多いと思う。卑劣な犯罪が行われ、なんの瑕疵かしもない被害者やその家族らの映像が出てくると、なおさら「犯人を早く死刑にしたほうがいい」「こんな人間は生きている価値がない」という感情を掻かき立てられる。
しかし現代法では、死刑は「目には目を、歯には歯を」という復讐ふくしゅうのために行うのではない。犯罪抑止効果を最大化するのが刑罰の最大の目的である。
だから、死刑が求刑されるような犯罪が起きたときに、テレビの視聴者が「死んで償ってほしい」「犯人を殺してやりたい」というのを聞くとき、わたしは人類全体に対するいたたまれない悲しみと虚しさを感じる。なぜなら、復讐心は怒りの連鎖を生むだけだからだ。
人間が生まれながらに持つふたつの本能
人間にはふたつの本能がある。それは、「怒り」と「共感」だ。人間は生き残るために、いわば「戦う本能」と「仲良くする本能」のふたつを維持してきた。
怒りの本能とは、自分に危害を加える者に対して怒り、戦い、もし仲間がやられたら復讐するモードのことを指す。
はるかむかしの人類を想像するとわかるだろう。凶暴な獣が目の前に現れたとき、戦わないとやられてしまう。だから、獣と戦う本能が人間には備わっている。
この本能は、現代においては「勝ちたい」という本能に転化される。子どもの頃も、大人になってからも、「他人に勝ちたい」と思う人は少なくないであろう。個人差はあるものの、力や暴力によって勝ちたいという本能のみならず、成績やスポーツで他人に勝ちたいという気持ちも人間には備わっている。社会を見ると、この戦う本能にドライブされて生きている人は多いように思われる。
一方、人間の脳には共感の本能も埋め込まれている。
目の前に現れたのが獣ではなく、もし人懐っこい犬だったらどうだろうか? 人間は犬とは仲良く暮らせることを学び、危害を加えたり憎んだりせずに済む。いや、場合によっては獰猛どうもうな獣とだってともに暮らすことができるはずだ。
ましてや相手が同じ人間なら、親が子どもを育てるときの本能のように、相手の気持ちになって共感したり、互いに労いたわり合ったりできるはずだ。
20万年前から人間は進化していない
話を戻すと、人間は被害者に共感することができるが、同時に加害者にも共感できる本能も持っている。
「この犯人は許せない」「この人間は心が歪んでいる」と憎むこともできれば、「未熟さゆえにこんな罪を犯したのだ」「親からの虐待や社会の激しい格差のなかで育ったから、こんなことをしてしまったのだ」と想像し、共感することもできる生き物なのである。
ほかの動物にこんなことは到底できない。
いま目の前に危機が迫っている場合は、まず「戦う本能」が発動するだろう。凶暴な敵がやってきたときに「仲良くしよう」と思っていると自分の身が危うくなるため、先に戦う本能が発動するからだ。本能と本能とのせめぎ合いでは、怒りや「許せない」という復讐の感情のほうが先に出るだろう。
そんな、自分を守るために相手を敵として憎む本能と、みんなと仲良くしてコミュニティを安心安全に保つ本能――。どちらが発動するかで結果はまるで違うものとなるし、まるで異なる社会になるというわけだ。
いずれにせよ、わたしたちが狩猟・採集生活をしていた頃の本能が、現代社会でも変わることなく働いていることは間違いない。いってみれば、わたしたちは20万年前から進化していないのだ。
人類の進化のイラスト写真=iStock.com/Man_Half-tube※写真はイメージです
だからといって、狩猟・採集時代の本能を、いまわたしたちは?むき出しにすべきだろうか?
「死」は誰にでも等しく訪れる
人間は死んだら終わりだ(いろいろな意見があるだろうが、少なくともいまの人生は終わりだ)。
それゆえに、子どもを殺された親が「犯人は死んで償ってほしい」というのを聞くたびに、わたしは憂鬱ゆううつな気持ちになる。復讐心を掻き立てられても、問題は解決しないのに。
もちろん、わたしも子を持つ親のひとりであり、親が子を思う気持ちの深さが想像できないわけではない。ただ、人は死んでしまえばなにもなくなる。
死んでしまえば、加害者が自らの罪に苦しみ、後悔と罪悪感に苛さいなまれながらその行為を償うことはできないではないか。苦しくもつらくも、なんともないではないか。死んだら罪を償うことは不可能なのだ。その意味では、死ぬまで自分が犯した罪とともにある無期懲役のほうが、まだ償いになるかもしれない。
死んだら、「無」。それが現実なのだ。
墓の上に白いバラを置く男性写真=iStock.com/PeopleImages※写真はイメージです
被害者が亡くなっても、その家族や友人たちは生き続ける。その短い人生を生きるなかで、犯人の存在を世界から消去してしまいたい気持ちもあるだろう。もちろん、わたしもその親の無念を想像することはできる。
しかし、いずれすべての人は、遅かれ早かれ消えてなくなる。だから、「生きていることは死刑と同じ」だと比喩として述べてきた。今度は本物の死刑について述べているわけだが、両者を比べてみても、同じようなものなのではないだろうか。
つまり、死刑になってこの世からいなくなるのと、人生という死刑を生きていつか死ぬのは、同じようなものではないか。死んだあとの永遠の無に比べると、そこにたいした差はない。
多くの国で「復讐」が禁止になった理由
現在、EUではすでに死刑制度を廃止している。理由はいろいろあるが、ひとつにはキリスト教の伝統が影響している。
キリスト教では、人間を裁くのは神である。法的には多種多様な罰が社会において用意されるものの、最終的には神が人間を裁くと考える。そのため、死刑制度によって人が人を裁くのは、おこがましい行為だという思想が根底にあるのだ。
また、仇あだ討ちはしないという合意もある。新約聖書には、「右の頬を打たれたら左の頬も差し出せ」と記されている。たとえ痛めつけられても、その報復を否定したイエス・キリストの言動が大きく影響しているのだ。
一方、日本では江戸時代まで復讐が許されていた。自分の家族が酷い目にあえば、その仇を討つのは当然のこととされていたのだ。世界を見渡せば、約3800年前の法典であるハンムラビ法典にも「目には目を、歯に歯を」と記されている。むかしは仇討ちが許されていたのだ。
だが近代以降、多くの国で復讐を禁止することが合意された。いまの日本人も、多くの人が「あの犯人は死刑にすべきだ」などと発言するものの、すでに報復行為はやめたことになっているのだ。
なぜだろうか?
それは家族の仇を討つために復讐すると、仇を討たれた者の家族が、その仇討ちを考えるからだ。
そうして、復讐が世代を超えて連鎖していくからである。復讐を認めたとたんに、わたしたちの世界は仇だらけの世界になってしまう。
言い分と報復だらけの世界に平和は訪れない
わたしは広島で育った。
子どもの頃から原爆や戦争の悲惨さについて、また平和を希求する大切さについて教えられてきた。
なぜ広島の人や長崎の人、ひいてはすべての日本人は、人類史上はじめて2発の原子爆弾を人間の上に投下したアメリカに報復しないのか?
それは、日本人は恒久の平和を求めると合意したからだ。
広島の原爆ドーム写真=iStock.com/clumpner※写真はイメージです
「原爆を落としたアメリカを、わたしたちは永遠に許さない!」といっていたら、子孫末代に至るまで報復が連鎖するだろう。自分たちも相手も、いつまでも平和には生きていけない。
さまざまな説があるが、多くのアメリカ人は、原爆投下はそもそも日本が真珠湾を奇襲したからだと考えている。だが、日本にも真珠湾を奇襲した理由があった。互いに譲れない理由と言い分があるのである。
ならば、そんな言い分と報復だらけの世界で、どうすれば人類は平和に生きていくことができるだろうか?
復讐はダメなのに死刑は存続する日本
答えは、相手を「許す」ことだ。
論理的に考えて、「相手を許したほうが平和な社会になる」から、わたしたちは報復を捨てたのである。日本では死刑制度が存続しているが、ほかの多くの社会では、被害者の仇を討つのではなく、加害者に罪を償わせるという考え方に変化している。
その「償い」とは、その人の存在を消去することではなく、「より良き人」に変えることだ。「犯人は心の異常によって酷い行為をしたので、刑務所で更生し、より良き人になったらまた世の中で生きていい」と考えるのだ。そうしたほうが、社会が平和で生産的な方向へ向かうからである。
だが、日本人の精神性には、いまだ仇討ち的な考え方が色濃く残っている。見かけは西洋の価値観を取り入れながら、内実はそうではないところに、日本社会の歪ひずみのひとつが現れているというべきかもしれない。
無意識の利他性とは逆の、無意識の残虐性である。
「死刑にしろ」という人に足りないもの
「許せない」気持ちはわかる。しかし、人間は学習し、「許す」ことができる。
前野隆司『ディストピア禍の新・幸福論』(プレジデント社)前野隆司『ディストピア禍の新・幸福論』(プレジデント社)
人間に埋め込まれたもうひとつの本能――「共感」をより重視しながら、仇討ちよりも調和の方向へと、人類は少しずつ進んできたのである。
わたしは後者の可能性を信じたいと思う。
いずれにせよ、立ち戻るべきは「死んだらなにもなくなる」という客観的事実である。報復しようが死刑にしようが、いずれわたしたちはみな、この世から消えてなくなる。
いずれ消えてなくなる命なら、なるべく早く憎しみと報復の連鎖を断ち切ったほうが、続く世代の人間は平和に生きられるのではないか。
本能に駆られて「死刑にしろ」と叫ぶ人は、死についての総合的・包括的な思索が不足していると考えられないだろうか。また、自分の生に対する総合的・包括的な思索も不十分というべきではないだろうか。
-
上掲記事の死刑廃止論は、つづめて言えば「幸福になり、平和な社会にするために、死刑制度を廃止しましょう。」な訳だが・・・
かなり前の方で触れている「死刑による犯罪防止」って観点は、モノの美事にその「死刑廃止論」からは抜けおちている。多分、「死刑制度による犯罪防止効果は、無い」とか言う説があって(斯様な説は確かに在り、幾度か読んだ/見た覚えがある。後述)、その説が上掲記事を書いた前野隆司氏の中では「常識で在り、前提となっている」のだろうと、推定する。
が、その「常識で在り、前提となっている」であろう「死刑制度による犯罪防止効果は、無い」って説からして、私(ZERO)には「サッパリ判らない(*1))」のである。幾つか簡単な説明は読んだのだが、「死刑制度の廃止前後で犯罪率が変わらなかった。」とか、「地理的にも隣国で、歴史的にも人口構成も類似した二国(確か、カナダとアメリカ)を比較して、死刑制度のある国(アメリカ)の方が、死刑制度の無いもう片方の国(カナダ)より犯罪率が高い。」とか言う説明だった。
前者について言えば「単年度の犯罪率は変動幅があるだろうし、数年平均ならば、その数年間の時間経過を無視し得まい。第一、"死刑制度のよる犯罪防止"効果は、死刑とされかねない重大犯罪にこそ利きそうであり、全体的な犯罪率に大した意味は無い。」と思える。後者については「隣国で、歴史的にも人口構成も似ていても、他国なのだから、何処まで比較できるか疑問(*2)。」である。
所謂「社会実験」全般に言えることだが、実社会を相手としての「社会実験」は、「実験条件を定め、制限する」事が容易ではない・・・と言うより、大抵「厳密には不可能」だ。だから、「社会実験の結果/成果」は、実験室レベルで行われる普通の理科の実験ほどには、実施も評価も「簡単ではない」。カナダとアメリカの死刑制度有無と犯罪率だけを比べて「死刑制度に犯罪防止効果が無い」なんて結論は、先ず「暴論」と言うべきであろう。
更には、此処が尤も肝腎なことだと思うんだが、「社会実験の結果」は、往々にして再現性が低い。一般論として「死刑制度に犯罪防止効果が無い。」と言うことが「実証された」としても(左様な事態は、私(ZERO)には、一寸想像を絶するんだが・・・)、「我が国が死刑制度を廃止しても、犯罪防止効果は低下しない。」とは、限りそうに無い。
諄い様だが繰り返すと、「死刑制度に犯罪防止効果は、在る。」と私(ZERO)は確信している。その確信が「何ら実験的統計的事実に基づかず、主として常識的/観念的判断による。」事は認めるが、私(ZERO)の常識的/観念的判断を覆す様な「死刑制度の犯罪防止効果は、無い」という説には、お目にかかったことが無い。左様な説が実在することは知っているが、トテモシンジラレナイ。
さて、上掲記事で「常識にして前提」となっている(らしい)「死刑制度に犯罪防止効果は、無い。」という考え方を私(ZERO)が「真っ向から否定」する以上、話は「そこでお終い」だと思うが、敢えて更に突っ込もうか。
上掲記事は、「死刑制度廃止の背景としての、キリスト教的発想(一言で言ってしまえば”裁くのは神"って、恐ろしいまでの無責任。)」について縷々述べられているが、我が国でのキリスト教徒は昔も今も少数派。一説によると、10%=1割を超えたことは無い、とも言う。曾野綾子女史とか、渡辺昇一先生とか、今村均中将とか、「尊敬に値する日本人キリスト教徒」は結構心当たりがあるが、1割を超えぬ少数派であれば「日本人の思想的背景が、キリスト教徒的ではない。」のは当たり前で、その点は基本的に「キリスト教国の集合体」であるEUとは、大いに異なろうぞ。
で、そのEUは「死刑制度廃止国のみ」な訳だが・・・EU諸国は、日本よりも「幸福で平和な社会」となっている、のかね?私(ZERO)には、(少なくともEU諸国の平均値としては、)とても左様には思えないぞ。
「日本が死刑制度を廃止居すれば、既に死刑制度を廃止しているEU諸国よりも、幸福で平和な社会になる。」って主張、だとしても・・・そりゃ「宗教家の主張」であっても、「科学者の主張」とは思われない。喩え、「幸福学」なる珍奇な名前の学問であっても、な。
ああ、「幸福になるために、死刑制度を廃止しましょう。」って主張も、同様だな。一国の死刑制度の存廃を。「幸福」で決めるってのは、矢っ張り宗教だろう。
- <注記>
- (*1) それ以上に、「全く納得できない」。
- (*2) カナダには西部劇に対するノスタルジーも、カウボーイという歴史的アイコンも無さそうなので、これだけでもカナダとアメリカは、随分違う、と思われる。