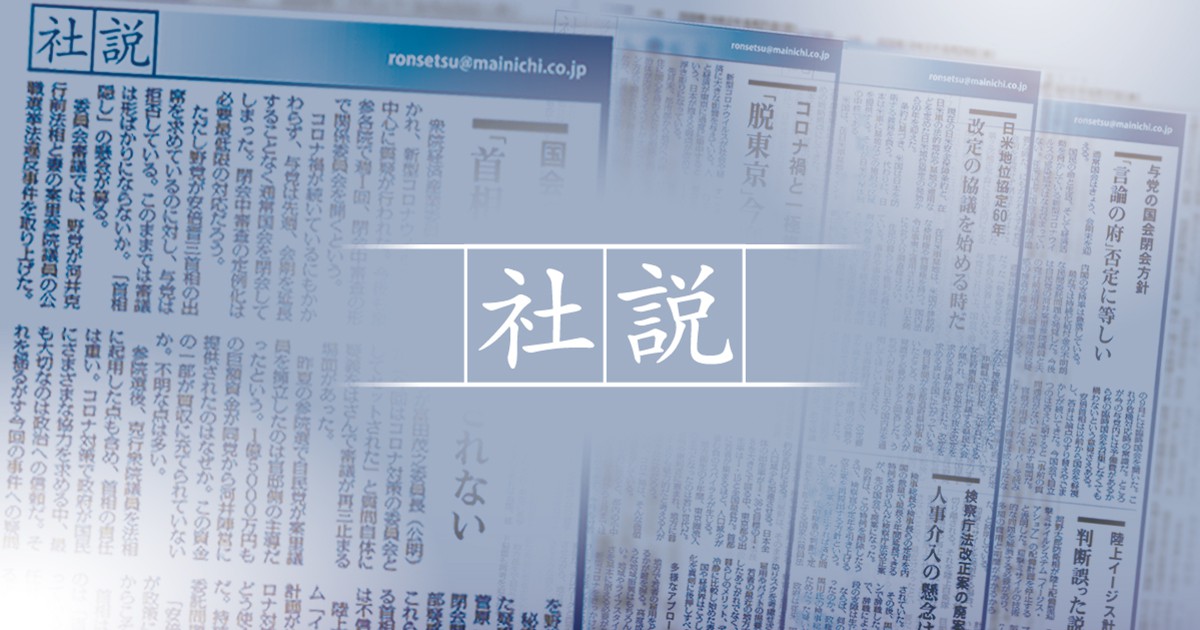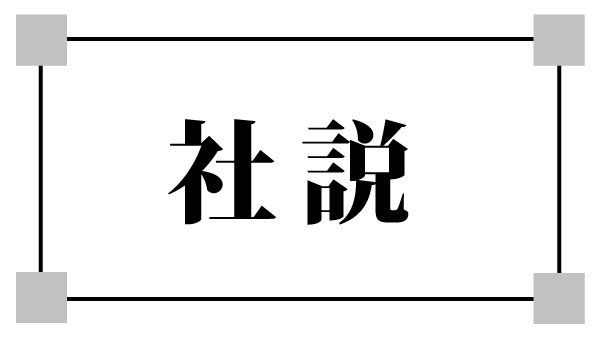-
ロシア軍のウクライナ虐殺と、アカ新聞各紙の社説
有り体に言って、ロシア軍と言えば、「略奪と強姦」で悪名高いのである。第2次大戦下では「ソ連軍(*1)」として、西は東ベルリンから東は満州、樺太、北方領土まで席巻したロシア軍(*2)は、行く先々で「略奪と強姦」をほしいままにした。
なればこそ、映画「氷雪の門」に描かれ、稚内に立つ「九人の乙女の碑」として後世に残されている樺太・真岡郵便局の交換手(*3)達は、真岡郵便局交換台を文字通りに「死守」し、最後はロシア兵の毒牙から免れるため、全員服毒自決して果てたのである。
真岡郵便局の交換手達「九人の乙女」は服毒自決であるから、「戦争の悲劇」ではあっても「虐殺」とは呼べまい。だが、虐殺でもロシア軍は実績十分で、第2次大戦末期のスモレンスク近郊カティンの森にて、ポーランド軍将校ら二万人以上を虐殺して遺体を埋めている。
かてて加えて、ロシア軍は「軍紀粛正ならざる」事でも有名である。「粛正ならざる軍紀」の意味するところは、カティンの森の様な「上官の命令に従って(*4)の組織的な虐殺・略奪・強姦」ばかりでは無く、下部組織や個人による「組織的ではないが、統制もされていない虐殺・略奪・強姦」も生起しうる/生起しやすい。と言うことだ。
であるならば、ロシア軍が撤退したキーウ(キエフ)近郊で「ロシア軍が虐殺したと思しき遺体が多数発見された。」というニュースは、「想定内」とは言わないが、「或程度予想できた」事。このニュースに対しロシア政府が「虐殺への関与を否定」した上、「虐殺は、西側向けの捏造/プロパガンダ」と言わんばかりなのは、ある意味「想定内」であるな。
因みに、カティンの森虐殺について、当時ソ連政府は「これはドイツ軍占領下にドイツ軍が虐殺したモノだ。」と反論だか弁明だかをしていたから、まあ、「歴史は繰り返す」って奴だな。
さて、前置きが長くなったが、かかる「21世紀のカティンの森虐殺」を受けて、日本のアカ新聞どもも一斉に「ロシアの戦争犯罪非難」の社説を掲げている。
①【朝日社説】侵略の惨状 戦争犯罪を非難する
②【毎日社説】ウクライナ侵攻 首都近郊のの虐殺 露は独立調査受け入れを
③【東京新聞社説】キーウ州で虐殺 戦争犯罪を重ねるな
④【沖縄タイムス社説】[ブチャの惨状]おぞましい戦争犯罪だ
- <注記>
- (*1) その一部がウクライナ人であったのも事実だ。ソヴィエト連邦を構成する共和国で2番目に大きいのがウクライナで、1番目がロシアだった。
- (*2) ウクライナ人含む
- (*3) 「交換手」ってのも、死語だよねぇ。その昔電話は、電話口で交換台を呼び出し、交換台に就いた交換手が手動で電話回線を相手側へと接続していた。
- (*4) カティンの森虐殺については、当時の最高権力者スターリンの命令が出ている。
(1)☆①【朝日社説】侵略の惨状 戦争犯罪を非難する
☆①【朝日社説】侵略の惨状 戦争犯罪を非難する
侵略の惨状 戦争犯罪を非難する
https://www.asahi.com/articles/DA3S15256759.html?iref=pc_rensai_long_16_article
2022年4月5日 5時00分
おぞましい惨劇である。この残酷な侵略戦争の結果を断じて容認できない。国際機関による真相解明を進め、責任者を処罰しなければならない。
ロシア軍が撤退したウクライナの首都キーウ(キエフ)近郊で、多くの遺体が見つかった。地元の住民らとみられ、現場の映像などが報じられている。
ウクライナ当局によると、ブチャという町で少なくとも410人にのぼる。後ろ手に縛られていたり、地雷をしかけられたりしていた遺体もあった。
ロシア政府は関与を否定しているが、そもそも彼らの侵攻で起きた戦禍である。これまでもロシア軍は病院や住民の避難所への攻撃を重ねてきた。
今も戦闘が続く南部マリウポリでは、住民約5千人が死亡したとされる。今回は、ロシア軍の撤退した首都圏で、国際メディアが確認できたものだ。
この現場を見るだけでも、ロシア軍が非武装の住民を非道に扱っている疑いは濃厚だ。東部や南部の激戦地域を含めた人道被害全体を考えると、国際法違反の戦争が生んだ「戦争犯罪」の規模は甚大であろう。
国連事務総長は今回の報道に「衝撃を受けた」とし、停戦と責任追及を呼びかけた。すでに開戦以降、多くの国からの要請を受けて、国際刑事裁判所(ICC)が捜査を始めている。
国連の常設機関である国際司法裁判所は3月に、軍事行動を中止するよう暫定的な命令を出している。こうした求めを侮蔑してきたロシアの独善は、強く非難されるべきだ。
ロシア軍は首都圏の周辺から部隊を引いた一方、東部や南部での攻勢を強めている。首都の攻略に失敗したため、ロシア国境に近い地域での占領地を広げる狙いがあるのだろう。
プーチン大統領は、ウクライナとの首脳会談にも応じていない。首都圏からの撤退の理由として「信頼醸成」や「停戦協議に向けた条件整備」が語られてきたが、即時停戦の意図はないことがはっきりしてきた。
プーチン氏は、ロシアの最重要の祝日とされる5月9日の対ナチスドイツ戦勝記念日を意識しているとの見方が強い。その日にウクライナでの「勝利」を演出して国民の支持を強めたい思惑とみられている。
仮にそうだとすれば、少なくとも今後1カ月以上の間、戦闘は続く。何の罪もない住民を巻き込む、さらなる戦争犯罪が繰り返される可能性が高い。
プーチン氏は人道に反する蛮行をただちに中止し、停戦協議のテーブルに着くべきだ。その実現のために、日本を含む国際社会は、より実効的な追加制裁を科すほかあるまい。
☆②【毎日社説】ウクライナ侵攻 首都近郊のの虐殺 露は独立調査受け入れを
ウクライナ侵攻 首都近郊の虐殺 露は独立調査受け入れを
https://mainichi.jp/articles/20220405/ddm/005/070/090000c
朝刊政治面
毎日新聞 2022/4/5 東京朝刊 English version 854文字
ロシア軍に占領されていたウクライナの首都近郊ブチャで、市民とみられる遺体が多数見つかった。重大な人権侵害が起きた可能性がある。調査によって、真相を明らかにしなければならない。
キーウ(キエフ)周辺からの露軍撤退後、現地に入ったジャーナリストなどが目撃した。ネット交流サービス(SNS)にも、路上に横たわる遺体の画像が投稿されている。
ブチャ市長は280人を埋葬したと明らかにした。ウクライナ司法当局によると、殺害された民間人は400人を超える。実際の被害はより深刻だとの見方がある。
ウクライナ政府側は露軍による虐殺だと主張し、欧米諸国や日本もロシアを批判している。
一方、露国防省は民間人殺害を否定し、遺体の写真や映像について、「ウクライナ政府が西側メディア向けに用意した作り物だ」と反論している。
欧州ではボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中の1995年、イスラム教徒約8000人が犠牲になる「スレブレニツァ虐殺」が起きた。今回はそれ以来の大規模殺害になる可能性も指摘されている。
20世紀前半に起きた2度の世界大戦では、多くの市民が命を落とした。その教訓から、国際社会は49年、ジュネーブ条約を改正し、戦時であっても民間人を攻撃対象とせず、捕虜を人道的に扱うことを決めた。
しかし、ウクライナでは産科病院や、子どもが避難する劇場が空爆された。これらの行為は戦争犯罪に当たるとみられる。今回、組織的に民間人が大量に殺害されたとすれば、「人道に対する罪」に該当する疑いも出てくる。
ウクライナ司法当局は住民の証言などを集め、実態の解明に乗り出す考えを表明している。ただ、一方の紛争当事者だけによる調査では客観性を欠き、ロシアが受け入れない恐れがある。
国連のグテレス事務総長は声明で、「独立した調査」によって、惨劇を引き起こした責任の所在を明らかにするよう求めている。
このままではジュネーブ条約が形骸化しかねない。民間人殺害を否定するのなら、ロシアは独立した国際機関による調査に同意し、積極的に協力すべきだ。
(3)☆③【東京新聞社説】キーウ州で虐殺 戦争犯罪を重ねるな
③【東京新聞社説】キーウ州で虐殺 戦争犯罪を重ねるな
キーウ州で虐殺 戦争犯罪を重ねるな
https://www.tokyo-np.co.jp/article/169854?rct=editorial
2022年4月5日 08時15分
その残虐行為を最も強い言葉で非難する。ロシア軍が撤退したウクライナのキーウ(キエフ)州で、多数の市民の遺体が見つかった。ロシア軍による虐殺の疑いが濃厚である。ロシアは度重なる戦争犯罪をやめて、停戦・撤退に応じるべきだ。
待ちかねたウクライナ軍兵士に抱きつく住民がいる一方で、ロシアの軍用車両の残骸が散らばる路上には、横たわる遺体。後ろ手に縛られた遺体もある?。ショッキングな出来事に国際社会からはロシアへの非難が一斉に上がっている。ロシア国家の尊厳は地に落ちた。
西側はロシアに追加制裁を科す構えだ。人道危機の広がりを食い止めるためにも、国際社会が一致してロシアへの圧力を強める必要がある。
ロシアの非道ぶりは目に余る。ウクライナ南東部の港湾都市マリウポリでは、女性や子どもが避難していた劇場が空爆されたのをはじめ、無差別攻撃によって大半の建物が破壊された。ロシア軍によって強制的に連れ去られた住民もいる。
非戦闘員への無差別攻撃や民間人の拉致は、国際人道法が禁じる戦争犯罪である。戦争犯罪を裁く国際刑事裁判所(ICC)は捜査を開始している。ロシアは虐殺事件の真相を明らかにすべきだ。
ところが、ロシアは相も変わらず関与を否定している。ロシアの元軍人らが訴追されたウクライナ上空でのマレーシア航空機撃墜事件、国家ぐるみと認定されたソチ冬季五輪での大規模なドーピング不正でも、ロシアが非を認めたことはない。
そんな倫理観が欠如したプーチン体制の体質も、軍の残虐行為を助長させているのではないか。
ICCは個人の犯罪を裁くので、戦争犯罪にかかわった一線の兵士、それを命じた上官も訴追対象になる。
加えて、軍の最高司令官であるプーチン大統領の責任も厳しく問われなければならない。ウクライナ侵攻自体が国際法違反である。侵攻を命じたプーチン氏への捜査も行われるべきだ。
④【沖縄タイムス社説】[ブチャの惨状]おぞましい戦争犯罪だ
[ブチャの惨状]おぞましい戦争犯罪だ
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/937678
2022年4月5日 07:52
写真は、人の残虐性と破壊の限りを尽くした跡を映し出していた。
ウクライナがロシアから奪還した首都キーウ郊外の都市ブチャで、民間人とみられる多数の遺体が見つかった。ロシアが侵攻を始めた2月24日以来、首都攻防の戦場になっていた。市民の殺害は国際人道法に反し、さらにジェノサイド(大量虐殺)条約違反の疑いも強まっている。
ロシア軍撤収後に現地入りした各国メディアが惨状を伝えている。地下室では体の一部が切断された子どもの遺体もあったという。耳が切り取られ、歯が抜かれていた複数の遺体は、民間人が拷問された痕跡を示唆している。
街中に地雷が仕掛けられ、爆弾は遺体にも付けられていた。ウクライナ政府は当面の間、市民に帰還しないよう呼びかけている。
ウクライナのゼレンスキー大統領は交流サイト(SNS)で道路に放置された遺体の写真を公開。米CBSテレビで「これはジェノサイドであり、国家と民族の破壊だ」と激しく非難した。
人口約4万人のブチャは約1カ月にわたりロシア軍の制圧下に置かれていた。しかしロシアは期間中、市民の被害は報告されていないと主張。「写真はウクライナ政府の挑発だ」としている。
戦争犯罪は決して見過ごしてはならない。国際刑事裁判所は直ちにブチャで起こった犯罪を捜査すべきだ。長期にわたる困難な捜査になるだろうが、関係各国が粘り強く支えるべきだ。
■ ■
ブチャを離れたロシア軍は、マリウポリを含む東部2州や南部での攻撃を強めている。
中でも1カ月以上ロシアの攻撃が続いているマリウポリでは10万人以上が、水や食料がないまま市内に残っているとみられている。ロシアは1日、マリウポリに人道回廊を設定すると発表したが、避難はむしろロシア側に妨害されているとの情報もある。
人道回廊の運用は停戦と一体でなければ難しい。国際社会は停戦の実現を急ぐとともに、住民避難の支援に力を注いでほしい。
ウクライナからは現在、約410万人超が国外に脱出した。国内避難者を含めれば国民の4分の1に当たる1千万人を超える。
戦況によって避難民はさらに増えるに違いない。周辺国だけでの対応は厳しく、受け入れの負担を国際社会で分担する必要もある。
■ ■
日本も傍観は許されない。避難民の受け入れを大幅に拡大すべきだ。
避難民の9割は女性や子どもで、国連は混乱に乗じて避難先での人身売買や性的搾取などの危険性が高まっているとして警戒を呼びかけた。避難先での安心安全を確保するため環境整備を急ぐべきだ。
沖縄ではウクライナの現状を知り、かつての沖縄戦と重ね合わせて平和資料館などを訪れる親子や若い世代が増えている。沖縄にいてもできることはあると自覚したい。
現地で苦しむ人々を支援するために、日本政府へ声を届けることも重要だ。
-
)アカ新聞どもも、[ロシアの戦争犯罪]を非難し、日本政府に「対露制裁の強化」を求める点で、大凡一致を見ているようだ。
それ以外にも日本政府に対して「ウクライナ難民の受け入れ」とか「戦争犯罪追求への協力/支援」などを求める意見も散見される。
まあ、主目標とも言うべき、特筆大書された「プーチンは停戦和平交渉の席につけ!」に比べると「小さな要求」ではあるが、その特筆大書された要求が「一番叶いそうにない」のも事実だろう。
アカ新聞の相当数は国際刑事裁判所(ICC)に大いに期待をかけているようだが、多分左翼の大好きな「国連信仰」の延長なのだろう。が、その「国連信仰の総本山」とも言えそうな「国連安保理」がロシアの拒否権発動で「完全なる機能停止の脳死状態」なのである。安保理なんぞより遙かに新しいのが国際刑事裁判所(ICC)だが、「国や組織では無く、個人を訴追する」モノだから、現場の実行犯から最高指揮官たるプーチンまで「辿り着く」のは並大抵のことでは無く、未だ歴史深からぬ国際刑事裁判所(ICC)には「最高指揮官まで訴追が辿り着いた」実績も未だ無いようだ。
国際刑事裁判所(ICC)が「プーチンを訴追し、有罪判決を下す」なんて事は、「全く期待できない」ぞ。
一方その頃、琉球新報社説は・・・
⑤【琉球新報社説】プラごみ新法施行 削減へ行動する一歩に
プラごみ新法施行 削減へ行動する一歩に
https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1496736.html
2022年4月5日 05:00
社説
mail_share
使い捨てプラスチック製品の削減に向けた新法「プラスチック資源循環促進法」が4月から施行された。
背景にはプラスチックごみによる海洋汚染の深刻化がある。政府は使い捨てプラスチックの排出量を2030年までに25%削減を目指す。事業者だけでなく私たち一人一人が、使い捨ての行動を変える第一歩としたい。
海に流れ出たレジ袋などのプラごみが生物に被害を与えている。沖縄美ら海水族館は21年11月、沖縄本島周辺のウミガメの約20%がビニールなどの海洋ごみを誤食しているとの調査結果を発表した。最近では、プラスチック製の不織布マスクが新型コロナウイルス禍によって世界各地の海へ流出していることが報告されている。
英ハル大などのチームは昨年4月、プラスチックごみなどが壊れてできる5ミリ以下の微小なマイクロプラスチック(微小プラ)が、世界各地の魚介類に含まれていたとの調査結果を発表した。
微小プラは、ごみとして海に流れ込んだ包装容器などのプラスチック製品が紫外線や波の力で劣化し、壊れてできる。人間は食事を通じて1人当たり年間5万個を超える微小プラを摂取している恐れがあるという。シーフードを好んで食べる日本の摂取量は世界平均よりも多く最大13万個に及ぶと推定。専門家は「人の健康への影響を評価するべきだ」と指摘している。
社会全体でプラスチックの使用量を減らしていくしかないのである。
今月から施行されたプラスチック資源循環促進法は、前年度に計5トン以上の使い捨てプラ製品を提供した事業者に有料化や軽量化、代替素材への転換などを義務付ける。
フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバーの12品目が対象となる。20年7月のレジ袋の有料化に続く取り組みだ。
国際的な連携も始まっている。国連環境総会(UNEA)は今年3月、世界で増加し続けるプラスチックごみを規制するため、法的拘束力のある国際協定をつくるとの決議を採択した。プラごみを削減(発生抑制)すると同時に、海外で海洋流出の原因になりかねないプラごみの輸出を中止し、再利用を進めなければならない。
プラスチック循環利用協会によると、19年のプラごみの総排出量は850万トン。うち85%が再利用されている。再利用が進んでいるように見えるが、実態はそうではない。
その6割が、燃やして熱を利用する「熱回収(サーマルリサイクル)」である。石油から作られたプラスチックを燃やすと二酸化炭素が発生する。この方法では地球温暖化につながってしまう。熱回収以外の再利用を工夫する必要がある。
・・・遠く離れたウクライナの虐殺よりも、身近なプラゴミ、かね?まあ、それも、一つの考え方、ではあるがな。
歴史的補遺 『九人(くにん)の乙女』の物語 稚内観光情報HPより
https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kanko/gaiyo_rekishi/9ninotome.html?msclkid=23892cdcb7b811eca0d18144e6e435bd
『九人(くにん)の乙女』の物語
九人の乙女の碑の写真
真岡町(現ホルムスク)は、人口約2万人で樺太西海岸南部に位置し、北海道の各港との定期船も絶えなかった平和な港町でした。
日本領である南樺太は、ソ連領である北樺太とは北緯50度線をもってきっちりと一線を画されており、昭和16年(1941)太平洋戦争(第二次世界大戦)に突入することになりましたが、日ソ中立条約(領土不可侵・中立維持を約束した条約)が締結されていたこともあり、国境での紛争はほとんどありませんでした。
ところが昭和20年(1945)2月に、米・英・ソの首脳によりヤルタ秘密協定が結ばれたこともあり、同年4月ソ連は日本に対して条約を一方的に破棄する旨を通告、対日戦に備えて満州や樺太、朝鮮の国境地区に兵力を集結しました。
ヤルタ秘密協定は『ドイツが降伏し、ヨーロッパにおける戦争が終結したのち、2~3ヶ月後には南樺太をソ連に返還することを条件に、ソ連が日本に対する戦争に参加する』ということを約束したものでした。
そして、昭和20年(1945)8月9日の朝、樺太国境警察がソ連軍の不意の攻撃を受け、40年間にわたる国境の静寂が破られたのです。
ソ連軍による進撃・砲撃は、国境を接する町から次第にその範囲を拡げ戦況は悪化する一方で、樺太兵団は、中央国境を突破するソ連軍を側面から支援する部隊が真岡地区にも上陸するものと判断、この地区の守りを固めようと努力を続けていました。
当時、真岡郵便局における電話交換業務は、市内・市外ともすべて女性交換職員による手動交換接続方式でしたが、特に戦時下における電話交換業務は国防用また緊急連絡用として重要な使命を担い日夜繁忙を極めていました。
この非常事態に、老人、子供、女性、病人等を優先して島民の緊急疎開が開始されました。そして8月16日、上田・真岡郵便局長は上司から「女子職員は全員引き揚げるよう、そのため業務が一時停止しても止むを得ない」との命令を受けました。
ほっと安心すると同時に、皆その知らせを喜んでくれるだろうと思っていた上田局長でしたが、意外な事に局員からは「全員、疎開せず局にとどまると血書嘆願する用意をしている」と告げられました。
上田局長はソ連軍の進駐後起こるであろう悲惨な状況を話し説得したが応じてもらえなかったといいます。
きっと彼女らは交換業務の重要性を認識し、その責任感・使命感を健気(けなげ)なほど感じていたからこそ、このような覚悟をしたものなのでしょう。友人や知人が次々と北海道へ向けて避難を始める中で、多くの女子職員が職場に踏みとどまり交換作業に従事していました。
そして、迎えた8月20日の朝6時頃、真岡は身にまといつくような濃霧でした。霧の中にぼんやりと見える埠頭倉庫のトタン屋根は霧にぬれてにぶく光り、疎開する島民を北海道へ輸送する船や北部から難を逃れてきた漁船等がぎっしりと岸壁についていました。
この霧の中をソ連船団は、真岡港に接近しつつありました。そして船団は湾の中央に進みそれぞれの部隊を上陸させ、船団が反転、退避するとこれを援護するため、上陸部隊の火器が一斉に火を吹き、たちまちにして真岡市街は戦火に包まれました。
臨海地区を手中に収めたソ連軍は、続いて山の手に向かって戦線を拡大し、各所に砲撃による火の手が上がり、黒煙がようやく霧の流れた空を覆い、火の粉が風下一帯に降り注ぎました。
最後の時が迫った恐怖から人々は裏山の芋畑やクマザサの茂る野をはうようにして尾根を越え、ある者は鉄道のレール伝いに逃げまどいました。
真岡郵便局では早朝5時半過ぎ、真岡の北約8kmの幌泊から、「ソ連の軍艦が方向を変え、真岡に向かった」との連絡を受けた高石ミキ電話主事補が、仮眠中の宿直者全員を交換台に着席させ、関係方面への緊急連絡を行うとともに郵便局長にこの旨、電話で報告を行いました。
郵便局は場所的にも戦火に巻き込まれる位置にあり、交換室にも弾丸が飛び込むなど、極めて短時間のうちに危機は身近に迫っていました。
しかし、緊急を告げる電話回線を守り、避難する町民のため、またこれらの状況を各地に連絡するため、最後まで職務を遂行したのです。
同じ樺太にある泊居郵便局長は、当日の状況をこう話しています。
「午前6時30分頃、渡辺照さんが、『今、皆で自決します』と知らせてきたので『死んではいけない。絶対毒を飲んではいけない。生きるんだ。白いものはないか、手拭いでもいい、白い布を入口に出しておくんだ』と繰り返し説いたが及ばなかった。 ひときわ激しい銃砲声の中で、やっと『高石さんはもう死んでしまいました。交換台にも弾丸が飛んできた。もうどうにもなりません。局長さん、みなさん…、さようなら長くお世話になりました。おたっしゃで…。さようなら』という渡辺さんの声が聞き取れた。自分と居合わせた交換手達は声を上げて泣いた。誰かが、真岡と渡辺さんの名を呼んだが二度と応答はなかった」と語っています。
高石さんの知らせで自らも郵便局にかけつける途中、腕に銃弾を受けてソ連兵に連行されてしまった真岡郵便局長は、数日後ソ連軍の将校の許可で局内に立ち入ることができました。
その時の様子を、同局長は「9人は白っぽい制服にモンペをはいており、服装はみじんも乱れていなかった。また、交換台には生々しい数発の弾痕があった。さらに、睡眠薬の空き箱があったことは見苦しくないようにするため、睡眠薬を飲んだあと、青酸カリを飲んだのであろうが、息絶えるまで送話器に向かって呼びかけていたようだ。」と語っています。
彼女達は、ブレストを耳にプラグを手に握りしめ、最後まで他局からの呼び出しに応ずるために交換台にしがみついたまま倒れていました。遺体の確認に立ち会ったソ連軍将校も、悲惨な室内の状況を目の前にして、胸で十字架をきって黙祷したといわれています。
当日交換業務を行っていた9人の中で最年長だった高石ミキさんは、殉職の日の前日、北海道に疎開する母を港で見送った時、“いざとなったらこれがあるから大丈夫”と胸をたたいて見せました。それが青酸カリだと知った母親は、顔色を変えたといいます。それほど、明るくて物事をはきはき言う人でした。
志賀晴代さんは、妹と2人で同じ職場に勤務しており、日頃から“いざというときは、自分が職場を死守するから、生きて内地に帰りなさい”と妹に言っていた責任感と気の強い人で、当日も非番にも関わらず、急を知って局に駆けつけた程で、交換技能も抜群の人でした。
殉職した9名の交換手達はいずれも10代の後半から20代前半の若い女性達です。通信確保の任務を果たし、最後の言葉を残して9人の乙女達は、若き青春に訣別して行ったのです。
彼女達の壮烈な最後は詩になり、小説になり、映画にもなって「九人の乙女」の悲しい物語として広く知られ、昭和38年(1963)には稚内公園内に彼女達の霊を慰め、その功績を永久に讃えるために『九人の乙女の碑』が建立されました。また、貴重な関係資料は、同公園内にある開基百年記念塔(北方記念館)に収められています。
お問い合わせ先
建設産業部観光交流課
稚内市中央3丁目13番15号
観光戦略グループ 0162-23-6468(直通) 連携推進グループ 0162-23-6272(直通)