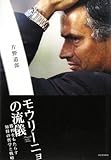勝利をもたらす知将の哲学と戦略/ウイニングイレブン2010
まず、読み物として素晴らしい。また、モウリーニョが凄いサッカー監督であることを再認識させられるのは言うまでもない。内容はインテルでの1年目を綴った軌跡である。トップ選手たちをモチベートし続けるメソッド、イタリアサッカーの戦術レベルの高さ、4-3-3の挫折、インテルの未来のための仕事など非常に興味深いものばかりだ。
だが、一番印象に残ったのはモウリーニョのサッカー理論に関する記述である。
11月5日についに新世代のウイニングイレブンが発売される。突破せよ。速攻をかけろ。というキーワードが掲げてある。新たに加わった300種類以上のモーション、7種類のフェイント、ついに実現した全方向へのドリブル、これが、ひとつのキーワード「突破」であろう。そして、もうひとつのキーワード「速攻」、これは新システム“スライダー”と“プレイスタイルカード”により徹底されたチーム戦術の追求と、ピッチ上で光り輝く個性を確実に表現できるという。
まず、プレイスタイルカードについては、ファミ通のネット記事を読むと、これまでのドリブラーやストライカーなどの特殊能力に変わるものとして設定されているとのことだ。今までの特殊能力は一切なくなってしまうということなのだろうか。カードの設定はオン、オフの切り替えができ、オフ・ザ・ボールの動きが要注目、アクセントを加える。
記事では、ナンバー10というクラシカルな司令塔タイプのカードが紹介されていた。どの程度種類があるのか、個人能力の違いがより明確になるだろう。
そして、スライダーについて。8種類のスライダーを0~100の間で調整して、チーム全体のプレイスタイルを明確に決められる。その8種類の項目とは、プレイヤーサポート、サポートレンジ、ポジションスイッチ、アタッキングスタイル、プレッシング、ディフェンシブライン、コンパクトネス、ディフェンシブストラテジーである。
ここで、話をモウリーニョに戻そう。
モウリーニョのサッカー理論はこうだ。サッカーというゲームは2つのレベルに分けて考えることが可能であるという。ひとつは、予見、制御、再現することも不可能な偶発性のレベル。(これをディティールのレベルと呼ぶ)
もうひとつは、組織、制御、予見することのできる必然性のレベル。(これを原則のレベルと呼ぶ)
モウリーニョの仕事、トレーニングの目的というのは、戦術というインプットを通して、チームにひとつのアイデンティティとプレースタイルを与えるために必要なプレー原則をチームに定着させ徹底することである。システムは変わり得るが、プレー原則は常に変わらない。重要なのはどんなサッカーをしたいかである。
プレー原則とは、ゾーンで守るかマンツーマンで守るか、ポジションチェンジを許容するかしないか、縦に奥行きのある陣形で戦うか横幅のある陣形で戦うか、ロングパスとショートパスどちらで攻撃を組み立てるか、などをいう。
これはウイイレ2010の新システム“スライダー”ではないか。つまりプレーモデルの構築と組織が、よりリアルに表現できる。これは凄い。
では、本書にあるモウリーニョのプレー原則に関する記述を次に羅列する。
ボールポゼッションの能力が高く、それを保つためのポジションバランスを重視、プレッシングを重視、攻撃においてはプレーの縦の奥行きよりも横幅を重視する傾向が強い、チームは常にコンパクトでなければならない、DFラインを常に高く保つ、ボールを失った直後からすぐに3~4秒間の非常に激しいプレッシングを行うこと、両サイドバックと第3の基準点となるプレーヤーを使ってのビルドアップ、アタッカーには最大限の自由を与えること。
これを8種類のスライダーに当てはめ、調整するとモウリーニョのインテルにどれだけ近づくことができるのだろうか。
11月5日が待ち遠しい。