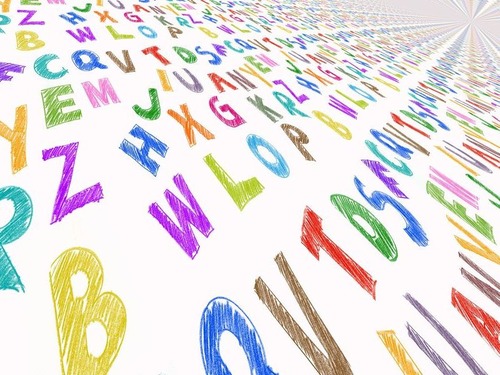「認知症」とその介護負担をどうするか、
超高齢化を迎える日本に突きつけられている大きな社会問題ですよね。
先日、「認知症とバイリンガル」に関わる記事で興味深いものがあったので、今日はそちらをご紹介します![]()
こちら↓はスペインで2020年9月に発表された研究。
大学の研究結果(英文)↓
https://www.uoc.edu/portal/en/news/actualitat/2020/360-bilingualism-alzheimer.html
「日常的に2か国語を話す人(バイリンガル)は1か国語を話す人(モノリンガル)よりも認知症が50%少ない」
という研究結果が発表されました。
スペインにはカタルーニャ語とスペイン語の両方を話す地域があるのですが、
その地域に住むバイリンガルの人と他のスペイン語のみ話すモノリンガルの人とを比較すると、
認知症の割合が50%も違うとか。
その他にも、同じバイリンガルでも2か国語を毎日使うのか、時々使うのか(受身的に)など使用の度合いに応じて、認知機能がどう変化するかという研究を行った結果、
”高い頻度で2か国を使う人の方が、時々使う人よりも認知症の発症が遅くなる”ということが分かりました。
これは脳の実行制御システムが2つの言語が混ざらないようにコントロールするシステムと関連していることからであり、
2つの言語を使い分ける”スイッチ”の使用頻度が高ければ、それだけ脳の認識能力が高まることを意味しています。
そして、バイリンガルの人は、その能力が高まることにより、例え脳が何らかの原因でうまく働かなくたっても、他の有効なシステムを脳が見つけ出して解決をすることができ、
認知症の発症自体が遅くなるというわけです。
同じような研究は過去にもいくつもあるらしく、
ワールド・ファミリー・バイリンガルサイエンス研究所が「バイリンガルと認知症に関する」既往研究をまとめています。
これらの研究結果を見ると、バイリンガルの人はモノリンガルの人よりも約4~5年ほど認知症の発症が遅くなるみたいです。
これらの研究は”バイリンガル”ということに着目した研究ですが、
2か国語を「話す」ことはできなくとも、長期間「聞く」だけでも脳の認識機能は高まるとか。
こちら↓の記事によると、”第二言語を「話す」のではなく「聞く」だけでも認知処理能力が高くなる”とあります。
この実験は7か月間、2つの言語を聞いて育った赤ちゃんと1つだけの言語を聞いて育つ赤ちゃんを比較してみると、
「聞く」だけですが、”バイリンガル環境で育った赤ちゃんの方が認知処理能力が高い”という結果が出たのです!
たかだか「聞く」だけのことですが、各言語の単語を耳で聞き分けるために認知的負荷が生じていて、その負荷が認知処理能力を向上させるのです。
これらの研究結果を見ると、バイリンガルになることによるメリットは大きいと分かりますよね。
そして、バイリンガルを目指して、
「子供の英語教育を早期に始めよう!」
と昨今高まっている英語早期教育の動きをより強くしそうな研究結果ではあります。
ただ、やはり私としては、
「だからといって早くからバイリンガルを目指す英語教育をした方がいい!」
とは簡単には言えない気がします![]()
それは今まで私のブログ内でも書いた、
・2言語を同時に学ぶとどちらの言語も遅れる→小さい頃に感情抑制ができない
・2言語どちらの言語も中途半端になる場合がある(ダブルリミテッド)
・思春期になると「自分は何者であるか」というアイデンティティーの問題にぶつかる
など、イギリスに住んでいた時の我が子を通して感じた問題や、イギリスで出会ったバイリンガルの日本人の友達に聞いた話から得たデメリットの部分も気になるからです。
今の日本の子育てを取り巻く環境でバイリンガルを目指して小さな頃から英語を学ばせることは
子供にとっても親にとって、経済的にはもちろん心理的にとても大きな負担がかかると思います。
そのメリット・デメリットを各家庭でしっかり話し合い、デメリットをきちんと認識し、それらにどう対応するかを分かったうえでバイリンガル環境に入れてあげないと、
色々な面で、後になって「思ってたんとちがう~!」
という結果になる可能性もあるので、よく考えてから行動に移して欲しいと思います。
そもそも、このバイリンガルと認知症の研究は日本でなく他の国で行われた研究。
同じ2言語といっても、「その2つの言語がどの程度、文化的に、または言語体系的に似通っているか」という点でバイリンガルになるための負担、それによって生じる問題も変化してきます。
つまり、「英語と日本語」と「英語とドイツ語」では、言葉がまとう文化も言語の体形の相違具合も大きく違います。
ドイツ人が英語とのバイリンガルになるために必要なエネルギーと日本人が英語とのバイリンガルになるためのエネルギーは全く違い、
バイリンガルになるために妥協しなければいけないことも大きく違うのではないかと思います。
ですから、「バイリンガルになる=認知症予防にいい」という研究を見て、
「英語と日本語のバイリンガルを目指すのがいい!」となったり、
「バイリンガル=将来にとってプラス=認知症予防にも効果的=子供の早期英語教育が良い!」
と安易に英語教育を早期に始めてしまうのは、日本においては良くないのかなと思ったりします。(個人的な見解です)
とはいえ、
先進国の中でも認知症の割合が多い日本。
これらの研究結果から、「日本はモノリンガルが一般的である」という事実と認知症の多さとは何らか関係しているのかもしれませんね。
私個人としてはバイリンガルになれるかは置いておいて、
「他言語を学ぶ」ということはとても意味があることとなので、何歳になっても勉強すべきだと思っています。
それはただ”他の言語を話せるようになる”という以上に、他の国の文化を知ることにもなり、
視野が広がり、面白いと思うことも増えると思うからです。
それによって人生もより充実する可能性があります。
今日書いた研究内容は「バイリンガル」に限定されていましたが、
要は言語をコントロールするスイッチの切り替えの機会をいかに増やすかが重要なのです。
それは正直、バイリンガルでなくとも、言語を勉強し続ければ起こる現象。
私自身もバイリンガルではないけれど、言語間のスイッチの存在も体感しています。
なぜこの記事を今日紹介したかというと、
別に日本でみんながバイリンガルを目指す必要はないんです。
他の言語を長期間学ぶことでも「言語を切り替えるスイッチ」をたくさん働かせることができると思うので、
「将来、認知症になるのが嫌だな~」と思っている方、
サプリ飲んだり、生活習慣を変えることもいいですが、
英語を含め、他の言語学習を始めてみるのもいいかもしれませんよー
とお伝えしたかったからです![]()
いくつになっても新しいことを始めると刺激的で楽しいですし、
その刺激が脳に良いのも事実です!
*関連記事*
アマゾンは只今セール中!
++++++++++
楽天roomでもステキなアイテムをご紹介しています↓
++++++++++