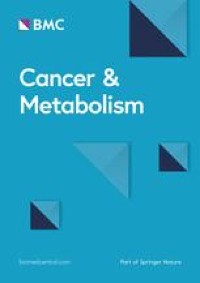私の会社には比較的若い(39)2型糖尿病の男性がいます。しかし6年ほど前からSGLT2阻害薬(ジャディアンス)で、それなりの血糖コントロールはできています。SGLT2阻害薬は体内の余分な糖を尿から出す仕組みなので、薬剤を使用した糖質制限ともいえます。でも糖質を一旦食べてから排出するので(原理的にも)食後高血糖はほとんど防げないようです。しかし空腹時血糖値は下げやすいです。彼の空腹時血糖値も、現在はほぼ正常範囲になりましたけど、HbA1cはまだかなり高めです。それでも彼は顔色も良くコロナにも強かったし、免疫状態はすごく良さそうです。
そしてこのSGLT2阻害薬のパターンは私の血糖パターンとも少し似ているのです。私は胃が無いので食後高血糖になりやすいです。厳格なケトン食の頃は空腹時血糖値、HbA1cのどちらも低めでしたが、最近はケトン食を少し緩めたので、空腹時血糖値は少し上昇しただけですが、HbA1cはある程度高めになってます(現在は空腹時約80,HbA1c5.5)
空腹時血糖値に比してHbA1cが高いのは、食後血糖値が高いことを意味します。
HbA1cと空腹時血糖値の数値がわかれば、下の表で食後血糖値のおよその数値がわかります。HbA1cは過去1~2ヶ月間の平均血糖値値だからです(暁現象やソモジー効果はこの場合無視します)私のHbA1cは5.5なので表での平均血糖値は約110です。ここから私の空腹時血糖値の80を引くと、その差は30になるので、最高は(平均値の110に差の30を足した)140になります。以前より高めですが正常範囲でしょう。これで体調は良好だし、インスリン抵抗性もありません。私はこれからも糖尿病にはならないと思います。
そして最近、SGLT2阻害薬(フォシーガ)が、手術不能の膵臓がんの化学療法の補助療法として、有益な可能性があったことを示唆する臨床試験の発表がありました。
原題:進行した手術不能な膵臓がん患者に対する、標準的な化学療法と併用したフォシーガ(SGLT2阻害薬)の安全性、許容性、有効性 第1b相観察研究
一部要旨:膵臓がんは代謝(エネルギー)をブドウ糖に過度に依存してるので、代謝療法のターゲットになります。しかしまだフォシーガ(SGLT2阻害薬)が膵臓がんを患う人に対して安全で有効であるかは不明です。
15人の膵臓がん患者が登録され、標準的なゲムシタビン+nabパクリタキセル療法とフォシーガを8週間併用し、12人が完了しました。結果は部分奏功(PR)が2人、安定(SD)9人、進行(PD)1人で、腫瘍マーカーのCA19-9も同様の傾向を示しました。しかしその後、化学療法を継続したのにもかかわらずフォシーガだけを中止すると、数人(7人)の患者で腫瘍サイズが増大したり、新たな病変が発生しました。これらのデータはSGLT2阻害薬による代謝調節(血糖コントロール)が安全で許容性も高く、膵臓がんに対して潜在的に効果的な治療法である可能性を示唆しています~ここまで
この(米国での)臨床試験は、ほとんどの患者が糖尿病患者でなかったそうなので、食事も普通食だったと思います。アメリカ人の一日平均摂取カロリーは日本人よりもかなり多く、糖質摂取量も日本人の1日約300gよりもかなり多いと思います。それゆえフォシーガで(ある程度の)糖質を排出してもケトン値や血糖値にはさほど変化はなかったようです。よってこの論文では、余剰なブドウ糖を減らすことが抗腫瘍の役割を果たす可能性がある、と考えているようです。(ただし腫瘍の退縮に関して、フォシーガが最高に反応した患者はケトン体が最も大きく上昇していた)
(注:SGLT2阻害薬は1日約50~80gの過剰なブドウ糖を排出させるそうなので、糖質制限やケトン食と組み合わせる場合には、充分な注意が必要です。糖質を急激に減らしすぎると緩衝が間に合わなくなり、ケトアシドーシスという非常に危ない状態になる場合があります。本来は薬剤なので、お医者さんの指導の下で慎重に服用するのが安全です)
私のブロ友さんに、膵臓がんで5年前に余命3ヶ月と宣告されたのにもかかわらず、御自身の懸命な努力と工夫で、現在も元気で過ごされてる方がおられます。やはりあきらめずに1日でも多く生きられるように希望を持った方が良いと私は思います。