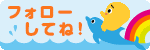雪が少し溶けた頃、源氏は大井の山荘を訪れました。
どんよりとした空の色がまるで自分の心を映したようだと明石の上は暗く沈んでいます。
いつもならば嬉しい源氏の来訪も今日ばかりは疎ましく感じられます。
源氏は小さい姫を引き取りに訪れたのでした。
明石の上は涙を浮かべて乳母(めのと)との別れを惜しんでいました。
「あなたまでいなくなってしまったら、この邸はさらにさみしくなってしまうわね。長い間共に暮らしたようにすっかり馴染んでいたのに・・・」
「わたくしも思わぬ縁で御方さまにお仕えできたのは心からの喜びでした。もうこれきりと会えないことはないと信じておりますが、悲しくて仕方がありません」
この二人には肉親の情のような絆が芽生えておりましたが、乳母は姫に付き添って二条邸に移るのです。
手を握り合って流れる涙を止めることのできない二人なのでした。
「おかぁたま。はやく、はやく」
何も知らない無邪気な姫は車に乗れるとはしゃいでいます。
「おかあさまは後から参りますから、乳母と一緒にお乗りなさい」
明石の上は姫を不安にさせないようにいつものように優しく微笑み姫を源氏に引き渡しました。
わたくしの愛しいちい姫、どうか幸せに。
健やかに立派に成長されますように。
紫の上さま、くれぐれも姫をよろしくお願いいたします。
ゆっくりと邸を離れていく車を、端近なのも気にせずに尼君と見送りながら、明石の上は姫の幸せだけを祈って己を支えているのでした。
小さな姫を膝に抱き、車に揺られながら、源氏は明石の上を不憫に思っていました。
母親にとって子供を取り上げられることほど辛いことはないでしょう。
この罪は深く許されるものではないと心が重くなります。
せめて姫の将来を明るく希望のあるものにすることでその罪が少しでもそそがれればよいのだが、と深い溜息をつきました。
源氏が二条邸へ戻る頃には、陽はとっぷりと暮れていました。
いつのまにか姫は可愛らしい寝息をたてて、すやすやと寝入っております。
源氏はそっと姫を抱き上げると紫の上の住む西の対へと運びました。
「まぁ、なんて愛らしい稚児なのでしょう」
紫の上はその姫の品よく愛らしい様子に声を潜めて感嘆しました。
そっと触れた頬は柔らかく、愛しさが込み上げてきます。
姫はふと目を覚ますと辺りを見回しました。
見たこともない邸に知らない女人が顔を覗き込んでいるのです。
優しげな美しい人でしたが、心細くなり母を求めて泣きだしました。
乳母は源氏の邸があまりにも立派で場違いな感じがして気圧されていましたが、姫の泣き声を聞いて、はっと我に返りました。
「ちい姫さま、大丈夫ですよ」
いつものようにあやされて、姫も少しずつ落ち着いてきたようです。
「お腹がすいているのではないかしら」
紫の上の一言で大井を出てから乳を与えていなかったことを思いだした乳母はすぐに姫を抱き上げました。
乳母は乳をやりながら、初めて間近で紫の上を目の当りにして言葉を失いました。
まるで咲き乱れる樺桜のように麗しい女性です。
明石の上も気品があって素晴らしいと思っていましたが、さすが源氏の北の方と言われるだけあり、並々ならぬ美女です。
そして小さい姫を愛しそうに見つめるまなざしは菩薩のように慈愛に満ちているのです。
この御方ならば姫を立派に養育してくださるに違いない、と乳母は強く感じました。
この『源氏物語』は私がアレンジして書いているもので、人物描写なども私の想像などが重きを占めています。
また失われた巻についても想像で描いているので、オリジナルのものとは違います。
お問い合わせが多いのでこの場にて・・・/ゆかり