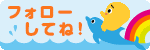叔母は噂以上の邸の荒れように言葉を失いました。
「このように恐ろしく荒れてしまって、お気の毒に」
とうわべは親切そうに取り繕っておりますが、内心では皇族など所詮生活力がないではないか、と鼻白んでいるのです。
それでも皇族という血筋と関わりがあることは家の見栄にもなりますし、姫を邸に引き取って娘達の召使にでもしてやろうという魂胆があるので、あくまでもやんわりと姫を誘います。
「うちのお邸に参られればもうなんのご心配もありませんわ」
しかし姫はこの邸を離れるなど考えてもいないので、すぐにお断りしました。
どこまでもお高くとまっているものよ、と思うと癪に障り、それまで被っていた猫は何処へやら、叔母は強い口調で言いました。
「まさかまだ源氏があなたを救ってくれると思っていらっしゃるのですか?あの方は遠い須磨の浦にあっていつ赦されるかわからない身の上ですよ。それに二条邸の紫の上とかいうたいそう美しい御方を娶ってからはその方一筋というお話です。こう言っては何ですが、あなたのように器量の悪い姫なんてとうに忘れ去られているでしょうよ」
ずけずけと遠慮のない言葉に耐えられず、姫はしくしくと泣きだしました。
するとさすがの叔母もばつが悪く、
「何も意地悪で申し上げているのではありませんよ。あなたが夢見がちで心配ですから本当のところを言ったまでです。よく考えてからもう一度お返事を下さいまし」
そうして叔母は帰って行きました。
まったく扱い辛い姫であるよ、と叔母は思い通りにならなかったことを口惜しく感じました。
こうなるとどうしても召使にしてあの赤い鼻をさらに赤くしてやりたいものだ、などと意地の悪いことを考えるものです。
姫は叔母に言われたことを反芻していました。
この姫は素直な性質なので、叔母が親切心から言ってくれたものだと信じて疑いません。
断るにしてももう少し機嫌を損ねないような言い方があったのではないかと反省しましたが、それでもやはり邸を離れるという決断だけは下せないのでした。
姫はぼんやりと源氏を想いました。
美しい君はいつでも優しく語りかけてくれたものでした。
その言葉の数々に嘘偽りがあるとは思えないのです。
今は大変辛い思いをされているので致し方の無いことですが、晴れて都へ戻った暁には必ずや自分のことを思い出してくれるに違いないと思うのです。
姫は側に控える侍従の君に話しかけました。
「侍従や、わたくしは縁あって夫婦になった源氏の君をただ一人の夫と決めているの。そんな気持ちがいつかは届いて、君が帰京されればまたお会いできるのではないかと思うのよ」
侍従はこの姫の純粋な気持ちを踏みにじることができなくて、
「そうなればこれほど嬉しいことはありません」
と姫の手を優しく握りました。
源氏と出会い姫は女性として内面がずいぶんと磨かれたようです。
あいかわらず口下手で気持ちを表現することは苦手なのですが、以前とは違って風趣を解する心が芽生えているのでした。
この『源氏物語』は私がアレンジして書いているもので、人物描写なども私の想像などが重きを占めています。
また失われた巻についても想像で描いているので、オリジナルのものとは違います。
お問い合わせが多いのでこの場にて・・・/ゆかり