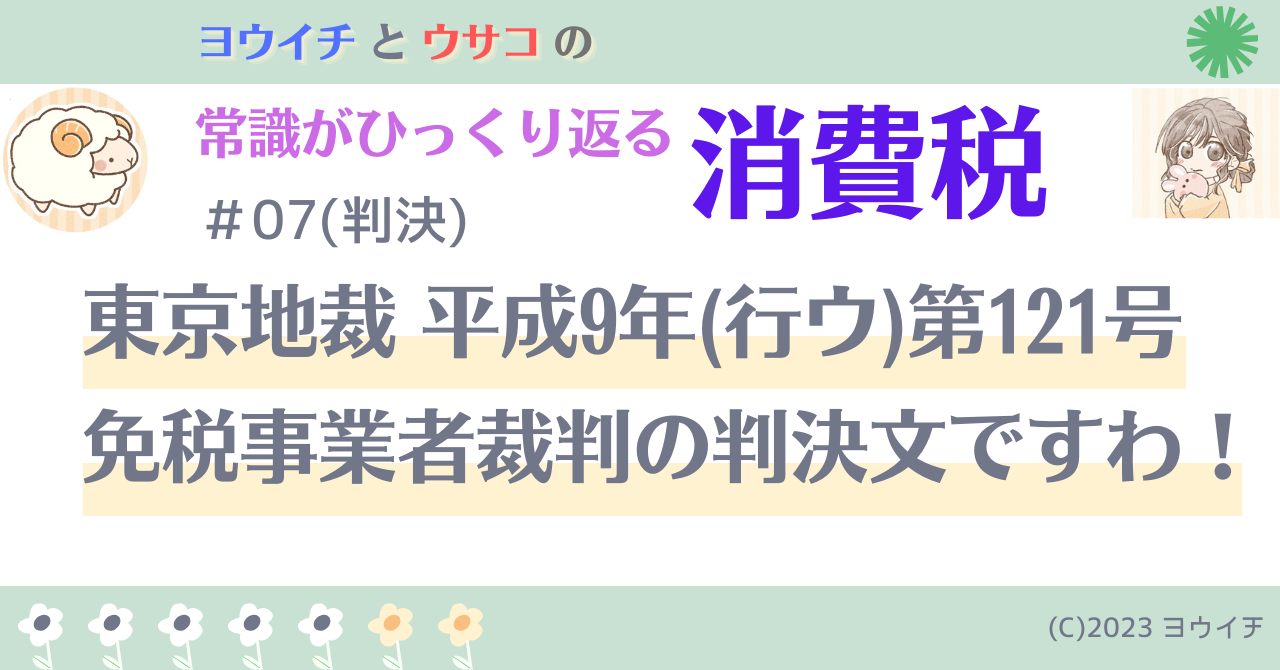立憲民主党の原口一博衆議院議員が、元自民党衆議院議員の安藤裕先生を招かれて、1月19日(金)に開催された、第23回日本の未来を創る勉強会。それを分けた原口先生の解説動画の2回目(21日(日))。
~~~ここから~~~
原口先生、ありがとうございます。所々で本音が思わずポロッと漏れてましたが、お気持ち、お察しいたします。
(1)110円のボールペンを買った時
誤:100円のボールペンを買って10円の消費税を払った
正:110円のボールペンを買った
これは、消費税法の第4条(課税の対象)と第5条(納税義務者)に加えて、下記裁判の判決を知っておくと、理解できると思います(自分はそうでした)。
『国と国民との間の課税関係(納税義務の発生)は、納税義務者につき課税物件(課税の対象とされる物、行為又は事実)が帰属したときに成立するものである。』*1
消費税において国と課税関係が成立するのは、納税義務者の事業者につき課税物件の売上が帰属した時です。買手の消費者は、国と消費税の課税関係が成立しないので、支払代金(対価)の110円に消費税そのものは存在し得ません。事業者の税込み売上になって初めて消費税10円が発生し、税込み売上110円が税抜き売上100円と消費税10円に分かれるのです。
この判決が更に重要なのは「消費税は買手と売手で授受不可能」という事実を示している点です。これは、買手が事業者で売手が仕入先の「仕入」においても同様です。
でも、110円の対価に消費税10円が含まれているじゃないか、と思われる方もいらっしゃるでしょう。ここが大切な所ですが、その10円は「消費税」ではなく「消費税相当額」です。「相当」とは、全く同じではないという意味です。消費税10円と消費税相当額10円。何が違うのでしょう?
金額は同じですよね。違いは「税」です。消費税相当額とは「税」ではなく「金額のみ」なのです。そこで問われるのは「税とは何か」です。この説明が無いから、混乱します(自分がそうでした)。
結論だけ記しますが、税は「代金」ではなく「負債」です。なぜか? 個人事業主は自己破産しても、税の滞納は免責されませんが、その理由を調べると「国の租税債権は非免責債権だから」と分かりました(*2)。
え? 債権? 債権の債は「貸した金銭」という意味だよね? 国から金を借りた覚えはないんだけど? ところが国から税を課された「納税義務者」は強制的に「貸付無しの借金状態」になるのです。憲法30条の「納税の義務」とは、貸付無しの借金を背負わなければならない義務だったのです。だから、絶対に納付して「返済」しなければならず、絶対に徴収される。
そんな「負債」を事業者が消費者に渡せるでしょうか? 否です。消費税(負債)は他者に渡せません。しかし、返済の元手は他者から「消費税相当額」という金額で工面することは出来る。だから110円のボールペンを買った時。あなたは「110円のボールペンを買った」だけなのです。自己破産しても免責されない恐ろしい「消費税」は課されても払ってもいませんから、安心してください。
なお、消費税3%導入時に、それ以前の価格を本体価格として「消費税=本体価格*消費税率」のイメージが出来ましたが、商品の価格は売手と買手の力関係で決まりますし、消費税法にも「消費税分を本体価格から算出して、その金額を価格に上乗せ(価格転嫁)しなさい」という規定はありませんから、国は「事業者が消費税率通りに値上げしたという前提」で、下記計算式で消費税(売上税額)を算出させます。
売上税額=売上総額(対価)*消費税率/(消費税率+100)
消費税率10%なら10/110、8%なら8/108
つまり、本体価格から消費税を算出するのではなく、対価(税込価格)から売上税額を算出します。レシート表記の「消費税」は、この「売上税額」です。そして、対価-売上税額=税抜き売上(本体価格)になります。
税抜き経理の問題点は、この「税抜き売上」しか「売上」に見えないという点です。
税込み経理 売上110円(総額主義=全額が事業者の私有財産)
税抜き経理 売上100円+仮受消費税10円
(税抜売上100円しか事業者の私有財産に見えず、仮受消費税10円は
消費者の私有財産に見える)
*1東京地裁 平成9年(行ウ)第121号(行政事件裁判例集)
免税事業者の売上に消費税が存在するかが争われた裁判
判決は、第9条が第5条の例外規定であり「存在しない」
*2個人事業主が自己破産したら未納税金はどうなるの?(2013/09/10)
(2)消費税の実質負担者は消費者。消費税は間接税。
国のこの説明を読んで、誰が「消費者は、事業者に課された消費税を『税』ではなく『金額のみ』負担している」と読み解けるでしょうか。しかも「消費税は間接税」という説明が「消費税は消費者の税金」という誤解をさらに強固なものにしています。昨日の動画で「間接税の定義はあやふや」と安藤先生も原口先生も仰っていましたが、そこは違います。
法律の直接税 納税義務者(租税債務者)
→納付
法律の間接税 納税義務者(租税債務者)
→特別徴収義務者(徴収と納付義務者)
→納付
独自の間接税 実質負担者(税法に定めが無いのに租税債務者に位置づけ)
→納税義務者(租税債務者であるのに特別徴収義務者に位置づけ)
→納付
独自定義の間接税は、70年前に輸出還付をしたかったフランスが直接税の還付を禁じたGATTに「付加価値税は間接税」と説明した時のロジックですが、この定義の間接税を認めていたら、それはあやふやになります。「消費税は直接税」と主張されるのならば、憲法84条を遵守した「直接税と間接税」の定義を用いるべきだと思います。
(3)消費税は第二法人税
法人税 利益=売上-仕入-人件費等 に課税
消費税 粗利=売上-仕入 に課税
どちらも事業者の私有財産を納付する「直接税」です。間接税の入湯税は、入湯客の私有財産を預かって納付するので、事業者の私有財産には含まれません。
これらの関係は、税込み経理で見ないと、まず分かりませんし、間接税の入湯税も含めると、法人税はもちろん消費税が直接税であることが分かりやすいと思い、下図を作成しました。
間接税の入湯税の特別徴収義務者の売上構成を、税込経理と税抜経理で見た図
以上、ご参考になりましたら、幸いです。
~~~ここまで~~~
「税は代金ではなく負債」「独自定義の間接税は税法に基づいていない」「消費税は第二法人税で直接税は、税込経理でないと見えない」の3点。2点目については次回で付加価値税の歴史、そして輸出還付金とを併せて、更に考察を進める。
「消費税は課税ベースが異なる『第二法人税』の直接税だ!その証拠は税込み経理で見よう」にご賛同いただける方は、
↓のバナーをクリック!↓