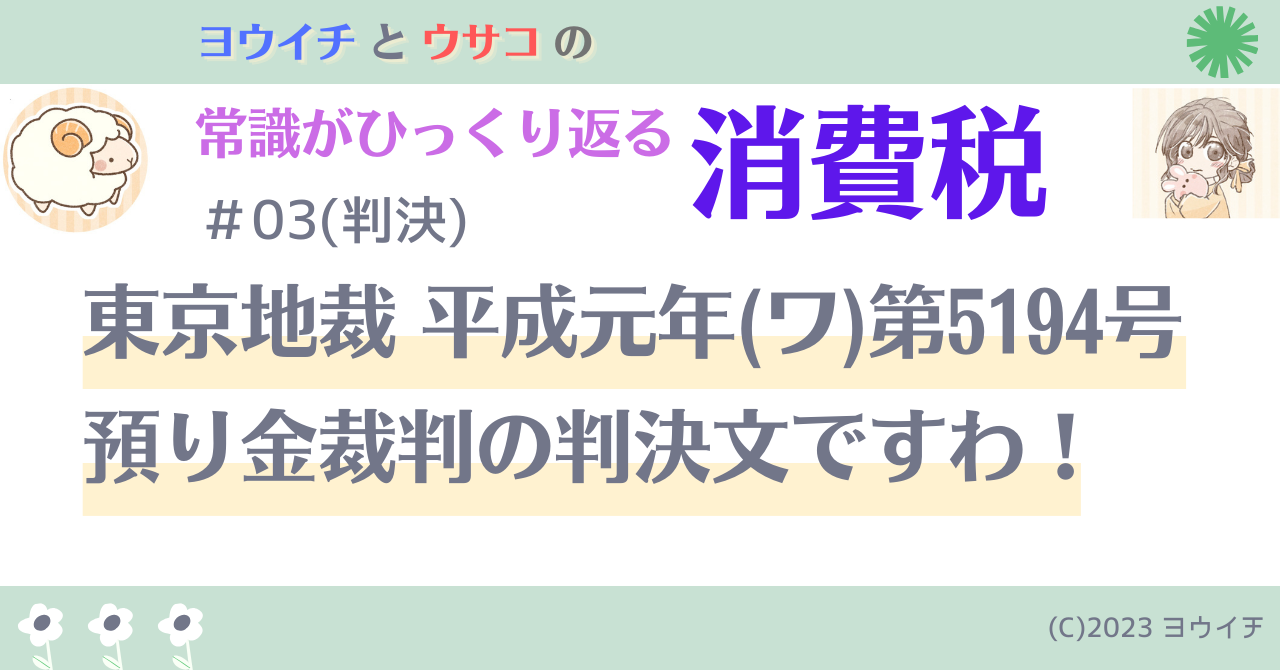立憲民主党の原口一博衆議院議員が、元自民党衆議院議員の安藤裕先生を招かれて、1月19日(金)に開催された、第23回日本の未来を創る勉強会。それを何回かに分けての解説動画が翌20日(土)から始まった。
いま確認したところ、自分が投稿したコメントが消えていた。次回以降は残っているようだが、誤字の編集を行ったのが、長文の繰り返し投稿でYoutubeにスパムと判断されたのかもしれない。このコメントで直接税と間接税の定義を整理した。
~~~ここから~~~
原口先生ありがとうございます。まず直接税と間接税の定義ですが、日本は法治国家なので憲法84条で「租税法律主義」が定められています。
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
この条文を分かりやすく説明しているのが、他ならぬ国税庁です。
法律によらなければ、国家は租税を賦課徴収できず、一方、国民は租税を負担することはないことをいう。
「租税を課す」とは「国民の私有財産を強制的に徴収する侵害行為」ですから、不要な侵害を行わないように、税法では必ず「何に税を課すのか」という『課税の対象』と「誰の私有財産から税を徴収するか(申告納付させるか)」という『納税義務者』を定めます。
その納税義務者が自分で「申告納付」するのが『直接税』(納税義務者と納付義務者が同じ)、特別徴収義務者が納税義務者から税を「預かって」代わりに申告納付するのが『間接税』です(納税義務者と納付義務者が異なる)。
国税はすべて直接税です。間接税は地方税のごく一部のみです(地方税法では直接税は「納付」間接税は「納入」と記述を分けています)。
ここでもう1点押さえておく必要があるのは、国が国民に税を課した時、国は「租税債権者」、課された国民(納税義務者)は「租税債務者」になるという点です。租税債権でググれば分かりますが、この債権はもっとも優先されます。個人事業者が自己破産しても税の滞納が免責されないのは、この理由によります。つまり税は「代金」でなく「負債」なのです。
閑話休題、ところが税法上の間接税の定義に基づかずに(憲法84条違反)、財務省は
「事業者に課される消費税相当額は、コストとして販売価格に織り込まれ、最終的には消費者が負担することが予定されています。(「直接税」と呼ばれる所得税などに対し、このように納税義務者と実質負担者が異なる税を「間接税」と呼びます。)」
と独自の定義を行っています。
この定義自体は財務省が定めたものではなく、1954年にフランスが世界で初めて付加価値税を導入した時に、直接税の還付を禁止していたGATTに「付加価値税は直接税ではなく、間接税」という説明に用いられたロジックです。実に、70年も使われている定義なので、これを疑う人はほとんどいません。しかし、この「法律に基づかない」独自定義の「間接税」を認めてしまうと、「直接税と間接税の定義があやふや」という、誤った結論になってしまいます。
法律の直接税 納税義務者(租税債務者)
→納付
法律の間接税 納税義務者(租税債務者)
→特別徴収義務者(徴収と納付義務者)
→納付
独自の間接税 実質負担者(税法に定めが無いのに租税債務者に位置づけ)
→納税義務者(租税債務者であるのに特別徴収義務者に位置づけ)
→納付
独自の間接税の定義が、いかに税法を無視した憲法84条違反の定義であるかが、お分かりいただけると思います。
なお、実質負担者(*)の意味は、消費税を例にとれば、事業者が消費税相当額(消費税ではなく「金額のみ」)を販売価格に上乗せした時に、その上乗せ分を含んだ「価格支払者」という意味です。繰り返しますが、実質負担者は租税債務を負っていませんから「税負担者」ではありません。納税者でも納税義務者でもないという事実は、預り金裁判の判決でも示されています。
間接税の入湯税の特別徴収義務者の売上構成を、税込経理と税抜経理で見た図
預り金裁判の判決文の「判決」
*厳密に言えば、事業者が価格の上乗せをしていない場合、利益減少という「実質負担」が生じるので。事業者自身が実質負担者であり、独自定義でも「直接税」になります。上乗せしていても100%の上乗せでない場合、事業者と消費者(支払金額の増加という負担が発生)の双方が実質負担者で、直接税でもあり間接税でもあるという状態になります。
~~~ここまで~~~
「実質負担者」の本当の意味をほとんどの人は知らないと思う。これが「納税者でも納税義務者でもなく、消費税相当税が価格に上乗せされた場合の金銭負担者」という事実は、預り金裁判を読んでいないとまず分からない。
誤:法に定められた租税負担者(租税債務者=納税義務者)
正:税ではなく、税相当額(税ではなく金額のみ)の金銭負担者
前者で理解してしまうと、財務省の思惑通りに「消費税は消費者の税金で、事業者が納める間接税」と誤認してしまう。
法律に規定された間接税とそれに基づかない独自定義の「間接税」は、表記を分ける必要がある。この点は、翌日のコメントにも再掲することになる。
「税法に規定が無い『実質負担者』を用いた独自定義の間接税は表記を分けよう!」にご賛同いただける方は、
↓のバナーをクリック!↓