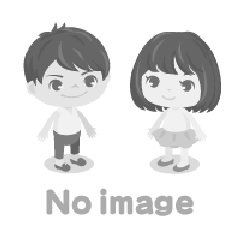定員割れの私立大学に漫然と入学すれば大学の先生は大変、学生は迷惑
「大学の再編・統合や撤退を国が支援する必要…中教審が答申、少子化で定員未充足や経営難『避けられない』」という見出しを有する読売新聞オンライン令和7年2月21日記事を拝見した。
定員割れは特に、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員が3000名以下の小規模私立大学では著しいが、定員割れの急速進捗の少子化に因ってすでに定員割れを起こし、それが改善されないままに、年を追う毎に定員割れが多い時には倍々になっている多くの私立大学について、その記事によれば、その総会で文部科学省の中央教育審議会は、大学の統廃合と共に、学生総定員数の縮小を大学に行わせるという答申をまとめ、文部科学大臣に提出する。令和6年の出生率は前年度とそれ以前のものに比べてさらに少なくなり、大学の定員割れは、今後、改善するどころか、年を追う毎にさらに深刻になる。
文部科学省が私立学校共済事業団に行わせている全国の私立大学の現状情報(インターネット上に展示されていて、だれでも見ることができるし、そのためにインターネツト上に展示されている。)によれば、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員が3000名前後程度以下である福岡県内の福岡女学院大学を含む有名な3つのお嬢様小規模私立女子大学もすべて、すでに、1乃至2割前後以上から3割余前後という著しい定員割れを起こしている。この定員割れの大きさは、今後、減少するというのではなく、大学経営が破綻する程度の大きさになっていき、早ければ数年後には経営破綻になってしまう予兆がある。私立大学の規模縮小というのは、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員を減数させることであろう。1つの大学の大学教員の人数は、一定の学生数に応じて定められている。そのことは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などと同様である。文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員が減数になれば、学生の減数に応じて、大学教員の人数についても少なくなる。
私立大学の場合、その経営母体である学校法人は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」という労働契約法第16条の条規を法的根拠として、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員の減数で、不要になった人数の大学教員を適法に解雇することができる。業務がなくなったことでの解雇を整理解雇と言う。無論、それには一定の場合が必要である。その場合とは、上述した労働契約法第16条の条規を反対解釈することで分かる。すなわち、当該の解雇には、< 客観的に合理的な理由を欠 > かないし、 < 社会通念上相当であると認められ > る場合は、適法な解雇を行うことができる。
私立大学の経営母体である学校法人は、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員の減数で、不要になった人数の大学教員を適法に解雇する際に、解雇の対象となる一定の人数の特定の大学教員の個々人のこれまでの公私の言動や行動と勤務状況、大学の建学の精神や方針との差異、思想傾向などから、< 客観的に合理的な理由を欠 > かないし、 < 社会通念上相当であると認められ > る解雇理由を顧問弁護士に案出してもらうことになる。
特に、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員数が3000名以下の小規模私立大学に受験したり、進学したりする高校生は、大学入学後、自分が取っている授業やゼミの担当の大学教員が、今後は、上述の整理解雇で、ある日ある時に、突然に大学から消えて無くなってしまうことを覚悟しなければならない。大学側は、その大学の先生の突然のいなくなりについて、学生たちに対して、普通は何も説明しない。このことについても、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員数が3000名以下の小規模私立大学に入学した学生は憂慮し、心配しなければならない。そのような憂慮や心配を回避したいのであれば、文部科学省から認可された大学全体の所定の1年生から4年生までの学生総定員が3000名以下の小規模私立大学への入学は止めた方が無難であると遺憾ながら言わざるを得ない。