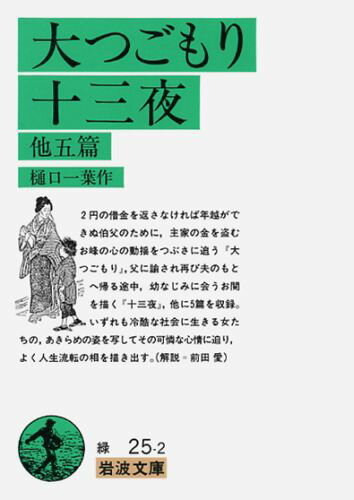https://www.taitogeibun.net/ichiyo/
あらためて一葉の才を識る一葉記念館
その日の東京入谷、竜泉の街は
ひっそりと静まり返っていました。
人影もまばらです。
めったに人に出くわすようなことも
ありませんでした。
そんな静かな細い路地の一画に
「一葉記念館」はありました。
館の前には歩行者天国になった
細い道路を挟んで
児童公園があるのが印象的です。
その公園内にはこんな碑がありました。
佐佐木信綱(歌人、国文学者)氏による
「たけくらべ記念碑」です。
『たけくらべ』はこの界隈を舞台にした
作品で、昭和26年11月に建てられたそうです。
では向かいの一葉記念館に
早速入ってみましょう。
撮影についてですが、
展示物のうち撮影禁止マーク🚱の
ついたものは撮影できませんので
ご注意ください。
マークのついていない
著作権等に絡まない資料は
撮影が許可されています。
ですので、ここに掲載しているのは
許可されているものだけになります。
樋口一葉(1872-96 本名:樋口奈津)は、
実生活において非常に苦労した文人です。
父親の則義、母多喜の次女として、
現在でいう千代田区内幸町に生まれますが、
学校も高等科四級(現在の小学校)を
首席で卒業するも、
多喜の考えで学業は要らぬと判断。
その結果、上級に進学せずに退学をします。
晩年は長兄、泉太郎の死とともに、
則義の事業の失敗と病死によって、
奈津が戸主となります。
母親と残りの兄弟のために
生活の困窮に陥り、給士などの数々の
仕事をしながら、生活を支えます。
その傍らで、和歌を学び
半井桃水に師事することにより、
1891年、若干20歳で
同人誌『武蔵野』に『闇桜』を発表。
その後、この地、龍泉寺町で
雑貨・駄菓子を販売しながら、
名作『たけくらべ』を執筆しました。
この地で生活していた経験が
名作を誕生させているのです。
その後1894年には駄菓子屋を引き払い、
現在の文京区西片に移り、
矢継ぎ早に作品を発表していきます。
1894年12月には『大つごもり』、
そして1895年は『にごりえ』『十三夜』、
翌年にかけて『裏紫』と
次々に作品を世に送り出しました。
この期間を「奇跡の14か月」として
一葉研究家の和田芳恵は名付けているように、
11作の小説作品を次々に発表しています。
この期間にこれだけの数の作品を書くのは、
よほどの決意を有していたものと感じとれます。
おそらく、自身の健康を案じての
決死の執筆作業であったのでしょう。
館内の説明などを見ても、
子どもの頃から利発で
賢明な人物であったと推定できます。
文壇でこのような秀才が
24歳で早世してしまいますが、
健康的で、充実した活動が
されていたならばと思うと
本当に鳥肌が立ちます。
旧五千円札のモデルにもなった人物です。
これだけの逸材が讃えられるのも、
この記念館に来てみると納得がいきますね。
また、近くには一葉の住んだ
旧居跡地(竜泉3丁目15)があります。
現地は今は碑と案内板があるだけですが、
併せて見学してみてください。
*2024年12月2日〜2025年1月31日まで、施設内工事のため休館になりますので、ご注意ください。
アクセス:地下鉄日比谷線三ノ輪駅下車 徒歩10分
住所:東京都台東区竜泉3丁目18番4号
円熟期に書かれた『十三夜』、『うつせみ』
一葉の書く文体は「雅俗折衷体」といって、
平安時代の文語の表現と日常の俗語を
混ぜ合わせた文体です。
地の文は文語体、会話は口語体で
書かれたもので、明治の初期に
多くの作家が使っていました。
一葉の「雅俗折衷体」の特長は
1 ゴロの良さ
2 一文が長め
この二つがまず読んで
感じることではないでしょうか。
ゴロの良さは
全体を通じて感じることですが、
『うつせみ』の最後の一文を
例に挙げてみましょう。
「いつぞは正気に復(かえ)りて夢のさめたる如く、父様母様(ととさまかかさま)といふ折の有りもやすると覚束(おぼつか)なくも一日二日(ひとひふたひ)と待たれぬ、空蝉(うつせみ)はからを見つゝもなぐさめつ、あはれ門(かど)なる柳に秋風のおと聞こえずもがな。」
【*( )は送りがな】
読んでいきますと、
思った以上にすらすらと
言葉が流れていくように思われます。
初めは読み慣れなれず、
意味もつかみにくく、
石につまづいたような
心持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、読み進めて「雅俗折衷体」に
読み慣れていくと、どんどんと
言葉の深みが感じられて、
不思議とゴロがいいために、
頭に残るようになります。
あとは、句読点(、)をマル(。)として捉え、
ゆっくりと読んでみることをお勧めします。
読み慣れている頃には、
不思議なことに一葉作品を読むことが
止まらなくなってきます。
豊富な語彙の魅力に取り憑かれ、
一葉文学に引き込まれている自分に
気づくことでしょう。
ご紹介する作品のひとつ目ですが、
『うつせみ』になります。
若い病人の雪子は精神の病いで、
ひと月ごとにわがままに転宅を繰り返します。
原因は雪子が植村の交際を断ったことによる
自殺への罪悪感を感じているのです。
良家の一粒種で両親も気が気でなく、
雪子の狂気がどんどんと募ってゆく話です。
良心に反した人間の背徳感が
描かれているわけですから、
読者は先の展開が気になるのも
当然のことですね。
そして、二作目は『十三夜』。
官吏の夫の虐待に我慢ができずに、
実家に逃げ帰ったお関。
一子を儲けていましたが、
着の身着のままで戻って悩んで
父母に相談をします。
しかし、父はそんなお関を諭し、
嫁ぎ先に帰らせます。
その帰り道の人力車の車夫は、
かつての幼馴染で煙草屋の一人息子
録之助でした。
互いにかすかな恋心があった二人。
お関の結婚後は録之助は
失意のうちに捨て鉢な態度で
資産を使い果たし、
車夫に堕ちていたのです。
お互いにどうしていたのが
一番幸せだったのかが気になります。
そうした人間の
この世を生き抜くむずかしさを
教えてくれる話です。
どちらの作品も人の感情を扱う意味では、
読者の心に響いてくるはずです。
引き続き、他の作品にも踏み込んで
読んでいければと思っています。
わたしは一葉の生涯に
関心を持つようになりましたので、
これからも作品とともにぜひ伝記も
読んでみたいと思いました。