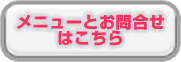未来企画 幸せになる!メモランダムワンポイントWEB講座
「わたしと家族の年表(故人)」の三度目の見直し記入をしました。

見直すたびに新たな気づきが。
この年表では、故人の年忌を書き入れていくのですが、
1回目の時は、
亡き主人と父母の年忌スケジュールが一目でわかるようになりました。
2回目の時は、
亡き主人の十七回忌の時に私が76歳。
まだまだ元気!!ということを確認。
3回目の今回は、亡き父母の「弔い上げ」と私が亡くなったときにお墓を守ってもらう親族に「亡き主人と私の年忌法要を何回忌まで行うのか」を菩提寺に相談することも必要かと思いました。
近年、核家族化が進み「夫婦のみ」と「一人親家庭」世帯が増加する反面で、「夫婦と子」世帯は年々減少傾向にあるようで、
親世代もよくわからないお寺との関係。
私の父が亡くなったとき
父母は「夫婦のみ」世帯で、私を含む娘たちは、「夫婦と子」世帯
生前にお墓を購入していることは知っていましたが、菩提寺については、あまり知りませんでした。
父が亡くなり、気が動転していた母は、葬儀の準備の時に菩提寺のことを忘れてしまったのか、お通夜は、葬儀社が手配したお坊さんに来ていただき、菩提寺のご住職に叱られた記憶があります。
一方、義母が亡くなったときは、
義父母は、一族とか本家・分家という家制度の名残が色濃く残る地方出身で、しかも親戚同士だったので、親戚一同が葬儀の段取りからお坊さんの手配までを進め、その後、義父の強い希望で、一族が檀家となっているお寺にお墓を立て、義母の納骨を済ませました。
その後、墓守については大きな問題が発生しました。
お墓をだれが守るのか。
お墓の形態も変化しつつあり、お墓を持たないという概念も広がってくるような。
長寿化により親の介護問題が議論されることも多いですが、少子化により、先祖代々の墓守も問題化してくるかも。
ある統計では、
戦後すぐに生まれた、いわゆる「団塊の世代」が人生の終わりを迎えることで、日本の死亡者数は徐々に増え、2040年には年168万人でピークに達すると予測されています。
「墓地不足」が問題となり、一方で、生涯未婚の人の増加で「墓」を守る人がいなくなる問題も深刻化するといわれています。
墓守をしている身だから身近に感じる大切なこと。
この記事を読まれ、ご興味を持たれて方は、
☆*:::;;:::*☆