<週末の対談>部分の文字起し
誤字脱字、理解違い、カタカナ表記間違い
があるかもわかりませんが、お許しをm(__)m
DJ:近藤真彦
ナビゲーター:ちわきまゆみ
<週末の対談>
MATCHY OF THE WEAKEND
ゲスト・東儀秀樹さん 第3回目/全4回
・・・続き
篳篥(ひちりき)

竹で出来てますね
竹の筒で出来ていて、それがヨーロッパに渡って行ってホーボエとかクラリネットとかの楽器になるルーツなんですよ
うーん
竹で出来てて、人間の声のように聞こえる・・とか
そうそうそうそう
そうですよね
うーん人の声に・・・
地上の音をあらわしてるという・・・
ちょっと聞かせて頂いてたんですけど、歌詞が無いんですけど
物語りがちゃんと聞こえてくるような
それはねー
多分僕の才能なんだなー
えーっ!!(笑)(笑)
なんかこう聞こえてくるんですよ
歌詞が!!
凄くこう難しい楽器で、まず音が出しにくいから
入門者の人が思いっきり吹くと耳障りで勘弁してくれっていうような音になるのね
それをうまーくコントロールするのと、あと音程がとっても不安定で
例えばミが出るはずの指を押さえているのに
【レ】が出ちゃうし、ソが出ちゃうかもしんないってすっんごく不安定な楽器なんでそれを全部コント―ロールするとほんとに自由自在に好きなようにすりあげたり、ビブラートさせたりとか・・・
僕は東儀さんの音を聴いてると、ほんとに自由に
考えてないですよね
自分の気持ちが音となって伝わってて
そうそうそう
・・・僕が聞くとなんか語り掛けてるようにも聴こえるし
歌詞にも聞こえるし、
あー凄く嬉しい
やっぱり歌う気持ちで楽器が届くといいなーと
僕、思っているから・・
なんかだから、もちろん歌詞だと“愛してる”って言われれば
愛してるって言ってるなーって聞こえて来るんですけど
音でも愛してるって言ってろるんだろうなーっていうように思える部分もあったりとか・・
なかなかいい表現するねー
そうですか~
そういう風に感じたんですけど・・
あっ、後でね見せて頂こうかなと思ってますけど・・・
・・あります?
あるよ
えっ!!
あるんですか?
本物ですねー
これは竹で出来てて・・
これはねー本体の部分が18㎝ぐらいの竹の筒に9つの指穴が開いていて
これぜんぶあれですか?
竹に何巻いてあるんですか?
これ巻いてあるのは桜の木の皮を剥いで細く小刀で線状に切って、
繋げてひも状にしたものを巻いて、あと漆で固めてある
売ってるんですか?それ?
売っていますけど、やっぱり普通の楽器屋じゃなくて、専門の職人が作ってる楽器やっていうのがあって、
骨董屋に行くと、江戸時代ぐらいの篳篥がたまにあったりとか
あるんですか?
これは、代々うちの祖父が演奏してたようなやつだから200年ぐらいは経ってるものだと思うんだけど・・
凄いですねー
チョット吹いてみましょうか。
お願いします
少しだけ~生演奏~
凄いなー、凄いなー
何なんでしょうね
この空気感
独特の音がするねー
その音が鳴った時の・・・
![]() 東儀秀樹
東儀秀樹 ![]() 海
海![]()
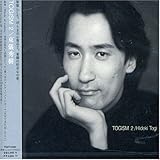 |
TOGISM 2
2,412円
Amazon |
なんか、昔、これが日本に入ってきたのは1400年前で
この形も作り方も音色もまったく変わっていない
出来たのは大陸のシルクロードのどこかで、
1500年前から2000年前に出来ているんだけれど
その雅楽の古文書を読んでいると、昔の人達の音楽の
雅楽折り込めたものってのがあって、
陰陽道って知ってる?
いやーわかんない
陰陽師っていう、昔の奈良時代とか平安時代の占い
占星学とか色んな統計学で病を治したりとか
そういうものも折こめられているって言われていて、
でなんか、古文書によると、ドレミファ ソの音って言うのは青とか緑とかに対応する音だとか、東を向いているんだとか、春を表す音なんだとか、
西を向いている音は、ミの音でこれは白い色と相性が合うとか、
でもっともっと読んでいくと、ソの音は肝臓と波長が合うとかね
ミの音は、呼吸器系にいいとかそういうノウハウが大昔はあった
統計とって、
それをうまく音楽に当てはめて出来たのが雅楽だっていうから
それうまく引き出すと、自然との調和みたいなものが生まれるんだっていう話なんです
そもそも、その雅楽って・・どなたに聴かせるんですか?
神や仏に聴かせる音楽・・として定着してたんですよ
大昔からね
お客さん居ないんですよね
お客さん居ない
だから・・もちろんそれだけじゃなくて娯楽で楽しむ部分もあるから
例えば平安時代の貴族たちは小さいころから雅楽をやるのが当たり前で
出来てなきゃいけないと、一人前じゃないとぐらい習い事のひとつだったのね
それは平安時代の貴族たちは、こう音楽を楽しむだけなんだけど、
雅楽師たちのやっているって言うのは、皇室の儀式とか、
お寺や神社のこの仏や神に捧げる儀式の中での音楽って事なんです
宮内庁の雅楽師の方って何人ぐらいいらっしゃるんですか?
今ね25人
25人の方は、お仕事は雅楽ですよね?
そう結局、国家公務員なんですよ
皇居に務めてる人たちは・・
公務員なんですね
それじゃあ今回、皇居の中で何かがある時に25人の方たちが集まって演奏する?
皇居の中の雅楽師のメインの仕事って結局、
儀式のための音楽をやるってだけなんですよ
一般的な演奏会が・・・
サントリーホールとかでやらないですもんね
やらない
それは特別日本の雅楽を日本の文化を人に知ってもらうためにって
年に1.2回人前であるんだけど
それはメインの仕事じゃなくて、メインは皇居の中の儀式とか・・
儀式ってなんだ?っていうと、普通の家庭でいう法事みたいなもの
おじいちゃんの何回忌とか先祖◯◯の何回忌とかあるじゃん
あーいうことが歴代の天皇にあるから、
◯◯天皇、何100年なんとか
例えば僕が居た時に色々あったけど、後醍醐天皇の600年祭とかね
後醍醐天皇の600年祭25人の雅楽師が集まって
で、後醍醐天皇に捧げる
後醍醐天皇のお墓に数名いって、その数名が皇居の中の神殿で残って
中に神殿があってね、演奏したり
そういうのが月に何回かあるんです
誰も知らないし、報道されてないんだけど
そうですよねー
あの人の方って神主さんみたいな恰好されてない時ってどんな格好されてるんですか?
普通の我々のこんな格好してるよー
どんな想像してるんですかー
皇居に住んでるわけじゃないし、
通うんですよね
普通に生活していて・・
ほぼ毎日通うんですか?
毎日
仕事なくても?
仕事なくても・・
儀式がない時は、音楽を絶やしちゃいけないから
練習をするために通う。
日課って言うのがあって、今日はこれとこれとこの曲を
この配役でやりましょうっていうのが先々まで決まっていて、
それをずーっとこなして行くことで継承が成り立つと
すごいなー
扱いは普通の国家公務員だからね
9時-5時ってピッタリした時間決まっていてラッシュアワーの電車にのって
えーっ電車に乗って帰るんですか?
そう
そういう方が・・
例えばネクタイとかしたりとか、
普通に背広着て、ネクタイして
背広着てネクタイして皇居に入って行く人見たら
まさか雅楽師だと思わないですよね
思わないだろねー
『篳篥』の画像は
東儀秀樹さんのHPより拝借
http://www.togihideki.net/et_cetera/gagaku/index.shtml
来週につづく・・・



