小笠原藩政の時代になると藩内の農村部は手永制
という農村行政組織が整備され大庄屋が統括しまし
た。東谷地区は小森手永になります。その範囲は東
谷に加え中谷、西谷の一部を含みます。この手永制
は明治になるまで続き小笠原藩政の農村統治の要
になりました。以下は東谷要覧には書かれていませ
んが幕末から明治の初年にかけての東谷の沿革で
す。小倉藩(小笠原藩)は幕末の対長洲戦の小倉口
の戦の主力として九州の大名連合の中心として戦い
敗れ、小倉城を自焼して幼い城主以下、田川郡香春
方面へ落ち、小宮民部や島村志津摩など残った小倉
藩幹部が曽根方面から平尾台にかけて最終防衛線
を敷きこれを背水の陣として山縣狂介率いる長州軍
にゲリラ戦を仕掛け勇猛に戦いました。そしてついに
降伏ではなく藩存続の講和を勝ち取りました。
東谷、中谷、西谷はその場所から戦場となり多くの
農民が苦しむ所となりました。また戦後は企救郡は
長州藩の管轄となり農村の行政は大混乱をきたし
ました。このとき発生したのが原口九衛門さんの
企救一揆です。以上が幕末から明治初年にかけて
の東谷沿革の補填です。
話がだいぶそれたのでそろそろ元に戻します。
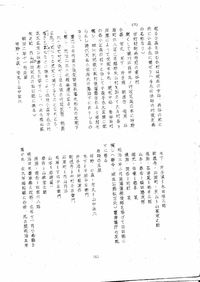
次回は版籍奉還から廃藩置県、市町村令発布までの東谷の変遷を紹介します。